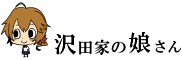夕焼けに照らされ、オレンジ色に染まる道路を笹川君と並んで歩く。
普段ならばその状況に歓喜して、会話をしようと必死になるところだが、生憎今はそういった気分にはなれない。
ツナは大丈夫だろうか。
多分、シャマルさんはあの時気絶はしていなかった。口付けした時に軽く頬が強張ったのが感じて取れた。だからきっと、気づいていた、と思う。
あとはシャマルさんにかかっている。私のような子娘の言う事に聞く耳を持ってくれればいいのだけれど。今は彼の「俺は女の子の味方」という言葉を信じるしかない。
私の隣を歩く、ジャージ姿の彼を横目で見る。こんな状況だと言うのに、笹川君を見るだけで、じんわりと胸が暖かくなる。いつもそうだ。私の体は空気を読まない。
だって、嬉しかったのだ。
ランニング中に困っている私を見かけて助けに来てくれた笹川君にすごく感動してしまった。後先考えずに私の為に来てくれた笹川君が嬉しかった。キスしたくないと思っていたのを止めてくれて、本当にありがたかった。沢田って普通に呼んでくれていた。涙が出そうだった。今だってこうして、我がままを言った私を家まで送って行ってくれている。事情も何も、問い質そうとせず、笹川君は私の言う事を聞いてくれている。
本当に良い人だ。優しくて、素敵で、こうしてる今もどんどん好きになっていく。
それに引き換え私はなんなの。
一人でうじうじ悩んで、口ばっかり偉そうで行動が全く伴っていない。ツナが心配だとか、笹川君が好きとか言いつつ、結局自分の事ばかり考えて保身にばかり走っている。
自分が恥ずかしい。どうして私はこんなんなんだろう。今こうして笹川君と並んで歩いている事すら恥ずかしくなってくる。
悔しくて仕方が無い。
「さ……わだっ!?どうした!何故泣いている!?」
気がつけば、とめどなく涙が流れていた。それに気づいた笹川君が、目を見開いておろおろとしている。
必死に涙をぬぐうも、止まらない。ああ、駄目だ。笹川君が見ているというのに。
「ごめっ……止ま……っんない」
「大丈夫か!?どうした?まさかさっきの痴漢に何か……」
切羽詰まった声で問いかけられたので、首を左右に振る。笹川君が安堵の息を吐くも、その表情は直ぐに困惑したものへと戻る。どうしよう、違うのだ。私は笹川君を困らせたい訳じゃないのに。
「あー、泣かせてやんの!」
ランドセルを背負った子供たちが、笑いながら私達の横を通り抜けて行く。
「俺が泣かせた訳ではない!……いや、俺が泣かせたのか!?だああ!極限に分からんぞ!」
「ちわげんかだー」
「ちっ痴話……!?違う!断じて違う!」
「彼氏が怒ったー逃げるぞー!」
握り拳を作り、力の限り笹川君が叫び出すと、子供達はきゃあきゃあと騒ぎながら走り去っていく。
「だああ!待たんか!違うと言っているだろうが!」
そのまま追いかけようとしたのか、子供達の方へと足を踏み出すも、笹川君は踏みとどまった。慌てて体をこちらの方へと戻し、私の様子を伺って来る。
「沢田、まさか本当に俺が何かしたか?」
「違うよ、それは絶対ない」
思い切り首を左右に振る。
「私、最悪なの」
「何がだ?」
手で涙を拭きながら鼻をすする。笹川君は急かすことなく、黙ってこちらを見ている。
「ワガママばっかりで、自分の事しか考えてなくて、最低なの」
止まりかけていた涙が再び溢れ始めてくる。それと共に、言葉も止まらない。
「うじうじしてて、悩んでばっかりいて、悩んでるだけで何もしなくて」
「……」
「笹川君に助けて貰うような価値ないの、自分がすっごく嫌い、恥ずかしい、悔しいし情けない、こんな自分嫌、変わりたいよ」
次から次へと、止むことなく言葉と涙が溢れてくる。景色が滲んで笹川君の顔すら見えない。今彼はどんな顔で私の話を聞いているのだろう。呆れているだろうか、それとも、意味が分らず困惑しているのだろうか。
「沢田、目を閉じろ」
「は?」
不意に顎を持ち上げられる。びっくりして、反射的に目を閉じると、目元がごしごしと拭われた。ちょっとだけ痛い。
手が離れたので、目を開く。どうやら私の涙を拭ったのは笹川君のジャージのようだった。笹川君のジャージの袖に染みが出来てしまっている。何だかびっくりしてしまって、自然と涙は止まっていた。
「すまん。タオルは俺の汗で濡れていて他に拭くものがなくてだな」
「え、あ……ううん、ありがと……っていうか、鼻水ついちゃったけど」
「極限に問題ないぞ!」
びっくりして、目をぱちぱちさせていると、笹川君が微笑む。その表情はとても優しいけれど、瞳にはとても強い意思の光が見えた。
「沢田は自分と戦っているんだな」
そういう笹川君の声は、とても優しい。ぼんやりと彼を眺めていると、視線が混ざり合う。
「大丈夫だ!悔しいと思う気持ちがあるなら、それが必ずバネになる。変わりたいと思うなら、力の限り進めば良い。それにこれはあくまでも俺の意見だが、お前に価値がないなんて俺は思わんぞ!」
ぐっと握り拳を作り、笹川君は歯を見せて笑った。
「俺はお前と話していると楽しいし、恥ずかしいなんて一度も思った事はないからな!少なくとも俺がいる限りお前は最低でもないし最悪でもない!自信を持て!」
夕焼けに照らされ、笑顔を向けてくる笹川君は、太陽のようだった。彼の一挙一動が、私には眩しくて仕方ない。
彼はどうして、こんなにも私を喜ばせるのが得意なんだろう。