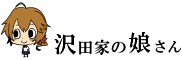「ドクロ病?」
私達は並盛公園の池のほとりを走っていた。説明する時間をも惜しい状況らしく、ツナの人探しと同時に状況の説明をして貰っているのだ。
ツナの話を要約すると、ツナは今不治の病に侵されていて、今日の夕方には命が尽きてしまうらしい。とまあ、そんな不治の病を治せる名医が一人いて――不治の病なのに治せるのか、という話は置いておく――リボーン君が日本に呼んでくれていたらしい。彼に治療を頼もうとしたところで、ツナの死を望んでいるビアンキさんがそのお医者様を連れ出し逃亡。目下彼らを捜索中、との事だ。
しかしその病名がいかんせん聞いた事の無い名前なので、どうにも信じがたい。またリボーン君にからかわれているのではないかと疑ってしまう。
「ドクロ病なんて聞いた事ないけど」
「死ぬ気弾を10回撃たれると発症する不治の病らしいんだ……本当に死ぬかはともかくとして、今すぐに治さないと!」
「死ぬのはともかくって、他にも何か問題があるの?」
「うっ……そ、それが……この手なんだけど」
ツナが手のひらを見せてくる。そこにはドクロのペインティングが施してあった。
「なあに、これ」
「これが、喋るんだよ!」
「はあ?」
頭がおかしくなったんじゃないだろうか、と不審に思いつつツナを見やる。気にする素振りもせずツナは続ける。
「このドクロが俺しか知らない人に言えない秘密や恥をどんどん喋るんだよ!しかも、死んだ後まで喋り続けるとかって……うわああ!嫌だよ!死んだ後まで恥じなんかさらしたくないよぉお!」
「ああっ!おいたわしや、十代目っ!」
うぐぐっと獄寺君が涙する。にわかには信じがたい話だ。
『はずかしやーパンツを後ろ前に履いておしっこ漏らした事があるはずかしやー』
三人の誰ともない声が、言った。ぴたり、と全員の動きが止まる。
「…………」
明らかにあの声はツナの方から聞こえた。でもツナの声ではなかった。いや、大体ツナがあんな事を自ら言うとは思えない。っていう事は、つまり、それがドクロ病のあれなんだろう。
「……あ、俺、何も聞こえなかったっす」
気まずそうに獄寺君が沈黙を破った。明らかに嘘であろうそれに、ツナが恥ずかしそうに唇をかむ。
なにはともあれ、今ので分かった。ドクロ病というのは本当に病気らしい。至極、間抜けではあるけれど。しかしそうとなればこうのんびりもしていられない。
「とにかく、まずいじゃない。夕方まで一時間かそこらしかないよ。早くその人探さないと。で、どんな人な訳?」
「う、うん。黒髪で、黒の色シャツに白衣を来たおっさんで、名前をシャマルって言うんだけど……」
「ビアンキちゃああああんっ」
「ん?ビアンキちゃん?」
会話を遮るように男の声が割って入って来た。声のした方を見てみれば、そこには白衣を来たおじさんがだらしのない笑みを浮かべながら走っていた。前方にはビアンキさんと思われる姿。
「ちょっと、ツナ、あれじゃない!?」
「あっ、本当だ!十代目!行きましょう!」
「う、うん!」
会話を中断し、私達は男の背中を追いかけ走り出す。とにかく、ツナの命が関わっているのだ。何が何でも捕まえないと。
***
「待ってくださーい!シャマルさーん!!」
「おい、十代目が待てっつってんだ!待ちやがれ!」
「ビアンキちゅわあああん!」
背中に向かって怒鳴るも、シャマルさんはビアンキさんの背中に夢中といった具合で、一向に振り返る気配が無い。時間もないというのに、これではらちが明かない。
「っていうか、何であんなこっちに気づかないの。ビアンキさんに何か盛られたんじゃないの?」
「盛られたっていうか、何て言うか、ビアンキが私を捕まえる事が出来たら幾らでもキスしてあげるってシャマルに」
そこまでしてリボーン君を連れ戻したいのか、ビアンキさん。っていうか、キスって、そんな事であんなに必死になる?普通。
「もしかしてシャマルさんって、ビアンキさんの事好きなの?」
「ビアンキが好きっていうか、世の中の女全てが好きっていうか」
「なにそれ」
訳が分らない。
「こんのっ、待てっつってんだろうがっ!!」
痺れを切らしたのか、獄寺君がシャマルさんの背中へと飛び掛かる。彼の渾身のタックルは成功し、シャマルさんと獄寺君の二人はごろごろと地べたへダイブした。
「いってて、何すんだ!……って隼人じゃないか」
「隼人じゃないか、じゃねえ!テメェ!早く十代目を治しやがれ!」
不愉快そうだったシャマルさんは、獄寺君を見た途端に表情を和らげる。対照的に獄寺君は苛立ちを一切隠そうとせず、今にも殺しかねないような形相で彼を睨んでいた。どうやら二人は知り合いらしいが、その関係には温度差があるようだ。
「二人とも、知り合いなの?」
「あ、はい。こいつは昔うちによく出入りしてたもんでして」
ツナの問いかけに、獄寺君はシャマルさんの胸倉を掴んだまま答えた。無礼を働く獄寺君とは対照的に、ツナはシャマルさんの前に立ち、頭を深く下げた。
「シャマルさん、お願いします!俺の病気を治してください」
「あー、だから駄目だって。言っただろ。俺は男は診ないんだよ」
「そんなぁ!」
申し出をばっさりと切り捨てられてしまい、ツナが悲痛な声を上げる。しかしシャマルさんはまるで興味なさげに、走っていくビアンキさんの背中へと視線を送っている。
ちょっと待て。なんなんだこの人は。段々と怒りが沸き上がって来た。
「ちょっと、待ってください!男は診ないってなんですか!ちょっと転んで怪我したとかじゃなくて、命に関わる事なんですよ!お願いだから診てあげてください!」
「うわああ、姉さん、落ち着いてよ!怒らせたら治せるものも治してもらえなく」
「おやおやおや?」
怒鳴る私を止めに入るツナを押しのけて、シャマルさんは私に近づいてくる。驚いて後ずさろうとすれば、彼はそれを遮るように恭しく私の右手を取って、微笑んだ。
「可愛いねえ、お嬢さん。こいつのお姉さんなの?名前は?」
「さ、沢田ソラです。挨拶は良いですから、早く弟を診てあげてください」
「うんうん、気が強い所がたまんないねえ、おじさんがちゅーしてあげよう」
「はあ!?」
訳が分らず身を引こうとするけれど、いつの間にかがっしりと腰を掴まれていて身動きが取れない。まずい、と思っている内に、どんどんとシャマルさんの顔が近づいてくる。