158
※当サイト比で長い話です。
明治だか大正時代に建てられたらしい古びた洋館が、海里の住む町にある。
外国からやってきた大富豪の一族が住んでいたと聞くが、世界大戦以降その一族の行方は知れず、人の手入れも行き届かなくなった、かつては絢爛豪華だったであろうその館は、今や蔦がはびこるお化け屋敷と称され、庭木は荒れ果て、外観もすっかり美しさを失っている。
大人達は危ないから近寄ってはダメだと言うし、噂を聞きつけた若者やメディアが肝試しがてら散策しようにも、古く大きな門扉は錆び付きのせいかうんともすんとも言わないし、なんとか屋敷をグルリと囲む剣先フェンスを登って辿り着いたところで、古い扉ながらも頑丈に施錠され、窓ガラスも一階と二階は真っ暗なカーテンと面格子、三階より上は木製の雨戸がピタリと閉められていて中の様子が少しも見えないし、格子も扉も、少しの力で今にも朽ち果てそうなのに、意外や意外に固く頑として動かないのだから、恐怖心を煽られる以前にお話にもなりゃしないので、人はてんで近付かなかった。
海里も小学校に上がり立ての時、親の言いつけを破り、クラスの友達と興味本位で見に行ったことがある。雲ひとつない快晴の日曜日、真っ昼間だと言うのにその洋館のおどろおどろしい雰囲気に飲まれ、即ユーターンしただけだが、子供心に振り返れば屋敷から何かが追ってきて食われてしまいそうな不気味さを感じ、猛ダッシュしたのを覚えている。
不幸は突然やってきた。
海里が小学二年生の頃、両親がそろって事故で他界したのだ。母親の祖父母が海里の引き取り手となり、かつて住んでいた町よりは都会の方へ引っ越したので、悲しくも慌ただしく、不安定な精神を引っ提げながら新しい土地での生活に慣れようと懸命に日々を消化していく中で、海里はすっかり洋館の事を忘れてしまった。洋館のある土地は、両親との思い出の地だ。思い出すには辛する。
洋館の事を忘れてしまった事に気付いたのは、大学進学したての夏、バイト先の仲間内で怖い話に盛り上がっていた時だった。今やネットで何でも調べられる時代なので、海里は仲間の話を聞きつつ、思い付く限りのワードを入力して検索を掛けてみた。オカルト板にチラリと書かれていたが、上記の通り中に入れないので面白味もない。行くだけ無駄。と書かれてあるだけだった。それなら仲間への話のネタにもならない。窓を閉じて、海里は再び話の輪の中へ参加した。
大学の三年生の秋、高校二年の春に亡くなった祖父に次いで、祖母が亡くなった。成人式の日に海里のスーツ姿を見て涙を流した祖母が笑いながら「これでいつでも向こうに行ける」と冗談めいたのが本当になってしまった。
両親に代わり、他人から見ても大事に育ててくれた祖父母には感謝してもしきれない。社会に出て稼ぐようになってからが本当の孝行が出きると思ったのに。心残りしかないお別れに、海里は泣き伏すしか出来なかった。
一人になってしまった。
四十九日を過ぎた頃、空っぽになった海里は就職活動にも身が入らなくなってしまった。
友人の誘いも学業も、全てがどうでもよくなって、自分も早く皆のところに行きたいと思う事が多くなって、ふと思ったのだ。
あの場所に帰りたい。
まだ孤独も不幸も知らない、小さな頃の幸せでいっぱいだったあの場所へ。
これが最後の気力だと、着の身着のまま、ポケットにスマホをひとつ突っ込んであるのを確認してから家を出た。電子マネーとスマホケースに交通系ICカードを挟んであれば、あとはどうにでもなる。
たどり着いたのは夕暮れ時だった。
電車を乗り継ぎ、駅からバスに乗って聞き覚えのある町で降りれば、記憶の中の町とは随分違っていた。商店はコンビニに、年中テナント募集していたビルは病院に、公園の遊具は健在しているが、雑草は延び放題で子供のよりつく場所ではない。道中、活気のあった商店街は軒並みシャッターが下りていて、商店街だというのに地方では大手展開のスーパーマーケットが電光明るく我が物顔をしていたのには驚いたし、寂しくも感じた。
かつての同級生達とは転校を機に連絡を経っている。両親は知らないが、子供だった海里はご近所付き合いなんて解らないので、懐かしの土地には実質知人はゼロになる。
(来てみたかっただけだし)
元から賑わいのない町だったが、この十数年で畳み掛けるように萎んだようだ。家族だろうか、数羽のコウモリが飛んでいくのが遠くに見えた。
(家族・・・)
海里は最後の心の拠り所である、家族三人で住んでいた小さな一軒家へ記憶を辿りに、途中迷いながら足を運んだ。見覚えのある表札や軒先には、自然と鼻がツンとした。
急かす気持ちに押されるように、向かう足が早くなる。家を見たところで入れやしないし、この町の有り様だ、もしかして売り地かもしれない。そしたらいよいよ何をしに来たんだろうと自分に笑えてしまうが、ここを曲がったら、白い壁に水色の屋根が──。
(・・・あぁ)
あぁ、他人の家になっている。
思い出の家は、丸々リフォームされてすっかり洋風な作りの新築になったいた。お洒落な表札が掲げてあるし、海里の家の面影は少しも残っていなかった。手入れもされず、荒れた庭と外観を、それでも形が残っている事を予想していた分、海里へガツンとくる衝撃が凄まじい。
潰されてぺしゃんこになったであろう我が家を思えば泣けてくるが、新しい家主の住む庭から犬が吠えてきたので海里は慌ててその場をあとにした。
心の拠り所がなくなると言うことは、心残りがないと言うことだ。
変わってしまった町並みをとぼとぼ歩き、これからを思えば気分は余計に沈み込む。日も沈み、間隔が空きすぎる街灯がポツポツと誘うように行き先を照らす。考えもなく明かりに従って足を動かせば、どういうわけか行き着いた先はかの古い洋館で、最後の灯りは役目を終えたというようにジジッと不穏な音を立ててプツリと切れてしまった。
まるで導かれたような展開に、海里の身体はゾッと冷えた。
昔見た記憶と寸分狂わず、否、余計に不気味さが増しているのは夜の闇と僅かな月明かりのせいだろうか。とにかく此処にいてはいけないと本能が警鐘を鳴らす。
・・・戻ろう。
行くあてはないが、昔感じた嫌な予感が蘇り、海里は塗装されていない道を一歩後退った。その時だった。
ガシャン、キィ・・・。
と、風もないのに長く閉ざされていた門扉がゆっくりと開いたのだ。
ギョッとしたが、金縛りにあったように足が地面からはなれない。
ドッ、ドッ、ドッ。
海里の鼓動が緊張と恐怖から大きく高鳴り、身体が震え出す。
「こんばんは」
「───────!!!」
そして中から肌の白い金髪の青年が現れたのだから、ついには声にならない叫び声をあげてしまった。
「ああ、ごめん。驚かせたね、申し訳ない」
歩み寄る青年を両手で制し、息を整える。
お化けは信じていないが、だからってまさか人間が出てくるとは思わなかった。恐怖への無駄な杞憂のせいで心臓への負担が激しいし、見ず知らずの人に奇声を浴びせてしまったのも申し訳ないし恥ずかしい。
「こんなところで何をしてるんだい?」
海里の呼吸が整ったところでにこやかに話し掛ける青年の姿が、雲の切れ間から射し込む月の明かりでよりはっきり見えた。
肌の白さ、ゆるくウェーブのかかった金髪、そして外国人のような顔立ち。
思わず魅入ってしまうが、掛けられた言葉に返す言葉が見つからない。
何をしているかなんて、自分も解らないのに。
それにどちらかと言えば、こんな時間にふらふらしている自分の方が不審者だ。海里は、いや、あの、と小さくモゴモゴと言いながら、暗い地面に視線を落とした。自分の行く先のように真っ暗だ。
「行くところがないなら、今夜うちに泊まればいいよ」
蔦だらけの煉瓦の門柱に寄り掛かる青年は親指で背後の洋館を指す。
うち、とは。
海里は思わずその洋館と青年を見比べる。かつて誰も足を踏み入れたことのないお化け屋敷だ。
「え、いや、でも此処は」
「私の家だよ。まぁ、持ち主はおばあ様だけど、日本が好きでしばらく一族で住んでいたんだ。だから僕はこの見た目で日本出身の日本育ち。日本語上手だろう?」
「う、うん」
「ほら」
手招きをして踵を返した青年は、腰まで延びた雑草を掻き分けることなく長いアプローチをすいすいと進んで行く。もう一度振り返り、ニヤリと笑ったように見えた青年は軽々と重そうな扉を押し開けた。
「どうする?」
一瞬躊躇して、人の親切に少し警戒しながらも甘えることにした海里もその後へ小走りで向かう。
門は勝手に閉じて内側から施錠されていた。
「これは我が一族の肖像画だ」
「すごいな・・・」
入った玄関は真っ暗なのも一瞬で、どこのスイッチを触ったのかすぐに部屋中が暖かいオレンジ色の光に包まれる。ユラユラ揺れているのは蝋燭のように見えるがLEDだろう。中央には豪華なシャンデリア。それをぐるんと囲む螺旋階段が各階へと繋がっている。
通された客室であろう大きな広間は西洋の王室風の家具ばかりで揃えられ、壁には音楽室で見たような厚塗りの人物画が金の額縁にずらずらと並んでいたのだから凝視してしまう。
それを一族というのだから、やはり海外の大富豪と噂は本当らしい。
テーブルには華美なティーセットが並んで、ティーカップからは暖かな湯気が上がっている。用意したての様なお茶は、まるで海里が来るのを知っていたかのようだ。けれど実際は、飲んでいる途中に自分に声をかけてくれたんだろう。柔らかな椅子の上で縮こまっている海里が横に立つ青年をチラリと見上げると、綺麗な笑顔を返された。
「気を楽にしていいよ」
「あ、ありが──」
「その方が、痛くないからね」
▽
「──は!」
海里は急に目が覚めた。
起き上がるには身体がだるい。顔を動かして天井と左右を確認するが、見たことのない部屋だ。視界に入る情報と背中の感触から察するに、初体験の天蓋付きのベットで身体が沈むマットレスに身を預けていたようだ。部屋は暗いが、部屋の四隅にほの明るくランプが付いているので見えないことはない。
ここは、ええっと。
ぼんやりする記憶を辿る海里は、部屋を閉めきるカーテンの前に、揺れる影を見た。そっちへ目を凝らせば、ゆるりと影は自分の方へ向かってくるではないか。
「やぁ、おはよう。と言ってもまだ夜中・・・丑三つ時ってとこだね」
思わず身構えてしまったが、思い出した。あの外国の青年である。先程とは違い、額を出すように髪を上げているので印象は変わるが、赤茶色の瞳にベッドサイドに灯したランプの炎が揺らめいている。
上半身を起き上がらせた海里を労るように、青年は大きなベッドに腰を下ろして背中を支え撫で上げる。
言い様のない疼きが海里の背中に走った。
「・・・あ、すみません。俺、寝ちゃったんですね」
「構わないよ。吸血との引き換えに相手には苦痛を和らげる催淫剤効果が与えられるんだけど、気分はどう?ああ、少し体温が上がってきてるね。でも気持ち悪くはないだろう?」
ペラペラ喋りながら、青年は海里の額から始まり、頬や首筋、脈を計るように手首にも触れ、仕上げと言わんばかりに手の甲に唇を落とした。
「おわっ!?」
それにはさすがに驚いて、反射的に起き上がり青年を思い切り払いのけた。顔を赤くしてわなわなと震える海里がベッドの上で身を小さくするも、青年は変わらない笑みを浮かべるだけだ。
「な、なに、なにを・・・!え、きゅうけつ?さいいん?何の話を・・・」
「君の首を噛んで血を吸った。私は吸血鬼だ。これでも150年は生きている。そして血を吸われた代償に、君も吸血鬼になったのだよ」
サラサラと流暢に何を言っているのか。
青年の行動に呆気にとられていたが、話を聞いて笑いの息が漏れてしまう。
「吸血鬼?いやいや、ないない。え、寒。なにそれ。どんなコントだよ」
「喜劇ではない。事実だ。証拠にほら」
「あっ?!」
海里の腕に鋭い爪を立てられると、あっという間に掻き傷からぷっくりと血が浮かび、たらりと垂れる。しかしそれはタイムプラスを逆再生したかのように、あっという間に皮膚がもとの通りに戻ってしまった。傷ひとつ残ってないなんてあり得ない。自身の変化に言葉をなくすと、青年は更に豪華な装飾が施された手鏡を海里に握らせた。恐る恐る覗くと映るはずの姿が映っていない。
怪我の治りが早いのも、鏡に映らないのも、海里が知っている吸血鬼の知識そのものだ。
「は、嘘だろ?なにこれ、ドッキリ?」
「フフッ。不老不死の身体もすぐに出来上がるよ」
海里の発言を一蹴するような笑みを浮かべたまま、青年は海里の口に指を突っ込んだ。親指で奥歯を探っては、うっとりとした恍惚な表情へと変貌していく。
「あぁ。もう牙に生え変わりつつあるね。実にいい」
「〜〜やめろっ!」
その顔つきに、海里は不気味さの他に身の危険を感じて青年をベッドから突き落とした。そして自分も肌触りのいいシーツが足元に絡んで危うく転びそうになったが、何とか耐えて部屋の扉へ急いで向かった。外から鍵でも掛かっているのか、いくらドアノブを回そうが、押そうが引こうがびくともしない。
「おや。もしかして帰るつもりかい?」
「そうだよ!」
「どうやって?」
「来た道を往復するだけだろ!」
「もうじき朝だ。朝日を浴びれば死ぬぞ」
それを何ともない風に、世界の常識だろとでも言うように青年が冷たく言うのだから、海里の身体が強張った。
「私と一生、此処にいるといい」
自分が吸血鬼になっただなんて、にわかには信じられないが、でも、もしかすると。
ほんの一瞬躊躇ったが、海里は青年へ振り返り、自嘲気味に笑って見せた。
「・・・両親も祖父母も死んで天涯孤独だ。いつ死んだって構わないつもりだったから好都合だよ」
死んだところで何の未練もないのだから。
悲しんでくれるような深い交じりのある友人も彼女もいないし、自分一人いなくなったところで何だと言うのか。
だからこのドアを早く開けろと口を開こうとすれば、なぜか青年は口を押さえてふるふる震えていた。心なしか、目が、好機に輝いて見える、ような。何だと海里が問う前に、青年は一瞬にして距離を詰めると正面から堂々と海里に抱きついた。
「それならやはり!君は私がもらい受けよう!」
「ぎゃあああ、あああっ!?」
抱きつかれた事で一度叫び、青年の背後の天井からコウモリの大群がキィキィと鳴き、踊るように舞い始めたのだから二度も叫んでしまった。
理解が追い付かない。
「だぁいじょうぶ!天国のお母様にもお父様にも、おばあ様もおじい様も泣いて喜ぶような君の豊かな毎日を約束しよう!だから君を私の同胞にしたんだ!ほら、契約の契りを交わそう!そうしたら我々は生涯番となり永遠のパートナーだ!」
「えっ、怖っ!無理無理無理!!」
再びベッドへ海里を連れていこうと手をぐいぐいと引っ張る青年に抗いつつも、目はコウモリを追ってしまう。
まさかこれ、ずっと天井にいた?
何匹かは青年の肩や頭に懐くように止まり、ついでに海里の頭にも止まるものだからこっちも追い払わなければならない。
「くそっ!何で俺なんだよ!」
「おや、知りたいかい?」
まるで理由があるかのような口振りに、海里の目が丸くなる。
秘密を打ち明けたくてたまらない子供のように、うずうず、きらきらしている青年に、海里は握られた手を急いで引き抜くと少しの距離をとり、恐々と小さく頷いた。
「そうだな。まず私の親族は世界大戦を機に祖国ルーマニアへ帰郷したのだが」
「ルーマニア・・・」
吸血鬼発祥の地。
ガチじゃないかと、げんなりしてしまう。
「私は日本育ちだし、爆撃にあったところでこの身体はどうともないし、この子達と此処に残っては荒らしに来る奴らを門前払いしたり、意趣返しをして遊んだり、何不自由なく毎日暮らしていたのだが」
この子達、と青年は指に止まらせたコウモリに頬擦りすると、コウモリも応えるように身を擦り付ける。その様子に海里は祖父母が飼っていた文鳥を思い出す。海里の方が後から家族になったのに、ずっと懐いてくれた可愛い子だった。もう天寿を全うしたが、似たようなものだろうかとどこか懐かしい気持ちになってしまう。
「君があの日、あの時、私の前に現れたから欲してしまったのだよ」
「・・・あの日?」
「うーん。君の年は五、六歳といったところか?日本人は年齢が解りづらい」
見た目ハタチの150歳が言うことか。とは思ったが、ここはスルーを決め込むことにする。
「とにかくあの日、君が振り返ったら仲間にして、ずぅっと私の手元に置いておこうと思ったんだよ。それがまさか今になって夢が叶うなんてなぁ。長生きしてみるものだね」
思い返せば六歳の頃、かつての友人とこの屋敷を訪れたことがある。しかし外観の不気味さで、すぐに帰宅したはずだ。中になんて入っていないし、誰にも──この青年にも勿論会っていない。
しかし海里は思い出す。
あの日、あの時、振り返れば何かに食われてしまいそうな悪寒を感じたことを。
まさか、屋敷の中から自分を見ていたのか。悪寒の正体は彼だったのか。
「今日、君を見かけたと報告を受けた時は胸が高鳴ったよ。無事にこの屋敷へ来てくれてありがとう」
「報告?」
眉間にシワを寄せた海里が聞き返すと、青年の肩に止まっていたコウモリが気まずそうにプイッと背くと、ソソソッと彼の首の後ろに隠れてしまった。
ああ、夕暮れ時、コウモリを見たな。
ここまできたら、もううんざりするしかない。
「しかし小さい頃の君も愛らしかったが、成長した姿も乙なものだね」
「ショタコンかよ。最悪だ」
「違う違う。君が、良かったんだよ。二度と会えないと思ったからね、有無を言わさず同胞にしたのは悪かったが、後悔はしてな──ぐわっ!」
いけしゃあしゃあと言うものだから、海里も初めて人を殴り飛ばしてしまったが後悔はしていない。そもそも吸血鬼だから人間じゃないし。コウモリ達が慌てて彼に集まってる姿は胸に刺さるものがあるが、元凶は君達のご主人様だと思えば痛んだ良心の回復も早かった。
「親に顔向け出来ないだろ。なんだ、子供が吸血鬼になって不老不死になったなんて」
「うん?その親は、もういないんだろう?」
悪意もなさげに、心配からピィピィ鳴いているコウモリ達の頭を撫でる青年は不思議そうに小首を傾げた。
この男はなぜ、逐一琴線に触れてくるのか。
海里のこめかみの青筋はぶちギレた。
「は〜〜あ!?天国で泣くわ!天国で親もじーちゃんもばーちゃんも肩身狭いだろ!周りからお宅の息子さん吸血鬼になって人襲ってますわよとか言われてたら悲惨だわ!かわいそ過ぎるだろ!俺だってこんな風に生きたかないわ!さっさと此処から出せよもう!」
「人の血を吸わなくとも、しばらくは赤ワインと生肉で食い繋げるから心配はない。此処からは出さない。私とずぅっと一緒にいると約束してくれ」
「無理っ!」
「あいたっ!」
約束、と出された小指を逆方向に折り曲げると、変な音を立てて青年が痛がったが、それはすぐに元に戻る。
ああ、ああ。いったい何が何で、どうなったのか。どうなるというのか。
海里は目の前が真っ暗になった。
「ちょっと待って、疲れた・・・」
「ん?」
「久しぶりにたくさん歩いたのと、大きい声で話したから、苦しい」
「おまけに催淫効果で興奮しているんだろう。難儀だな」
どの口が、と睨んだつもりが、身体に力が入らない。膝から絨毯に崩れ落ちてしまう。眠気とも違うが、目はとろんとしてくるし、確かに身体が興奮状態にあるようで息も上がるし身体も熱い。
ってゆうか、催淫剤効果とは難だ。
荒い息を吐きながら青年を見上げると、膝を折って海里の顔を覗き込み背中を撫でる。
「まあまあ。聞きたいこともあるだろうし、私も話したいことはたくさんある。しかしまずは、その身体を落ち着かせることが先決だ。そうだろう?」
そしてあっという間に海里の身体を抱き上げると、再び天蓋付きのベットに逆戻りされてしまった。
「ようやく身体中に媚薬効果が回ってきたね。さては君、酒には強いタイプだな」
楽しそうに何か言う青年に、言葉を返す気力も、身体を跳ね返す体力も海里にはなかった。
それから。
夜な夜なお化け屋敷から男の怒声と子供には聞かせられない怪しい声が聞こえてくると言うことで、新たな心霊スポットとして長年にわたり語り継がれることとなる。
ただし声の正体を見たものは誰一人帰ってこなかった。
おわり
門扉開け閉めしたのも部屋の明かりつけたのもお茶の用意したのも全部コウモリちゃん。
吸血鬼の名前出なかったな。
「159」に続く。
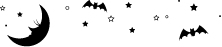
小話 158:2021/11/17
次|小話一覧|前