136
「こんな時にならないと、言ってくれないんだね」
真っ白で大きな入道雲が浮かぶ真夏の青空。
ミンミンと蝉が、カンカンと踏切の警告音が。
じりじりと照りつける太陽に流れる汗。
陽炎立つアスファルト。
それらを背負った夏服の制服姿の彼は、困ったように笑って、そして泣きながら皮肉に言った。
「好きだって」
ハッと目が覚めた。
今でも夢に見る十八の夏。こめかみを伝う汗を腕で拭うと、その腕も汗でじっとりと湿っていた。朝から暑い夏の朝、蝉はすでに鳴いていた。
わずかに開いていたカーテンの隙間から入る直射日光、高温、そして蝉の声。
あの日の夢を見た要因はこれだろうかと朝から重い溜め息をついた。
暑さのせいだけじゃない、嫌な汗だ。
「最っ悪・・・」
手にしたスマホの示す時刻は六時三分。休みの朝にしては早い時間に目が覚めたものだが、もう二度寝する気にもなれないので風呂場に向かう。この汗と夢に見た光景を洗い流したかった。
□
「あ!嘘!当選した!チケット確保できましたって!」
「えっ!マジで!?俺だめだったんですけど!」
「やったー!ライブ行けんぞ!」
「うわーっ!」
興奮のあまり勢いよく両手でバチっとハイタッチして、お互いに痛いと喚きながらも爆笑した高二の夏。
高校生という青春時代を一番長く共に過ごしたのは、多分舜也だ。家族を除けば。
右目の下に縦に連なる泣きぼくろが二つあって、笑ってるのに涙が流れてるみたいだなってのが舜也の第一印象だった。けれどそれとは正反対に、舜也は底抜けに明るい奴で、一年生の初対面の頃から馬が合って、好きな音楽もノリも合って、ほぼ毎日一緒につるんでいた舜也と、高二の夏に好きなアーティストのライブに参加を決めた。同じバイト先で同じくらいの額を貯めて、先行申し込みも同時に申し込んで、当落発表の日まで同じようにソワソワしたりして。
結果、俺のエントリー分が当選。二人でバカみたいに「やばいやばい」を毎日繰り返して、迎えた当日色違いのライブTシャツを着込んで張り切って、最高に楽しかった。
「なあ、俺、シゲが好き」
ライブ後、退場しようとする興奮冷めやらぬファン達のうごめく波の中、くん、と舜也が俺のライブTシャツを引っ張った。
なに、と振り向くより先にそう告げた言葉に、周りの何人かが視線をくれる。
「・・・ありがとう?」
「うん」
「何、どしたの、急に。照れる」
「ん〜。なんてゆーか、思った時に伝えとかないとなって。今日めっちゃ楽しかったし、シゲと来れてよかったなーって、しみじみ思っちゃってさ」
「なにそれ」
ライブで何かに感化されたのか、もしかして日頃からそう思っていたのか、舜也は変に照れたり笑ったりもなく、ころりと言葉を吐き出した。
それから、それをきっかけに舜也は俺に対して「好き」をよく伝えるようになってきたのを覚えている。
体育祭の二人三脚で一位をとった時、購買で買ったパンをひとくち分けた時、舜也が取り損ねたノートを貸した時。本当にもう色んなシーンで、ちょっとしたことで、「好き」を言う。
安売りしすぎじゃ?と思ったけど、舜也は俺にしか「好き」を言わないし、それを言うときの表情は本心だと告げてるように、柔らかくて優しくて。
それでも、舜也が何でも話せる友人と言えど「好き」というワードは俺にとっては照れくさく、舜也に言われる度に「ありがと」って、「大袈裟だな」って軽く笑って、受け流してばかりいた。
本当は悪い気はしなかった。むしろ心地よかった。
舜也が他者から「好き」を貰う度、やわりと断っているのを知ると、ひどく安堵したし、高揚した。
多分、きっと、いつからか舜也が俺に向ける「好き」が恋愛のものだと、そして自分もそれが嬉しいのだと、ジワジワと実感していた。俺と舜也の間に漂うものが以前より少し違うものだと、お互いにちらちらと感じてはいたと思う。
けれど俺は、やはり舜也に「好き」を告げることができなかった。
舜也のいる毎日は当たり前で、また明日と手を降るのも日常の一部で、三度目の夏を今年もまた変わらず一緒に過ごすんだろうな、今じゃなくてもいいんじゃないか、なんて思っていたからだ。
そして悪夢の夏の日だ。
明日から夏休みという日の朝、教室に違和感を感じた。舜也が登校していない。机がなぜか寂しい気がする。
ホームルームで出席をとる担任は、舜也が休みで、今日このあとの一日の流れを軽く確認していたが、急に歯切れ悪く黙りこくった。
「あー。あとな、今日休んでる琴岡なんだが、実は──」
鞄もスマホも置いて教室を飛び出した。
いや、昨日まで俺と一緒に下校したじゃん。教材を俺みたいに置きっぱなしにてたじゃん。「また明日」って言った舜也を当然のように信じてしまった。だから気付かなかった。
──実は、ご両親の都合で海外へ引っ越しするんだ。前から決まっていたことで、本人からの強い意向で最後まで口止めされていたんだが、まあ連絡をとれるやつはこれを最後と思わずに、これからも良き友達として──
教室と机の違和感。舜也だけじゃなく、荷物が消えていたからだ。
時刻はまだ朝礼の時間だ。教師に挨拶をして荷物を引き上げに来たなら、もしかしてまだ間に合うんじゃないかと足をフルに動かした。走るとお腹が痛くなるのはインナーマッスルが鍛えきれてないから内蔵が揺れるせいだよ。冬のマラソンで息も絶え絶えな俺の隣で余裕ぶって笑うどうでもいい舜也のうんちくを思い出してしまった。
パラパラ漫画をめくるように、俺と舜也の今までがバァッと浮かぶ。どのページを開いても、登場人物は俺と舜也だけだ。
おい、なんだ、俺達の話はここで終わるのか。
荷物をスクールバックに詰めた舜也を見つけたのは、舜也の家へ向かう路線電車が走る駅だった。
踏み切りの向こう、カンカンと音を鳴らしながら遮断機が降りてくる。電車の姿はまだ見えない。
「シュン!」
ピクン、と後ろ姿の頭が上がった。
「っ、シュン!ごめ、ごめんっ!」
ああ、走りすぎて腹が痛い。息を切らしながら話すのなんてクソダサい。舜也の言う通り、インナーマッスル鍛えとけば良かった。
電車の迫る音が聞こえてくる。
「俺、お前が、ずっと好きだった!」
振り返った舜也が目を丸くしていた。
けれどそれが、すぐにクシャリと歪んだ。初めて見る顔だった。
タタン、タタン、と規則正しい音で電車はもうすぐ来てしまう。
「何で、最後になって言うの」
あの夏の日を、俺は忘れることが出来ない。
俺が逃げ腰で、ずっと舜也からの「好き」を避けていたせいで、最後の最後に引き留めるような、追い縋るような、もう遅い残酷な「好き」を返したせいで、舜也を泣かせてしまったからだ。
目を見開いて、困った風に笑って、涙を流して、あいつは確かに言ったんだ。
「こんな時にならないと、言ってくれないんだね。好きだって」
ゴォッ、と、電車が舜也の姿を拐うように消してしまった。
□
呪いのような言葉だ。
永遠なんて、ずっとこのままなんて、そんなものはないんだとようやく気付いた時にはもう遅かった。
俺の甘さ、卑怯さ、ずるさをズバリと責め立てる舜也の言葉は十八の俺にはひどく堪えて、いまだに俺の心を締め付けている。
シャワーのコックを捻って止める。
ほぼ水のような温度を被り続けて、ようやく目と思考が覚めてきた。適当に掴んできた下着とTシャツを着て、雑に髪を拭き上げる。寝室に戻る途中、廊下に昨夜から置きっぱなしにしていた、海外から持ち主と共にやってきた赤いトランクケースが目に入る。
「おい、朝」
「おーきーてーるー・・・」
「嘘つけ」
「てかいま何時ぃ・・・」
「六時半」
「・・・早くなぁい?俺、時差ボケあるんだから・・・」
もぞもぞと動く手が俺の手を掴んだ。
伸びた手から辿る腕や肩、上半身はいまだ裸だ。下半身はシーツが被さっているけれど、パンツが床に落ちたままだから多分全裸なんだろう。
枕に顔を半分埋めたまま、ボサボサの髪の間から特徴的な二つの泣きぼくろを連ねた目元が弧を描く。
「もうちょっと寝ようよ、ね、シゲ」
□
電車が通り過ぎた後に上がる踏み切り。
姿を消すものだと思った彼が駆け寄ってきた。
「──遅いよ、ばぁか」
舜也が俺の手を取り泣きながら笑ったあの日の夏を、俺は一生忘れない。
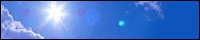
おわり
小話 136:2020/03/14
次|小話一覧|前