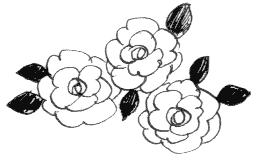二:5/7 夜勤明け
「んなボーっとしながら歩いてんじゃねえや。今からどこ行くんですかィ?」
よく見ると、目が赤い。瞬きの回数も多く、少し水っぽい。その症状は、最近鏡の前で目が合う自分の姿と酷似している。
(まぁ、赤いけど腫れてはねえみてぇだし……)
要するにあれだ、俺と同じく寝不足だと思う。
「えっと、お店に」
時間としては、今は朝の6時台。7時開店のあの店への出勤時間としては何らおかしくはないのだが、気になる点がある。
「その恰好で?」
店ではいつも着物姿なのだ。しかし今は違う。初めて会った時と同様に、和装ではない。かといってあの時のようなワンピース姿とも違う。似合わないというわけではないのだが、かなり雰囲気が違って軽装だ。
「はい、今日は掃除に行くので」
「掃除?」
「はい、営業再開に向けて」
「…………あー、はいはい」
(はいはいはいはいはい、忘れてた)
そういえば、この連休中は店を閉めて孫に会いに行くだの何だの言っていた気がする。だいぶ前から聞いてはいたが、すっかり頭から抜け落ちていた。
「そういやあ休みか。次、店いつからでしたっけ?」
「明後日からです」
ここ最近はちょうど忙しくて顔を出せていなかったから良かったが、もし通常の仕事量に戻っていたら普通に行ってたわ。危ねえ危ねえ。
(つーか、じゃあナマエちゃんも休みだったってことか)
「ずいぶん長ぇ休みですよね。あんたの目が赤えのは、おおかた夜更かしでもしたってとこですかィ」
「はは……お恥ずかしながら、昼夜逆転してしまいまして」
「夏休みのガキかよ」
気まずそうはにかみながら、髪に手櫛を通す。「生活リズム戻さなきゃ」と言いながら毛先まで通すと、その毛束を背中側に払い除ける。髪を下ろしているせいなのか、ふわりと靡くと柔らかい香りが漂う。
(……うっわ、)
肩を叩いた時から気付かないフリをしていたがもう限界らしい。清潔感のある石鹸のような甘いにおいの中に、控えめに主張してくる金木犀。彼女の“女”の部分が俺の鼻腔を暴力的に刺激してくる。
(寝不足の体に、女の匂いは毒かもしれねぇ)
あぁ、そういえば女ってこんな匂いのする生き物だった……とか。思考回路がそれこそ夏休みのガキ同然にまで低下しそうになる程に。それもこれも連日朝から晩まで男とべったり、朝日まで一緒に拝んじまうくらいの激務を柄にも無くこなしたせいだ。
「金木犀?」
「え?」
「あ、やべ……いや、今日、なんか香水とか付けてやすか?」
付けてる香を言い当てるとかちょっと……いや、結構キモいかもしれない。ある程度親密な仲ならまだしも、俺達の距離感はそれを軽い雑談として話題にあげられるほどのものではない。だが口に出してしまった以上、言い淀むよりは一層のこと聞いてしまう方がこの際潔い。
「すみません。苦手でしたか?」
「いんや。普段付けてたっけって思っただけでさぁ」
「飲食店なので、仕事中は付けてませんね。今日はお休み中の癖で、つい」
まあ確かに、飯処で働いている人間が香水を身に纏うのは暗黙のタブーなのかもしれない。今日は掃除しかないと言っていたし、セーフだと思うが。
何となく、店では見ない一面を見たというか。休みの日は女らしく色気づいたり着飾ったりしているのだろうか。
(……いや、)
こいつは元々、誰が見ても女らしすぎる程に女らしいと思う。初めて会った時も似たようなことを思ったが、妙な色気がある女なのだ。
腰より下、太ももあたりまでの長さのオーバーサイズのTシャツにデニム。露出も少なく体のラインが隠れるような恰好をしているにも拘わらず、長い髪が垂れ下がる白い首筋、長袖からチラリと見える細い手首に勝手に目が行く。
『精々巻き込まれねぇよう休みの日は家で大人しくテレビでも見ときなせぇ』
たしか最後に店で会った時、彼女にそんな忠告をした。とはいっても俺の発言で彼女の行動を縛れるようなそんな拘束力はないし、そんな間柄でもない。実はもう知らない間に友人の一人や二人こさえているかもしれないし、俺の忠告なんか無視して夜な夜な街へ一期一会という名の遊びに繰り出しているかもしれない。ただ、どれも想像に過ぎず断言できる話では無い。
(……まぁ、)
今この瞬間、目の前でこうして面を突き合わせて話しているのだ。それが結果的にこの連休中、何事もなく無事だったという一番の証拠。そこまで気にする必要はないだろう。
「……ナマエちゃん」
「はい」
名前を呼ぶと短い返事をして、いつもの見慣れた微笑を向けてくる。こういう女をたぶん、聞き上手、喋らせ上手と言うのだろう。完全にこちらに会話のボールがあって、それを投げてくるのを余裕たっぷりに構えているように見える。
(……、一人の時、)
この女は、どんな顔をしているのだろうか。一週間以上あったであろう休日を彼女が実際どのように過ごしていたのか。正直、俺には全く想像がつかない。
『江戸に誰も知り合い居ないって言ってたからねぇ。寂しいんだろうねぇ、なかなか休みたがらないんだよ』
『しっかりしたお嬢さんですがね』
『だからこそだよ。頼り方のわからない不器用な子なんだ』
『まぁ確かに心配ではありますね。気丈に振る舞っているようにも見えて』
自分より一回りも二回りも長く生きている人間の意見を参考にするならば、今目の前で笑っている女は無理をしているのということなのだろうか。あの時店で繰り広げられていたおばちゃんとイケオジの会話に、俺は疑問符が浮かんでいた。しかし、今は少し賛同できるような気がする。
(……さっきみたいな顔してんのかねぇ)
先程通り過ぎて行った彼女の表情。そもそも、俺が声を掛けたのはそれが理由だ。
また目の前を見ているフリをして、別の光景を写しているのだと思った。しかし近づくにつれて見えてきたその双眸は、別の光景どころか“何も見ていない”気がした。そう思ってしまう程、その表情には光も影も何一つ際立つものが感じられなかったのだ。
(例えるなら、アレだ。落とし物の人形みてえな)
駅とか、テーマパークとか、それこそ何の変哲もない道端とか。落として忘れられてしまって、ポツンと佇む。そんな居場所や行先を見失った人形のような表情をしていた。
『もし街で見かけたりしたら気いかけてやってくんないかい?』
このタイミングでようやく、おばちゃんにそんな事を言われていたことを思い出した。どうやら俺は、その言葉を思い出すよりも先に体が先に動いたらしい。
(なんつーか……このままいなくなりそうで、)
何を考え、どこへ向かっているのか。まったく真意が読めない。そんな彼女を見て、追い掛けた方が良い、という切迫した気持ちに急かされた。
いつもよりも小さく見えたその背中に、次に店に行った時にはもういなくなっているのではないか、とさえ思った。仮に店主夫妻から「突然店辞めちまったんだよ」と言われても、俺はそれに対して「あ、そうなんですかィ」とたった一言で片付けざるを得ない。あぁ、やっぱり……と。自ら消息を絶ったのだろう、と。そう思うから。
しかし、あの二人は違うだろう。「あの子がどこへ行ったか知らないかい?!心当たりとかないかい?!」とすごい剣幕でうちの屯所に飛び込んでくる姿が浮かんでしまう。
(……つってもなぁ、)
正直、俺には何も思い浮かばないし想像もつかない。それは他の常連客もそうだろう。
良い子だった、綺麗な人だった、優しい人だった。嘘ではなく本音だとしても、そんな月並みな言葉を並び立てる。でも何が好きなのか、とか。行きそうな場所、懇意にしている人間。何も思いつかない。そして最後には皆、口を揃えてこう言うだろう。
“よく考えてみたら、あの子の事全然知らない”
何となくあの店主夫妻が、俺と彼女を関わらせようとしている気配は薄々感じてはいた。嫌がる相手を無視して強引に、というわけでもないし、勿論面白がってそうしているわけでも無いだろう。『家族がいない』と言っていたナマエちゃんに対して、あの店主夫妻が親のように気を掛けるのは自然な流れだと思う。だから気付いていてもスルーしていた。
『総悟くんがナマエちゃんと仲良くなってくれたなら安心だねぇ』
(あれはつまり、仲良くなれと)
そういう事なのだ。例えば、厠で“いつも綺麗にご利用いただきありがとうございます”という貼り紙を見たことがあるだろう。あれと同じだ。もう仲良くなっている前提で話を進めてしまう。こちらもそれ相応の行動を取るのが当然だと思わせる、一種の刷り込みだ。
(にしても、なんで俺に……いや、)
考えてみれば、案外単純な理由だと思う。まだ俺には親心やら何やらの立場になってまで想像することは出来ないが、女一人で何かと物騒な江戸へ出て来たのだ。だからこそ、交友関係を広げてほしいのだろう。それはまず自分達の手の届くところ、安全の保障が出来る範囲から。その選択肢が野郎だらけの常連客しかないというのであれば、普段の店主夫妻への態度を含め、歳の近い警察の俺に声が掛かるのは不思議な事ではない。自分でも選抜されてもおかしくないと思う程、あの店での俺は少し猫を被っているのだから。
(なかなか面倒な事押し付けられてる気がしなくもねぇが……)
「あの……総悟くん?」
「……あぁ、すいやせん」
思いのほか長考してしまった。名前を呼んだあとの沈黙に耐え切れなくなったのか、斜め下から掬い上げる上目遣いを寄こして来る。そして様子を窺うかのように、長い睫毛に縁どられた瞳をぱちり、ぱちりと瞬かせる。
(……やっぱ、目ぇ引くんだよな)
正規の手続きを取って店を辞めて、自らの意思でいなくなるってんなら、正直俺の出る幕は何もない。ただ、失踪だとか、行方不明だとか。いつかそんな事態もあり得るのではないか、と根拠のない不安が過る。それは初めて会った時に、男に囲まれていたあの状況を目の当たりにしたせいかもしれない。あの店主夫妻も、彼女が何か厄介事に巻き込まれた際の心配も含んだ上での“俺”という選択肢なのだと思う。
(だったら、)
もう一層の事、先手を打っておいた方がのちのち楽だろう。手綱を握ってしまえば良いのだ。自分の目も、手も、声も届くように。それが一番手っ取り早い。
「あの、店に5月の休みって貼ってやすよね」
「はい」
「写メ撮るの忘れちまって。今から店行くなら、あとで撮って送ってくれやせんか?」
嘘ではない。あそこは不定休なので、いつも前月に翌月の休みを書いた紙が壁に貼りだされる。しかし先月は撮り忘れてしまっていて、そのことに気付いたのは今この一連の会話の最中。連休のことを失念していたのもそのせいだ。
「良いですよ」
「すいやせんね。んじゃあ連絡先、良いですかィ?」
「はい」
懐から携帯電話を取り出して見せると、彼女も手提げ鞄の中から自分のものを取り出した。
「店に着いたら送りますね」
「頼みやす」
連絡先を交換して、お互いに携帯電話を仕舞いながら言う。
「んじゃあ、また店行きやすんで」
「はい、お待ちしてます」
そう言った彼女の表情を見ると、少しキュッと跳ね上がった目尻のライン。いつもよりクシャっとした笑顔が、大人びている彼女を可愛らしい印象に見せる。
(……ま、普通に笑ってくれる分には構わねえや)
それが決して俺に対して向けられたものではなく、瞳の奥にあの店主夫妻を宿したが故の笑顔だとしても。
俺は彼女に背中を向け、手をひらひら振りながら歩き出した。そして数歩歩いたその先、右手に見える細い路地の中へ入る。そこには『先に帰れ』と言ったにも拘わらず、趣味の悪い覗きをしていた瓶底眼鏡野郎がニヤニヤしながら待っていた。
「隊長って、あんな感じで女の子の連絡先聞き出すんですね」
「……」
「隊長にも年相応の一面があるんっすねぇ〜いやぁ、良いもん見れましだあぁぁぁう!!」
俺はクリップが利く厚めの靴底の踵で、思いっきり神山のつま先を踏みつけた。
(2023.5.7)