君待つ宵
厚手のコートにマフラー、帽子。
できうる限りの暖かい恰好をして、幸村はドアノブに手をかける。
廊下に出ただけで防寒した筈の衣服から寒さが伝わってきた。
冬の真夜中はことさらに寒い。
白い息を吐きながら、彼はマンションの階段を一歩ずつ登っていった。
皆が寝静まっている無音の空間に、靴の音がやたらに大きく響く。
「今夜もいるのでござろうか」
階段の終わりまで登り切って、幸村はそう呟くとそっと目の前のドアを開けた。
ぎぃぃっと重たい音と共に冷たい風が己の頬を撫でる。
あまりの寒さに身震いしながら前を見ると、満点の星空の下にいつもの人物はいた。
「こんばんわ、旦那」
床に膝を立てて座り、空を見上げていたお隣さんは、幸村の姿を見て柔らかく微笑む。
「佐助」
幸村はパタパタと近寄って、彼の格好を見て眉を顰めた。
「こんなに薄着で……風邪をひくぞ」
幸村はしっかりと厚着している一方、佐助は薄手のカットソーにジャケットという真冬の夜に出かけるには不釣り合いな格好をしていた。
「大丈夫、寒さには強いんだ」
佐助は幸村の咎めるような視線すら心地よいとばかりに、そっと目を閉じる。
「何でだろうね。あんまり寒さが気にならないんだ」
「しかし……」
幸村はなおも言いたそうにしたが、佐助の様子を見て隣に腰を下ろした。
白い息が空へと舞いあがる。
光りのない地上から見上げる星空はとても美しかった。
「旦那こそ、この寒い夜に毎回来なくてもいいんだよ?」
「俺が行かなければ、お前は一晩中ここにいるのだろう?」
「あらら、わかっちゃうんだ」
上目使いに図星を指されて苦笑する佐助。
「でも、心配はいらないよ。俺様も眠くなったらちゃんと部屋に帰るし」
「そんなことを言っているのではない」
白々しくおどけて見せる佐助に、幸村は溜息をついた。
「わざわざこんなところで待たずとも、会話をしたくなったら俺の部屋にたずねてくればよいのだ」
「それだと、優しい旦那は独りになりたい時でも、眠い時でも俺様を部屋に入れちゃうでしょ? それは嫌なんだ。旦那を俺の我儘に付き合わせたくない。邪魔者だとも思われたくない」
思わず見た佐助の横顔はどこか愁いを含んでいて、幸村の心は痛んだ。
「俺はお前を邪魔だと思ったことはないし、我儘はいつも俺の方が言っているぞ」
そっと呟いた幸村の言葉に佐助はそっと首を振る。
「戦も何もない今の世の中じゃ、俺は旦那にとって何でもないんだ。もう、互いを縛るものも繋ぐものもない」
「……」
――本当は、アンタのことを探すべきではなかったのかもしれない
そうした呟きを、佐助は口の中で噛み締めている様子が見て取れる。
そんな彼の心中を想いながら、幸村はそっと過去に想いをはせた。
戦国時代。彼らは共に命を預けて戦った。
佐助は幸村の命を護ろうと。
幸村は佐助の心を護ろうと。
依存しあう2人の存在はまるで光と影のように、離れられないものへとなっていく。
互いが互いを、互いがいなければ自分でいられなくなるような危うさを抱えて死と隣り合わせの生活を送っていた。
その記憶を持ったまま再びこの世に生まれた幸村は、時代は変われど環境はさほど変わらなかった。
父や兄は優しかったが、母には前世同様に疎まれ育った。
昔は10を過ぎれば元服にもなるが、今は20歳にならないと大人と認めてはもらえない。
もどかしさの中で歯を食いしばり、大学入学と共に家を出た。
恵まれていたのは、幼馴染として過去の好敵手や見知った人たちがいたことだった。
家で辛いことがあっても、友人たちといる時は純粋に楽しかった。
けれど、そこに己の影はいなかった。
そして、幸村が独り暮らしを始めた頃、彼の隣に佐助が越してきたのだった。
――久しぶり、旦那
挨拶に三色団子を持って玄関に立っていた佐助は、社会人特有の落ちついた微笑みを幸村に向けた。
しかし、隣に越してきたものの、佐助は幸村の部屋を訪れはしなかった。
幸村としては話したいことも聞きたいこともたくさんあったが、仕事が忙しいのだろうと気を遣い、彼からも佐助の部屋の前に立つことはなかった。
ふと、夏の星の綺麗な夜。
あまりに部屋の中が暑く、幸村は近くのコンビニまでアイスを買い、夜空を見ながら食べようとマンションの屋上へと足を伸ばした。
そこに、佐助はいた。
――嗚呼、やっと来た。旦那
そう言ってニッコリと笑う彼に、莫迦野郎としか言えなかった。
ずっと待っていたのだ、佐助は。
「くしゅん」
小さなくしゃみが屋上に響く。
「旦那、大丈夫?」
「今日学校で手袋を落としてきてしまって、手だけ冷たかったのだ。心配はいらぬ」
そう言って笑う幸村の手は寒さで真っ赤になっていた。
ふぅと息を吹きかけて暖めようとする幸村の姿を見て、佐助は己の指で彼の手を包む。
厚着をしていても氷のような幸村の手に比べて、薄着にもかかわらず佐助の手は温かい。
「とりあえずはこれで我慢してよ。今晩はもう帰ろう。……でも、もう少しだけ星を見ていたい」
佐助の温もりに指先がじんわりと暖かくなっていくのを感じながら、幸村はそっと頷く。
――俺に会いたくなったら、屋上に来て。夜はずっとそこにいるから。
そう言う佐助の顔がどこか儚くて、幸村はそれから毎日、彼に会いに屋上に向かうようになった。
星空が見たいと佐助は言うが、本当は己を待っているのだと幸村には分かっていた。
毎晩毎晩夜遅くまでこんなところにいて、仕事はちゃんとできているのか心配になるが、過去に己が大将になってからもほとんど眠っていなかったことに気づく。
生き残ることが難しい動乱の世の中では、命を懸けた絆が互いを結び付けているのだと思っていた。
共に武田を護るために必要としているのだと。
しかし、今はそんなものはない。
なくても互いを必要としている。
何のためなのか、その先に何があるのか、何も分からないまま。
只、その存在を求めている。
過去に主従だった関係がなくなった今、新しい関係を築いていけばいいと幸村は思っていた。
主従ではありえなかった、本当の兄弟のように絆を結ぶことも今なら可能だろう。
友として、年上の兄として、幸村は佐助を素直に敬える。
そう伝えると、佐助は少し傷ついたように笑っていた。
「綺麗だね、昔はそんなこと思えもしなかったけど」
ポツリと呟く佐助は、繋いでいた手をふいに強く握った。
そっと彼の様子を窺えば、星に見惚れている彼は己の手に気づいてはいない。
この真夜中の逢瀬でさえ、佐助はどこか引け目を感じているようだった。
彼の真意はわからない。
今までも、佐助は己の心の内を見破っても、己が佐助の心を見破ったことはなかったから。
きっと、彼は全ての気持ちを隠し通し、己の言葉など聞きはしないのだろう。
ならば、彼の心が変わるまで、己は彼の傍でゆっくり待とうと思う。
どれほど時間がかかろうとも、彼の望む関係の形がどのようなものであろうとも、己はきっと受け入れられる。
他でもない、己の影なのだから。
「そうであるな。人の心も、時代も変わっていく。然れども、星はいつの世にも瞬いておるのだな」
己も再び空を見上げ、佐助に気づかないように手に力を込め返す。
白い息が満天の星空に溶けた時、スッと星が流れて行った。
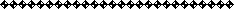
↓ゴマ様の【訳】から抜粋
この小説は、『糸切りサロメ』と同時期に書いたものです。サイトの方向性をグロ系か切な系か迷っていた時に、2つの作品を書き比べていました。結果としてグロ系になったのですがw
こういった、恋人未満な関係が好きなのですが、もっと糖度高いお話がお好きな方には物足りなく感じられるかもですが、お付き合いいただけると嬉しいです。
ダテサナも好きですが、同じくらい佐幸も好きなので最後に更新できてよかったです。
[ 120/194 ]
[*前へ] [次へ#]
厚手のコートにマフラー、帽子。
できうる限りの暖かい恰好をして、幸村はドアノブに手をかける。
廊下に出ただけで防寒した筈の衣服から寒さが伝わってきた。
冬の真夜中はことさらに寒い。
白い息を吐きながら、彼はマンションの階段を一歩ずつ登っていった。
皆が寝静まっている無音の空間に、靴の音がやたらに大きく響く。
「今夜もいるのでござろうか」
階段の終わりまで登り切って、幸村はそう呟くとそっと目の前のドアを開けた。
ぎぃぃっと重たい音と共に冷たい風が己の頬を撫でる。
あまりの寒さに身震いしながら前を見ると、満点の星空の下にいつもの人物はいた。
「こんばんわ、旦那」
床に膝を立てて座り、空を見上げていたお隣さんは、幸村の姿を見て柔らかく微笑む。
「佐助」
幸村はパタパタと近寄って、彼の格好を見て眉を顰めた。
「こんなに薄着で……風邪をひくぞ」
幸村はしっかりと厚着している一方、佐助は薄手のカットソーにジャケットという真冬の夜に出かけるには不釣り合いな格好をしていた。
「大丈夫、寒さには強いんだ」
佐助は幸村の咎めるような視線すら心地よいとばかりに、そっと目を閉じる。
「何でだろうね。あんまり寒さが気にならないんだ」
「しかし……」
幸村はなおも言いたそうにしたが、佐助の様子を見て隣に腰を下ろした。
白い息が空へと舞いあがる。
光りのない地上から見上げる星空はとても美しかった。
「旦那こそ、この寒い夜に毎回来なくてもいいんだよ?」
「俺が行かなければ、お前は一晩中ここにいるのだろう?」
「あらら、わかっちゃうんだ」
上目使いに図星を指されて苦笑する佐助。
「でも、心配はいらないよ。俺様も眠くなったらちゃんと部屋に帰るし」
「そんなことを言っているのではない」
白々しくおどけて見せる佐助に、幸村は溜息をついた。
「わざわざこんなところで待たずとも、会話をしたくなったら俺の部屋にたずねてくればよいのだ」
「それだと、優しい旦那は独りになりたい時でも、眠い時でも俺様を部屋に入れちゃうでしょ? それは嫌なんだ。旦那を俺の我儘に付き合わせたくない。邪魔者だとも思われたくない」
思わず見た佐助の横顔はどこか愁いを含んでいて、幸村の心は痛んだ。
「俺はお前を邪魔だと思ったことはないし、我儘はいつも俺の方が言っているぞ」
そっと呟いた幸村の言葉に佐助はそっと首を振る。
「戦も何もない今の世の中じゃ、俺は旦那にとって何でもないんだ。もう、互いを縛るものも繋ぐものもない」
「……」
――本当は、アンタのことを探すべきではなかったのかもしれない
そうした呟きを、佐助は口の中で噛み締めている様子が見て取れる。
そんな彼の心中を想いながら、幸村はそっと過去に想いをはせた。
戦国時代。彼らは共に命を預けて戦った。
佐助は幸村の命を護ろうと。
幸村は佐助の心を護ろうと。
依存しあう2人の存在はまるで光と影のように、離れられないものへとなっていく。
互いが互いを、互いがいなければ自分でいられなくなるような危うさを抱えて死と隣り合わせの生活を送っていた。
その記憶を持ったまま再びこの世に生まれた幸村は、時代は変われど環境はさほど変わらなかった。
父や兄は優しかったが、母には前世同様に疎まれ育った。
昔は10を過ぎれば元服にもなるが、今は20歳にならないと大人と認めてはもらえない。
もどかしさの中で歯を食いしばり、大学入学と共に家を出た。
恵まれていたのは、幼馴染として過去の好敵手や見知った人たちがいたことだった。
家で辛いことがあっても、友人たちといる時は純粋に楽しかった。
けれど、そこに己の影はいなかった。
そして、幸村が独り暮らしを始めた頃、彼の隣に佐助が越してきたのだった。
――久しぶり、旦那
挨拶に三色団子を持って玄関に立っていた佐助は、社会人特有の落ちついた微笑みを幸村に向けた。
しかし、隣に越してきたものの、佐助は幸村の部屋を訪れはしなかった。
幸村としては話したいことも聞きたいこともたくさんあったが、仕事が忙しいのだろうと気を遣い、彼からも佐助の部屋の前に立つことはなかった。
ふと、夏の星の綺麗な夜。
あまりに部屋の中が暑く、幸村は近くのコンビニまでアイスを買い、夜空を見ながら食べようとマンションの屋上へと足を伸ばした。
そこに、佐助はいた。
――嗚呼、やっと来た。旦那
そう言ってニッコリと笑う彼に、莫迦野郎としか言えなかった。
ずっと待っていたのだ、佐助は。
「くしゅん」
小さなくしゃみが屋上に響く。
「旦那、大丈夫?」
「今日学校で手袋を落としてきてしまって、手だけ冷たかったのだ。心配はいらぬ」
そう言って笑う幸村の手は寒さで真っ赤になっていた。
ふぅと息を吹きかけて暖めようとする幸村の姿を見て、佐助は己の指で彼の手を包む。
厚着をしていても氷のような幸村の手に比べて、薄着にもかかわらず佐助の手は温かい。
「とりあえずはこれで我慢してよ。今晩はもう帰ろう。……でも、もう少しだけ星を見ていたい」
佐助の温もりに指先がじんわりと暖かくなっていくのを感じながら、幸村はそっと頷く。
――俺に会いたくなったら、屋上に来て。夜はずっとそこにいるから。
そう言う佐助の顔がどこか儚くて、幸村はそれから毎日、彼に会いに屋上に向かうようになった。
星空が見たいと佐助は言うが、本当は己を待っているのだと幸村には分かっていた。
毎晩毎晩夜遅くまでこんなところにいて、仕事はちゃんとできているのか心配になるが、過去に己が大将になってからもほとんど眠っていなかったことに気づく。
生き残ることが難しい動乱の世の中では、命を懸けた絆が互いを結び付けているのだと思っていた。
共に武田を護るために必要としているのだと。
しかし、今はそんなものはない。
なくても互いを必要としている。
何のためなのか、その先に何があるのか、何も分からないまま。
只、その存在を求めている。
過去に主従だった関係がなくなった今、新しい関係を築いていけばいいと幸村は思っていた。
主従ではありえなかった、本当の兄弟のように絆を結ぶことも今なら可能だろう。
友として、年上の兄として、幸村は佐助を素直に敬える。
そう伝えると、佐助は少し傷ついたように笑っていた。
「綺麗だね、昔はそんなこと思えもしなかったけど」
ポツリと呟く佐助は、繋いでいた手をふいに強く握った。
そっと彼の様子を窺えば、星に見惚れている彼は己の手に気づいてはいない。
この真夜中の逢瀬でさえ、佐助はどこか引け目を感じているようだった。
彼の真意はわからない。
今までも、佐助は己の心の内を見破っても、己が佐助の心を見破ったことはなかったから。
きっと、彼は全ての気持ちを隠し通し、己の言葉など聞きはしないのだろう。
ならば、彼の心が変わるまで、己は彼の傍でゆっくり待とうと思う。
どれほど時間がかかろうとも、彼の望む関係の形がどのようなものであろうとも、己はきっと受け入れられる。
他でもない、己の影なのだから。
「そうであるな。人の心も、時代も変わっていく。然れども、星はいつの世にも瞬いておるのだな」
己も再び空を見上げ、佐助に気づかないように手に力を込め返す。
白い息が満天の星空に溶けた時、スッと星が流れて行った。
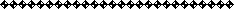
↓ゴマ様の【訳】から抜粋
この小説は、『糸切りサロメ』と同時期に書いたものです。サイトの方向性をグロ系か切な系か迷っていた時に、2つの作品を書き比べていました。結果としてグロ系になったのですがw
こういった、恋人未満な関係が好きなのですが、もっと糖度高いお話がお好きな方には物足りなく感じられるかもですが、お付き合いいただけると嬉しいです。
ダテサナも好きですが、同じくらい佐幸も好きなので最後に更新できてよかったです。