

「オニーサン、落としましたよ?」
明るい声に振り返ってみれば、人当たりの良い笑顔に迎えられる。
「………」
どうも、と自分でも分かるほど辛気臭い声で礼を言い、空いていた席に座った。
「俺も、ここ良いですかー?」
「──…」
平日のこんな時間、田舎を走る普通列車である。車両はガラ空きだというのに、その青年は彼の前に座った。
座席が向き合う形で固定されているため、どうあっても独りにはなれない。
青年は、渡したものを示すと、
「それ、また捨てんじゃないかと思ってさ」
「…見ていたのなら、何故?」
「だってもったいないじゃん、そんな綺麗なの。てか、捨てるなら売りゃ良いのに」
「余計な世話だ」
むっつりと応えれば、相手はもう触れては来なかった。だが代わりに名乗られたので、仕方なく答える。
物を捨てた方は長政、拾った方は佐助といった。長政は二十代半ば過ぎの社会人で、佐助は驚いたことに、まだ高校生だという。
高校生がこんな時間に私服で?いつもの長政なら問い詰めたところだが、今日はそんな気すら起こらない。
「さてはフラれたね?捨て身のプロポーズに、指輪突き返されて」
佐助はクスクス笑うと、「一度断られたくらいで、人生終わりみたいな顔しちゃってさぁ」
「…勝手なことを」
長政はムッと眉を寄せ、「一度でなく、数えきれないほどだ」
そう言い、指輪の入ったケースをポケットの中へしまった。
「そーなんだ……ね、良かったら聞かせてくんない?話せば、少しは軽くなるかもよ」
誰が、と言い返そうとした長政だが、目の前の彼の不思議な雰囲気にスッと消される。年下なのに同年代にも思えるような、口調とは違う落ち着いた空気がそうさせるのか。
しかし一番の理由は、やはり長政自身が吐露したかったから…であったのだろう。
プロポーズを断るのは本人ではなく、彼女の家族や親戚だ。
二人の付き合いは大学からで、長政はその土地へ就職、彼女は地元へ戻った。
卒業間際に彼女の実家へ挨拶に行ったのだが、それは大層な家柄で……平凡な家庭に生まれ、両親を早くに亡くした長政は、「相応しくない」と、門前払い。
とにかく嫌われており、彼女にもろくに会わせてもらえない。ケータイも没収されているらしく、今回も、顔を見ることすらできなかった。
それが数年も続いているとあらば、誰であっても落ち込みはする。仕事は多忙、そのくせ薄給という苦難にさらされながら、必死で取った休日だというのに。
『こんな安物』
鼻で笑われ、指輪を侮辱された。
彼らにとってはそうかも知れないが、長政の辛苦の結晶である。今までは買えもせず、今回少しは見直されるだろうかと期待していた分、えぐられた胸の傷は深い。
(市……)
どんなに厳しい拘束下にあるかは、容易に予想できる。
…だが、時々思ってもしまう。
もう、自分のことは諦めているのでは。
どうしても会いたいのならば、全てを投げ打ってでも現れるのではないか?…彼女は、本当に自分を好いてくれているのだろうか。
そうであるなら、少しは積極的に動いてくれても良いのに。
これでは、まるで自分だけが…
外では毅然と振る舞う長政だったが、内では限界が近付いていた。

「はー…、なかなかシビアだねぇ」
佐助は気の毒そうな顔をし、「でも、羨ましいわ」
(…どこがだ)
苛立つ長政だが、停車駅から乗車した人が入ってきたので、口をつぐむ。
一方、佐助は通路に身を乗り出し、
「旦那っ、こっちこっち!」
「!佐助ッ」
(…?)
手を振り相手を招くと、二人の席に一人の少年が寄ってきた。
中性的な面立ちをしているが、男には違いない。
「俺様の連れなんだ」
「初めまして…」
幸村というのだと紹介すると、佐助は長政のことも彼に話す。
知らない人物に戸惑ってはいたが、彼の事情に同情したのか、幸村の固さはなくなった。
「旦那、電車間違えずに乗れたね」
「いくら俺でもな」
佐助の隣へ座った幸村が、苦笑する。しばらく二人で笑み合った後、互いの手を繋いだ。
「あ、ごめんね?俺様たち、久し振りの再会でさ〜」
「お見苦しいかとは思いますが、お許し下され」
「──…」
照れ笑いをする佐助に、頬を薄桃色に染める幸村。
思いもよらぬ展開に、長政は唖然としてしまうのだが。
「会いたかったよ、旦那…元気してた?ご飯ちゃんと食べてる?」
「俺も、会いたかった…うむ、きちんと食べておる。そう心配するな」
ふふ、と幸村が笑えば、佐助は彼をギュッと抱き締め、
「ああ──旦那だ……旦那……だん、なァ……」
「こ、こら佐助」
「駄目、絶対離さない。俺様の気が済むまで、絶対…」
「佐助……」
佐助の腕に抱かれ、幸村はひどく安心した表情になる。その内静かになったかと思うと、寝入ってしまっていた。
佐助は慈しむように微笑み、自分の膝に彼の頭を乗せる。
その髪を優しく撫でながら、
「何か悪いねぇ。お宅ロンリーなのに、思いきりイチャついちゃってさ」
全く悪びれた様子もなく、佐助は含み笑う。
「羨ましい?」
「…いや」
佐助は笑い、「だよねー、男同士だもんな。ごめんね、びっくりさせて」
「そうではなく」
「え?」
佐助が聞き返すと、長政は腕を組み、
「貴様らがやたら似合いなので、羨みも妬く気も起こらんという意味だ。驚いたのは、人前で手を繋いだり──貴様は、もう少し節度を持つべきだな」
と、呆れた様子で小言を吐いた。
「………」
佐助は、しばし言葉を飲むと、
「アンタ、変わってるってよく言われない?」
「ああ。友人は皆無に近い」
「やっぱし…」
苦笑したが、佐助の瞳は長政を嘲るものではない。
「さすが、何年も愛に生きてる人なだけあるね」
「………」
戯れ言を、と思うが、長政は詰まってしまう。…こんなとき、彼女が傍にいれば、『何を馬鹿なッ』と、本心とは反対のものを大声で叫んでいた。
膝の上の彼が増えたときから、彼女の顔が頭にチラチラ浮かぶ。ああは言ったが、こうして二人一緒にいられる状況には、やはり…
「世の中、アンタみたいな人ばっかだったらなぁ」
佐助は再び苦笑すると、
「俺ら、中学まではいつも一緒だったんだけど、うちが引っ越しちゃってさ。お互いケータイも持ってないしで、今日会えたの半年振りなんだよ」
「…今時、珍しいのだな」
高校生で、しかも佐助のようなタイプなら、何としてでも持ちそうなものなのに。
「ま、アンタと同じで友達もいないし、それは問題ないんだけど…俺様後妻の連れ子だから、我儘言えねーの。それに、引っ越したの俺様のせいだしね」
「………」
至極普通に身の上話をするので、長政は返答に悩むのだが、
「中学んとき、暴力沙汰起こしちゃって。それで」
「それは……意外だな」
と長政は呟き、「…ああ、彼のためか」
おー鋭いねー、と佐助はおどけた調子で応え、
「旦那、ずーっと苛められててさ…俺様、全然気付かなくて。旦那は腕が立つから、相手を傷付けるのを怖れててね。抵抗せずに、やられっ放しで。で、ある日現場見て…」
「………」
それまで大人に見えていた彼が、急に逆のように感じた。…今にも、泣き出してしまいそうな。
だが、口を閉ざすことはせず、
「しかも、原因は俺様。見られてたんだ──旦那と手ぇ繋いだり、抱き締めたり、…キスしたり。旦那、脅されて…俺を庇っててさ。
キレた俺様は、旦那の苦労を全部水の泡にしちゃった。田舎だから、噂ってすーぐ広まるんだよね。学校だけじゃなく、街中から好奇や侮蔑の目で見られて、親の逆鱗に触れて──で、引っ越しってわけ」
「………」
長政は、かける言葉が見つからなかった。
「逆だったら良かったんだけどね。だから、旦那は今でもたった一人なんだ。家族からも避けられて。当然、俺と旦那は一生会わせないようにと、どっちの親も目くじら立ててるし…」
眠れてないんだろうね、と佐助は幸村の頬を、優しく撫でる。
“ 四面楚歌 ”──…
…他人のことでこんなに胸を痛めたのは、初めてかも知れない。
長政の頭には、さっきよりも鮮明に、彼女の顔が浮かぶようになっていた。
佐助は、そんな彼に向き直ると、
「指輪、絶対喜ぶと思うよ。だから、捨てちゃ駄目だって」
と、再び最初に見た笑みに変わり、心細そうな陰も消えていた。
「あ、俺様たち次で降りるから」
佐助が幸村を揺すると、「何故、起こしてくれなかったのだ…」と、落ち込んでいたが、
「ゴメンゴメン、旦那の寝顔見るのも、久し振りだったからさぁ」
「ぬぅ…」
佐助の甘い言葉と態度には、めっきり弱いらしい。顔をほころばせ、先ほどの話が信じられぬほどの、はにかんだ表情をする。
「じゃあね、長政さん。会えて良かったよ」
「お家まで、気を付けてお帰り下され」
「…こちらこそ、色々……」
二人は、幸せそうな笑顔で長政に手を振った。
降りたのは、周りが田畑ばかりの無人駅。
荷物一つ所持せず、どこへ、何の用事で行くのだろう。
そう浮かんだ際には、電車はもうホームを発っていた。
「佐助、何故彼に話したのだ?俺たちのことを」
「聞いてた?──ごめん」
「いや、責めているのではなく、珍しいと思ってな」
「ああ…」
佐助は軽く頷くと、「まー、諦めて欲しくなかったっつーか…他人事には思えなくてさ」
「彼と恋人の…?」
「そうそう」
佐助は笑い、「あの特急に、乗り直してると思うよ。戻って、速攻お姫様を奪還!格好良いよねぇ」
プァン、という音を立て、その電車がホームに近付いてくる。この駅には停まらないので、確認はできないが。
「上手くいってもらいたいよね」
「うむ…」
しかし、と幸村は言うと、「俺は、乗っておらぬと思う」
「え?」
ゴーッと電車が通過し、佐助の声は消された。
静かになると、
「彼の恋人のお屋敷というのは、お前の町にあるのだろう?」
「まぁ…そうだろうね。同じ駅で乗ったから」
「では、協力して差し上げたらどうだ?お前は、そういうのが得意じゃないか」
思ってもみなかった言葉に、佐助は目を見張り、
「だね…連絡先、聞いときゃ良かったよ」
そう悔やむが、幸村は微笑んで、
「大丈夫だ、すぐに会えるから。…あの電車」
(え?)
佐助が戸惑っていると、再び電車が近付いてきた。今度は普通列車で、二人はあれに乗るのだが、
「あと、俺たちが何もせずにこのまま帰る理由、話す用意をしておいた方が良いぞ」
「えぇ?」
佐助は顔をしかめ、
「『かけおちの予行練習です』って?…ただ電車に乗ってるだけだってのに、恥ずかしいんですけど」
「良いじゃないか。それに、きちんと卒業してから家を出るのだし。勘当されれば、かけおちではないだろう」
まぁね…と佐助も笑って返せば、列車が到着した。
幸村の言う通り、長政は本当に乗っていたらしく、ホームに飛び出るや否や、
「貴様ら、早まるな!貴様らのような二人が幸福にならずして、何が平和な国だ!?『心中』なぞ、馬鹿な真似──」
……でっけぇ声。
別人のような鬼気迫る表情に、佐助と幸村は顔を見合わせ、ふわりと笑みを交わした。
( …いつの日か、四人で )
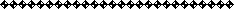
‐2012.6.9 up‐