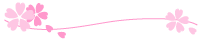
亜細亜の希望の子【早乙女忠視点】
『あのね、あのね、亜希子のお名前はね、亜細亜の希望の子って書いて亜希子なのよ』
半紙にデカデカと書かれた【亜希子】と言う名前の由来を自慢気に説明してきた幼い少女。
あの日のことを今でも鮮明に覚えている。
妹のように思っていた。10歳下の小さな女の子は俺を兄と慕ってくれた。だから俺も良い兄でいようと思っていたんだ。
俺の父は【エラい先生】で、本妻と子どもがいる。ほんの出来心で母に手を付け、俺が生まれたのだ。男の甲斐性として面倒は見ると、本宅の離れに住まわせてもらい、母子が最低限生活できるくらいの援助はしてもらっていたが、俺たち母子は妾と庶子として陰に隠れて生活していた。その生活は息苦しく、肩身が狭かった。
本妻とその子どもには蛇蝎の如く嫌われ、義兄たちにはよくいじめられた。妾の立場である母は表立って庇える立場でもなく……義兄達の憂さ晴らしとも言える暴力が始まると、いつも俺はうずくまってそれが終わるまで我慢していた。
いつかこんな家出ていってやると心に決め、俺は必死に学んだ。負けん気を発揮したことが功を奏したのか、俺は義兄たちよりも優秀な成績を修めることとなった。
優秀な息子のほうに父の関心が向いたらしい。俺に家庭教師を用意し、義務教育ではない高等小学校へ通わせてくれた。
父からは『援助は惜しまない。私の期待に応えて、いずれは最高学府・帝国大学を目指すように』と言い付けられた。
別に父のためではない。父の期待に応えたかったわけではない。
こんな生活から抜け出したかった。父からの援助に頼らないで生きられるようになったら、母を連れてこんな家から出て行きたかったのだ。
そのためなら何だって活用してやるつもりだった。
だが、そのせいで正妻から睨まれた。正妻からの嫌がらせはますますエスカレートした。
俺の方が優秀だからと、攻撃がさらに増したのだ。母は俺のやりたいようにしなさい、旦那さまの期待に応えなさいと背中を押してくれたが、日に日にふさぎ込んでいった。
とうとうその母が心を病んで弱ってしまった時、俺も一時は帝王大学進学を諦めかけたが……。
母の幼馴染である亜希ちゃんのお母上が、母の窮状を知って家に招いてくれたのだ。しばらく家から離れて過ごしてみてはどうかと言われ、それに甘えることにしたのだが……その期間中は緊張することなく、勉強に集中することが出来たと思う。
母さんもタダ飯食いは気がひけると言って、宮園夫妻の仕事を手伝うようになってから元気を取り戻し始めた。
元々母は仕事をするほうが向いていたのだろう。水を得た魚のように仕事を覚え、楽しそうに笑う姿をよく見かけるようになった。
ロウソク明かりのもとで勉強をしていると、ヌッと手元が陰った。
火が消えたのではない。人が明かりを遮ったのだ。
『…亜希ちゃん、もうご本を読み終えたの?』
『何回も読んでるもの。飽きちゃった。…亜希子もお勉強がしたい』
その下宿生活で1人の幼い少女はよく俺の部屋に出没しては、勉強する俺の手元を覗き込んできた。
邪魔はしないのでそのままにしておいたが、興味津々な目つきで見つめてくる少女の目に耐えきらずに、比較的簡単な事を教えてあげると、彼女はランランと瞳を輝かせていた。
彼女はどうも勉強に興味があるらしい。だが女性が勉強するとなると、眉をひそめられる時代だ。学生になった彼女がそれに傷つかなければいいが…と思いつつも、純粋に勉強に興味を持つ彼女が応援したくなり、自分が幼い頃使っていた尋常小学校の教科書を彼女に貸してあげると、彼女は跳び上がって喜んだ。
予想外だった。とにかく彼女は地頭が良い。女に生まれたのが間違いであるほど賢い女の子だったのだ。
嫉妬するかと言われたら…流石に10歳下の女の子に嫉妬するほど自分はガキではない。彼女が望むなら勉強を教えた。
落ち着いた環境で勉学に没頭できたおかげで、帝国大学に無事合格し、俺は大学近くに下宿するためにお世話になった宮園家を後にした。
母はそのまま奉公人の形で下宿することになった。あの家に母一人で戻るのは耐えきれないであろう、宮園夫妻にも俺から頭を下げたのだ。
その後、俺は父が望む進路へ真っすぐ進んだ。だがこれはすべて自分のためだ。それが偶然父の望みだっただけである。
父は俺を誉れと言い、妾の息子だと言うのに内外にお披露目しては自慢する。
…思うところはあったが、俺は何も言わずに父に合わせて挨拶をした。妾の子だと後ろ指さされ、虐げられる生活には戻りたくない。そのためなら何でも利用する。…彼らを見返してやりたかったからだ。
大学卒業後はそのまま、軍人への道へ進んだ。海軍所属となり、真新しい制服を母にお披露目しに、久々の宮園家にお邪魔すると、奥からピョコッと一人の少女が現れた。
『忠お兄様!』
自分の記憶の中の幼い少女はいつの間にか花開く乙女に成長しており…あまりにも美しくなっていたので、思わず見惚れてしまった。
だが、その好奇心でいっぱいの瞳だけは変わらなかった。
『忠お兄様、私女学校に入学しましたのよ。いずれは…私もお兄様のように大学に入りたいわ』
昔のように親しげに話しかけてきた彼女は、相変わらず俺を兄と慕ってくれていた。
昔はそれが嬉しかったのだが、美しく成長した彼女を前にしたら複雑な心境に陥ってしまった。
10つも年下の女の子じゃないか。妹のように思っていた相手じゃないかと自分に問いかけたが、彼女を目の前にしたら、もう妹とは見れなくなっていたのだ。
両親に愛された彼女はスレたところなどなく、真っすぐで素直で……俺はそれが羨ましいと思っていた。
賢くてお転婆……眉をしかめる人間もいるだろうが、俺はそんな彼女を好ましく思っていた。汚職や金、愛憎や裏切りなどを目にしてきた俺には、偽りのない彼女が眩しくて、だけど目が離せなくなっていた。
守りたい。
側にいたい。
…娘らしくなった彼女は更に匂い立つような美女に成長するであろう。そうなればきっと引く手あまたに……
そんなの、許さない。
彼女は俺のものだ。
そう思った時、俺は自分の想いを自覚した。
だけどまだ娘である彼女に迫るのは大人げないと考えた俺は、彼女が女学校を卒業するまではこの想いを伝えずにいようと決めた。
…でないと、自分が抑えられないと思ったからである。
俺の気持ちは、母も宮園夫妻も理解している。
亜希ちゃんの気持ちを優先にするようにと言われているので、我慢しているがここ最近彼女に見合いの話が立て続けに舞い込んでくるらしい。
しかも、宮園家で住み込み書生を迎えたと言って……亜希ちゃんはその大学生と仲良くなっていた。
天真爛漫な彼女のことだ。勉強が大好きな彼女なら、現役大学生と勉強を通じて親しくしたがるのは目に見えていた。
最初は大学生の青年もそこまで関心を持っていなかったようだが、日を追うごとに、彼の亜希ちゃんを見る目が変わって……嫁入り前の娘だからと、相手には牽制はしてきたが、どうにも怪しい。
──嫌な予感は的中した。
あの青年はよりによって、花街の手前で亜希ちゃんに結婚を前提とした交際を申し込もうとしていたのだ。ナヨナヨした優男だと思ったらとんだ傑物だった。
寸前のところで邪魔をしたが……亜希ちゃんはあまり気にしていないようだ。恐ろしいくらいに警戒心がない。
ただでさえ書生の吹雪君のほうが彼女と年が近い。年頃の男女がひとつ屋根の下に住んでいる。俺は不利な立場なのだ。今は亜希ちゃんが彼を意識していないが、これからどうなるかわからない。
俺がこんなにもヤキモキしているとは知らない亜希ちゃんは現在、ふわーんとした笑顔で氷菓を頬張っている。
普段は大人っぽい彼女が年相応の少女に変わる。その姿が可愛くて、俺はそれに目が奪われていた。
そんな俺の視線に気づいたのか、亜希ちゃんははっとして氷菓を匙にひとすくいすると、俺の口元に近づけてきたではないか。
「忠お兄様も召し上がります? はいあーん」
「……いいから、全部君が食べなさい」
…お転婆でも、才女でも、俺はそんな彼女が好きだが……やっぱりたしなみは必要だな。
俺は本当の兄じゃないんだぞ、亜希ちゃん。頼むから、恥じらいというものを身に着けてくれ…
……彼女には警戒心というものを身に着けてもらったほうが良いのかもしれないな。
|