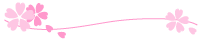
【弐】
私は混乱していた。
なんか…私が口説かれているような気がするのだけど。吹雪さんは吉原の遊女さくらに恋をするというのに、何故私の手を固く握っているんだ。
私、ちょい役だよ? 2話くらいで出番終えた役。あなたが愛の告白するのは別の……あ、まさか吹雪さんは、あわよくば私の婿となり、大商家であるウチを牛耳って、さくらを身請けする金を狙っているの?
……つまりこれはやっぱり逆玉狙い!!
「亜希ちゃん、奇遇だね。こんなところで何をしているの?」
私がぴーん! と閃いていると、感情を抑えた低い声が私と吹雪さんの間に流れた微妙な空気を切り裂いた。
「忠お兄様!」
「チッ…!」
「舌打ちなんて行儀が悪いよ吹雪君。亜希ちゃんが真似しちゃうだろう?」
思っていたより声が大きくなっていたのかしら。忠お兄様に存在を勘付かれていたらしい。失敗した。
吉原の外からでられない遊女・さくらは1人その場にぽつんと残されたままこちらを見つめていた。きっと忠お兄様を見つめているのだろう。
運命の女性を放置だなんてマズいと思うの。
「お兄様、あちらの女性はよろしいの?」
「あぁ、いや彼女は…」
「真っ昼間からお盛んですねぇ、吉原で郭遊びですか? 海軍はよほどお暇なんですねぇ」
「…違うが。君は何かを誤解しているな?」
ぴしりとひび割れた音が擬音として聞こえてきたような気がした。彼らはお互いの姿を目に映すと、表情を険しいものにさせた。
この2人…仲悪いんだよねぇ…いや、あのドラマでも恋敵同士だったし、けっして仲のいい間柄ではなかったけども……ドラマの舞台が始まる前から仲悪いんだな。
2人は私を間に挟んで睨み合っている。平和に行こうよ、平和にさ。
吹雪さんは貧乏な長屋で育った苦学生だ。食べるのも飲むのも苦労して、努力して大学に通えるようになった人なのだ。生育環境もあまりよろしくなかった。
そんな彼は花形の海軍である忠お兄様を妬んでしまうのは……仕方がないのかな。海軍エリートといえば、天上人のような存在だもの。少なくとも一庶民から海軍のエリートへの道を進むというのは苦難の道かと想像つく。
…誰にだって僻んでしまう心は生まれてしまうもの。
だけど吹雪さんは誤解している。忠お兄様だってぬくぬく育ったわけじゃないのだ。
忠お兄様はいわゆる庶子、なのだそうだ。どこそのお偉いさんのお妾さんから生まれた子ども。今では海軍軍人としての肩書があるお兄様は堂々としていらっしゃるが、昔は妾の子として肩身狭そうに生きておられたのだ。
私の母と忠お兄様のお母上は幼馴染で、お兄様達の不遇を聞いた私の母が気を遣って家に招くようになった。
そこから私達の交流が始まったのである。私と忠お兄様は年の離れた兄妹のように育った。私は一人娘だけど、お兄様がおられたから、全く寂しくはなかった。
ちなみに私が勉学に目覚めたのはお兄様の影響である。この時代娯楽はないに等しい。そうなると私は勉強の楽しさに目覚めてしまったのだ。
その辺の女の子のようにお人形遊びをしたり、お嫁さんに憧れたりするわけでもなく、勉強に没頭する私を心無い人が「女の子らしくない」という人もいたが、忠お兄様はいつだって「亜希ちゃんはすごいね、賢い女の子だ」と褒めてくださった。
私はお兄様に褒めていただけるのが嬉しくて更に頑張った。
忠お兄様はすごいんだ。帝大を優秀な成績でご卒業された後は、ストレートで海軍に入隊して、エリートコースを進んでいらっしゃる。
身長は190cmを超える巨体で、パッと見だと威圧感がすごいけど、すごく、すごく優しい方なの。勤勉でいらっしゃるし、私をレディ扱いする割には、色眼鏡で見たりしない。
お顔立ちは精悍でいらして男前。本当に本当に素敵な人なんだ。
……最初に、『本当のお兄さんのように思っている』と言ったけど、あれは嘘だ。そう思い込もうとしているに過ぎない。
私はほのかな恋心を忠お兄様に抱いていた。だけど私は彼よりも10歳下。子ども過ぎた。
将来有望で素敵なお兄様は女性によくモテる。私などお呼びではないのだ。
──彼には運命の女性がいるとわかっていた。だから、諦めたのだ。
私は戦う前から退いた敗走兵なのである。笑えばいいさ。
だって、運命の人に勝てるわけがない。
大門前でこちらを切なそうに見つめている遊女・さくら。あのドラマの主人公である彼女は色っぽく、男性が好むような従順な女性だ。男のように勉学に励み、どちらかといえばお転婆な私とは正反対だ。
彼女は、忠お兄様のそばにいる私を見て……ギッと睨みつけてきた。
「…え」
あれ、今私睨まれた? 目の錯覚かな。
まぁ、でも好きな男性のそばに他の女がいたら嫉妬で睨んじゃうこともあるよね……ちょっと、あのドラマの“さくら”とイメージが違ったからびっくりしちゃったけど。
あのドラマで、忠お兄様に恋をした“さくら”は突然現れて牽制してきた“亜希子”にも恐縮した様子だった。
『忠お兄様は日の本をお守りするためにとてもお忙しいの。文などを送ってお兄様の気を引こうとしないで。お兄様の負担になっているのを自覚してちょうだい』
…と“亜希子”から釘を差された時ですら、“さくら”は負い目を感じて、忠お兄様から離れようとしていたもの。
“さくら”からの恋文が途絶えたことで、忠お兄様が異変を感じて、その後話がこじれるが……結局2人の恋の炎が燃え上がり、二人の絆が強くなるという展開だった。
つまり“亜希子”はライバル役というより、彼らの恋の炎を更に炎上させるマッチ役なのだ。
私はマッチ売りの少女ならぬ、マッチ本体なのだ!
ただでさえ遊女という立場のさくらは自分の身分に負い目を感じていた。吉原全盛期の江戸時代ならともかく、大正時代の遊女は下に見られがちだったからだ。
嫉妬して睨みつける、普通の女性の反応としてはなにもおかしいことはない。きっと好きな男性のそばにいる女として警戒されているのだ。だから私を睨んだのだ。
恋する女性だもの。仕方がないよね。
でも、安心して欲しい。私は身の程をわきまえている。
“さくら”の運命の人を奪えるだなんて思っていない。私は自ら太陽に近づくおろかなイカロスではないのだ。
ダメだとわかっているから妹ポジションで我慢している。これ以上忠お兄様を好きになったりしない。自分が苦しいだけだから私はこの感情を見て見ぬ振りする。
私は親の決めた相手と結婚する運命になるであろう。その相手と幸せになるんだ。それがベストな答えなのだ。
「亜希ちゃん、いつまでもここにいるのは良くない。おいで、新しく出来たカフェーに連れて行ってあげよう」
「えっ」
私が1人考え事をしていると、忠お兄様から手を握られて、カフェーに行こうと誘われた。
か、カフェー…いち女学生として、はしたないから1人では行けない大人の社交場…!
行きたい。あそこにはアイスクリンがあるのだ。あまり時代考証されていないドラマの舞台とはいえ、その辺りは大正時代と同じような文明なのだ。甘味に乏しいこの時代でアイスクリンは贅沢品扱いなのである。
「あ、アイスクリン…食べても良い?」
「いいよ、何でもお食べ」
私が恐る恐るお伺いを立てると、忠お兄様は優しく微笑んで、心強いお言葉をくださった。
やったぁアイスクリンが食べられる!!
目に見えて嬉しそうな私の様子がおかしかったのか、忠お兄様は目を細めて見つめてきた。その目を直視した私はトクンと胸が高鳴った。
……その目だ。時折私に向けてくるその瞳は優しげに見えて火傷しそうに熱い。忠お兄様がそんな目で見つめるようになったのはいつ頃からであろうか……妹扱いだったのが、いつの間にかレディ扱いに変わり……自惚れそうになるところを既のところで押し留めている。
そんな目で見つめないでほしい。私は必死に恋心を抑えているのだから。
「色気より食い気のお嬢さんを甘いもので釣ろうという魂胆ですか?」
「ちょっと吹雪さん! それは私に失礼ですよ!」
私がときめきを抑えていると、横から吹雪さんが割って入ってきて、私に対して失礼なことを言ってきた。
否定できないけどひどい。私だって年頃の乙女なのだ。暴言は控えてもらおうか!
私が吹雪さんに前言撤回してくれと訴えていると、くいっと手を引かれた。
顔を上げてみれば、忠お兄様が苦笑いを浮かべていらした。
「さ、亜希ちゃん、行こうか」
あ、そこは否定してくれないのか。忠お兄様も私が食欲旺盛な花の女学生だとお認めになられているのね。
ちょっとショックです。
|