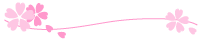
【玖】
「──どうぞ」
「あ、どうも」
お茶を差し出された。
さくらさん手づから淹れてくれたお茶を私はありがたく頂戴する。
この時代は遊女の立場も低くなり、教養を持つ人も大分減ったのだが、それを考えるとさくらさんの所作は綺麗だった。見世の楼主が躾けたのであろうか。
「あの…」
「長話はよしましょう。単刀直入に聞くわ。……あなた、転生って信じる?」
持っていた湯呑を落としそうになった。
まさかそんな単語がさくらさんの口から飛び出してくるとは思わなかったからだ。
「えぇと…?」
私は返答に困って微妙な顔をしてしまった。どういう意味なのか測りかねたからだ。
それは、輪廻転生…仏教的な意味なのか、それとも……
「あたしの名前はさくら。この吉原の遊女…そして、この世界の主人公なの」
「!?」
私はちょっと浮かれ気味だったのかもしれない。この大正時代風のドラマの世界に転生したのは自分だけと思っていた。
まさか主人公のさくらまで転生者だったなんて。
ここにいるさくらはこの先の運命を知っている?
ではなぜ、彼女は忠お兄様と結ばれる気配がないのか。吹雪さんが彼女に恋する様子がないのか。……どういうことなの?
──バシャッ
熱湯と言うほど熱くはないお茶を正面からかけられた。ポタポタと水滴が畳に落ちて、水分を吸っていく。
「そしてあんたは脇役なの…知ってた?」
……お茶をかけてきたのはさくらさんだ。彼女はその目を血走らせ、私を射殺すように睨んできた。一瞬で清楚に整った美貌が鬼婆のように変化したのだ。
「あたしのための世界なのに、なんであんたがでしゃばってるのよ」
私が濡れた顔を手の甲で拭っていると、さくらさんがゆっくり立ち上がり、私の真横まで近づいてきた。
──そして
私の頭皮に引きつる痛みが走った。
「邪魔なのよあんた! なんで彼の側をチョロチョロしているのよ! どうしてあの大学生はあたしに惚れないのよ! 話が進まないから、私はいつまで経ってもこの吉原にいなきゃいけないじゃないのよ! 冗談じゃないわ!」
彼女は金切り声を上げながら、私の髪を鷲掴みして引き倒してきた。髪を掴まれて、真朱色のリボンでまとめていた髪が乱れてしまった。あのリボンは忠お兄様が私に似合うからって贈ってくださったものなのに。大切なの、毎日使っているの。
それをさくらさんは裸足の足でぐしゃっと踏みつけにした。
「やめて、そのリボンはお兄様が」
「うるさいわね! なのでなのよ…このあたしが、さくらが手紙を送っているというのに、無視よ!? ありえないでしょうが!!」
さくらさんは足を振り上げて私を蹴りつけた。背中を蹴られた私は「ぐふっ」とむせた。グリグリと踏みにじるように私を踏みつけにしている彼女は、呪詛を吐き出すように恨み言を吐き出した。
「ドラマの世界なのに……大正浪漫・夢さくらの世界なのよ? あたしが主人公なの、わかる!?」
「わ、私はあなたから忠お兄様を奪おうとは思っていないわ。私はいいところ妹分だもの。私は当て馬にも満たないマッチ役、ちゃんと自分の身の程を弁えてる!」
そうだ、私はお兄様の優しさに甘えてきたが、それ以上を求めたことはない。恋心を伝えたことはないし、男女の距離感は守っているつもりだ。
大体、10も下の私を結婚相手として見てくれているかもわからない。いいところ妹扱いだ……きっとそうに違いない。
私はちゃんとわかっている。私はただのマッチ役だって。
……彼女は、さくらさんは確かにこの世界の主人公だ。だけどそんな、彼らをただの盛り上げ役の舞台装置みたいな言い方をしなくてもいいじゃないか。
確かに、ドラマの忠お兄様はあなたを選んでこの吉原から出してくれた相手だ。遊女という仕事は大変なのはわかっている。ここから逃げ出したいという気持ちも想像はできる。
……だけどそうだとしても、お兄様が吉原から解放してくれる役割みたいな言い方しないでほしい。
そこには恋も愛も存在しない。ただ利用しているかのような言い方じゃないか!
「忠お兄様も吹雪さんも今を生きる現実の人間なの。ちゃんと尊重して!」
私の大切な人を傷つけるような言い方しないでほしい。いくら主人公さくらでもそれは見逃せない。
主人公だからって何でもしていい存在ってわけじゃないのよ!
私が反論したことを不快に思ったさくらさんは更に顔を険しくさせてこちらを睨めつけていた。
「なによ…あんただってドラマの人間だと思ってるんでしょうが! あんた言ってることがぶれてるのよ、マッチ役と自称しながら、あの人に本気になってんじゃない!」
「そんなこと…」
「あたしはね、あんたみたいな温室育ちのお嬢様が大嫌いなのよ…! そう言ってキレイ事ばっか言って……あたしを綺麗可愛いって言ってきた男全員結局は、あんたみたいな育ちのいい娘を選ぶのよ!」
…本当腹立つ! と悪態をつくさくらさん。完全に頭に血が上っているようだ。冷静な話し合いはできそうにない。
私はこの場から逃げたほうが良さげだ。
なのだが、私の身体は先程から力が入らない。
全身痺れているようで、手足に力が入らないのだ。
「…あぁ、やっと効いてきた? お茶に薬を仕込んでおいたのよ。流石いいところのお嬢様ね、人を疑うことを知らない……恨むなら自分の軽率さを恨みなさいな」
ふふふっと笑うさくらさんの顔はまるで悪役のようで。
彼女の手がこちらに伸びてきて、私が着用している着物を剥ぎ取った。
「いい仕立てねぇ。これはあたしがもらっておいてあげる。…あんたにはこっちの方がお似合いよ?」
そう言って私が身に着けていた着物を奪うさくらさんはまるで地獄の奪衣婆のようだ。美しいと思っていた彼女の顔が鬼婆のように歪んだ。
スラッと音を立てて、先ほどの傷の男が入室してきた。彼は風呂敷包みを抱えておりそれを広げると、テキパキ中身を取り出し、私にそれを着せてきたのだ。
抵抗しようにも、身体が鉛のように重い。抵抗にもならない抵抗しかできない。舌が回らない私は呻き声を上げていた。
私は重い衣装を着せられ、さくらが髪を整え、顔に白粉を塗り始めた。
「……とても綺麗よ。……たくさん可愛がってもらってね?」
隣の部屋に続く襖の向こうには赤い布団が敷かれていた。
傷の男に引っ張られ、その布団の上に倒された。私は痺れる身体に力を入れて這いずったが、それを嘲笑うかのようにさくらさんは観察していた。
この部屋の中には煙が充満していて、変わった匂いが漂っている。……これは、香…?
「水揚げが大好きな客がいてね。あたしの妹女郎全員その人のお手つきになったの。次はどうしようかなと思っていたんだけど…あんたがここに現れてくれて助かったわ」
水、あげ…?
それって……
私が顔を上げると、別方向の襖がサッと開かれた。その先にいたのは、見知らぬおじさんだ。その人は私を頭の先から爪先まで眺めると、にまぁと気色の悪い笑顔を浮かべた。
「どうぞ、この子生娘なのよ。かわいがってあげてくださいな」
「ほう…これは美しい」
「初めてだからあの香を焚いておりますわ」
明かり取りの下に香炉があり、そこからこの不思議な匂いが発生しているようだ。……あの香ってなに?
「お楽しみくださいな」
さくらさんは私とおじさんをその部屋に残して立ち去っていった。
私は自分がこの先どんな目に遭うのか理解していた。逃げなきゃと頭の中ではわかっていた。
だけどお茶に淹れられた薬と、このおかしな香の香りで体の動きも思考も鈍ってしまっていた。
「うんうん。緊張しているのか? 大丈夫、私に任せたらいい夢を見せてあげるぞ…」
私の体の上におじさんがのしかかってくる。吹きかける息が生臭くて吐き気がする。
先程着せられた遊女のような衣装を乱していく。私は触れられたくなくて、「や、いや、」とか細い声で抵抗していたのだが、それを怖がっているだけと誤解しているおじさんはやめてくれない。
襟元を肌蹴られ、露出した首もとや鎖骨におじさんが吸い付いてくる。気持ち悪い、嫌だ、嫌だ。
──なのに身体が熱い…
嫌なはずなのに、抵抗できない。身体が動かないのだ。
私は怖くて怖くて泣くしか出来なかった。
着物の裾に手を突っ込まれ、太ももと撫でられる。
どうして私が。
知らないおじさんに身体をあばかれなくてはならないのか。
嫌だ。嫌だ。
忠お兄様……!
「ひゃぅっ…!」
嫌悪でいっぱいなのに、私の身体は生まれつきの淫乱のように敏感に反応した。
肌を撫で擦る男の手は気持ち悪いのにそこからは感じたことのない快感が走るのだ。
「うんうん。素直になりなさい。一緒に極楽を見ような……」
私は涙をこぼした。涙は目の横を流れ、耳の穴にこぼれ落ちる。
嫌だ、気持ち悪い、助けて。
「やぁ…」
叫びたくても喉まで痺れて大声が出ない。
それに叫んだってここは吉原。誰も助けてはくれない。
私を守ってくれる人はいないのだ。
「あぁ、綺麗な身体だなぁ……」
着物を乱して、私の身体をうっとりと鑑賞するおじさん。私が嫌がっているなんて思ってもいないのだろう。
──このまま、男に穢されるくらいなら舌を噛んで自害してやろうか。
「あぁ…んっ」
なのに私の身体はうらはらに淫らに感じている。自分の口からは信じられないほどいやらしい声が漏れ出る。
舌を噛み切ってやりたいのに、顎に力が入らない。
胸元に男が舌を這わせる。
気持ち悪い…!
私の身体が震えた。恐怖に、絶望に、愉悦に、快感に。
私は見知らぬ男に花を散らされようとしていた。
|