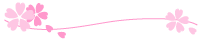
【陸】
先日の試験で主席だった私へのご褒美で、港付近に出来た新しいカフェに連れて行ってくれると約束してくださった忠お兄様と一緒に今日はお出かけをした。
車に乗ってたどり着いたそこは、潮風の匂いを肌で感じる海辺の街。うちの家も港に近いが、それよりもさらに海に近い。初夏の陽気に海の磯の香り。私は間近の海を目で、鼻で、耳で楽しんでいた。
水面がキラキラ輝いてとても綺麗。
忠お兄様が贈ってくださった西洋の帽子が風で飛ばされぬよう手で抑えながら、私は海の向こうを見つめた。
こちらは太平洋。このはるか先に異国の地がある。
──海。
一度陸から離れたら辺り一面海。そう、海水の世界。今日のように天気が良くても風が強ければ海は荒れる。夜だと尚更危険だ。私は地上から降りることはないが、お兄様はお仕事が海を守るお仕事だから海の天候など慣れっこであろう。
私は海が怖いと感じることがあるけど、お兄様は怖くないのだろうか……?
記憶に残る、ドラマの海上戦闘シーンが脳裏によぎって私はゾッとした。
この先どう足掻いてもやってくるのは戦争だ。軍靴の足音は確実に近づいてきている。
今隣に立っている忠お兄様はご出陣なさる。それは軍人である彼の使命であり義務である。
だけど、いざ見送る立場に立つと、私は恐ろしくてたまらなくなってしまう。
「そこにいるのは早乙女か?」
「新垣」
「一緒にいるのは……へぇ、この子が噂の……女学生とはやるじゃんお前」
私が暗い思考に陥っている所に声を掛けてきたのは、普段忠お兄様が身にまとっている同じ軍服に身を包んだ男性だった。
忠お兄様の同期だというその人を紹介された私は少しばかり驚いていた。なんでかって、真面目な忠お兄様とは正反対に見える軟派な感じの男性だったからだ。体つきは軍人らしくがっちりしているが、その顔立ちは柔和で、戦いに行く人間にしては少々迫力に欠ける、そんな印象であった。
「早乙女にはうちの妹を娶らせたかったんだけどなー」
ジロジロと値踏みするように見られた私は少々居心地が悪かった。
ていうか海軍内でも私の噂が立っているのか…? 大丈夫なのそれ。
「その話は断ったはずだ…新垣」
忠お兄様がその視線を遮るようにして身体で私を隠すと、「おお怖い」とお友達さんがヘラヘラ笑っている雰囲気がした。
「年頃の女の子を不躾に見つめるな」
「悪かったって」
覗き込んできたその人はニコッと微笑むと「ごめんね」と首を傾げていた。私はどんな反応をしていいのかわからずに、苦笑いを返す。
「そういえば、 基子 のこと聞いたか?」
「さぁ…」
「今住んでいる立派なお館があるってのに、基子の旦那が新しい家を建てているらしいぜ。成金様の考えてることはわかんねぇな」
基子?
誰それ。
聞き慣れない、女性の名前に私はピクリと反応した。それに気づいたのか、新垣さんが面白そうな顔をしてこちらを見てきた。からかう気満々の顔である。
「基子って気になる? 基子ってのはこいつの昔のオンナ。だけど働いていた店に来ていた客と懇ろになって捨てられちゃったんだよねー」
「うるさい、余計なことを言うな」
つまり、忠お兄様の元カノってことか。……別に驚くことではない。こんなにも素敵な人に奥さんどころか恋人もいないのがそもそもの間違い。
ていうか忠お兄様の運命の人は遊女のさくらじゃない。元カノが何だ。そんなの二人の恋の障害にもならない。
……モヤッ
わかっていたこと、なのに……
ジリジリと焦げそうなこの胸のざわめきは一体何なのだろうか。
■□■
「ごめんね亜希ちゃん、あいつ根は悪いやつじゃないんだけど、人をからかう悪い癖があって」
「いえ…」
新垣さんと別れて…というか忠お兄様が追い払った後に気を取り直して目的のお店に入店した私達。
ハイカラな店内にはポツポツとお客さんの姿。調度品の一つ一つが大正ロマンを感じる味のある一品。普段の私なら、網膜に焼き付けようと目を皿のようにして店内を観察するのに、今日はそんな気が起きなかった。
明らかに元気を失った私を気遣うように忠お兄様が声を掛けてくれるけど、私は生返事を返していた。失礼なのはわかっていたが、どうにも気持ちがスッキリしない。
……忠お兄様の昔の恋人のことでモヤモヤしているのだ……
お兄様は男性だもの。女性との交際経験があってもおかしくない。……だけど、大正浪漫・夢さくらの【忠】は一途で、二人の恋は純愛で……
なんだかすごく嫌だ。
私が勝手に一人で理想を抱いて、勝手にがっかりしているだけ。お兄様は何も悪くない。頭ではわかっているのに、心が納得できないんだ……
「……亜希ちゃ」
「……ちょっと、お花を摘みにいってまいります…」
忠お兄様に呼ばれた私だったが、それを遮るようにして席を離れた。思考がグチャグチャになってしまってるから、ここを離れて一旦落ち着こう。
一体私はどうしてしまったんだ。
貴重なお休みにここへ連れ出してきてくれたお兄様に失礼ではないか。私の態度は失礼すぎる。
私は鏡に映る自分の姿を見て、自分の口元がへの字になっていることに気がついた。両手の人差し指を口端に持っていき、口角を上げる。
過去のこと、過去のことだ。それにお兄様が不誠実なことをしたわけじゃないもの。なんの問題もない。さくらと恋に落ちたらきっとさくらに夢中になるはず。
……自分にいくら言い聞かせても、私の胸はモヤモヤするだけで、広角も下がったままだった。
あまりにも戻りが遅いと心配させるなと思って、私は浮かない気分を抱えつつ席に戻ってきた。
……するとなぜか、私が先程まで座っていた席に知らない女性が座っていた。
忠お兄様が呆れて先に帰っていった?
ううん、違う。お兄様は先程と同じ席に着いている。…じゃああれは誰だ?
そこには20代後半と思わしき女性と、3歳位の男の子の姿があった。彼女はその男の子を側に付いていた壮年の女性に任せる。男の子は壮年の女性に連れられて退店していった。
ここに残ったその女性はテーブルに肘をつくと、忠お兄様の顔を覗き込む姿勢をしていた。
私は何が起きているのかわからず、その場に棒立ちしていたのだが、彼らは私の存在など見えていないのか、会話を始めた。
「君の息子は大きくなったな、今何歳だ?」
「もうすぐ4歳よ。…忠は順調に出世街道歩んでいるみたいね」
「お陰様で」
女性と話す忠お兄様の姿が妙に大人に見えて、私はなんだか疎外感を覚えた。
その女性は、私の知らない忠お兄様を知っているような口ぶりで「あなたは出世する人だと思っていたわ」と笑うと、煙草を吸い始めた。
彼女は上流階級の人であろうか。身につけているものは上等。髪や肌も綺麗に手入れされている……誰なのだろう。
忠お兄様と同じ席に着席していても、違和感のない大人の女性……
ジクリ、ジクリと私の胸が傷んだ。
「私達、あの頃に戻れないかしら」
「…何を馬鹿なことを」
「子どもを産んだらあの人は私を女としてみてくれなくなったわ。今では別の女に夢中よ。それも吉原の遊女!」
女性は自嘲すると、思いっきり煙を吐き出した。
ていうか今ものスゴい発言を聞いちゃった気がする。既婚者の子持ちの女性だよね? それが独身の忠お兄様に不倫を持ちかけた…?
この大正時代に不倫はないとは言えない。
だけど、女性がそれをしたらどんな目に遭うか…この時代を生きる人ならわかるだろう……正気かこの人。
だいたいお兄様のお知り合いなら、お兄様の生い立ちを知っているはず。お妾さんだったお母様から生まれた忠お兄様は辛い境遇で大変御苦労なさったのに……そんな相手にあまりにも無神経な……
「折角のお誘いだが、遠慮しておくよ」
忠お兄様は冷静な声で迷いなくお断りしていた。
私はそれを聞いてホッとした。
ありえないとは思っていたが、もしも揺れてしまったらと不安もあったのだ。
忠お兄様は椅子からゆっくり立ち上がると、ゆっくり歩を進めた。そして腕を伸ばすと、女性に見せつけるように私の肩を抱いた。
「連れが戻ってきたので失礼するよ。基子さん…君の夫君にはよく伝えておくよ」
私がここにいることを忠お兄様は気づいていらしたみたいだ。私はてっきり存在を忘れられているかと思っていた…。
……ちょっと待てよ、いま基子って呼んだ? この人が先程話題に上がった元恋人!? 忠お兄様を捨てたという噂の…!
「…あらそう。残念だわ」
女性の口ぶりはあまり残念ではなさそうである。寂しさを埋めてくれる相手なら誰でも良かったのだろうか。
忠お兄様を捨てて、別の男性と結婚した彼女は今、旦那さんが吉原の遊女に夢中になっていると言っていた。
遊女も生きるためとはいえ、なんだか切ない話だ。
「君には息子さんがいるんだ。あまり自棄になるんじゃないぞ」
「わかっているわよ」
苦笑いを浮かべた女性は、煙草を灰皿でもみ消すと「邪魔したわね」と言ってこの場から立ち去っていった。
変な空気になったので、私達もお店を出て、来たときと同じく車で帰ることにした。
私の周りでは結婚が決まった同級生もいる。女の子は皆、結婚がゴールと信じて疑わない。花嫁になることを夢見ている。
だけどそれは通過点に過ぎない。
女学校を退学した先輩が嫁ぎ先で酷いいびられ方をして何度も流産しているという噂を聞くこともあるし、逆に乗り気じゃないけど親に逆らえずに結婚した人は意外とうまくいっているとも言う。
好きな人と結婚するために駆け落ちして失敗して、離れ離れになったという話も聞く。
結婚はおままごとじゃない。結婚とは周りの家族も関わっていくこと。自分たちだけが幸せならハッピーってわけには行かないのだ。
この時代はあくまでお見合い結婚。親の決めた結婚。恋愛なんて結婚してからするものだと考えられていた。
あのドラマ、大正浪漫・夢さくらのように互いの想いが叶う話はめったに無いのだ。
忠お兄様が車を運転している間、私も彼も無言だった。本当はもっと外の風景を眺めていたかった、カフェを楽しみたかった。彼と沢山おしゃべりしたかったのに……お兄様に悪いことをしてしまったわ…貴重なお休みに連れてきてくださったのに……
家の前まで送り届けられた私は、車のドアを彼に開けてもらって降車した。
別れる前にせめて今日のことを謝ろうと思ったのだが、見上げた先にいた忠お兄様の表情があまりにも真剣で、私は声が出せなくなった。
「亜希ちゃんがもうすこし大人になったら伝えたいことがあるんだ」
「……伝えたいこと?」
大人になったら、って?
お兄様の中でまだ私は小さな子供なの?
私はいつも子供扱いしないでと言っているのに…!
「もうお兄様!」
子供扱いに文句を言おうとしたら、彼の大きな手が降りてきて私の頭をそっと撫でた。
小さな頃から撫でられてきたその手。
私はその手に撫でられると嬉しくて、もっともっと褒められたいと思っていた。
なのに、今は触れられている部分が熱い。
「…さ、もううちに入りなさい。今日は色々とごめんね」
お兄様の手がゆっくりと離れていく。だけどまだ撫でられた感触が残っている。
待って、今じゃ駄目なの?
お兄様、私に何を伝えようとしているの?
踵を返して車に戻ろうとする彼へ「待って」と手を伸ばそうとして空を切った。
お兄様は振り返ることなく、車に乗り込んだ。エンジンを噴かせて車は走り去っていった。
彼の中で私は未だに幼子のままなのであろうか。
彼に褒められたくて勉強を頑張った。
彼のお陰で勉強することの大切さを学んだ。
彼に近づきたくて頑張った。
彼に釣り合う大人になりたかった。
はやく大人になりたい。
だけど大人になったら、もう子どもには戻れなくなる。
今日会ったお兄様の元恋人である基子さんを思い出しては苦い気持ちが蘇った。
大人になりたいはずなのに、まだ子どもでいたいと矛盾した感情にかき消されそうだった。
「亜希子お嬢さん? どうしたんです、外でボーッとして」
住み込み書生の吹雪さんがうちの玄関から出てきて声を掛けてきたが、私は上の空状態のまま、しばらくその場に突っ立っていた。
|