ワタシはひなた
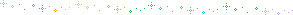
『もういいよ! お母さんの馬鹿! ケチ! 大嫌い!』
『こらひなた待ちなさい!』
その日の朝、私は親と喧嘩して飛び出すようにして家を出た。
理由は些細なことだった。駄目だと言われて憤慨した私はお母さんと口論になったのだ。一方的に憎まれ口を叩くと、お母さんが止める声を無視して学校にでかけたのである。
私はイライラしながらバス停でバスが来るのを待っていた。そして定刻遅れでバスが到着したので、定期券を乗車口の機械にタッチしてバスに乗り込むと、ひとり席に座っているのがお決まりとなっているあの人の姿を見つけた。
【ご乗車、ありがとうございます。次はー△△前ー】
(今日も同じバスにいた。…髪の毛切ったんだ、短くなってる)
あの人の後ろ姿を見つめるのは毎朝の光景。最初は同じ高校だ、カッコいい先輩だなって思っていただけなんだ。
(体調悪そうな人に席譲ってあげてる。優しいなぁ)
よく周りに気づく人なのか、バスの中でその人は何かと人に親切だった。
車椅子の人がいたら、スロープを出している運転手さんのお手伝いをしてあげていた。他にもバスの中で騒いでお母さんを困らせている子どもがいたら、そっとその子を窘めた結果、子どもに懐かれてバスを降りそこねたり。
人によってはおせっかいにもなることかもしれないけど、私は優しい人だなぁと感心していた。
私の存在を把握しているかもわからない、話したこともない人。
今日も私はこっそり彼の観察をしながらバスに揺られる。
だけど、その日はいつもとは違った。
──ドォォォン!
大きな、身体に響く衝撃音とともに、横からものすごい圧力を全身に感じ取った。席に座らずに立っていた私はその衝撃に耐え切れずに横に吹っ飛ぼうとしていた。
バスの右車体には大きな歪な窪みが出来上がり、その部分の椅子が外れて座っていた人が吹っ飛んだ。辺りには窓ガラスが散乱していた。
何が起きたのかわからなかった。そんなこと悠長に考える暇もなかった。
ギュイギュイとバスのタイヤがアスファルトを削っている音が耳に刺さる。何らかの事故に巻き込まれてバスは操作不能となり、蛇行運転をしていた。
挙句の果てにバスが横転し、ものすごい衝撃に身体が投げ出された。
為す術もない。今の衝撃で手すり棒から手を離してしまった。縋るものがなにもない私は背後に飛ばされ、どこかに頭をぶつけると覚悟したその時、どこからか伸びてきた腕が私を包み込んだ。
その人の腕からは優しい香りの柔軟剤の匂いがした。誰かに守られながら、私の意識は暗転したのだ。
■□■
「……」
目が覚めると、そこは白い天井だった。身体が重怠くて動かすのが億劫だったが、肘を使ってなんとか起こすと、周りは白いカーテンに仕切られていた。
ここはどこだろう。
思い出そうとして私は考え込む。
──そうだ、私はバスで事故に巻き込まれたのだ。
そして、“真夜”は自分が作り出したもう一人の自分。
私は鏡の世界の夢を見てきたんだ。
私が望んだ、正反対の世界。
私は、元の世界に戻ってきたんじゃない。夢から目覚めたんだ。
──もう真夜ちゃんとは会えない、望とも。
だって、もともと存在しない人間なんだもの。私が作り上げた夢の世界の人だから。
ここに戻ってくるのを望んでいたのに、私は泣きたくなるような気持ちに襲われた。
「…ひなた?」
その声に私は顔をあげる。
そこにはクマをこさえたお母さんがいた。動きやすさを重視しておしゃれに無頓着なお母さんは見慣れたトレーナーとデニム姿だった。
ブランド物に身を固め、香水の匂いのするおしゃれだけど冷たい眼差しを向けるあちらの世界のお母さんではない。
「お、かあさん」
「よかった、あんた一ヶ月以上目覚めなかったのよ」
お母さんの優しい声、優しい眼差しに私の声は震えた。
ずっとずっと会いたくてたまらなかったお母さんにやっと会えたことが嬉しくて。
「おかあさん、おかあさん! わがまま言ってごめんなさい。ひどいこと言ってごめんなさい!」
事故に遭う直前に喧嘩別れした時、私はお母さんにひどい言葉を投げかけて家を出ていった。
私はひどい娘だ。甘えて不満ばかりで、本当にわがままな人間だった。私が見た夢は、もうひとりのワタシが私を叱り飛ばすために見せた夢なのだろう。気持ちを入れ替えなければ、元の世界に帰さないぞって。
もうあんな冷たい世界懲り懲りだ。私が馬鹿だった。悪いところは直すから許してほしい。
私はお母さんに飛びつくと、しがみついてわんわん泣いた。お母さんは驚いたみたいだけど、私が泣き止むまで私の頭と背中を撫で続けてくれていた。
私はバスで通学途中に事故に巻き込まれた。原因は信号無視の車に横から突っ込まれてのバスの横転事故だ。
事故直後に運ばれた病院で受けた精密検査では頭の怪我ははなんともなかったのに、原因不明で一ヶ月以上意識不明だったのだという。
私は事故によって足首を強く打って骨折していた。全治3ヶ月らしいが、手術などは意識がないうちにササッと処置されたそうなので、後は骨を固定している金具を取る手術を受ける程度で、看護師さんからはさっさとリハビリしなさいと促された。
意識を取り戻してから改めて精密検査を受けても骨折以外はなんともないとのことだったので、お医者さんには今週末には退院してもいいと言われた。とは言っても、治るまで通院だし、リハビリにも通わなきゃいけない。
しかし、このリハビリが曲者で。
私の場合一月以上寝たきりだったので筋肉まで退化しているせいでなかなかうまく行かない。
だけど諦めてはなんにもならない。いつまでも学校を休むわけには行かないし……お母さんは「入院が夏休みと被ってよかったね」と言ってきたが、全然良くないんだけど。夏休みが病院一色で終わってしまうよ。
退院まであと数日。私は時間が空いたら筋肉を解すストレッチをしたり、リハビリをして過ごしていた。
意識不明のときに見ていた不思議な夢のことを忘れたわけじゃないけど、私はちょっとずつ前を見て歩けるようになっていた。
「ふぅ…」
リハビリしていてもまだ治っていないので以前のようには歩けない。移動はもっぱら松葉杖である。
松葉杖の扱いもこなれはじめた私はひょこひょこと移動していた。頑張りすぎたから病室でストレッチしてマッサージしよう。そんで夕飯までの時間に、学校の友達がわざわざ持ってきてくれた課題をやろう。
私は入院患者と医療従事者が利用する入院病棟の廊下を進んでいた。ここには外来患者は来ないため、そこまで人通りは多くない。
壁寄りをひょこひょこ進んでいた私は反対側からパジャマ姿の男の子がこちらに向かって歩いてくる姿を見つけた。売店で買い物したのか、手には袋をさげている。
私はその人の顔を見て、思わずつぶやいた。
「望…」
なぜ、気づかなかったのか。
私が毎朝目で追っていた彼が、鏡の世界に私の夢に出てきた“彼”だったのだ。
彼の頭にはグルグルと包帯が巻かれており、その胸元にも白い包帯がちらりと見えた。
ただ違うのは、派手で軽薄そうだった望と違って、髪は真っ黒で真面目そうな人なのだ。
……そうだ、彼とは同じバスに乗っていたんだから、同じ事故の被害者に決まってるじゃないか。
私は彼が恋しくなって声をかけようとしたが、寸前で踏みとどまった。
……望と同じ顔だけど彼じゃない。彼は私が作り出したノゾミだ。彼は私のことなんか知るはずがないのに、急に知らない女から話しかけられたら不気味なだけだろう。
あの時、最後の別れの瞬間、言葉はなくても想いを交わしあった気がしていたのに、現実は非情である。
自分の願望に傷つくなんて馬鹿みたいである。
じわりと涙が滲んで視界が歪む。私はぐっと目元を手の甲でこすると一呼吸置いた。
無い物ねだりするのはやめたじゃないか。ひとりよがりはやめるんだ。私は前を見て生きるのだ。
よしっと気を取り直して私は踵を返した。ちょっとトイレにでも行って顔を洗おう。
「──ひなた?」
前を向くと決めたのに、その声を聞いてしまったら私の決意は簡単にくしゃりと潰れてしまった。……正反対なのに、彼とは違うはずのに同じ声。なんでよ、なんでなの、私の夢のはずなのに…!
一度は堪えたはずの涙が溢れ出す。たまらなくなって、踵を返したはずの身体を戻すと彼に近づいた。
しかしちょこちょことしか進めない松葉杖に焦れて、それを手放すと包帯グルグルの足をひきずりながら駆け寄った。
鏡の世界にアナタもいたのね。
「望! …ぅわっ」
支えを失った私はバランスを崩しかけたが、彼が抱きとめてくれたので転倒は免れた。
まずは庇ってくれたお礼を言うべきなのだが、抑えきれない彼への想いが溢れて止まらなかった。
「あんな別れ方じゃ悲しい、もう一度知り合うところからやり直してほしいの!」
また一から、友達からでもいいから、私と知り合いになって、それから親しくなってほしい。彼女にしてとかそんな厚かましいことは言わないから。
ダラダラと流れる涙は止まりそうにない。彼の指が私の頬を撫でてくれるが、また新たな涙がこぼれてきてしまって私の頬はビシャビシャになっていた。
「朔。俺の名前は朔だよ」
「朔…」
私はぐしぐしと病衣の袖で涙を拭うと、彼を見上げた。そしてすんすんと鼻をすすりながら、今自分が出来る精一杯の笑顔を向けた。
あの時言い損ねた気持ちを彼にどうしても伝えたかったから。
「あのね、私、あなたのことが──……」
なのにまたその言葉を紡げなかった。
ふわっと乗せられた唇は夢の中で感じた柔らかさ、ぬくもりと同じだった。
また、キスによって告白を封じ込められた。私は彼の口づけを受け入れてそっと瞳を閉ざす。返事の代わりにキスをされて、ぎゅうと抱きしめられると、彼の心臓の鼓動がダイレクトに伝わってきた。
私はこの世で彼と再会できたことが嬉しくて、あたたかい彼の胸元に顔を埋めて泣いた。この腕の中を知っている。…パジャマから香ってくる柔軟剤の優しい香りが決定的だった。
横転するバスの中で私を守ってくれたのは彼だったのだ。
「…あなたが好きよ、鏡の世界の望も、現実の朔も全部ひっくるめて大好き」
私が囁くように中断させられた告白の続きをすると、朔は「知ってる」とくすぐったそうに笑っていた。
そして私達はどちらからともなく、もう一度口づけを交わしたのだ。
フシギな鏡の世界で出会う前から、あなたは私を守ってくれていたんだね。
──鏡の中には、もうひとりのワタシがいるの。
鏡と同じで自分とは正反対。同じ人間のはずなのにまるっきり反対のワタシがいつもそばにいる。
だけど気をつけて、一度鏡の国に入ってしまったら、二度と戻れなくなるかもしれないから──
-オワリ-
[*prev] [next#]
[ 6/6 ]
しおりを挟む
[back]