鏡の向こうのワタシ
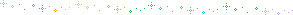
「じゃあ、あんたの居場所、あたしにちょうだい?」
鏡の中の私はそう言って、こちらへと手を伸ばしてきた。
ヌッと現れた手に私は恐怖で固まっていた。
これは、夢なのだと。
とてもたちの悪い夢なんだと思い込みたかったのだ。
幼い頃、私は不思議なことを言う子どもだった。
『鏡の向こうのお友達』とおしゃべりをしたと大人たちに楽しそうに報告していたとか。大人たちは不気味に思ったが、その年頃ではよくあるイマジナリーフレンド現象だろうと片付けられていた。
だけど、本当に彼女はいたのだ。
鏡の向こうにいるお友達の名前は“真夜ちゃん”。彼女と私は双子以上に瓜二つだった。
真夜ちゃんはいつもお姫様みたいにひらひらのお洋服を着ており、普段お古ばかりの私は彼女のことが羨ましかった。真夜ちゃんとお話した後は必ずお母さんに可愛い洋服をねだっては、「お金がないからダメ」とあしらわれていた。
真夜ちゃんはたくさん習い事させてもらえるのに、欲しい物何でも買ってもらえるのにどうして私は駄目なのか。親に尋ねてもあしらわれて終わりだった。
親のくせに何もしてくれない。
高校は公立じゃなきゃ駄目、大学に行くなら国公立で自宅通いでないと駄目。どうしても私立大に進みたいなら一人暮らしがしたいならバイトと奨学金を借りろ。と言われた。
私は友達と同じ大学に進みたいし、おしゃれな私大に通って素敵な彼氏が作りたい。
親なら何でもしてくれるはず。産んだ責任があるのに!
私は両親に対して怒りの感情を抱いていた。子供の望みが叶えられないなら子どもを産むなって。あんたたちの欲望のために生まれてやったのだから願い事を叶えろって腹の底でいつも怒りがくすぶっていた。
私は友達の顔色をいつも伺っていた。
仲間外れされると落ち込むし、皆と足並み揃えないと落ち着かない。孤独に苛まれそうになる。
私にはなんにも取り柄がなかった。
自分がなかった。
■□■
鏡の中に引き込まれた私は“真夜”として過ごしていた。
お金に苦労しない真夜ちゃんの環境に最初はウキウキしていたが、仮面をかぶったような彼女の両親に違和感を抱いた。顔は同じなのに、まるで別人。経済的に豊かだが、心は空虚で仮面のような両親。
一方で鏡の向こうで私と入れ替わった真夜ちゃんは毎日楽しそうだった。
私のお母さんと料理しただの、友達を誘ってどこどこに行っただのと楽しそうな報告を受けた。
『そのままその世界にいたら、あんたの希望は叶うのよ?』
最初のうちはそれを望んでいたが、私はこの世界の歪さに気づいてしまった。
戻りたいと思っても、真夜ちゃんはまだ満足してないから嫌だって返すだけだった。
「真夜あんた右利きだったっけ?」
「え? うん」
真夜ちゃんの友達は私とは正反対のタイプだった。流行と男を追いかける今どきの女子たちで、友人にも関わらず女同士格付けし合っている空気を感じた。
そこでも私は空気を読んで彼女らに合わせていた。
「真夜、あんたこれ好きでしょ」
そう言ってレーズンを挟んだサンドクッキーを差し出されたが、私は眉をしかめてしまう。
私はレーズンなんか好きじゃない。
「…あんまり好きじゃない」
「好み変わったの?」
食べられないので差し出されたお菓子を返却すると、相手からは怪訝な顔をされた。
「ねぇねぇそれよりもさ、Y工業の男子との合コン話あるんだけど…」
「えぇ? あんた大学生の彼氏いるじゃん」
「だって試験前とか言って会ってくれないんだもーん」
腹のさぐりあい
男の取り合い
格付け
女同士がおしゃべりする悪口ならわかるんだけど、彼女たちからは野生の肉食獣のような空気感が漂っていて私は息苦しくて仕方がなかった。
「真夜も行くっしょ?」
「え……えっと、ごめんね、もうすぐ試験があるし、私勉強しなきゃ」
勉強しなきゃ行きたい大学にすすめない。やることはちゃんとしないと、私の人生を棒に振ってしまう。それに合コンとか怖いし、そういう空気苦手だから行きたくない。
「ノリ悪くない?」
「あんまいいたくないけどチョーシ乗ってない?」
ギロリと睨まれて、不快な気持ちを押し付けられたら私は萎縮してしまう。
「あ…」
複数の目が私に突き刺さる。異物を見るような、裏切り者を見つめるような鋭い眼差し。怖くて声が出なくなっていると、隣に座っていた子が私の肩に腕を回してきた。
「ね? 悪い夢は見せないからいこうよぉ」
「……」
どうして私はここにいるんだろう。
私は自分の世界でも友人たちの顔色ばかり伺っていた。親にはわがままを言うのに、友人たちの前では借りてきた猫のようにおとなしくしてた。
こんな時、私の友達のあの子は私の意見を聞いてくれた。もうひとりのその子は意見が違えば違う案を出してくれた。
あぁ違う、気を遣っていたのは私だけじゃない。
彼女たちも私を見て気を遣っていたんだ。
自分は友人に恵まれていた。
いつだって顔色伺っていたけど、自分を出せばきっと友達は普通に受け入れてくれたはず。
私は傷つき裏切られることを恐れて本当に友達を理解しようとしなかったんだ。
ブーッブーッとマナーモードに設定したスマホが振動する。真夜ちゃんが使っていたスマホ。液晶画面には知らない男の人の名前が表示されていた。
スマホには動画・SNS・ゲームのアプリの他に出会い系サイトの利用履歴もあった。SNSで会ってくれる男性を探して交流していた履歴もあった。
私はそのどれも触らず無視していた。これは真夜ちゃんのものだから私が好き勝手に触っていいものじゃないだろう。
いつも一人ぼっちだったのかな?
寂しさをごまかしてきたのだろうか?
真夜ちゃんは昔から買ってもらったものや習い事、彼氏のことを自慢していたけど、実は孤独だったのかもしれない。私の前では虚勢を張って隠していたのだろうか…
私は親に恵まれていた。
決して裕福じゃないけど、お母さんはパートで疲れても温かいご飯を毎日作ってくれる。私はそれをいつも手抜きだとケチつけていた。
しつこく話しかけてくるお父さんが鬱陶しいと思っていたけど、ここでは話しかけてくれるお父さんが存在しない。
真夜ちゃんの両親はお互いに別のパートナーを見つけて、そちらの相手をするのに夢中。娘のことなんてほったらかし。
今は私が真夜ちゃん。
──私はいないモノ扱いなんだ。
私はこの世界でひとりぼっちだった。
[*prev] [next#]
[ 1/6 ]
しおりを挟む
[back]