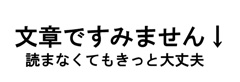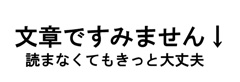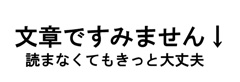 (19-1(文章)) (19-1(文章))
18の続き、というかあの後。
拙い文章なので先に謝っときます。
たぶん読まずに19-2へ行っても平気です。
――――――
マルコの車の助手席に乗り込んでシートベルトを締める。
何度か送っていってもらっているけど、好きと自覚してからは初めてだからかシートベルトを締める手が小さく震えた。
マルコがいつも吸ってるタバコの臭いが微かに漂っている、そんなことにさえ今はただバカみたいにドキドキして。
マルコが運転席に乗り込みチラとおれを見るので、なんとなくいたたまれなくなってパッと窓の外を見た。
なにを言っていいのか分からない、言葉を発していいのかすらおれには分からなかった。
沈黙は別に嫌いじゃないが、今この場での沈黙は非常に厳しい。なにか変なことを口走ってしまいそうだと思った矢先、ふいにラジオから声が聞こえた。マルコも同じように思ったのだろうか、ふと隣を見ればマルコもこちらに気づいたようで、「タバコ、吸っていいかい」と箱を掲げる。
「窓は開けるからよ」
「いいよ、別に」
いつも勝手に吸うくせに、なんて思いながらおれはまた窓の外に視線を移した。ラジオの音に混じってライターの火をつける音がして、少し長めのため息のような――マルコが煙を吐いたのだろう、臭いがこちらまで漂ってきた――音が聞こえたと思ったら、エンジンがかかって車が出発した。
密室に二人きりだ、意識すれば体は火照り微かな音にも気配にも敏感になってしまう。
マルコが灰皿を取り出すときやシフトレバーに触れるとき、伸ばされる手がおれに向くのではないかと自分勝手な恥ずかしい妄想をしては体が跳ねる。
マルコはなにも言わなかったけれど、どう考えたっておれの反応はおかしかったに違いない。
だんだんとおれはこの二人きりの空間が苦痛にしか感じなくなってしまった。それはそうだ、好きな相手とこんなにも近いのに、なにもできない、なにもされない、だなんて。
気づけばおれは早く家につかないか、とそればかり考えていた。
家まで車で20分。
今のおれにとって、20分は長すぎた。
ようやく家の近くに差し掛かる。
そこへ来てひとつの疑問が浮かんだ。
このまま、終わってしまっていいのだろうか。
先程の決意はいったいどうしたんだろう、マルコに想いを伝えなければ、と、確かにそう思ったはずのに。
おれから行動しなければきっとなにも始まらない、幸いマルコはおれを嫌ってはいないようだし、言ってなにか変わるなら。
マルコの気持ちが少しでもおれに向いてくれるのならば、行動することに価値はあるはずだ。
ローも言ってた、おれから告白しろとか、誘ってみろとか、なんとか。
おれだってこれ以上我慢はできないし、不安ばかり募っていく毎日なんてまっぴらごめんだ。
マルコを好きだと気づいてからこっち、おれの胸中にあったのはマルコへの大きすぎる好きと、大きすぎる不安だけだった。
嫌われたくない、関係を壊したくない、好きだ、好きすぎて辛い、こっち見ろよマルコ、ダメだ、おれに触れないで、息ができなくなる、あんたが好きすぎて怖いよ、こっち見んなよ、心臓破けて、しにそう。
毎度毎度、マルコの一挙一動にドキドキさせられて、まるで全身が心臓になったくらい体が脈打って。たいがい女々しい、わかっていても体が反応してしまうのだから仕方がない。平然としていたつもりだったけど態度には出てしまっていたように思う。
どうしてこんなにも好きなんだろう、男同士だとか年の差だとか、そんなもの通り越してただひたすらに好きだ。こんなに欲しいと思った人が他にいただろうか。
――そうだ、おれはこの人が欲しい。
じゃあ、やることはひとつじゃないのか?
ぎゅっと唇を噛んで両手でシートベルトをキツく握る。
決心とほぼ同時に、車はゆっくりと停車した。
「着いたぞ」
「…へ、」
外を見やればそこはおれのアパートの前で、いつの間にこんなところまで来たんだろう、と思った。
あまりに物思いに耽りすぎて記憶が全くと言っていいほどない。
マルコを見ると降りないのか、と言いたげに首をかしげている。
だけど今降りたら、また今日のような日の繰り返しになってしまうのではないか。
もやもやと考えて、決心をして。それなのにマルコの前になると怖じ気づいてなにも行動できなくて。それを悔やんで、また決心をして、それで?
いつかマルコが店に来なくなるかもしれない、おれに興味を失うかもしれない、そんな日が来たらおれは今この場でなにもしなかったことをきっと後悔するだろう。
ついさっき決心したばかりじゃないか。
好きだと一言言えばいい、なにも難しいことじゃない、はずなのに。
手をドアに伸ばしながらも開けるのを躊躇しているおれを不審に思ったのか、マルコの訝しげな声が降りかかる。
「エース?降りねぇのかい」
「……あ、いや、」
酷く喉が渇いていた。相づちの一言さえ喉に引っ掛かって掠れていると言うのに、大事な言葉は果たしてきちんとマルコに伝わるのだろうか。
相変わらずマルコの顔を見ることも出来ず、かといって言葉が口をつくでもなく、ただ鯉のようにパクパクと開閉を繰り返すだけだった。
なんて、なんて言えばいい。
帰りたくない、まだ側にいたい。あんたが、好きだから。
目頭が熱くなってきた。
気持ちを伝えるというのは、なんて難しいことなんだろう。
好きな人に気持ちが伝わらないのがこんなにももどかしいだなんて。
マルコも、もしかしたら以前は、こんな風に悩んだだろうか。
あんなに軽々と口にしてはいたけれど、心の中では、店の外では、後悔や不安でいっぱいだったのだろうか。
いや、マルコはおれみたいなガキじゃないし、言葉にするのは簡単だったのかもしれない。
おれに振られたところで痛くも痒くもないだろう、マルコには言い寄ってくる女だって多いはずだ。
冗談半分、だったのかもしれないし。
考えれば考えるほど思考はネガティブになっていき、ドアに伸ばす手に力がこもる。
――でも、でも。
今日は、ダメだよ。なにもせずには帰れない。帰りたくない。一緒にいたい。
気づけばおれの右手はマルコの方に伸びていた。
本当はすがり付きたいけれど、抱き締めてもらいたいけれど。今のおれでは、マルコのスーツの端を掴むのが精一杯だった。
<< back >>
|