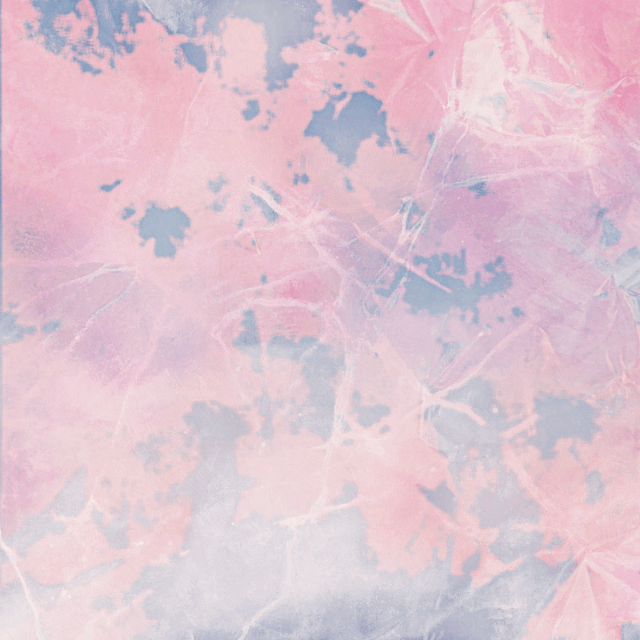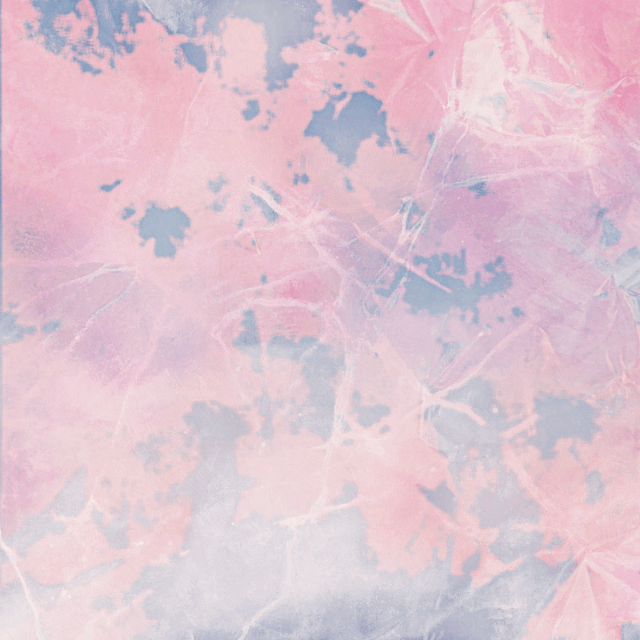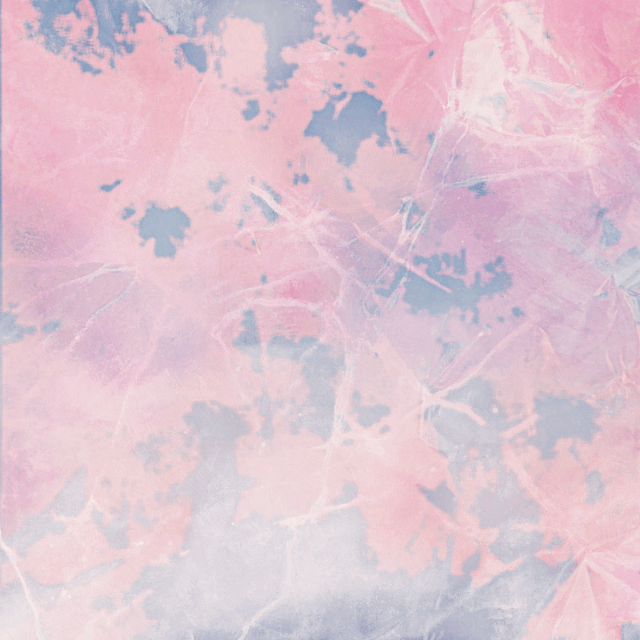
地獄の桜の樹の下には
2
桜の樹の下には幼馴染が埋まっている!
これはとても信じられないことだし、信じたくもないことだった。けれど、直視しなければいけないのだ。俺の手にはまだ、幼馴染のクララの屍体にかけた土の感触が残っている。夢にまで見た。夢で何度も、もう一人の幼馴染の蒼と一緒に、彼の屍体を埋めた。そうして朝、目を覚ますと、やはり、幼馴染の姿はどこにもない。どこにもなくて、ただただ悲しくて、俺と蒼は自殺を考えるのだけれども、どうしても死ねなくて、毎日が過ぎるばかりだった。
――と、ここまでの夢の話すら、夢の中の話だった。それに気づいたのは、俺が館に来てからのことだった。どんな経緯だったかはなぜか記憶がないのだが、とにかく、俺と蒼が館に住み始めることになった時、当たり前のように、クララも同じ日に入居していた。一緒に歓迎会に出席し、「実は僕たち、幼馴染なんです。ね、」と、クララはマイクに向かって照れたように笑っていた。ああ、クララを埋める夢を見たり、自殺未遂をしたりした日々のことは、夢だったんだ。俺と蒼も、顔を見合わせて、はにかんで笑った。
館にも、桜の樹が植わっていた。館には広い庭があったが、そこではなくて、館の入り口の門も前の庭のところに、桜が何本か植えられていた。どれも大木だった。
俺たちが入居したのは三月半ば頃だった。荷ほどきや部屋の整理などをして、日々をあわただしく過ごしているうちに、桜は見ごろを迎えた。食堂の前の廊下にある、伝言用の大きなコルクボードに、『お花見会開催決定!』『とき:3月2×日』『ところ:入口の門の前の桜』と書かれたポスターが貼ってあるのを見つけた。いや、見つけたのはクララだったか。
「桜の樹の下に、タイムカプセルを埋めに行こう」
クララは、そのポスターを指さして言った。「ほら、タイムカプセルを埋める企画があるんだって。お花見会に」俺と蒼は顔を見合わせた。クララは無邪気な笑顔で言った。「蒼とキリネも、やろうよー。僕、絶対やるから」
そういうわけで、俺は、ほどいた荷物の中から、ひと巻きのリボンを探し出した。紅い色をした、サテンリボン。これは幼いころ、クララにあげた花束を結うのに使ったものだ。俺と蒼で花屋に行って、やっぱりいろんな色の花があった方がいいよな、とかなんとか言って、色とりどりの花を一輪ずつ選び、なけなしの金をはたいて、良く言えばカラフル、悪く言えばまとまりのない花束を作った。それを、ピアノの発表会での演奏を終えた直後のクララに渡したのだった。
お花見会当日、館の住人の多くが門の前の桜に集まり、桜を愛でた。どこから引っ張り出してきたのか、運営委員会が野外用のテーブルとイスをずらりと並べて、料理も出してきて、パーティみたいだった。館に来て初めてのイベントだった。さわがしかったが、心地よかった。人見知りの蒼も、会の雰囲気に影響されて、少し上機嫌だった。
クララだけが、少し、上の空だった。いつもどこか、遠くの空を眺めていた。魂がどこかへ飛んでいっているようだった。どこ見てんだよ。空見ても、花曇りで、雲しかねえよ。とは言えずに、俺はアップルジュースの入った紙コップをすすっていた。
タイムカプセル企画の代表者が、大きな箱を持ってきた。入れたいものがある人はこの中に入れてねー、と、大きな声で言った。俺たちは一緒に席を立って、箱の方へ向かった。
「蒼、それ何」
「手紙」
「誰宛?」
「未来の俺宛」
蒼は封筒を一度ひらひらさせてから、箱の中に放り込んだ。俺もリボンを放り込んだ。他の住人達も、次々に何かしらを入れていった。手紙を入れる者が多かったようだ。
「クララは何にしたの」
「ちょっと、後で。置いてきちゃった」
はは、と、クララは笑っていた。「みんな手紙、入れるんだね。僕もそうすれば良かったなあ、あはは」と、言っていた。
俺たちがわいわいと箱の周りに集まっているうちに、タイムカプセルの企画者たちは、桜の樹の下に穴を掘り終えていた。人が入れそうなほど大きな穴だったが、この箱をいれるにはそのくらい掘らないといけないのかもしれない。ついに、箱に蓋がされる。
「クララ、さっき入れてなかったけど、もう入れたの」
「うん。もう大丈夫」
大丈夫、という響きに合わせて、クララの金髪がさらさらと揺れていた。
男性二人がかりで、箱は穴へと運び込まれた。企画者たちが、箱の上にしずしずと土をかけていく。箱が埋まりきり、『××年に埋めたタイムカプセル』という標が立てられると、自然と拍手が起こった。ぺちぺち、と、クララは弱々しい拍手を捧げていた。
じゃあ、そろそろお開きにしまーす、みなさん、テーブルとイスを片付けてください、というアナウンスが流れた。紙皿と紙コップは所定のゴミ袋に捨てた。テーブルやイスは、きちんと畳んで、そういうものをしまってある倉庫に運び込まれた。三十分ほどで、すっかり片付いた。満開の桜だけが残った。
人気のなくなった庭から、桜を眺めていた。すっかり皆は館に戻ってしまっていた。残っていたのは俺と蒼だけだった。桜からはひとつの花びらも落ちてこない。静止画のように、どの花一輪も、五つの花弁を揃えている。ずっと見ていると、背中をぞわりと大きな芋虫が這っているような心地が急にしてきた。メランコリックで、エロティックで、ミステリアス。俺は急に、あの、夢の中の、強烈な吐き気を誘発させるような、腐乱したような、あの土のひどく臭いにおいを思い出した。こんなに美しくて、気色の悪い桜がどうして自然に生まれるのか。いや、生まれない。
ああ、桜の樹の下には屍体が埋まっている!
気づくと、隣に立っていた蒼がしきりに脇汗を拭いていた。俺も、べとべとするような、気持ちの悪い汗をかいていた。
ああ、この世のどこかの桜の樹の下には幼馴染の屍体が埋まっている!――そして、それを埋めたのは俺たちだ。
「ああ、まだいたの」
声がして、はっと振り向いた。クララがそこに立っていた。「桜って、綺麗なんだね」と言いながら、桜の方へ歩いていく。そして、一本の桜の樹の幹を撫でた。春風が吹いて、汗をかいている背中に張り付いたTシャツを引きはがした。
クララはにっこりと笑った。いや、彼は、本当にクララなのか。蒼の喉ぼとけが上下して、唾を飲み込んでいるのがわかった。俺は、唾が固すぎて飲めなかった。ああ、神様、俺たちは幼馴染だけれど、本当に幼馴染なのでしょうか。俺は今、クララのゆっくりと開く唇を見て、次のクララの言葉は、絶対に聞きたくないと思ってしまいました。身体が竦んでしまいました。神様、もう、俺たちは、許されません。
「もし僕が死んだら、桜の樹の下に埋めてほしいな」
桜のようにほんのりと紅くなったクララの頬が、やわらかく上がった。天使のような残酷な微笑みに、俺たちは無言で、全てを切り裂かれていた。春風がまた、強く吹いた。