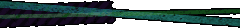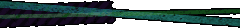
オオカミの皮を被ったウサギ R18
珍しく帽子屋が、酷く酔っている――。
暦の上では夏が終わって、季節は秋だけど、まだ残暑が厳しかった。
それでも夜になれば、爽やかな気持ちいい秋風が吹き、昼間の暑さを忘れさせてくれる。
馴染みの店からの帰り道。
酔い醒ましにも丁度いい、その風を受けて、白うさぎと帽子屋は深夜の人気のない街を歩いていた。足元の覚束ない帽子屋を白うさぎが支えながら。
「ほら、しっかりしろ!」
「あれぐらいの酒でぇ〜、俺わぁ〜、酔わないぞぉ〜」
あの帽子屋がケラケラと笑っている。
しかもいい事でもあったのか、かなりのご機嫌モードだ。
いつもは人を喰ったような笑みで、自分のペースを乱さない帽子屋のこの姿は、ある意味、貴重かつ、見物だ。
写真でも撮っておきたいくらいだ。
しょうがねぇーなと思いつつ、帽子屋の珍しい姿を拝めただけでも白うさぎは満足し、帽子屋をよいしょと抱え直して、帰路を急ぐのだった。
宿に着くと白うさぎは帽子屋を部屋まで連れていき、ベッドにそのまま帽子屋を放り込んだ。
「俺はー、うさぎちゃんのことぉ、大好きだぞーぉ…」
帽子屋が白うさぎに絡んでくる。
「ハイハイ、わかったから」
酔っ払いの云うことなど、いちいち聞いていられない。白うさぎは帽子屋の軍靴を甲斐甲斐しく脱がしていく。
「なんだぁ、信じていないのかぁ?…証拠を見せようかぁ?大尉殿ぉ…」
帽子屋はクスクスと笑って立ち上がると、酔っ払いのくせに足音も立てずに近付いてきた。
そしてするりと白うさぎの首に腕を回す。
白皙の頬を今は朱く染め、酔って潤んだ蒼い瞳が白うさぎを映す。
にっこりと微笑んだ帽子屋の表情は妖艶さを含みつつ、いつもよりあどけなさを感じた。
そんな帽子屋から目が離せなくなっていると、首に回った腕で強引に引き寄せられて、唇を奪われた。
「っ?!んっーーーっっ!!」
突然のことに白うさぎの反応は遅れた。
帽子屋はそんなことはお構いなしに更に口づけを深くしてくる。
白うさぎの少し乾いた唇を舐め、薄く開いた隙間から舌を差し入れ、咥内を貪った。
舌で歯列を舐め、上顎を擽る。白うさぎの蠢く舌を捕らえて、くちゅくちゅと絡め合わせれば、口端から唾液が伝う。
「ん、うっうぅーーーっんっっ!!」
長い口付けに白うさぎが息苦しさを覚えて、帽子屋の背中をバンバンと叩き、やめるようにアプローチする。
- 1 -
[*前] | [次#]
目次 拍手
TOPへ