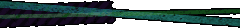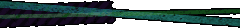
今の異常な状況に、ダムはまともな思考能力を失いつつあった。
普段のダムなら今の帽子屋の云うことなど、無視することもできたはず。しかし勝手に部屋に入り、ベッドの上で淫らな行為をしていた後ろめたさと悦楽に浸っていた頭では冷静な判断など無理だった。
だから、帽子屋の声に逆らえず、上着のボタンに手をかけてしまう。
緊張と羞恥心でボタンを外す手が震える。そしてダムはゆっくりとした動きで上着を脱ぎ捨てた。
帽子屋がいつもの冗談だと云ってくれるのを期待していたからだ。
でもその動きは帽子屋には勿体ぶって、煽っているようにしか見えなかった。
「どうした?手が止まっているぞ」
「っ!……」
だけどダムの考えは期待はずれに終わる。
帽子屋の表情からはやめようという意思は窺えない。
ダムは諦め、中途半端に脱いでいたズボンに手をかけて、緩慢な仕草でズボンから脚を抜くと、それをベッドの下に落とした。
そこでダムは一旦動きを止め、帽子屋をもう一度窺い見る。
「俺は全部と云ったはずだ。まだシャツと下着が残っている」
物分りの悪い生徒を叱るように帽子屋は云い放った。
今度こそ完全に淡い期待は打ち消され、ダムは観念して残りのシャツと下着を潔く脱ぎ捨てた。
身に一糸も纏うものがなくなり、そこからどうしていいか判らずに所在なさ気にする。
帽子屋の視線から逃れるように脚を閉じて隠そうとするダムに、
「いいぞ、再開しろ」
と、意地の悪い笑みを口元に浮かべ、帽子屋は促す。
帽子屋の声には魔力があるんじゃないかと、思えるほどに勝手に手が動き出す。
上下に扱くと、萎えかけていたソレは簡単に力を取り戻した。
「ぁん……はぁ…ぁ……んっ」
「よく見えるように、もっと脚を開け」
「……っ!」
非情な命令にダムは、一瞬身体をびくりとさせるが、帽子屋の真っ直ぐにこちらを見ている蒼い瞳に逆らえずに、おずおずと脚を大きく広げた。
部屋の明かりも点けずに、差し込む月明かりだけを頼りに浮かぶ、ダムの痴態はとてもなまめかしく、帽子屋を充分に愉しませた。
「あっ……ん…ぼ、ぼう…し…やっ」
帽子屋が自分を見ている。
自分とは対照的に脚を組み、悠然と椅子に座っている帽子屋の嬲る視線だけでもダムの身体を熱くさせ、手の動きが速くなる。
- 3 -
[*前] | [次#]
目次 拍手
TOPへ