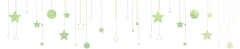 wonder(海王天王)
wonder(海王天王)悠雅のベッドは気持ち悪いくらいふかふかで、倒れこむとズブズブと体が沈みこんだ。仰向けになったらきらきらした小さな光が散りばめられたシャングリラ?とかいうやつと、果てしなく高い天井が勝手に目に映る。嗅覚が紅茶の匂いをキャッチした。果物……しかもオレンジティーか。相変わらず洒落ている。しかも淹れるのは悠雅本人ときたもんだ。執事とか雇わないのかと訊いた事がある。そしたら、悠雅は真面目な顔して、そしたら俺自身が怠ってしまうからと言っていた。悠雅のそういうところが、俺は、キライだ。
「むーちゃん、紅茶が入った。スコールもある、食べないか?」
「んー」
適当に返事を返すと、俺は起き上がって、悠雅が持っていたスコールを慣れた手つきで取って食べた。ぼうとしている俺は悠雅の顔がぼうとしか映らない。けど肌色の面積が多いから、ああこっち見てるなと思って、俺は親指についたスコールのカスを舐めた。スコールはこんがり焼けている。味は、ま、まあまあかね。
「わざわざ俺のを取る必要があるのか?」
「ない」
間髪入れずに返すと、悠雅は俺の事をよーく分かってるから、それ以上追求して来なくなった。優雅な佇まいで紅茶を飲む悠雅は、そのままそっくり絵にしても誰も文句は言わないだろう。悠雅はお坊っちゃんだ。型にはまったお坊っちゃんだ。俺は何の型にもはまりたくないと思った。だから髪も整えてないし、よくサボるし、親には期待も何もさせていない。体が羽のように軽い。
しかし悠雅は、そんな俺の唯一の枷なのだ。緩いのか鋭いのか分からない悠雅は俺をまどわせた。
「高校、決まったのか?」
「希望光」
「サッカーの名門か」
「サッカーはやらない」
「嘘をつけ。むーちゃん、サッカー大好きだろう」
「誰も好きとは言ってないだろ?」
「言ってないけど、分かるさ。ボールに込められた思いが分からないほど、俺は落ちぶれてはいない」
悠雅の言葉は、一言一句に重さが宿る。ずっしりと漬け物石のように重い言葉は俺の枷へと変わる。当の本人はまた、可笑しそうに無邪気に笑って、軽くキーパーの構えをしてみせたけれど。これがきっと、生まれ持ったものの違いだろう。悠雅が指先を動かすだけで、俺が通っている学校の人間のほとんどを、従えさせる事も出来る。天皇院財閥。どんなに足掻いても外される事のない悠雅の枷は、俺の十倍以上の大きさはあるだろうか。
それでガチゴチに動けなくなっていたら、今頃俺は悠雅の傍にいなかったに違いない。
「よし、俺も希望光に行こう」
「………………聞こえなかった」
「それならもう一度言おうか。希望光のサッカー部に入る」
むーちゃんと一緒に。そう言いながら、紅茶をその立派な喉に流し込んだ。いっそ紅茶と一緒に、先程の発言も流れてしまえばいいと思った。けれども奴の言葉は重くて重くて持ち上げると腰が痛くなるから、それくらいではびくともしない事を、俺は悠雅より知っていた。
「あそこは曲がりなりにも、何年か前に日向と西園寺のお嬢さんが入っていた場所だ。お父さんが拒む理由はない」
「………いくら幼馴染みと言えど、一緒にいる理由はないはずだ」
「あるさ。お前がなくても俺にはある。むーちゃんは俺の世界だからな」
「困る。俺はそんなでかい存在になりたくない」
でかい存在である悠雅のでかい存在なんて真っ平だ、俺は雀の鳥の羽根の一部で十分なのに。でかくなって何になる。俺は小さく生きていたい。そのために幾度となく嘘を重ねてきたはずなのに………悠雅は何故か、俺を嫌わないのだ。
悠雅はおもむろに立ち上がると、観音開きの窓の前に立って、ゆっくりゆっくりと押し開けた。それは何かを切り開く扉にも、こじ開けた心の窓にも見えた。太陽の光が一斉に、悠雅に向かって雨のように降り注ぐ。雨にしては、俺には眩しすぎたけれど。
「なあむーちゃん、俺は世界を見たい。世界を歩いてこの目で見たいんだ。そのためにはここから出ないといけない、でも出れない。でもむーちゃんに着いていけば、ほんの僅かだけど世界を見られるような気がしてならないんだ」
鋭く力強い瞳を、何処とも言えない地平線に向ける悠雅は馬鹿みたいにまっすぐだった。俺には決して不可能なまっすぐだった。齢十五のお坊っちゃまは、生まれてこの方学校へ行った事がないらしい。パーティくらいしか外に出ることは許されない。正に監獄の世界。だから学校に行ってしまえば世界を知って世間体を知って、その瞳が曇る事になるだろう。
面白そうではあるが、非常に勿体無い。俺は何も言えずに、あ、そう。とだけ返して、早々に屋敷を後にした。もうそれが三年前とは信じられない。
「おはよう、むーちゃん」
「だからそのむーちゃんを止めろ」
寮まで同じな悠雅とは毎朝目を合わせるが、今日は何だか一段と輝いていた。共に飯を食って、朝練へと向かう。朝の清々しい空気を纏った無駄に………いや人数考えたら妥当な大きさの部室は、今日また新たな一歩を踏み出す俺達を迎えてくれていた。
「おはよう」
「おはよう、早いな根室」
「………今日、また新たな部員が入って来るのが楽しみで。あまり夜も寝てないんだ」
「子供みたいだな」
「とか言っておきながら、さっき一年に負けてられるかって意気込んでたのは誰だ?むーちゃん」
「さあ?誰だろーなー」
「人の事言えないぞ魚沼」
中に入ると、両側に備え付けられたロッカーの間に鎮座するベンチに、根室が座っていた。既にユニフォームに着替えている部長と談笑しながら俺もレギュラーユニフォームへ着替える。これが朝練になると皆表情が厳しくなるのが不思議だ。
「新しい日ねえ」
「ん?」
「お前はなーんも変わってないよな」
俺を見下ろす、力強くまっすぐな瞳。あの三年前から、悠雅は何一つかわっちゃいなかった。それはつまらなくもあったし、面白くもあった。
分かった事は、奴は世間体などというちっぽけな物では揺るがないどころか、微動だにしないという事だ。それほど太い芯があっても尚、悠雅は俺から離れようとしないのだ。
俺はまだ、悠雅の世界なのだろうか。聞いたら何と言うのか、まあ驚くのは確定としても。いや、そんな事聞いてられないけどな。
「先グラウンド行ってれんしゅーしとく」
「分かった」
「よし、行こうむーちゃん」
そして差し出されたその手のひらは俺の世界の半分……もっと、大半を占めているという事は、悠雅は一生知らずに死んでいくのだろう。
それもまたアリだと、俺はふっと笑みが漏れながらサッカーボールを取った。悠雅には、機嫌が良いと言われた。