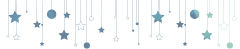
2013/11/01 02:44 はっぴーはろうぃん 「ぁ、…みやじさん…っ待って…っ」 「うっせぇ。ちょっと黙れ」 恋人を路地裏に引っ張りこみ、その身体を両腕で囲い、通りから見えないようにする。 待って、駄目、と呟き続ける分からず屋に、ほら、と、大人しくするように促すが、なかなかそれを聞き入れようとはしない。 「みやじさんってば…っ!ここ外…!」 「あーもう、だから早くしろって」 そんなに外ですることに抵抗があるのか。という程、恋人は外でこの行為に及ぶことを嫌がる。別に気持ちが分からない訳ではないが、緊急時にはそれなりに対応すべきじゃないのか。 宮地は開襟シャツの襟首を無理矢理開き、ぐいとそこに顔を埋めさせた。 甘ったるい匂いが、鼻腔を刺激する。 「……すいません、」 はぁ、と自棄に熱い息が肌を擽る。 耳元で小さく呟く声が聞こえたと思ったその瞬間、ちくりと痛みが走り、じわりじわりとそこから熱が広がる。 「ん…は、」 「…く…っ」 痛い、とは思わない。 そこから感じるのは甘美な癖になるような痛み。 じわり、じわりと、まるで、何かの病気にでも身体を蝕まれているかのような。 「ふぅ、ん…っん、」 まるですがりつくかの様に、伊月はくしゃりと宮地のシャツを掴む。ばか、すがり付きたいのはこっちだ、なんて思いながら、もっと、もっととでも言うように体重を預けてくる伊月の身体を支えた。 やがて、肩から重みが消える。 労るように、名残惜しげに、傷口をちろりと伊月の舌が這う。 まるで溺れるかのような、不安定な快感から逃れたことへの安堵なのか、それともただ緊張していたのか。思わず、熱い息が漏れ出、首筋にも同様に、しかし、唾液でそれすらひやりと冷たい息が掛かる。 突然、かくんと腕の中の身体が力を失い、驚いて宮地はそれを支える。 「血ぃ奪った側がなに力抜けてんだ。轢くぞ」 罵ってやれば、血を吸い疎らに赤く染まった唇が、薄く笑みを見せた。 「すいません」 まるで生気を感じられない。けれど、充分に血を吸い、白い肌に頬を朱に染め、儚く笑う、それさえも美しく、宮地はこの表情に惚れた。 胸に体調の戻りきっていないその身体を抱き締め、まるで赤子でもあやすように、とんとんと拍子を刻んで背を叩く。 ゆっくり、ゆっくりと、伊月の呼吸が戻ってくる。 彼の身体には、長時間の日光は危険だ。 けれど半分だけ流れる人間の血が、暗闇に生きることを許さない。 伊月は吸血鬼の母と人間の父の間に生まれた。 女系家系である、母の美しさを色濃く受け継いだ、姉と、妹の、その間の長男として生まれた伊月は、当然のように母の血を濃く受け継いでいた。 黒髪と、切れ長の目の美しい男鬼。 それが、伊月だ。 出会い、想い、想い合い、幾らかの年月が過ぎた。 いずれは、宮地も吸血鬼になるのだと。 宮地自身そう思っていた。 伊月とであれば、永遠の命を生きてみても構わない。 そう思える程に、この妖怪に惚れていた。 周りなど、見えなくなる程に。 ††††† 伊月は、普段は普通の高校生として生きている。 宮地とは学校が違い、しかし、同じバスケ部で、たまに試合なんかで顔を合わす程度が始まりだった。 それが今や恋人だと言うのだから、不思議なものだ。 学校が別であるから月に何度か作る時間は伊月と会うための逢瀬の時間。 伊月の学校の最寄り駅に降り立ち、暫くすると艶やかな黒髪が遠くにぽつりと現れる。 もうすぐ日が暮れる夕暮れ時。 「宮地さん!」 「おぅ。お疲れ」 お疲れさまです!と宮地を見つけた伊月は嬉しそうにその前に立つ。 えへへ、とはにかむ笑顔になんだよ、と返してやれば、なんでも、なんて含んだ笑いが返ってくる。 なにこいつ可愛い。 思わず伸ばした掌は、そのまま伊月の形のいい頭に伸びて、綺麗な黒髪をぐしゃぐしゃに乱す。 伊月が抗議の声を上げて、宮地はそれを笑い飛ばすように先に歩き始める。 まずは夕飯だ。 いつものファミレスでいいよな、と後ろから着いてくる気配に言うとはい!と声を張る。 ねぇ君、と、男の声が聞こえて、こんなとこでナンパかよと思ったが、そう言えば後ろの気配が急に消えていた。 「伊月!」 振り返ると背の高い男に絡まれる伊月の姿。 おいおい相手は男だぞ、と男に惚れてる自分のことは棚に上げて、美貌を持つ吸血鬼の血筋を少し恨む。 宮地さん、と、無邪気な笑顔が男の影から顔を出し、ナンパ男がみやじ、と彼の名を呼んで振り返る。 気安く呼んでんじゃねぇよと怒鳴ろうとして、それが知ってる声だと気づく。 「宮地って、秀徳の…?」 「………森山…?」 知ってる声だと思ったそいつの顔は、確かに知ってる奴で、もう日も暮れかけているというのにその目がやけに綺麗に見えた。 伊月と飯を食うときに限りだが行き付けのファミレスの、いつもの席の、宮地の向かい側で、伊月と森山という珍しいにも程がある組合わせが女子高生もかくやの大騒ぎをしながら話を弾ませている。 「へぇ、通りで!宮地と伊月、なんて組合わせ珍しいと思ったよ!」 そして、森山の変なテンションが、いつの間にか恋人だなんてことまで白状させられている。さすがに事のきっかけなんかは吐かされなかったので命拾いだ。 そんなもの話したら、伊月が吸血鬼であることまで白状するようなものだ。 とは言うものの、折角のデートを邪魔された気分でいっぱいの宮地は思わず大きな溜め息をついた。 「何々〜?宮地!溜め息ついたら幸せが逃げちゃうよ?」 「今、現在、進行形で幸せの邪魔をしてるお前にだけは言われたくねぇよ」 「うっわ!宮地ってば心せまー!」 どうとでも言っとけ、と不機嫌を露にしていると、伊月が申し訳なさそうにすいません、と小声で言った。 「……別に、お前のせいじゃねぇよ」 しょぼと小さくなる伊月の頭に手を伸ばそうとすると、それを塞がれる。 ぴきっと頭の血管がはりつめる音がしたような気がした。 「そうだよ、伊月!君は何も悪くなんかないよ!」 「おい」 「こんな心の狭い宮地なんかやめて俺にしてみるのはどう!?俺、伊月だったらイケる気がする!!」 「森山!」 冗談のような軽口に、なんとなく嫌な予感がして本気で怒鳴ると伊月が宮地さん、と名前を呼んだ。 妙に怒られたような気分になる。 「光栄ですけど森山さん。俺は宮地さんが好きなんで、遠慮します」 「……………そっかぁ。残念」 森山は少しの間、じっと伊月の顔を見つめ、そして、息を吐いた。 「じゃーあ、俺はナンパに戻ろっかな」 「てか帰れよ」 「やだよ。俺は青春を謳歌するって決めてんだから!」 大きな溜め息を吐いた森山はちゃり、とテーブルに自分が食べた分の金額を置いて立ち上がり些か大袈裟な身振りで宮地と伊月を後にする。 「あ、伊月」 ファミレスを出ていく直前に、くるりと顔だけを伊月に向けた。 「いつでも乗り換えは歓迎してるから!相談にも乗るから、いつでもおいで」 そう言った先、ファミレスの店員に可愛い女子がいたらしく、俺と君との出会いは運命だのなんだのという声が聞こえた。 伊月と顔を見合せ、苦笑する。 あいつ、ナンパ癖と変な運命論がなければモテるのに。 なんて、至極真っ当な意見だと思う。 ††††† 「ふ、…ん、…ん…っ」 「…っ」 こくり、こくりと伊月の喉がそれを飲下する。 伊月が、体内の血を啜る度に、言い様のない感覚が全身を駆け巡る。それは、確かに甘美な快感で、一度吸われた人間はそれの虜になるとはよく聞く話だ。 「は、…ぁ…」 宮地の首筋から唇を離した伊月は、ちろりとその傷跡を労るように舐める。 その感触にびくりと身体を震わせ、伊月の背中を抱いた。 血を与えた直後は宮地ですらまともに立つのも難しい。 伊月は伊月で、宮地と付き合うようになるまでにあまり人から血を分けてもらうようなことがなかった為に、食事と同等であるその行為ですら体力を消耗する。 伊月とふたり、力の入らない身体をお互いに抱き締め合って、宮地のベッドへと倒れこんだ。 「宮地さん、」 「ん?」 伊月の手が伸びてきて、宮地の頬をなぞる。触れるか触れないかの距離は妙にそれにすりよりたい衝動に駈られ、思わず掌に頬を寄せれば、くすりと伊月が笑った。 「……いつも、すいません。宮地さん」 「…別に。気にすんな」 今さら、伊月に血を分けることなど気にも留めない。 寧ろ、そうやって伊月に触れている時間が幸せなどと、どうやったらこのネガティブな男は納得してくれるのだ。 それよりも、宮地は気がかりなことがあった。そもそも、吸血鬼には男が多い。それは、子どもを産む強さと体力を持つ若い女の血を栄養とするからだと。 ならば、男の、しかも通常で摂取できる量の少ない宮地では、足りないのではないか。 そんなことばかり。 宮地が吸血鬼になれば、それも問題はないだろうに。 伊月の頬に手を伸ばすと、伊月はふわりと微笑む。頬をなぞり、耳を擽る。 伊月は仕返しだとでも言うように、宮地の頬を包んでいた両手で同じように首筋を擽った。 伊月のものになってしまいたい。 吸血鬼の契約とは、相手の体液を体に取り込むことを指す。 諸説ありはするが、昔から、血を吸われたら吸血鬼となる。キスをすると、永遠を共にすることとなるーそんなことを言われているが、それに実際に間違いはないのだと。 宮地が吸血鬼になることを拒む伊月は、絶対に唇を合わせようとはしないのだ。 「伊月。なぁ、伊月」 「はい」 甘い、甘い、血の匂い。微睡む。 「なぁ伊月、」 本当は、言ってはいけない。 伊月はその言葉をずっと拒んできた。 「伊月、俺と永遠を生きてくれないか。……伊月と、永遠に生きたい」 それが、血塗られた道でも。 ほろりと、伊月の瞳から雫が落ちる。 月明かりで、恋人の瞳が赤く光った。 思った通り。 デートだと言っていた伊月と宮地と別れて、だいたい3時間ほど経っただろうか。 元の駅に戻り、適当に可愛い女の子を物色する。 君との出会いは運命だと、そんな時代遅れの常套句を飛ばしてやれば、めんどくさい女は去っていく。 こういう言葉を真に受けるのは馬鹿な女かまたは飛びっきりの美人だ。そして、いい女の血は美味いのだと、森山は知らず知らずに唇を舐めた。 「森山さん!」 やっぱりね、と、後ろから聞こえた声に舌なめずりする。来ると思っていた。 きっと、遠くない未来に、想像できることだった。 伊月、と名前を呼んで振り返れば、さっき戦友と共に消えた、同族の姿。 「すいません、森山さん…」 相談に乗って貰えませんか。 泣いたらしい目元の赤さだとか、走っていたらしいその荒い息だとか。 「どうかしたの?伊月」 全てを俺のものにしてしまいたい。 元々嫌いなめんどくさい駆け引きや、向こうからやってくるのを待ってもいいと思える。 その位、欲していた血の香りは甘く、魅力的な。 ††††† 「ね、伊月。宮地なんてやめて俺にしない?」 「……え?」 伊月の話を一通り聞いて、そう持ち掛ける。 「だってさ、今の話を聞いた所によると、ずっと一緒にいることで傷付けるのが怖いってことだろ?」 問いかけると伊月は少し考えて、そういうことになりますかね。と納得して見せた。 「なら、俺にしときなよ。女の子なんて沢山いるんだから、宮地は心配ないよ」 それをつたえると、伊月は複雑そうに視線を下げる。 そもそも、それを言うならば、森山にだって同じことは当てはまる。つまり、何を言いたいかと言うと、 森山と伊月は同じである、ということ。 「それに、俺なら、伊月とずっと一緒にいるよ」 森山さん、と伊月が顔を上げる。 なんとも表現しにくいかのように、その瞳が揺れる。 伊月、と同族の名前を口にすると、血に飢えている時のように、目の周りに熱が集まるのを感じた。 「伊月」 森山さん、と、薄い唇が森山を呼んだ。 *†††††* おわり。 おかしをくれなきゃイタズラしちゃうぞ! ……………伊月をくれなきゃイタズラ…伊月にしちゃうぞ |