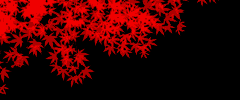
☆★☆ 車の隣の席には、ごついサングラスの男と、あの日向という人だった。 「名前は?髪長いな、女か?でも言葉遣いは男みたいだな」 「伊月。女だよ。ねえ、おじさん。何で俺達のお願い聞いてくれたの?」 「おじさんなんてやめてくれ、老けた気がする。 せめて日向さんにしてくれ。 そうだな、理由は、俺にもお前くらいの歳の一人息子がいんだ。 それでな、子供繋がりでお前と重なっちまったからさ」 苦笑した日向さんの、サングラスで見えないはずの目が、何故か優しく、温かく、何かを愛おしんでいるように見えた気がした。 「ところで、下の名前は教えてもらえないのか?」 「ダメ。願いは叶えてくれたけど、俺と、母さん達を引き離したから」 俺がぶっきらぼうにいっても、日向さんは笑って受け流していた。 いつの間にか時間は過ぎ、独房のあるであろう場所についた。 風呂敷包は一度取られ、いろいろされたがすぐに返された。 中の様子はあまり覚えていない。 いや、今までの記憶があまりにも覚えすぎていただけだった。 そうして、どこもかしこも白い独房に入れられた。 そこから、あの着物が届くまでの三年間の記憶が俺にはない。 きっとあまりに辛く、感情を締め出していたため、記憶に残っていないのであろう。 着物が届いた五日後の真夜中に、俺は、俺以外の妖怪にあった。 その妖怪は、最初、コウモリの姿だった。 しかし、 〔ポンッ!〕 と、音をたてコウモリの姿が煙りに包まれた後、そこには妖怪が立っていた。 妖怪は、人と妖怪を見分けることが出来るのだと、その時なんとなく思った。 その妖怪は、水色の髪がストレートで、肩より少し長い。 目も水色のようで、瞳は猫のように細くまる目だった。 白いノースリーブでブイ字ネック、裾が膝の少し上まであるワンピースを来ていた。 足は裸足だった。 |