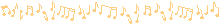▼ 衝動買い ああ、やっぱりこのひとは綺麗だ。 しろい華奢なゆびがティーカップを持ち上げるのを見つめながら、ゴールドは心中で息をついた。学生時代からの先輩であるグリーンは、結婚して仕事を退職してからも、時々こうしてゴールドの呼び出しに応じてくれる。こういうふうに未だかわいがってもらえることは、ひどくしあわせなことだと思う。けれど。 ――彼女が結婚した今もなお、捨て切れない想いを抱いているゴールドにしてみれば、胸の裡を満たすのはしあわせだけではなかった。 「おまえさ、」 シフォンケーキにもったりとしたクリームを乗せながら、グリーンはかたちのよいくちびるに性質のわるい笑みを浮かべる。綺麗な見た目をしているくせに、彼女はそういう表情が昔から似合っていた。そんな表情もいとしい。 「なんすか」 「彼女つくんないわけ?」 つくらないです。まだ――あなたをすきだから。 彼女のそのわるい笑みもこころも、そうやって食べてしまえたらいいのに。咀嚼して飲みくだして、そうして――自分だけのものに出来たらいいのに。 仄暗い思考が悟られてしまうことのないように、ゴールドは明るい声でグリーンに応える。俺に彼女できたら悲しむ子がたくさんいますからね、なんて。まるで道化だ。彼女に笑ってほしい、ただそれだけのために、思ってもいないことを言わずにはいられないなんて。 「ばーか」 ちいさく吹き出した想い人に小突かれて、ゴールドはちいさくしあわせを噛み締めた。 ** * 「今日はありがとな」 「いえ、俺こそ……楽しかったっす、久しぶりに話せて」 ゴールドがそう言うと、夕陽を背にグリーンは微笑った。普段紅茶の色をしている彼女の髪が朽葉色のひかりを孕んで、見惚れてしまうほどにうつくしかった。家まで送ります。ゴールドがそう、くちにした時だった。ゴールドの声を掻き消すようにクラクションが鳴らされる。 「ゴールド、」 「レッド先輩!」 レッドの乗った車が、滑るようにこちらに寄せられる。窓から顔を出して、レッドは嬉しそうに目を細めた。 「グリーンの今日の待ち合わせ相手ってゴールドだったんだ。僕にも言ってよグリーン。ゴールドに会いたいのはグリーンだけじゃないんだからさ」 「あ…っごめん、」 「うん。……それにしてもゴールド、ひさしぶりだね」 タイムリミットか。どこか感慨深げにそう言うレッドに、ゴールドはぼんやりとそう思った。レッドは仕事の帰りに偶然通りかかったみたいだけれど。このままグリーンを車に乗せて、そうして連れて行ってしまうのだろう。だってふたりは――夫婦、なのだから。 「じゃあね、ゴールド。今度は僕も誘ってよ」 「あ、ハイ!」 「ふふ」 吐息のようにレッドが笑った。ゴールドの思った通りに、当たり前のようにレッドがグリーンを促して。ひらりとレッドが手を振ったのを最後に、ふたりを乗せた車はすぐにちいさく遠くなっていった。 ( …あれ? ) ふたりの車を見送ってから、ゴールドはある違和感に気がついた。レッドが来てから、ゴールドはグリーンと話していない。"また会いましょう"のひとことすら、言わないまま。 ( まぁまたメールすればいいか ) レッドと会うのも楽しみだけれど――またグリーンとふたりで会えたらいい。そんなふうにゴールドは思った。 ** * 「グリーン、」 「は、い……」 「ねぇ、前に僕言わなかったっけ?僕がいないとこでほかの男と会うなって」 「言ったけど、でも…ッだって相手はゴールドだぞ?!レッドだってよく知ってるし、あんなにかわいがって、ッ!」 狭い車内に乾いた音が響いた。数瞬遅れて、火がついたように打たれた頬が熱くなる。振り返った彼女の、そのみどりいろの瞳がじわじわと恐怖の色に染まってゆくのを見つめながら、レッドはその顔にあどけない笑みを浮かべた。 「ごめんね、痛かった?」 「ひ…っ…、」 「でも、グリーンがわるいんだよ?こんなに僕が言ってるのに、どうしてわかってくれないの」 「……な、に………」 「ゴールドがどういう目でグリーンのこと見てたか、わかってる?」 「、え……?」 「あいつはずっと――……まあいいや。おしおきの続きはうちに帰ってからね」 |