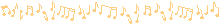▼ ぼんぼんボンジュール! ――来るんじゃなかったな。網膜に嫌というほど馴染んだ、やわらかな胡桃色の髪を見下ろしながら、僕はぼんやりとそう思った。 そもそもの始まりは、母さんからの電話だった。 ( ねえレッド、一日だけでも帰って来られない?あんなナナミちゃんを見るのは、なんだか辛くって……) もともと、お盆というのはオーキド家の行事だった。オーキド家というよりは、ナナミさんとグリーンのふたりの行事と言う方が正しいかもしれない。 と、いうのも――オーキド博士がこれに参加しているのを、ついぞ見なかったからなのだけれど――いつしかグリーンが僕のことを誘ってくれて、3人でするようになったのだ。旅に出る前までは、きゅうりやなすで馬をつくるのは僕とグリーンの係だった。 僕がものごころついたころにはもう、グリーンたちは両親を喪くしていて、夏の盛りにナナミさんとグリーンが火を燈すのは、ただそのひとたちのためであるようだった。いつも明るいナナミさんが、お盆の時期にはどことなく元気がなくなる。そんなナナミさんにあまえるように寄り添うグリーンが、ほんとうは誰よりもナナミさんを支えているのだとわかったのはいつのことだっただろうか。さりげなくだれかのことを支えられるおさななじみのことが誇らしくて、僕はいっそう――どうしようもないほどにかれに惹かれていった。 「レッドくん、」 「、はい」 「そろそろ火、点けようと思うの。手伝ってくれるかしら」 「あ――もうそんな時間ですか」 「そうなのよ…ふふ、お昼食べてのんびりしてるとあっという間よね」 やわらかな笑みは変わらない。だけど、どこか疲れたような影が、綺麗なナナミさんの頬に落ちていた。 燃えやすい木の枝とマッチの箱を持って――今年は母さんも加わって、3人で外に移動した。ナナミさんがマッチを擦ると、ちいさな火は瞬く間に燃え広がってゆく。ゆらめく炎は、まるで呼吸しているかのようにしろい煙を吐き出して……立ち上る煙を前にナナミさんが祈るようにてを合わせる。 「グリーン、」 幾度となく聞いてきた――僕が幼いころからまったく変わらないこえが、今はもうここにいないかれの名を呼ぶ。 「グリーン、私はここよ。わかる?迷わずにうちにかえってこれる?」 ナナミさんのこえはみるみる濡れて重たくなって、ついにはぐじゅりと潰れて途切れた。ふるえる華奢な肩に、いたわるように母さんがてを伸ばす。 ――ぼんやりと、けれどずっとずうっと感じていた罪悪感が徐々に自分の中でかたちづくられてゆくのがわかった。 そうだ。そういうことなのだ。グリーンをよみがえらせてからずっと、理由もわからないまま感じていた罪の意識の正体。 生きている間も、グリーンが死んでしまった今もなお、僕はグリーンを縛り続けている。それは、こんなふうにかれの名前を呼んで――かえっておいでと泣くナナミさんのところに、グリーンを絶対にかえしてあげないということだ。これからもずっと、ナナミさんはグリーンのために火を燈すのに。 ――だけどそれでも。ナナミさんのためにもグリーンを解放しようとは思えないのだった。 「泊まっていかないの?」 ボールからリザードンを出した僕の背中に母さんのこえがかかる。振り向かないまま、僕は頷いた。 「うん。――もう行かなきゃ」 「そう……」 「――レッドくん」 ナナミさん。目を向けると、彼女はもう泣いてはいなかった。しろい肌に泣いた跡の残る眦が、痛々しいほどあかくなっていた。 「来てくれてありがとう。おばさまも、本当にありがとうございました。ひとりでやってたら、……きっとさみしくてもっと泣いちゃってたわ」 淡く浮かべられた笑みに、僕はもう息が詰まりそうだった。帽子をかぶり直して、リザードンに跨る。はやくグリーンに会いたかった。 「……ただいま」 グリーンの待つ部屋のドアを開けると、うとうととまどろんでいたらしいグリーンがぱっと飛び起きてこちらに駆け寄ってきた。 「れっど、おかえりなさい!」 「ただいま、グリーン。先寝てていいよって言ったのに」 「だってそしたられっどがさみしいでしょ?おきてるよ!」 にこにこしながらかわいいことを言うグリーンに自然と顔がほころぶ。思わずその頬を撫でると、グリーンは不思議そうに首を傾けた。 「れっどなんかあった?」 「…え?」 「なんかかなしそうなかおしてる」 「……そう、かな」 「うん。ぐりーんがなでなでしてあげるね」 ――そっと触れたてのひらは、泣きたくなるくらいにあたたかくて。僕はちいさな身体を思わずきつく掻き抱いた。 |