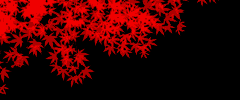
物心ついた頃から"風"が気になっていた。 ただ頬を撫でていくだけのそよ風でさえ、 狂おしいほどに心をざわつかせる。 「今日はちょっと風が強いのう……」 「そうだな」 拗ねたように頬を膨らませていう友人に、 相槌を打ちながらついてく。 「急ぐぞ立花!早くいかぬと限定パフェが売り切れてしまうのじゃ!」 そう言ってガラシャがわずかに歩を早めた時、 ビュオオと突風が二人の髪を乱して駆け抜けた。 『ギン千代』 途端胸の奥からどうしようもない寂しさがこみ上げてきて、 彼女は思わず立ち止まり顔を覆った。 そうしなければ、瞳から雫が零れてしまいそうだったから。 風が通り過ぎる瞬間、聞こえてきた声は、 全く知らない声だった。 それなのにどこか懐かしく、たまらなく愛しいと思える声。 「立花?泣いておるのか?」 先を歩いていたガラシャが、 突然立ち止まったギン千代に声をかける。 「なんでもない。目にゴミが入った」 そう言うとギン千代は、さっと涙を拭い再び歩き出した。 爽やかな風が一陣、二人の間をすり抜けていった。 いつもと違いざわついていたギン千代の心は、凪いだように穏やかだった。 物心ついた頃から"雷"が気になっていた。 空に走る稲妻を見ると、轟く雷鳴を聞くと、 不思議と心が落ち着いた。 「雷か」 「は?」 本に目を向けたままポツリと零された一言に、 一人の男が何のことかと問いただそうとした瞬間、 空に稲妻が走り、雷鳴が轟き、一緒にいた二人の肩がビクリとゆれた。 「び、びっくりしました。 それにしても宗茂殿はすごいですね、また雷を予見してしまわれて」 一人が苦笑を交えて言う。 小さな頃から、何故か雷が近づくと不思議とわかった。 「なぜわかるのじゃ貴様は」 「何故と言われてもな……俺にもさっぱり」 そう答えた瞬間再び轟音が空を駆け抜けた。 『宗茂!』 不意に聞こえてきた声に弾かれた用に顔をあげる。 この場に自分を呼び捨てするのは政宗一人。 しかしあの声は、雷鳴の中凛と自分を呼んだ声は、 低めでありはしたが明らかに女性の声だった。 全くしらない、それでもひどく懐かしく、そして愛しさが溢れてくる声。 「宗茂?」 「どうかされたのですか?」 友人二人が不思議そうに顔を覗きこんでくる。 「いや、何もない。空耳だったようだ」 そういって宗茂は、再び本に視線を移した。 未だに雷鳴が轟いている。 いつもなら落ち着くはずの心は、乱されたままだった。 その夜、二人は夢をみた。 雷を手に戦う女性と、風を纏い戦う青年の夢。 これは戦乱の世を生きた二人が、 遠い未来で再び出会う、ほんの少し前のお話。 しおりを挟む back ×
|