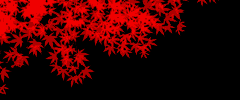
芹、薺、御形、はこべら、仏の座、菘、蘿蔔。 昨夜水に浸しておいた七草を刻んで、粥に入れる。 今日は1月7日人日の節句であるため、 朝から台所に立つギン千代は、 出来上がった七草粥粥をみて満足そうに笑みを浮かべた。 ちょうど良いタイミングでリビングへ入ってきた宗茂と軽く挨拶を交わして、 食卓ではなく、横のソファに腰掛けるよう指示すると、 ギン千代は七草を浸した水が入ったボールを手に彼の元へ向かった。 「この水に爪をつけろ」 「は?」 「さっさとしろ!」 宗茂が爪をつけたのを確認すると、 ギン千代は傍の引き出しから爪きりを取り出した。 「爪をだせ。切ってやる」 そういってギン千代は宗茂の手を掴むと、 濡れた指先をタオルで拭ってから、 パチンパチンと丁寧に彼の爪を切り出した。 普段ないサービスに、宗茂は疑問に思いつつも、甘んじて受け入れていた。 両の手すべて切り終わったあと、理由を訪ねてみたが、 ギン千代は照れたように顔を背け、知らぬと言っただけで教えてはくれず、 あとで元就にでも聞けばいいかと、おとなしく引き下がる。 「ギン千代俺もおまえの爪を切ってやろう」 宗茂の爪を切り終わった後で自らの爪を水につけていたギン千代の手をとり、 同じように指先をタオルで拭いながら囁く。 いつもならば、自分でやると突っぱねられるが、 珍しいことに頼むと小さく返ってきた。 しなやかな彼女の指を傷つけないよう、慎重かつ丁寧に爪を切り、 仕上げに鑢をかける。 終わってから、なんとなくその指先に唇を落とせば、 ギン千代は面白いくらいに赤くなった。 「な、何をするのだ!貴様は!」 そう言って彼女は赤い顔のまま、ボールをもって台所へ入っていった。 爪きりを元の場所に仕舞ってから、今度は食卓につく。 少ししてギン千代が運んできた彼女お手製の七草粥を仲良く食し、 二人穏やかな朝を過ごすのだった。 その日の夕方、元就に爪きりの話を聞いた宗茂は、 それをネタにギン千代をからかい倒すのだが、それはまた別のお話。 しおりを挟む back ×
|