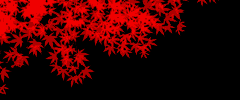
ある日立花家に珍しい客人が訪れていた。 井伊直虎である。 二ヶ月ほど前直虎は、 手のひらに乗るほど小さな子猫を拾ったものの、 家訓のために飼えずに困っていた。 そこで、猫好きなギン千代がその子猫を引き取ったのだった。 今回は引き取った子猫の様子を見たいと言った直虎を、 ギン千代が家に招いたのだ。 「お久しぶりです、ギン千代さん」 「ああ、元気だったか?」 「はい!」 他愛のない会話を交わしながら、 二人は猫のいる部屋へ向かう。 部屋では、二匹の猫が仲良く戯れていた。 栗毛の猫と、虎模様の猫だ。 「虎助、直虎殿だ。覚えているか?」 虎助と呼ばれた虎模様の猫は、 まっすぐに直虎へ向かうと、その足に擦り寄った。 その仕草に、覚えていてくれたんですねと、 直虎がうれしそうにつぶやいた。 虎助の名はその体の模様に因んで、 直虎がつけた名前だ。 「虎助は千熊とも仲が良くてな。手もかからず、良い奴だ」 そう自慢げに言うギン千代。 自分の名前が上がったことで、 ゆったりとした動きで栗毛の猫がギン千代に近づいた。 「その子が、千熊……ですか?」 虎助を撫でながら直虎が問うと、 ギン千代は千熊を抱き上げてフッと微笑んで答えた。 「そうだ。昔迷い込んできた猫でな…… もうだいぶ年をとったが、良く虎助の面倒をみている」 喉元を撫でてやれば、千熊がゴロゴロと喉を鳴らす。 かつて彼女と宗茂の間にあった蟠りを、 小さな体一つで取り去ってしまった。 それからずっと可愛がってきたのだ。 「ギン千代さんは猫が好きなんですね」 「な……!違うぞ?!私はただ……!!」 にこやかな笑みを向ける直虎の言葉を、 ギン千代は慌てて否定する。 猫好きを認めることは、彼女の矜持が許さなかった。 そんなギン千代の様子に、直虎は笑みを深める。 「あれ?でもなんで千熊……なんですか?猫……なのに」 ふと浮かんだ疑問を直虎が口にすれば、 ギン千代はすこし困ったように笑った。 「それは……虎助も同じではないか?」 「はう……そうでした。で、でも虎助は、 体の模様が虎さんみたいで……!」 ギン千代の指摘に、必死になる直虎が面白くて、 ギン千代は笑った。 笑われたことで直虎は頬を染め、しゅんと項垂れる。 しおりを挟む back ×
|