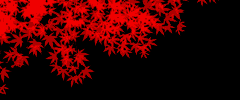
日がだいぶ傾き、あたりが薄暗くなった頃、 ギン千代はようやく帰宅した。 玄関の明かりがついていないところを見ると、 宗茂はまだ帰っていないようだった。 明かりをつけながらギン千代はほっと息をつく。 無意識に緊張していたらしい。 二人が同棲し始めたのは、ギン千代が大学に入ってから。 大学に通うのに都合が良かったことと、 婚約者同士の二人を互いの父がせっつき今に至る。 一年程たったが、二人だけでの生活にギン千代はなかなか慣れない。 リビングのソファにカバンを置き腰掛けると、 帰りに友人と買った本を取り出す。 「包装、するか……?」 テーブルに置いた本を睨みしばらく思案すると、 ギン千代は徐に立ち上がり、本はそのままに 自分の部屋に向かった。 部屋の片隅に置かれた小さな棚。 その一番上の引き出しを開けると、 中にあった小箱を取り出し、中身を取り出す。 そこにはバレンタインでーに使ったリボンの余りと、包装紙。 「とっておいてよかった」 黄色いリボンは十分な長さが残っていたし、 包装紙も緑に白でクローバーが印刷されていて、 派手すぎずかと言って地味すぎず、ちょうどいいデザインだ。 一人納得してギン千代はそれを掴むと、再びリビングへ戻った。 本を包みリボンを巻こうとして、別れ際の友人の顔が頭をよぎった。 宗茂に贈ることを否定していても、 それがいつもの照れ隠しだと彼女達にはバレバレだろう。 別れ際頑張りなさいよと言ってきた甲斐の言葉と表情が、それを物語っていた。 かぁっと頬が熱くなるのを感じ、ギン千代は頭を振る。 早く終わらせねば。止まっていた手を再び動かす。 ようやく包装が終わった頃、 玄関の扉が開く音がして、宗茂の帰宅を知らせた。 ギン千代は慌てて包装した本と道具を背後に隠し、身構える。 なんと言って渡すか。どうやって渡すか。 そんなことを考えながら、 リビングと玄関へと続く廊下を隔てる扉を凝視していた。 しばらくして扉が開きにこやかに笑う宗茂がリビングへ入ってきた。 「ただいま。……ギン千代?」 明らかに挙動不審なギン千代に怪訝そうな顔をする宗茂。 「お、遅かったな」 なんとかそれだけ絞りだしたギン千代に、宗茂はフッと笑った。 「帰り際にちょっとな……。心配したか?」 「誰が貴様の心配などするか!」 反射的に立ち上がって宗茂に詰め寄ったことで、 隠していたものが彼にさらされることになり、 ギン千代はしまったと表情を歪めた。 「ギン千代、あれは?」 宗茂が尋ねれば、ギン千代は顔を真っ赤にして誤魔化そうとする。 「アレは私が気になったから買っただけだ!」 そういうギン千代に、宗茂は笑みを深め追求した。 自分用に買ったのにわざわざラッピングしたのか?と。 「それは……!」 言いよどむギン千代を背後から抱きしめ、宗茂は笑顔で追い詰めていく。 ギン千代はしばらく腕から抜けだそうともがいていたが、 やがて諦めたように大人しくなり、 蚊の鳴くような小さな声でギン千代が言った。 しおりを挟む back ×
|