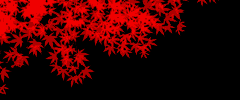
彼女は昔から、お淑やかという言葉とは程遠い女の子で、 同年代の女の子よりずっと行動的だった。 おしゃれよりも体を動かすことが好きで、 剣術の稽古には何よりも力を注いでいた。 今と違うのは、昔ほど感情を表に出さなくなったこと。 よく笑って、泣いて、怒って。 「ああ、怒りは今もよく表に出てくるな」 そう一人ごちて、口角を僅かに上げた男。 縁側に一人佇み、月を肴に晩酌と決め込んでいる。 今宵の満月は美しく、酒の味をより引き立てていた。 「そこで何をしている」 不意に背後から聞き慣れた声がかかった。 奴は何時からか、貼りつけた笑顔しか浮かべなくなった。 昔はもっと屈託なく笑っていのに。 自分よりも二つ年上のくせに、 甘えたなところがあって、女々しくて。 剣術だって、昔は自分のほうが強かった。 今は、敵わなくなってしまったが……。 「そこで何をしている」 縁側に佇み酒を呑む男に、ギン千代は声をかけた。 今や自分より強く、何でもそつなくこなす男は、 やはり貼りつけた笑顔で振り返った。 「ギン千代か。一緒に呑まないか?」 そう言って宗茂はギン千代に猪口を渡す。 それを無言で受け取った彼女は、 宗茂の横にドカっと腰を下ろした。 飄々として、風の様に掴みどころの無いところが、 ギン千代は苦手だった。 こちらのすべてを見透かされているようで、 そのくせ自分のことは決して見せない。 昔はこんなではなかった。 今はまるで見えない壁が二人の間に存在しているように、 二人が纏う雰囲気はどこかぎこちない。 「なんだ、呑まないのか?」 相変わらず貼り付けた笑みで尋ねてくる宗茂に、 ギン千代は耐え切れず叫んだ。 「なぜ貴様は……! いつも貼りつけたような笑顔しかしないのだ!」 立ち上がり、苛立ちのままにギン千代は、 持っていた猪口を地面に叩きつけた。 ガシャンと猪口が割れる音が月夜に響く。 怒りで肩を震わすギン千代に、 宗茂はあっけからんと言い放った。 「癇癪持ちな所は変わっていないな」 その言葉に思わずギン千代は拳を振り上げる。 しかしそれは振り下ろされることなく、 元の位置にもどった。 「もう……知らぬ!!」 吐き捨てる様にいって、 ギン千代は宗茂に背を向け、足早に去っていった。 「お前は、笑わなくなったな」 宗茂は見えなくなった彼女の背にむけ、小さくつぶやくと、 割れた猪口を拾い自分の部屋へ戻った。 しおりを挟む back ×
|