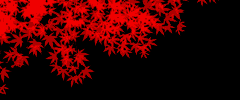
庭に植えられたもみじが色づき始めたある日の夕暮れ、 宗茂が帰宅すると嫌がらせのように、 彼の苦手な栗をふんだんに使用した料理が食卓に並んでいた。 (何か怒らせるようなことをしただろうか…) 少し血の気の引いた顔で考える。 思い当たる節が無いわけではない。 井伊家の女当主にギン千代より華があると言ったことか。 幸村の義姉をからかったことか。 「帰ってたのか宗茂」 「ああ、ただいま」 悶々と考えていたところにギン千代から声がかかる。 声色からはさして不機嫌そうな雰囲気は感じられない。 ならばこの大量の栗料理はどういうことか…。 そんなことを考えていると、 ギン千代の後ろからよく見知った人物が顔をだした。 「宗茂、随分遅かったな」 「父上?」 面食らう宗茂をよそに、宗茂の父紹運はさも当然のように食卓についた。 髪がすこし濡れているところを見ると風呂あがりだろう。 「父上…どうしてここに?それからギン千代、この栗料理は…」 「義父上は様子を見に来てくださったのだ。その…新婚…だからと…。 栗料理は、義父上のリクエストだ」 宗茂の質問に少し照れたように答えるギン千代をみて、 紹運は満足そうに頷いた。 「仲が良くて何よりだ」 紹運の言葉にギン千代の頬がサッと赤く染まった。 「それはそうとギン千代、この大量の栗はどうしたんだ?」 「ガラシャが持ってきたのだ。 婿殿に栗が食べたいとこぼしたら、大量に調達してきたらしくてな…」 ギン千代は苦笑いしながら、まだ栗の残る箱をさす。 箱からチラリと見える毬に宗茂は顔を歪めた。 「その…お前が嫌なら、お前の分は別に作るが…」 宗茂の栗嫌いは当然ギン千代も知っている。 先程から苦虫を噛み潰したような顔の宗茂をみて ギン千代がそう提案すると、横から紹運が口を挟んだ。 「ギン千代殿そんな気遣いはいりません。宗茂、食べろ」 「……」 「宗茂?」 笑顔ながら尋常では無い威圧感を放つ紹運に、 宗茂は渋々了承すると食卓についた。 「さ、ギン千代殿も」 紹運に促されてギン千代が食卓につく。 いただきますの号令とともに食事が始まったが、宗茂の箸の進みは遅い。 やっと宗茂が食べ終えた時には二人はすでに食事を終えて、食器を片づけた後だった。 完食し、一息ついた宗茂にギン千代が残酷な言葉を投げたかけた。 「宗茂…その、食後のデザートを作ったのだが…食べるか?」 マロンプリンなのだが…。 そういってギン千代は可愛らしく盛りつけられたプリンを差し出した。 紹運はすでに食べ始めている。 「原型を留めていなければ、食べられるのではと思ったが…無理か?」 プリンの乗った皿をもち、少し照れながら首をかしげるギン千代に 宗茂は食べる以外の答えをすべて封じられてしまった。 宗茂はほっとしたように微笑んだギン千代をみて、 彼女のこんな顔が見れるなら栗料理も悪くないと思うのだった。 「ギン千代、プリンならば食べられそうだ。また作ってくれ」 プリンを完食した宗茂の言葉にギン千代は一瞬目を丸くしたが、 すぐフッとわらって了承した。 後日ギン千代からプリンと彼女の例の仕草が父の入れ知恵であることを聞かされ、 複雑な心境になる宗茂であった。 しおりを挟む back ×
|