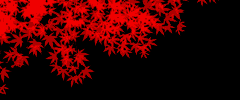
蝋燭の火がゆらりと揺れ、宗茂の神妙な面持ちを照らしだす。 重々しい沈黙が部屋に落ち、やがて絞りだすようにギン千代がつぶやいた。 「ばかな……」 「いくら俺でも、冗談でこんなことは言わないさ」 日頃の彼とは打って変わって、真剣そのものという声色に、 ギン千代の背は自然と伸びる。 ありえない……。ありえるはずがないのだ。 彼がそれが真実ならば振りかかるのは、あくまでも自分のはずで、 信じがたい言葉であるのに、彼の表情はとても偽りを述べているとは思えない。 動揺から視線を彷徨わせたギン千代の目に入ったものが、 彼女を一つの結論へと導いた。 「わかったぞ!四月馬鹿であろう?!」 そばにあった暦を指さして、声高に叫んだギン千代だったが、 いつもならおどけた様子でネタばらしをしてくる宗茂の様子が変わらない事に首を傾げた。 相変わらず表情を崩さず、彼に似つかわしくない、僅かに不安をたたえた目をギン千代に向けてきている。 「ギン千代……」 悲痛な声色で名を呼ばれれば、ギン千代は思わずたじろいだが、負けじと詰めていく。 「今年は!今年こそは騙されぬぞ!白状しろ!宗茂……!!」 「ギン千代……。お前まで嘘だというのか? 確かに今日は四月馬鹿の日ではあるが、必ず嘘をつかなければならないわけではないだろう?」 眉尻を下げ、普段の面影は何処かへ消え去ったように、消え入りそうな声で宗茂に縋られて、 ギン千代の混乱はその許容量を越えた。 ありえぬ!!絶対にありえぬ……!! 「そんな……!ありえるわけなかろう!男が子をは、孕むなど……!」 確かに夫婦である以上、子ができる事自体はありえないことではないし、 周りに望まれてることもわかってはいるがそれはあくまで女である自分のはずである。 目の前でうなだれている男が……なんてことはありえない。ありえないはずなのだ。 それなのに、宗茂の様子に四月馬鹿だという確信がゆらぎ出している。 「ギン千代……」 もう一度弱々しく名前を呼ばれれば、ギン千代の思考はいよいよ停止した。 「それは、まことに、まことか……?」 二、三度深く呼吸を繰り返してからゆっくりときりだした、 僅かにくすぶる疑念をにじませた問いかけに、宗茂はゆっくりと頷き、 それを見とがめたギン千代は、宗茂の手を掴み、たまらずに叫んだ。 「……っ!せ、責任は、とる……!」 しばしの沈黙が二人をつつんだのち、くっ…という小さな声がギン千代の耳に届き、 声の出処をたどれば、それはやはりと言うべきか、先ほどまで神妙な顔で佇んでいた伴侶。 表情こそ分からないが、肩の揺れと先ほどとガラリと変わった雰囲気から、彼が笑いだそうとしていることに、 ギン千代は気づいた。 「くっ……くく、はははっ……」 「貴様……!!」 怒りと羞恥に顔を赤く染め、思わず拳を振り上げるも、 軽々しく受け止められてしまい、ギン千代は更に怒りが募る。 「悪かった。ギン千代の反応が面白くてつい……な」 笑いはそのままに口先だけの謝罪を述べた宗茂が、 ギン千代の頭を撫でれば、きっと彼を睨みつけた。 「ふざけるな!貴様はいつもいつも……! だが今回は、騙されたわけではないからな!」 そう言って勢い良く顔をそむけたギン千代に、 宗茂の笑みは更に深くなるのだった。 「ああ、そうだギン千代。さきほどの冗談半分は真実だ」 すったもんだののち二人で囲んだ昼餉の席で、 唐突に放たれた宗茂の言葉にギン千代は思わず箸をとめる。 「どういう意味だ?」 「子ができたのは本当だ。俺ではなく、猫にだが」 初夏には子猫が増えるな。 宗茂がそういうが早いか、あっという間に残りの昼餉を平らげたギン千代は、 ばたばたと部屋を出て行った。 行き先はおそらく、彼らと同じ名をもつ、番いの猫の元。 <終> しおりを挟む back ×
|