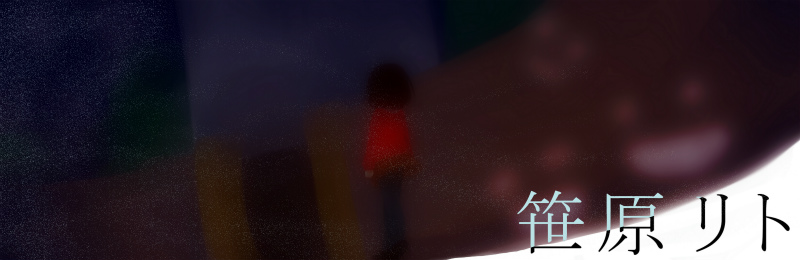依頼人という非日常くらいには敬語を使う
アディの家に居候してからの日数を数えなくなって、今日で10日目。何か矛盾があった気がするけど、気にしない。留守番をしていると、扉がノックされた。扉の横の窓から外を見てみると、緊張した様子の初老の男性がいた。
「はい?」
扉ごしに応対する。
「あっ、あ、あああのっ!あ、アディさんの、おおお宅ですか?」
電話じゃないんだから。まあそもそもこの世界に電話なんてものないけどさ。
「そうですが。依頼ですか?」
「あ、は、はい!」
「なら、彼は今出かけていますので、中に入ってお待ちください。」
心配性なアディに言われたとおり、玄関横の棚の上から護身用の小刀をポケットに入れて、扉を開けた。
「お、お邪魔します……。」
キョロキョロキョドキョドしながら依頼人が入ってきた。
「そこの椅子とかに座っといてください。」
私は、ラストひと袋になった紅茶をおろすことにして、お湯を沸かす。
以前にも言ったとおり、アディは殺人鬼だ。そして、本人は殺しを嫌っている。だからせめて悲しむ人を少なくしようと、殺人依頼を受け付けているらしい。けれどその残酷さから凶暴な人だと思われているらしく、依頼は少なめだ。彼は、このくらいが丁度いいと笑っていた。
少しアディと話してみれば、我慢強くて人見知りの、ただの大きい子供だとわかると思うのに。
お湯が沸いた頃、アディが帰ってきた。
「ただいま!リト、リト、聞いて、聞いて、紅茶、冬限定、発売してた!!」
「うん、よかったね。」
「うんっ。」
いい笑顔。
「で、頼んだ晩ご飯の買い物は?」
笑顔が固まった。
「……ごめんなさい。」
「……いってきます。」
「えっいや、僕が行くよ!」
「依頼人来てるよ。」
「えっ!?」
なんだ、気づいてなかったの。
椅子から立ち上がった依頼人とアディが挨拶合戦を始めた。ああいうのを見ると、アディも大人なんだなと思う。豆類食べられないけどね。
買い物のついでに、久しぶりに帰り道を探す散歩でもしようかな、と思いながら扉を開けたところで、アディに呼び止められた。
「いってらっしゃい。買ってきた紅茶、淹れとくね!」
すごく美味しいんだから、という口調からも表情からも、本当に大好きなんだなとわかる。
そんなに美味しいんだね。
「いってきます。」
なら、散歩はやめた。

←|→