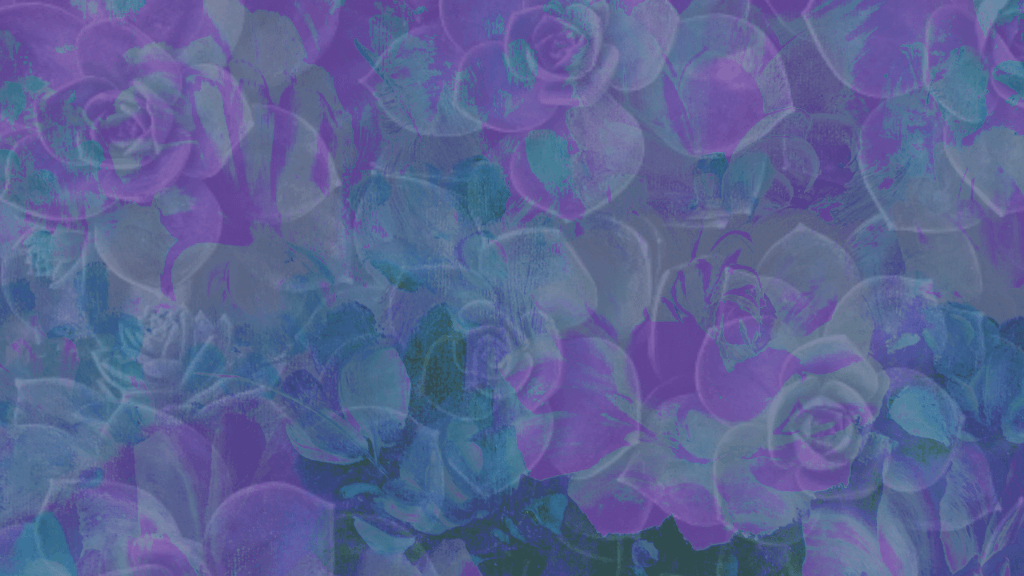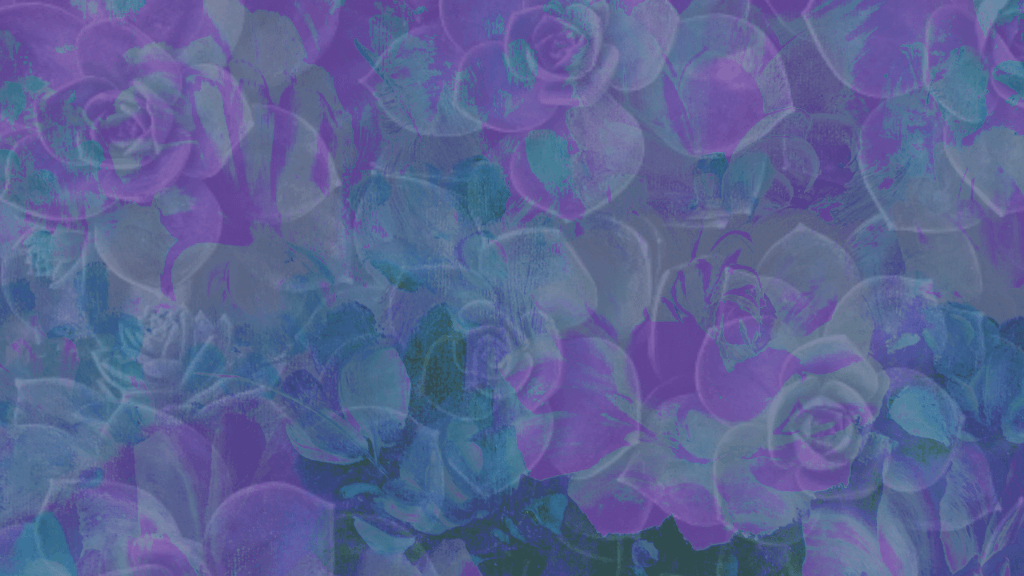
青いコートを身に纏っていた少女はスラム街の路地に追い込まれていた。
崩れかけたアスファルトの壁にぴったりと背を付け、自分を追い詰めたそれらを至極冷静な目で見つめている。
普通こんな所に追い詰められたら泣き叫ぶか許しを請うかのどちらかなのだが、少女は目の前の影にそれをするに値しない相手だという事を知っているから動揺すらもしない。
それどころか今から急ぎで行かなくてはいけない場所があるというのに。こんな低俗な奴らに構っている時間など一秒たりとも用意していないのに。
そう思いながら少女は仕方なしに太腿に括りつけていたナイフケースに手を伸ばす。
左右一つずつ括りつけられているケースから赤い宝玉が付いているナイフと青い宝玉が付いた黒と白銀の柄が見えていた。
柄を確り握り、相手を挑発する様にナイフを構える。
「すぐに終わらせます。だから、大人しくしていてください」
少女は顔を俯かせて丁寧な口調でそう言うと腰を低く落とし、目の前の敵……異形のそれに向かって走っていった。
否、走ってはいない。瞬間移動とも言える速さで移動した。
少女がナイフをケースに差し戻したその瞬間、背後で真っ赤な血が噴出する。まるで噴水の様に。
だが彼女は振り返らずに胸元に仕舞っていた懐中時計を開き、時間を確認する。その目は鋭く、視線でも何かを切れそうな位に研ぎ澄まされていた。
だが、走ればまだ約束の時間には間に合う事を知ると何処にでも居る少女の様な優しげな表情を浮かべる。
鼻から息を吐き出すと路地から飛び出るように少女はある場所へと走り始めた。
††††
清閑な、薄暗く古びた、誰も居なさそうな図書館に青年は居た。
ページを捲る乾いた音ですら響く位の古さの図書館で彼は誰にも邪魔されず、黙々とその場で本を読み耽っていた。
しかし何かに気が付いた様に彼は本を片手で閉じると、暗澹とした廊下をその目で睨み付ける。
耳を澄まさずとも革靴が石床を蹴る音が木魂している。無人だと思っていたが誰か他にこの図書館に居るらしい。
だが近付いているそれが何か解ると青年はその身から滲ませていた殺気を押さえ、手にしていた本を本棚の隙間に戻した。
「……アスタか」
暗闇から姿を現したのは息を乱した、青いコートの少女。
彼女から微かに漂ってくる血の臭いに青年は眉間に皺を寄せた。
だが少女はその場にそぐわない明るい笑顔を浮かべながら呼吸を整え、言葉を紡ぐ。
「ごめんなさい、バージル。探し物が中々見つからず、此処に来るまで時間が掛かってしまいました」
「……構わん。だが、その血の臭いをどうにかする事は出来なかったのか?」
「え?」
バージルと、そうアスタが呼んだ銀髪の青年は乱暴にアスタの腕を掴む。
そして自分の目線に合わせる様に上げさせると彼女の指を凝視した。
アスタが手に付けている革のグローブが不自然に切れている。其処から彼女の血の臭いがした。その他の比較的新しい他の物の血の臭いも混じっているが。
彼女が自分以外の血の臭いを付けてくるなんて理由は一つしかない。
「悪魔に襲われたのか」
「街に出てくる下級悪魔くらい一人で立ち回れます」
「手を切られている」
「でも治っているでしょう?」
くすくすと笑うとバージルは不機嫌そうにアスタの顔を見つめた。
確かにアスタの手に傷等はない。だが、怪我をされる事にバージルは少し腹を立てていた。
血の臭いによってくる悪魔も居る。血を流せば当然皮膚や衣服に微量でもにおいが付く。
わざわざ自分達の存在を奴らに教えてやる義理はない。バージルはそう考えていた。それはアスタも同じだと思っている。
戦う事を嫌っているはずの彼女だがそう居た事には無頓着で頭が働かない事についつい溜息を吐きそうになる。
「まぁいい。今後は気をつけろ」
そう言ってアスタの手首から手を離すと踵を返し、背を向ける。そして出口の方に向かって歩き始めた。
バージルの目当ての情報が見つからなかった事を悟ったアスタはすぐにバージルの背を追う。
小走りで歩き、すぐにバージルに追いつくと肩を並べる。
するとバージルは兼ねてから気になっていた事をアスタに問いただす。
「しかし、お前は何を探しに行っていた」
「……少しはバージルの手伝いが出来ないかと思い、魔具や魔道書を扱っているお店に。でもスパーダの事も魔界の事も何も……」
歩きながら顔を俯かせたアスタをちらりと横目で盗み見る。
彼女はいつでもバージルの事を優先にし、行動する。煩わしいとは思わない。だからこそ側に置いている。
だが、その行動は実に愚かしい。自分のための行動ではなく、他人のための行動でしかないから。
献身的な彼女の行動が理解できないからそう思うのだろうけど。
二人は図書館を出るとすぐに短期間のみ借りていたホテルに向かう。いつもの事だから特に何も気にならない。
今もこの地に居る理由は何かスパーダの足跡を辿れないかと思い、赴いただけなのだから。
目的の物が無いのであれば用は無い。明日にはこの地を発つ。そう言ったバージルにアスタは静かに頷いた。
此処を発つ前に色々と準備をしなくては。
体に巻きつけていたナイフケースとコートの中に隠していた銀色の銃と銀色の小箱ををテーブルの上に置く。小箱の蓋を開けるとその中にはキラキラした宝石が幾つも収まっていた。
証明の光を吸い込み光を放つ宝石にバージルは眉間に皺を寄せた。
「相も変わらず銃の動力はそれか」
「無駄な弾薬を購入するのは好ましくありません。それに此方の方が私にとっては何かと都合がいいんです」
バージルの言葉にアスタははにかみながら銃に赤く煌くダイヤグラムの石をはめ込んだ。
それだけの行動で銃を撃ち続けるのだから魔石の力と言うのは素晴しい。
悪魔を倒していたら時折銃に使えるような魔石を落とす事があるから態々金を払って仕入れる事もない。
尤もそう言った魔石を待っているのは上位の悪魔でしかなく、下位の悪魔では持つ事すら侭ならない代物だけど。
それに魔石の力を使えば少ない魔力で戦えるし、魔力で弾丸を生成してしまえば一々リロードする手間も省ける。隙も小さくなる。
「バージルも一度銃を扱ってみては如何ですか」
「俺は銃は扱わん。そう決めている」
「そうですか。ごめんなさい、変な事を言ってしまって」
「構わん。……銃にかまけるのも良いがナイフとブーツも手入れしておけ。お前の武器は銃だけではないだろう?」
「承知しています」
バージルの言葉は暗に「暫くまた戦う事になるだろうからな」という意味を織り込まれていた。
アスタは銃の扱いよりはどちらかと言うと接近戦での戦いを得意としていた。
先程路地で悪魔を倒して来た時も両手にナイフを持ち、ブーツに仕込んでいたナイフ付きのワイヤーを距離の開いた正面の建物に突き刺して勢い良くワイヤーを巻き戻したに他ならない。だから瞬間移動をした様に見えるのだ。
ワイヤーを駆使したトリッキーな戦いはバージルも何度も見ているし、自分には恐らく出来ないであろうその戦い方を時折頼りにする時があった。
バージルの武器は日本刀の様な形をしている魔剣・閻魔刀がある。
彼はいつでも閻魔刀を左手に持ち、数多の悪魔を切伏せて今此処に存在していた。
アスタと背を会わせる様に自身も閻魔刀の手入れに励む。
バージルは力を求めている。
偉大な父であり、魔界を封印した英雄、魔剣士であるスパーダを超える為。
あの日、母を殺した悪魔を、自分達を恐怖のどん底に、絶望の淵に立たせた悪魔共を根絶やしにする為に。
父が封印した魔界の扉を開き、魔界に行くのがバージルの、そして彼に付き従うアスタの今の目的だった。
その為にスパーダの足跡を追い、魔界の扉を開く方法を探し回っているのだがどれもこれも眉唾な話ばかりでアテにはならない。
バージルは静かに閻魔刀を鞘に納める。
アスタも愛銃であるアルカネットを腰につけているホルスターに仕舞うとふぅ、と小さく溜息を吐いた。
「アスタ」
不意に背後に居る彼女の名を呟く。
するとアスタは呼ばれたのかと思って「何ですか」と何時もの柔和なトーンでバージルに答えた。
「お前は、何故俺に付き従う」
「……そんなの、バージルが神になる瞬間を見てみたいだけです。それに、私は貴方のそばで戦いたい。貴方に始めて出会った時から、勝手ながらそう思い続けていました」
「……」
何時までも優しく、不快感のない甘い声にバージルは瞼を閉じた。
恐らく彼女の言葉には嘘はない。微塵も。
それは声音でも彼女が現在作り上げた空気でもそう感じる事が出来た。
しかしアスタも「あの、バージル」と言葉を繋いできたからバージルは思考を一旦停止させた。
「何だ」
「以前から気になっていたのですが、何故私を側に置いておくのですか。鬱陶しいとは思わないのですか」
そう言った声は先程とは違い、少しだけ不安に震えていた。
何時からだろうか。彼女を傷付けたく無い一心で、彼女に対しては言葉を選ぶ様になったのは。
アスタの方に一切振向かずにバージルは薄い唇を緩やかに動かした。
「お前は強い。強い女だから側に置いている、それだけだ。邪魔であれば斬り捨てている」
「……斬られたくなければ強いままでいろ。そういう事でしょうか」
「あぁ」
暫しの間沈黙が走る。別に沈黙は嫌いではない。だが、今のこの沈黙は少しだけ空気を重苦しい物に変えていた。
しかしバージルもアスタもあえて何も言葉を口にしない。
この沈黙が必要な物だと解かっているからだ。
だが何時までもこのまま沈黙だけを続ける訳にも行かない。
「……次は何処に向かいましょうか」
「そうだな。此処を発つ前に決めておこう」
地図を広げ、肩を並べる様に場所を相談する。
出来れば、スパーダの伝説が今でも継承されているような場所が良い。
そう言いながら二人は次に向かう街を決めた。
その街が二人にとって終焉を迎える地になるとは思いもしないまま。
2015/01/06