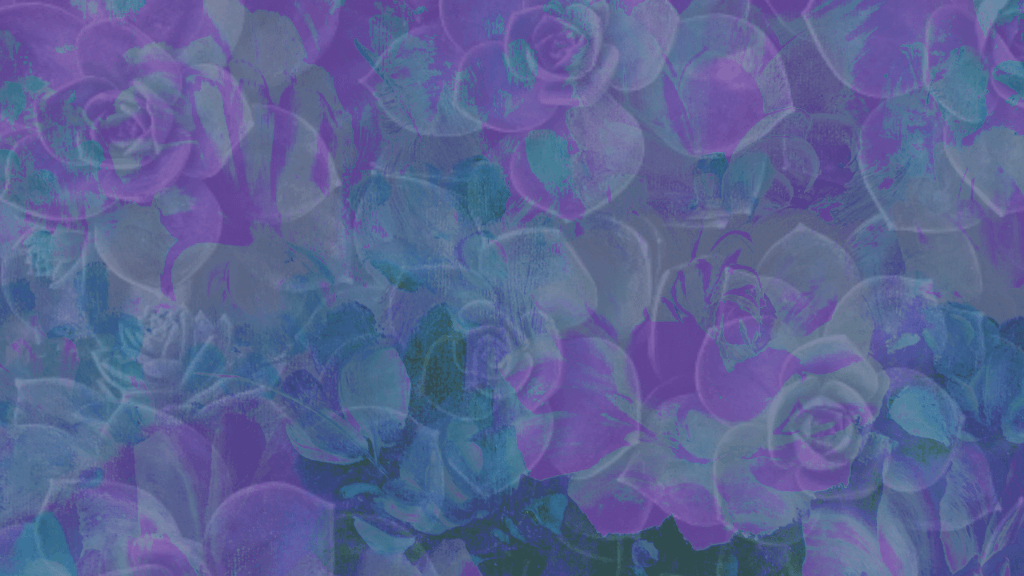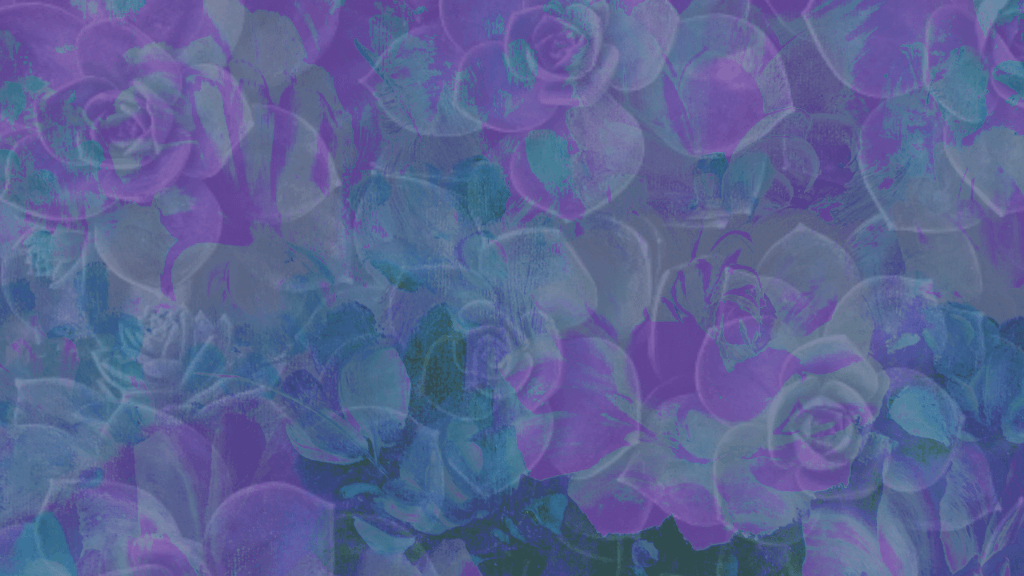
ダンテが地下歌劇場でネヴァンを倒した頃。アーカムを先頭に礼典室を目指すバージルとアスタは薄暗い廊下を歩いていた。響いているのはブーツが床を蹴る音のみ。それ以外は全くと言って良い程の無音だった。
しかし途端に靴音が一つだけ、ぱたりと音を止めた。アスタはその場で足を止め、必死の形相で背後を振り返る。
確かに感じたのだ。そして脳裏にダイレクトに映像が送られてきた。それは紛れもなく彼女が送ってきたものだった。
「ネヴァン……?」
「どうした」
バージルに声を掛けられるも心臓だけ体温が冷え切ったかの錯覚に陥り、冷たい汗が皮膚に滲み出る。
アスタの視界には青ではなく、鮮やかな赤が網膜に焼き付く。自分達の企てを阻止しようとする、もう一人の魔剣士の息子の背が。
ネヴァンがダンテを倒した。そのビジョンが送られてきたのだ。別に悪魔が倒されようが、消え去ろうが何の感傷もないが自分の恐らく先祖との約束を守り、力を少し貸してくれた彼女が自分が知らない所で倒されるなんてアスタには許せないし遣る瀬無い事だった。強く拳を握り締める。
「アスタ?」
「!! ごめんなさい。少し疲れてしまって」
「無理も無い。お前は大量の血を流し過ぎた」
「少し休むか?」と問われるがアスタは小さく首を横に振る。こんな所で立ち止まってはいけないと、バージルの手に触れてからすぐに一歩を踏み出す。
「良いのかね、休息を取らなくても?」
「構いません。それに、そんな暇は無いでしょう?ダンテが追いついて来ては面倒ですし」
「……」
その後は会話もなく、沈黙だけが続く。
後どのくらいの距離を歩けば良いのだろうか。その前にこの塔に果てはあるのか。そんなことすら考えてしまう。
しかし、目的地に大分近付いたのかアーカムが言葉を発する。
「この先が礼典室だ」
薄暗い廊下を抜けると今度は大きな閂が幾つも突き刺さった大きなドアが目の前に現れる。
「テメンニグルは完全な姿となり、我々は魔界へとたどり着く事が出来る。スパーダの封じた魔界へとな。しかし、その封印を解くのがスパーダの息子とは。……皮肉な話だ」
閂が機械的な音を立てて次々と外れる。
ドアの真正面に居たアーカムは後ろに数歩下がるとバージルとアスタに道を譲った。今鍵を手にしているのはバージルとアスタ。この二人が先に入らなければ魔界の扉を開く事は出来ないと、そう言いたいのだろう。
依然無言を貫いたままのバージルは先へ行こうとする。その後を付いていこうとしたが視界に入ったアーカムが元来た道の奥を見ていることに気付き、アスタは足を止めた。そういえば、先程からしきりに背後の道を気にしていたなと。
何かあればアスタとバージルが敵を倒す手筈になっていたが、何をそんなに気にする事があるのだろうか。
「そんなにあの女が気になるか」
バージルが問いかけると一瞬アーカムの目が驚愕に大きく見開かれる。
しかしすぐに普段の冷静さを取り繕い、言葉を口にした。この切替の早さは賞賛に値するとアスタは思った。
「何の事だね?」
「何故あの女を殺さなかった。恐らく貴様の娘だろうが。よもや情に負けたとでも?」
そういえばアーカム自身が言っていた。塔に侵入してきた女に関わりがあると。そして彼は彼女に会いにも行っていた。どんな会話をして来たかは解からないがあの口振りから推測するにはほのぼのとした家族の会話などではなく、殺伐とした碌でもない会話なのだろうけど。
しかし自身の娘であれば何故殺す必要があるのかとバージルの言葉に疑問を抱くが、目的の為に自身の双子の弟を刺すようなひとだ。それに、アスタも良く知っている。世の中には自分の目的の為に自分の娘を実験動物にし、愉悦に浸る父親も存在するという事を。
そこでアスタがアーカムに対し嫌悪感を抱いていた理由がここで漸く一つ理解する事が出来た。アーカムはあの男に少し挙動が似ている。だから嫌いなのだと。
「そんな事は……っ?!」
「バージル?!一体何を……」
鉄臭い臭いが突如として弱々しく鼻腔を通り抜ける。アスタは信じられないという視線をアーカムに向け、それ以降の言葉を失っていた。
バージルが静かに閻魔刀を鞘から抜き、近付いてきたアーカムの腹を刺し貫いたから。
彼の手にしていた赤い革表紙の本は冷たい床の上に落ち、滴る真っ赤な血を受け止める。
アスタはその様を目を見開いて見つめていた。
「悪魔の力を得る為、妻さえ犠牲にした。そう聞いたからこそ貴様を利用していた」
「……え」
バージルの一言にアスタは驚愕する。
アスタがまだ今よりもアーカムに対する不信感を抱いていない頃、彼は郷愁をその目に浮べながら口にしたのだ。「私の妻は悪魔に殺されたのだ」と。だからこそその時抱いていた懐疑もほんの少しは和らいでいたというのに。
その言葉や表情すらも演技、つまりは嘘と言う事にアスタは拳を強く握る。騙されていた自分も自分だけども。先程から感じていた己への腹立たしさで考えが上手く纏まらない。
そんな中嫌な静寂を冷たい声が切り裂いた。
「もう少し使える奴だと思っていたが、見当違いだったか」
バージルは閻魔刀を握る手を少しだけ捻る。突き刺さった刀身が傷を捻らせ、アーカムの傷を広げる。もがき、閻魔刀に手を添えようとした所を今度は勢いを付けて深く突き刺す。苦悶の声がその場に小さく反響した。
バージルは表情を変えずに吐き捨てる。
「不完全な力しか得られなかったのも頷ける」
その言葉にアーカムは鋭い目つきでバージルを睨み付けた。
「貴様はどうなんだ。貴様も不完全な存在だろう」
更に閻魔刀が深く突き刺さる。
"不完全な存在"。悪魔であり、人間である自身に劣等感を感じているバージルにその言葉は禁句だ。その禁句を口にしても尚、バージルの逆鱗に触れる言葉を態々選び、アーカムは言葉を喘ぎながらも続けた。
「人間でもない、悪魔でもない。不完全な……」
「黙れ」
アーカムの体から閻魔刀を引き抜き、血を払うと戻すべき鞘に納める。完全に鞘に収まった所でアーカムの体はその場に倒れ臥した。
「此処までくれば最早貴様に利用価値はない。……アスタ、行くぞ」
「……」
「……アスタ?」
今、一体何が起きたのかアスタは理解が出来ていなかった。怒りで思考が停止している所をバージルが無理に腕を引っ張る。漸く頭が何が来ているかを理解し、処理を始めたが、そのお蔭でまたバージルの事を直視出来なくなっていた。
もしかしたら此処まで共に行動してきたのも、自分の事も利用する為なのかとそう思って今って。
引っ張られている事で動いている足が今にも停止してしまいそうだ。
「……一つ、良いですか」
問いかける唇が恐怖で震える。
バージルはアスタから何か問い掛けの言葉が来ると解かっていたのか静かに返事を帰す。
「何だ」
「私の事も、利用していますか」
「お前を利用するなど、ありえん事だな」
「……」
「お前は何年の歳月を俺と共に過ごしている?そもそもお前は俺が利用しようとする前に俺の利に敵う動きをする。それに、何年も掛けて他人を利用出来る程俺は器用ではないし、アミュレット……鍵を預けるなどと言う事もしない」
そう言ってアスタの腕から手を離し、先へ進む。
そうだ。バージルはアスタから見ても不器用なひとだ。それに自分に接する時は彼は無意識なのだろうが"悪魔"のバージルではなく、"人間"のバージルとして接している事が多い。よく行く先々では"仲が良い兄妹"と称されたものだ。アスタはそう言われるのを嫌だと思わなかったし、事実血の繋がりは一切無いとは言え彼の妹の様な存在になっているという自負はあった。
アスタは吹っ切れたような表情を浮かべると数歩だけ駆け出し、バージルと同じ歩調でその後を付いていく。アーカムが居た事を除けば何時もとなんら変わりはしない。そう考えれば何も考える事はないし、怖い事等ない筈だ。
そんなアスタの表情を自分の肩越しにバージルはアイスブルーの瞳に写す。
「気だけは抜くな。お前は変な所で油断する」
「……解かっています。まだ、魔界の扉は開かれていない」
「それもある。だが……いや、何でもない。気にするな」
礼典室の前に着いた二人は黒金のドアをその手で開く。礼典室の中も暗く、しかし幾筋もの亀裂から発行している光が漏れていた。その為変に暗いという感じは見受けられなかった。
部屋のど真ん中には丸い窪みだけがある。他には何も無い。
「此処が礼典室?」
「その様だな。アスタ、アミュレットを」
「……!はい」
言われるがままに預かっていたダンテのアミュレットをバージルに確りと手渡す。
アスタからアミュレットを受け取ったバージルは少しだけ優しげに笑みを浮かべた。
「俺達の目的が達成される」
2015/05/22