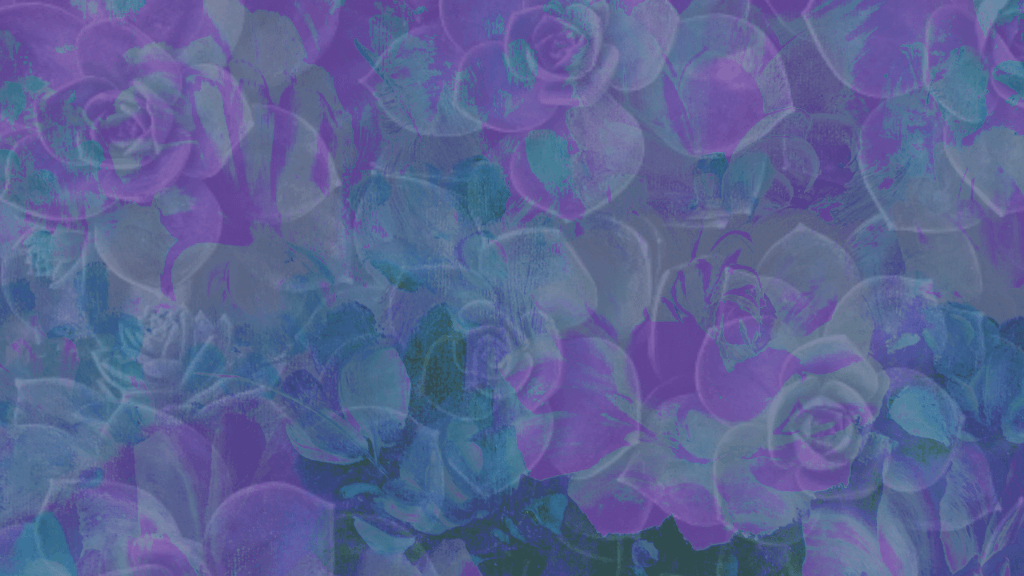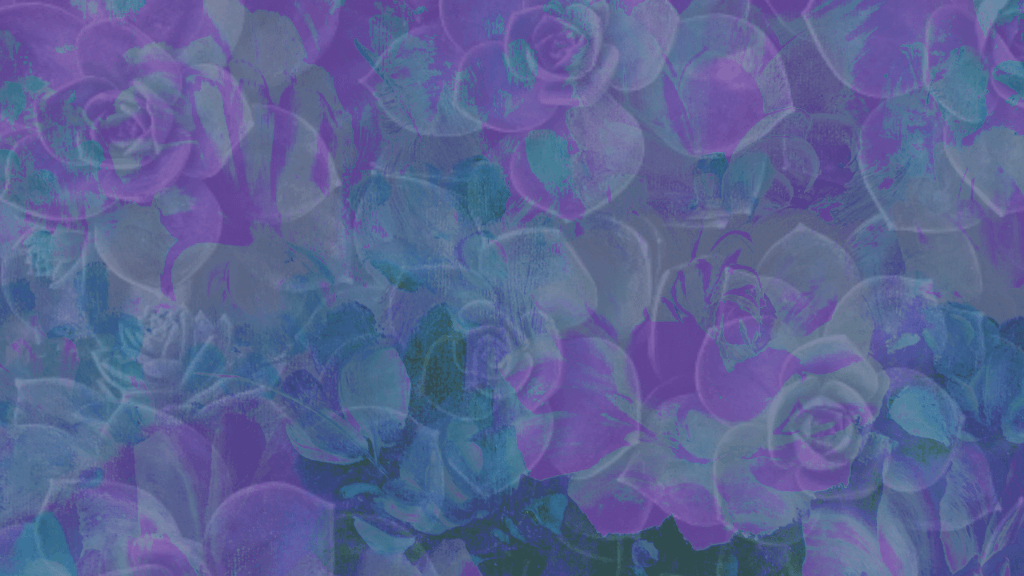
塔の頂上から降りた3人は再びテメンニグルの中を、封印を解除すべく最深部にある礼拝室を目指していた。
「アスタ」
バージルに声を掛けられ彼の方を見ようとするが上手く顔を見る事が出来ない。丁度顔のした、喉元に視線を向けると何かがアスタの方に放られる。照明の光を受けて光を放つそれを上手く両手で受け取ると両手に金属を掬った時の様な重みが感覚として残る。
キャッチした拍子に落とさない様にと閉じた手を開くと其処には赤い宝石を銀の金属台に埋め込んだアミュレットが目に映りこんだ。先程、バージルがダンテから奪ったアミュレットだ。
何故バージルがそんな物を自分に渡したのか。アスタにはその意図が解からずにいたが、すぐにバージルがその意図を言葉でアスタに伝える。
「お前が持っていろ」
「何故……」
「ダンテは必ず追って来る。だからだ」
ダンテにとってこのアミュレットが大切な物だという事はアスタは良く解かっている。
余り過去を語りたがらないバージルが郷愁の表情を浮かべ、アミュレットの事を話してくれたから。バージルにとっても、ダンテにとってもこのアミュレットは大切な母の形見で、大事な物だ。
だからこそダンテが追って来るとバージルは言っているのだろうし、アスタも何となくダンテは追って来るとそう予感していた。
アスタは少しだけ考えてから小さく頷き、バージルを追い越し、アーカムの背を追う。
しかしながらアスタは思うのだ。ダンテはアミュレットを奪還する為だけに追いかけてくる訳ではないと。
歩きながらアミュレットを首に掛け、着込んでいるブラウスの中に装飾を隠す。
その様を先頭を歩くアーカムが横目で伺っていた。
「アーカム。件の礼拝堂まではどの位距離がある?」
「最深部にある部屋だからな。まだまだ移動に時間は掛かるだろう」
「最深部……」
「どうかしたかね、アスタ」
アスタの呟きを拾ったアーカムにアスタは小さく「いえ……」と言葉を返す。
しかし、地下や最深部と言うと生き物の"死"を現す空間だ。
アスタは生来魔力を持っている魔女で、魔女は命を落とすと魂は魔界に引きずり込まれ、永遠の苦しみを与えられる。そしてその魂は永劫、転生する事は許されない。
そう、幼い頃に暗い実験室であの男にそう言われた事を思い出す。
死ねば魔界に行けるのだが、アスタには死ぬ事は出来なかった。死んだら目的が果たせなくなる。そもそも死んだら魔界に取り込まれてしまうのと同義だからそんな手段は最初から選べやしない。
「……行きましょう」
一つの靴音だけが冷たい印象の廊下に寂しく響いた。
何故、先程あの男の事を思い出したのか。あの件については大分前に吹っ切れた筈だったのに。暗闇に浮かぶ、あの歯に付けられた矯正器具の光沢が記憶の奥で煌いた。
思い出すだけでも吐き気がする。瞼を閉じ、何か他の事を思い出してあの男の事を払拭しようとアスタの頭は努めに入った。
あれからどれ程の時間が経過しただろうか。
先程の場所から大分地下に近づいた所で、大きなドアの前で三人は立ち止まっていた。
しかしアーカムもバージルもアスタもドアに何もしようとはしない。アーカムに至っては何時ものあの赤い革表紙の本を開き、その一説を口にした。
「人々はこの塔をこう呼んだ。テメンニグル……"恐怖を生み出す土台"と。……恐怖」
途端、アーカムは狂喜を孕んだかの様な笑いを喉から転がした。
矢張りこの男は何かを企んでいる。アスタはその疑いを見せない様に彼の動きを注意深く観察する。その隣でバージルも冷たい目でアーカムの背を見つめていた。
「そう、恐怖だ」
しかしその視線に気付いているのかいないのか、片手で本を閉じる。
「感じるか?」と質問なのか独り言なのか判断がつきにくい問い掛けに共鳴したかの様にドアが独りでに大きな音を立てて外側に開く。
「怨念を、怒りを。この地に封じられた哀れな者達。間の力を求めた彼らと共に。スパーダは魔界への道を封じたのだ」
その言葉にバージルは何かを考えるように瞼を閉じた。だが、すぐに瞼を開きアーカムの次の言葉が来るよりも先にドアの向こうへと足を進める。アスタも無言でそれに続いた。
だが、バージルはアーカムの動作を見ずに、彼が何かを気にしている事を察し、足を止める。
「どうした?」
「……何も」
不自然な間が空いた後の返事にバージルは何事もなかったかの様に先へ進む。
彼が気にしているのはダンテか。はたまたこの塔に侵入したという女か。どちらでも構いはしないが気になるのであれば今すぐ道を戻り、時間を稼いでこようかとすら思う。だがアスタはそれを口にしなかった。どうしてもアーカムの挙動に不信感を抱いてしまっているから。
††††
時を同じくしてダンテはリバイアサンと言う魔界の生き物の体内に居た。
新たな、バージル曰く「悪魔の力」が覚醒し、その力の凄さを身に感じながらテメンニグルの塔の側面を走りながら降りていたが、ちょっとした弾みで塔の周りを飛んでいたリバイアサンに丸呑みされてしまったのだ。
内臓の中に潜んでいた悪魔を倒し、動力部とも言える心臓を破壊し、食道を駆け上がり、ダンテは漸くの思いで目の部分まで到達した。
丁度到達した所で宙を泳いでいたリバイアサンの体が地面に叩き付けられ、その衝撃による若干の浮遊感にダンテは眉間に皺を寄せた。
「ったく、とんだ厄日だ」
そういえばどの位あの塔の中に居て、この巨大生物に飲み込まれたんだろうと考えるが、考えた所でどうにもなら無い事に気付く。そういえばろくに夕飯も食べてない。その事を思い出すと事の発端である、兄・バージルに対し怒りが僅かながらに蓄積された。
とりあえず此処から脱出する事の方が先だと、ダンテはリベリオンに魔力を注ぎ込む。何度も斬りつけるよりは此方の方が効率が良いかもしれない。段々とリベリオンの白銀の刀身は赤く染まっていく。
「Drive!One,two!」
リベリオンから赤い閃光の太刀が放たれる。その閃光はリバイアサンの赤い目玉を切りつけ、切れ目を付けていく。あともう一息と言う所でダンテはリベリオンを大きく振り上げ、斬りつけた。
押し寄せてくる血液と共に外に飛び出す。
案の定血塗れになった体に不快感を覚えながら、出来る限り血を払う。だが中々血は落ちてくれないから諦めた。
「あぁ、くそ。本当に厄日だな」
忌々しそうに呟くと目の先の壁には赤い文字で「Welcome」と道筋を示す矢印と共に、あの口喧しい道化師・ジェスターの顔のイラストが描かれていた。ルージュの伝言でもあるまいし。
その前にあいつが敵なのか味方なのかが段々解からなくなっていく。道化師だから自分さえ楽しめれば良いと思い、手を貸して要るのかもしれないがどうでも良い事だ。
「此処が次の会場って訳か」
リベリオンを担ぎ直し、矢印が示す方向に行こうとすると背後から銃を構える時特有の金属音と女の「待て!」と言う声が耳に入り込んできた。
本当は先程から彼女がいるのは気付いていた。だが、初対面の、命を助けた人間の頭にお礼の代わりに鉛玉をぶち込むような女に誰が自発的に声を掛けるのだろうか。
しかしと言って無視をするのもばつが悪い。ダンテは彼女に背を見せながら言葉を返す。
「デートの約束をしたいんなら……」
そこで漸く彼女の方に体全体を振向かせ、突きつけられている銃を流れに沿って手で払う。目の前の彼女はすぐに銃を構え直すが二度も同じ動作をしようとは思わなかった。
「お断りだね。人をオツムに銃ブッ放すような女は特にな」
かと言って両手持っているナイフで何度も体を切りつけようとしてくる女も御免被る。まだあちらの方が行動に動機があるだけましだとは思うが。
しかしそんな事を目の前のこの女に言った所でどうにもならないとダンテは言葉を飲み込む。
「悪魔とデート?ハッ、其処まで飢えてないわ。それに、血のニオイのする男も趣味じゃないし」
今の今までリバイアサンの悪臭漂う体内にいた事で鼻が麻痺していたが、自分の体の有様を見つつ、よくよくにおいを嗅いで見ると確かに血生臭い。思わず舌打ちをしてしまう。
だがその舌打ちは自身の体臭以外にも、空気を読まず無粋に現れたお客人達にも向けられたものだった。
素早くエボニー&アイボリーを腰のホルスターから引き抜き、目の前の彼女も同じタイミング、同じスピードで装備しているハンドガンやオートマシンガンに手を伸ばし、背中合わせに銃を乱射し、悪魔達を蹴散らしていく。
「そう言えば名前をまだ聞いてなかったな」
「そんなもの捨てたわ」
「だったらなんて呼んだら良い?」
「呼びたいように呼んだら?」
銃弾が絶え間なく、二人の周囲の悪魔に穴を穿ち、姿を四散させる。
その中でもダンテは自分に背を預ける形で銃を撃ち続ける彼女の呼び名を考えた。
「じゃあ、"レディ"」
それだけ告げて押し寄せてくる悪魔のドーナツサークルのど真ん中から、凄まじい跳躍力を見せつけて塔の入口に着地した。
「此処は任せるぜ。パーティに遅れたくはないからな」
銃を乱射し、悪魔に応戦するレディに向かい投げキッスを贈る。
しかしレディはその仕草に嫌そうな顔を浮かべ、空になったマガジンを排出し、新たなマガジンを装填する。
そして吐き捨てる様に今の心境を言葉にした。「悪魔なんかと共闘するだなんて此方から願い下げよ」とでも言いた気に。
「最初からアテにしてないわ」
2015/05/15