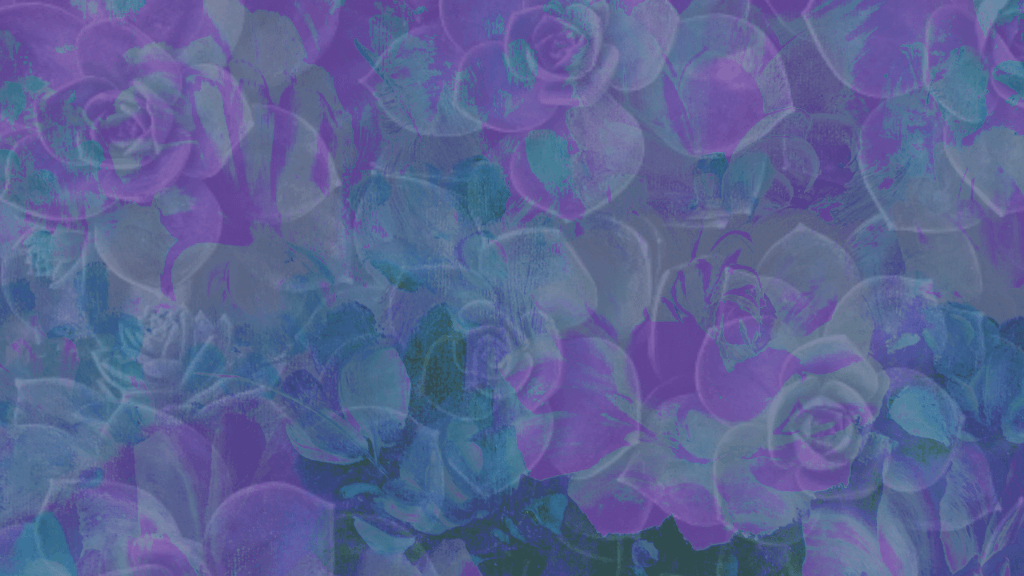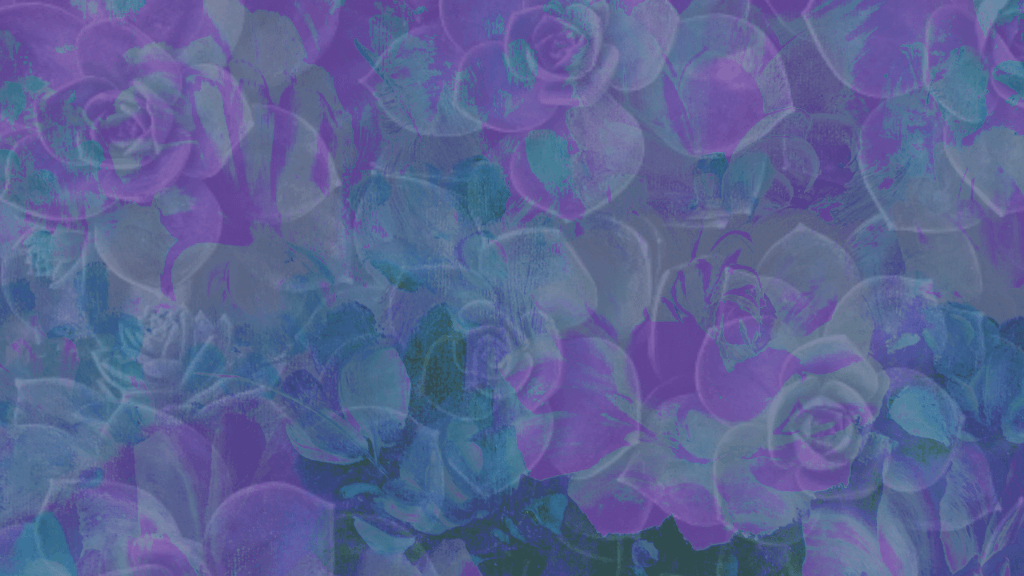
ダンテは苦戦していた。幾らデビルハンターとしてここ数年間悪魔と戦ってきた彼でも"初めて"戦う種類の悪魔と言うものもいるのだ。
目の前にいる犬型の悪魔はまさにそれだった。こんなに大きな体を持つ悪魔は今まで見た事が無い。
幼い頃、まだダンテ達が幸せな家庭で暮らしていた時の事。時折スパーダが悪魔の姿を見せてくれたがその時もこんなに大きな姿はしていなかった。せいぜい2mあるかないか位の大きさだった事をダンテは記憶している。
だが目の前の鎖に繋がれた氷を扱う悪魔はゆうに3mはあるだろう。
体が大きいだけではない。力もその体に見合うだけその身に宿していた。氷柱を落としてきたり氷塊を召喚したり。氷を纏った大きな手でダンテを攻撃してきたり。
しかしダンテはその攻撃を避け、エボニー&アイボリーで悪魔・ケルベロスが身に纏う氷を少しずつ溶かしていく。
本当なら豪快にリベリオンで斬り伏せてやりたいのだがそれが通用する敵ではないことくらい解っている。
「You scared?」
『舐めるな小僧!!』
それなりに知能はある様だが矢張り挑発には乗ってくるらしい。ケルベロスは叩き付ける用にダンテに向かって氷が剥がれた赤い手を振り落としてきた。だがダンテは華麗にその攻撃をサイドロールでかわす。
そろそろ締めに入ろうか。この強大な悪魔に敬意を示して一思いに片をつけてやる。楽しませてくれた礼だ。
助走をつけてケルベロスの頭3つの内、中心の頭に向かって高く跳ぶ。
そしてエボニー&アイボリーを両手に空中でダンスでもするかの様に弾丸を撒き散らす様に的確にケルベロスの頭の氷を均等に溶かしていく。
『くっ』
「どうだワンちゃん、鉛味のキャンディの味は?」
一度地面に着地すると激昂したケルベロスが限界まで鎖を伸ばし、雄叫びを上げてダンテに噛み付こうとする。だがダンテは口笛を軽く吹くとその場で軽やかに跳び上がり、リベリオンをその手に握り締める。
そして落下しながら3つ首目掛けて大きく振り落とした。
ダンテが再度地面に着地すると少し後にケルベロスの首が2つ、地面に落ちる。切断面からどす黒い血を滝の様に滴らせながら。
「チッ。一つ仕留め損なったか」
残った1つの首は苦しそうに喘ぎながら、尚もダンテを睨みつけている。
『貴様、人間ではないな!』
「さぁ?自分でも良く解らなくてね」
おどけた様にそういえばケルベロスは服従するかの様に、急に大人しくなる。
戦う直前は『人間風情が、調子に乗るな』といきんでいたのにも拘らずだ。
幾ら悪魔といえど本質的には犬の部分があるのだなとダンテは素直に納得した。
『いずれにせよ、貴様は力を示した。貴様を認めよう。我が魂を手に先へと進め!……我が牙の加護を!』
最後に残った赤目の首は一度呻ると黒く大きなその身を青白い光に変え、ダンテの目の前にふわふわと舞い降りる。ダンテも本能的にその光に手を伸ばし、手に取った。すると光は実態を得て、ダンテの手の中に納まる。
氷を模したかの様な鮮やかな浅黄色と白の色調の棍3本が銀色の鎖で繋がれている。
牙の加護とはこういう事か。そう思いながらダンテはその武器の性能を体で試す。
以前TVで見た胡散臭い物語のアクションスター宜しく、振り回す。その内にテンションが上がって来て記憶以上のアクションをその場で、一人で決めていた。
しかしダンテにはそんな事は如何でも良い。ポーズを決めて、ケルベロスを止める。
「Too easy!」
無事に塔の番人であるケルベロスを倒し、入り口に当たるドアに向かう。ケルベロスの氷の魔力で凍り付いていた扉は魔力の持ち主であったケルベロスが敗れた事により綺麗に解け去っていた。
「待ってろよバージル。今にあんたの取り澄ました面、ぶん殴りに行ってやるからさ」
それに彼が隣に置いていた少女の事も少し気になっていた。バージルの性格上(今の彼がどんな性格をしているかなど細かい事は知りもしないし、知ろうとも思わないが)、隣に女を置いているなんてダンテにはまず"ありえない"事だ。
しかし、塔の上に立っていた彼女もまた、自分達と同じ異質さを持っている事を僅かながらダンテは感じ取っていた。
そろそろ塔の中に入ろう。そう思いドアの前まで向かおうとすると外から轟音の様なエンジンの音が鼓膜を震わせる。段々近付いてきたそれはすぐに背後から氷で出来た窓を突き破りダンテの頭上から落ちてきた。
勿論ダンテはそれを簡単に跳んでかわす。
落下してきたのは真っ赤な改造バイクに跨った黒髪の女だった。一瞬の事で顔は良く見えなかったがそれなりに顔立ちは整っているとダンテは思った。
着地すると同時に、彼女に振り返る。丁度バイクも、地面を擦り停止する。
「あんたもパーティかい?慌ててるが、招待状はお持ちで?」
そう彼女に言葉を掛けると彼女はダンテには目もくれず、背中に背負っていたミサイルランチャーをダンテに向かって発射した。勿論それも容易にかわすがこんな物騒な女は初めてだ。
ランチャーの弾はダンテの背後の壁に当たり爆発する。
「ハハッ、やるねあんた」
ダンテが生きている事を確認しようとしたのかバイク女はゆっくりと振り返りダンテを一瞥する。その目は左右で目の色が違う、所謂オッド・アイと言うものだった。
すぐに彼女はバイクのエンジンを2、3回吹かしダンテに向かってバイクを走らせたかと思いきや、彼の目と鼻の先でバイクを浮かせ、先程ミサイルランチャーが壊した鉄格子の天井から塔の内部へ走り去って行ってしまった。
既にいなくなった彼女の方を振向き、鼻を鳴らす。
「こういう展開も悪くないか」
ただ、あの女に先を越されるのは癪だ。そう思いダンテは門番が守っていたドアを開け、塔の中に進んでいった。
††††
テメンニグルの中腹部分にテラスの様な部分がある。アーカム、バージル、アスタはその場から夜に移り変わった人界を見下ろしていた。
街は混乱などなかったかの様に人工色の光を点し、営みを普段通りに行っている。これから先、どんな恐怖が訪れるかも知らないで。
アスタは夜風に当たりながら、風で靡く髪を片手で押さえた。
「余計なものが紛れ込んだな」
「そうかね?」
バージルの言葉にアーカムは興味がなさそうに本を捲る。
「人間……女か」
「人間が何しにこの塔へ……警察か何かでしょうか」
「さぁな。だがそれであればすぐに引き返す事になるだろう」
そんなやり取りの中、アーカムは本を閉じ、重たそうに腰を上げる。
「どちらにしろ、招かざる客にはお帰り頂こうか。君もそれが望みだろう」。そう言いながら。
「その女とは少々関わりもあるしな」
そう言うとアーカムは塔の中に一人で戻っていってしまう。先程アスタが一人で塔の中を見て回ってきた時、数が少ないとは言え悪魔はそれなりに出てきたのだ。
アーカムは人間だ。それに武器も持っていない。持っているのはあの赤い革表紙の本だけ。
幾らアーカムが気に食わないと思っていてもアスタは心配で仕方がなかった。この先、魔界への扉の封印を解くのに彼の知識が必要になる部分が出てくるだろう。その事を考慮したら彼がいなくなるのは困る。
バージルも止める事無く、ただ彼の背を一瞥するだけだった。
「嵐が来そうだ」
それだけ告げてアーカムはその場から姿を消した。
しかしアスタには今のアーカムの発言に気になる節があった。
何故、彼は侵入者の女が自分に関わりがある者だと解ったのか。もしかしたら、いやもしかしなくても自分達はアーカムの掌の上で転がされているのではないのか。不躾にもそう思ってしまう。
侵入者の正体が解かるとなると自ら此処に招き入れるように仕掛けを作ったとしか考えられないからだ。
「放っておけ」
「! 私は何も」
「今、アーカムの言動について考えていただろう」
バージルの言葉に肩を揺らす。どうして彼は自分が考えている事を易々と見透かすのだろう。いつもの事ながら気になって仕方が無い。もしかしたら全部顔に出ているのだろうか。それならそうで言って欲しいとアスタは業と顔を俯かせる。
「あの男は下級悪魔如きでは死なん」
「何故そう言いきれるのです?彼は武器を持たないただの人間では?」
「……お前ではまだ何も察知出来ないのか」
「む、今地味に馬鹿にしませんでした?確かに言われるまで何かが動いてるな、位にしか思いませんでしたし、それがダンテだと思ってはいましたが」
むくれながそう言うとバージルは喉を鳴らして笑った。それを嘲笑だと受け取ったアスタは更に表情をむくれさせる。
我ながら子供っぽいとは思ってはいるが、バージルに対しては痛い所を突かれてもむくれるしか出来ない。戦いでも口喧嘩でもいつもバージルに負ける事を知っているからだ。
「馬鹿になどしていない。卑屈になるな」
「……」
「アスタ、そろそろお前も体制を整えておけ」
「?」
「お前もダンテと戦うつもりだろう」
「先程の言葉をそう捉えているが」と横目で視線と共に言葉を投げ掛ける。
先程の、といえば此処に戻ってくる途中、戯れで聞いたあの言葉だろうか。
「もし、私が先にダンテと戦ってダンテを殺してしまったら貴方は私をどうしますか」。自分でもくだらないと思ったこの問い掛け。それをバージルは真摯に受け止めたらしい。アスタの考えの一つとして。
それだけの事なのに何故だか急に嬉しくなって顔を俯かせたまま笑みを浮かべた。
2015/03/10