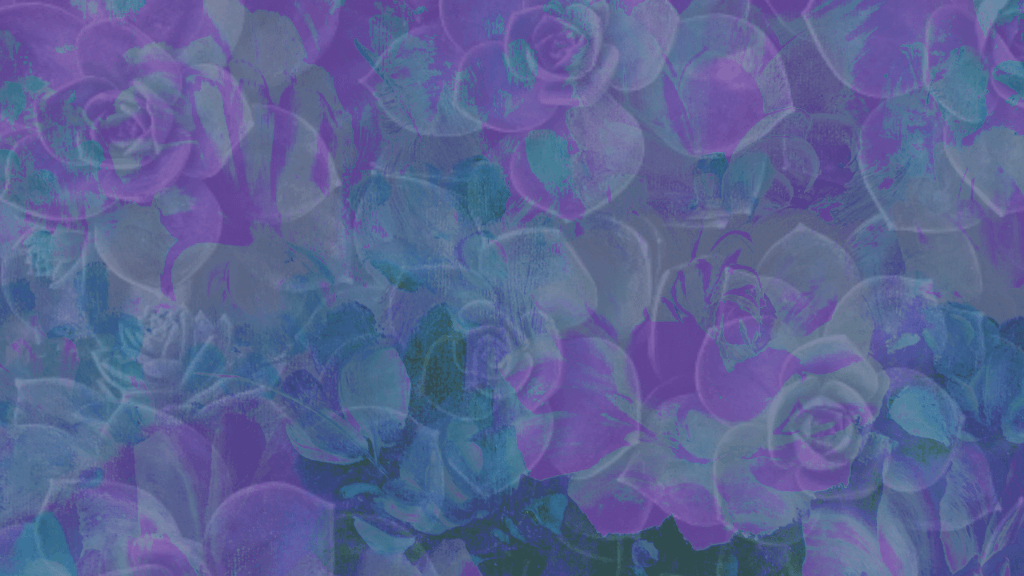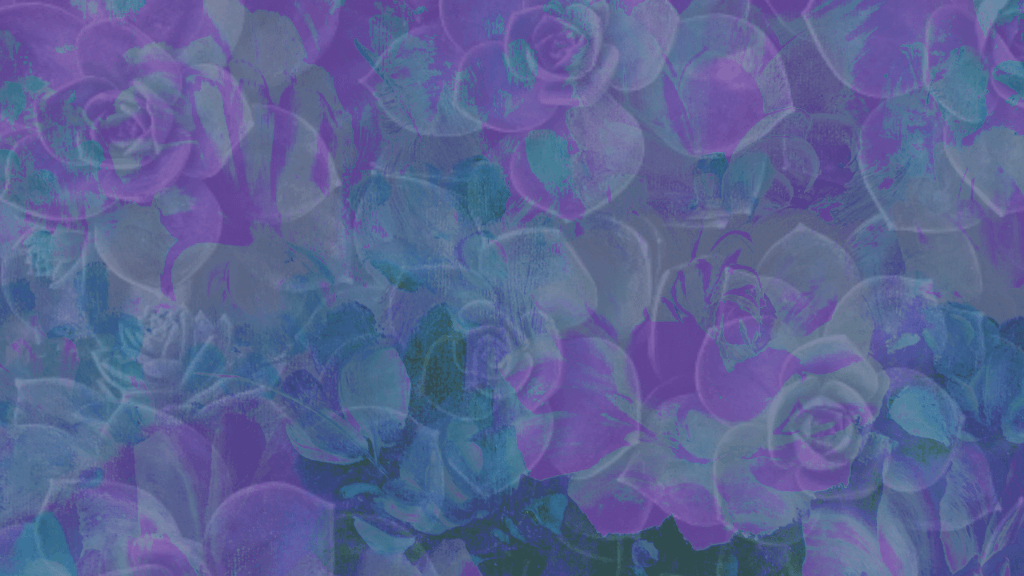
テメンニグルの中は伝承とは違い、近代的な部分が見受けられた。
しかし流石は魔界と人界を繋ぐトンネル。人間には到底解けない様な仕掛けが幾つも見受けられた。
魔力を帯びた魔道具に本棚の中には数多の、強力な魔術の使用方法や薬品の作り方が載った魔道書。そして魔力に反応する移動用の仕掛け。
これらは何者かが魔界の封印を解かないようにする為にスパーダが仕掛けた物なのか。もしそうだとしたら思っていた以上にスパーダは強力な悪魔だったのかもしれないとアスタは思わず戦慄した。
アスタの隣にはバージルの姿もアーカムの姿も見受けられない。それもその筈アスタは一人でテメンニグルの中を偵察していたのだ。アーカムに言われて。
気に食わない人間の中に位置するアーカムに顎で使われるのは未だに癪に思っているが、バージルにも内部を見てくる様に言われたから仕方なく、だ。
尤も、彼らに言われなくても"来るべきその時"が来るまでこの塔の中を調べようとは思っていたが。アスタには一度たりとも折られた事のない強い牙と、魔界のガンスミスが原型を作った銃、それにアスタが手を施した特殊なワイヤー入りのブーツがある。このブーツさえ上手く使いこなせていれば移動は実に容易な物だ。
「この先にもまだ仕掛けがある。それに、魔力が濃い……」
アスタが今いる階段が連なった広間の向こう。恐らく出入り口だろう、その先から氷の様な冷たさを纏った強大な魔力を感じる。
別に恐れる程の魔力ではないだろうが今は呼び覚まさないほうが賢明かもしれない。
アスタは少しだけ疑心を感じていたのだ。テメンニグルの封印を解く前からダンテがヘル・ヴァンガードと戦っていた事は漂ってきた魔力の流れで解っていたが、何故ヘル・ヴァンガードに止めを刺さずに逃がしたのか。
バージルには悪いがダンテはそれほどの力を有してはいないのではないのかと頭の片隅で議論が巻き起こっている。
それをどうにか止めるにはこの氷の悪魔の力を使うのが有効だと考えた結果だ。
一通り塔の中は見てまわっただろうし、そろそろバージル達の所に戻ろう。そう思い、塔内のドアを開いた際に目の前から青い魔力の矢が飛んできた。
すぐに蹴り飛ばし攻撃態勢に入るが自分が弾いた矢が折れ、先端がアスタの頬を掠める。赤い血の筋が頬を伝う。
「っ!この!!」
右脇に通しているアルカネット用のガンホルスターからアルカネットを素早く引き抜くと、矢を放って来た悪魔・エニグマのど真ん中に当たる目に容赦なく弾丸を撃ち込む。エニグマは思っていたよりも脆く、すぐに崩れ、死んでしまった。
アスタは何事もなかったかの様にアルカネットをホルスターの中に収めた。
しかし、今度は頭の中に誰かが語りかけてくる。語り掛けると言うよりはクスクスと笑っている。人の頭の中で不愉快だ。
「誰……」
声の主が近くにいると、そう思い、呼びかけてみても周りには誰も居ない。
この塔に封印された悪魔がアスタの魔力を察知して語りかけているのか。そう思う方が自然だろう。
「貴方は、誰?何処にいらっしゃるのです?」
『ふふっ、可愛い魔女ね。私は"此処"よ』
女の声が頭の中に響いてくる。そして魔力で語りかけてきている彼女がいる場所を脳裏に映像として映し出した。
アスタの脳裏に映り込んだのは沢山の蝋燭で明るく照らされた、小さな舞台の様な部屋。
その中にぽつんと一人だけ女性が部屋の真ん中に立っている。彼女はオレンジ掛かった長い赤毛を揺らし身の回りに蝙蝠を侍らせていた。肌の色が水色の所で彼女が悪魔だという事は容易に解ったが、彼女は何故自分に意思疎通を試みたのだろうか。
「お名前は?」
『あら、人に名前を尋ねる時は自分から名乗るのが礼儀じゃなくって?』
「……アスタ、と申します。一応、この塔の封印を解いた者の一人です」
『可愛い子。私は"ネヴァン"。嘗てスパーダと共に戦った悪魔よ。アスタ、貴方はスパーダの話を聞きたいかしら?聞きたいのであれば此処までいらっしゃい?貴方は道筋を知っているでしょう?』
「……」
何故だろうか。ネヴァンが頭の中に直接語り掛けてくると意識が何処かに吹き飛んだ様に頭の中がぼんやりとしていく。今もアスタの意思とは裏腹に足が勝手に彼女が送り込んできたヴィジョンの部屋に向かおうと足が勝手に動いていた。
しかし、アスタが向かおうとした方向とは反対にアスタの腕が引っ張られる。そこでアスタの意識は一度はっきりとした。
何かを感じた様に其方を振向くと其処にはいつも隣にいる、大切な人。
「何処に行くつもりだった」
「少し気になる場所がありまして」
「もう良いだろう。此処はあくまで目的を成す為だけに用意した場所だ。余り好奇心を働かせるな」
バージルはそのままアスタの腕を引くと元来た道を辿る様に階段を飛び越えていく。アスタもそのタイミングで一緒に階段を跳んで踏みしめていく。
そうだ。あくまでテメンニグルは魔界への道を開く為の手段でしかない。その事をすっかり忘れていた。
「そろそろ奴も此処に到着する頃合だろう」
「奴?……ダンテの事、ですか」
「ああ」
そう言ったバージルの声は何処となく楽しそうに聞こえた。
今しがた、バージルはこのテメンニグルは目的を成す為だけの場所とそう言ったが今の彼を見ていたら魔界の扉を開く為だけが目的ではないような気がしてきた。ダンテ、弟との再会を果たす。それも彼の目的の中に入っているように感じる。
実を言えばバージルから1年前、この街に来た折にダンテと会って話をしたという風に聞いていた。
しかし話の内容はアスタが思っていたよりも殺伐としていて、更に言えば深く、悲しい。
彼らは、殺し合いを始めたという。
その話の内容に併せて、バージルは昔からダンテとは折り合いが悪く、仲が悪かったとそう溢した。だからと言って殺しあう事はないだろうと思ったが世の中の双子が皆、全て自分達姉妹の様に仲が良い訳ではない事位、アスタだって心得ている。
「ダンテと」
「?」
「ダンテと戦うのもバージルにとっては大切な目的、ですか?」
「……いや。だが、奴からアミュレットを奪わなければならない。それ自体が目的、戦うのは二の次だ」
「バージル、あの……」
其処まで言葉を口にした所でこちらを見る事無く、話だけしながら先を歩いていたバージルの足が止まり、振向く。しかし振向き様に閻魔刀を抜いていた様でアスタの目と鼻の先には閻魔刀の切っ先が突きつけられていた。
距離的には1センチメートルあるか無いかの距離。アスタがバージルの動きに気付かなければ恐らくこの切っ先は容赦なくアスタの顔面に穴を開けていただろう。半魔にされた力の影響で刀が貫通しても生きてはいられる。だが、痛みがない訳ではないしアスタはいたいのは嫌いだ。
心臓を鼓動させる事と呼吸を忘れているアスタを見るや否やバージルは鼻を鳴らすと閻魔刀をそのまま鞘に納めた。
「アスタ、諺を知っているか?"好奇心は猫をも殺す"と」
「……」
こめかみから滲み出た油汗が顔の輪郭をなぞり、顎の先から一滴だけ零れ落ちた。
「お前は出来た女だ。唯一、信頼もしている。だが、それ以上俺の事情に踏み込むな」
「俺もお前の事情には踏み込まん」。静かに、いつもの調子でそう言うと石造りの廊下を靴音を鳴らしアーカムが待つ塔の天辺へと向かう。
しかしアスタの足はその場に縫い付けられた様に動く事が出来なかった。へたり込む事はないが恐怖で足が竦む。
「どうした。早く来い、アスタ」
「……先に行っていて下さい」
顔を俯かせてそう返すとバージルは溜息を吐いてアスタまで距離を詰める。そして背と膝裏に腕を回し、アスタの体を横抱きに持ち上げた。
彼らしくない行動且つ、女扱いをされている事に対しアスタは顔を真っ赤にさせる。
「手間を掛けさせる」
「それならば、置いていけば良いでしょう?」
「それは出来んな」
「お前は見ていて危なっかしい」と何時もの平坦な声でそう言われる。
確かに危ない事は良くするがアスタはちょっとやそっとじゃ死にはしないのだ。それともバージルのアスタに対する杞憂は何か別の所にあるのか。そう勘繰ってしまう。
それが、アスタとダンテの衝突だとしたら。アスタがダンテからアミュレットを奪って戻ってきたりしたら。
その時、バージルは自分に対してどんな感情を抱くのだろうか。
『あら、良く知らない人間に嫉妬でもしているの?』
「!」
「どうした」
「あ、いえ……」
急にまた頭の中に直接語り掛けて来たネヴァンに反応し、体を大きく揺らした。だがネヴァンの声はそれっきり聞こえなくなる。流石は悪魔、愉快犯の様な事をしてくれる。
だがダンテに対するこの胸の内のもやもやとした感情が何なのかが漸く解った様な気がする。
少しだけ距離が縮まっているバージルの表情を凝視しても特に表情の変化はないが、先程のあの愉悦を感じた表情をさせられるのは恐らく後にも先にもダンテしかいないだろう。そう思うとまた胸の置くがもやもやと鬱屈な感情を作り始める。
「ねぇ、バージル」
一つだけ、アスタの中でバージルに対して質問したい事が出てきた。
「もし、私が先にダンテと戦ってダンテを殺してしまったら貴方は私をどうしますか」
我ながら下らない質問だとは思う。だがどうしても聞く事を止められなかった。
今度こそバージルに殺されるかもなぁ、とも思ったがバージルはアスタを一瞥しただけで少し何かを考えただけだった。
そして、回答を告げるべくゆっくりと口を開く。
「別にどうもせん。ダンテに力がなかった、ただそれだけの話だ」
「そう、ですか」
「アスタ、今日はやけに饒舌だな。何かあったのか」
「……別に何も。言うなればただの"好奇心"って奴ですよ」
「バージルに殺されてしまいますね?」と悪戯っぽく笑うと、アスタの背中を支えていた筈のバージルの手がふっと離れアスタの頬を抓る。
「馬鹿が」
そう言ったバージルの表情は僅かに緩みを見せ、穏やかそうにアスタの瞳に映った。
2015/03/10