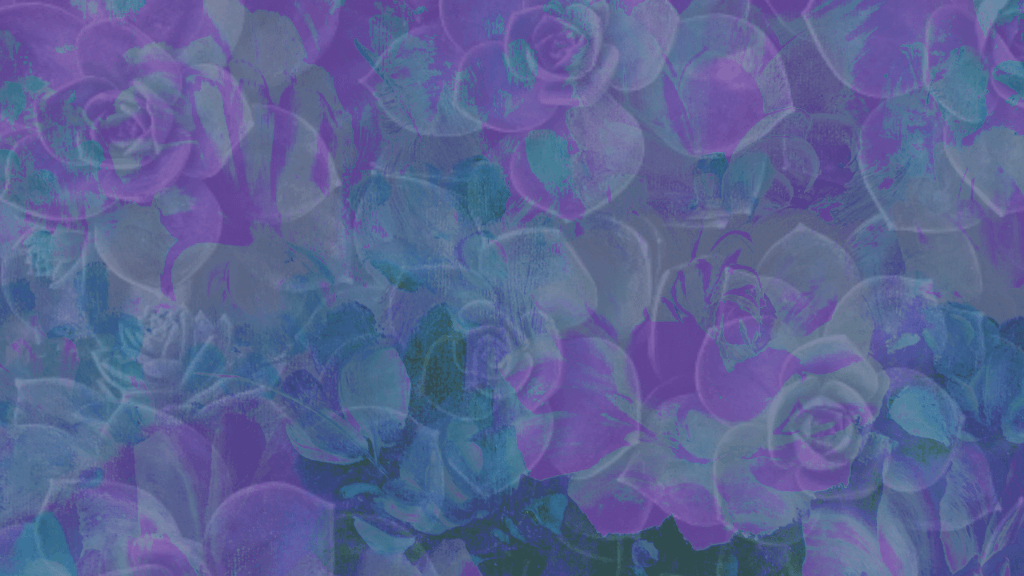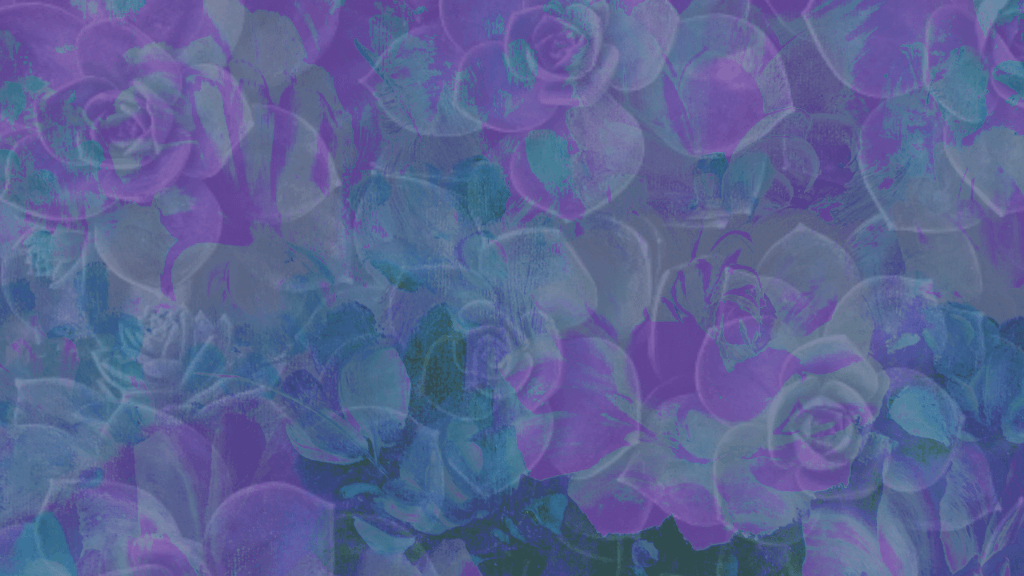
バージルは街頭が消えた街の中を一人で、片手に閻魔刀だけを携えて歩いていた。
あの後アスタとの約束通り飲み物を持っていってやり、少しだけ話をした。何の話をしたかは殆ど覚えてはいないが、話をしていた時のアスタが何かを憂うかの様な表情だけは脳裏に、網膜にこびリ付いている。
覚えている話は彼女が悪魔の力を覚醒させる前にあった話だけだ。
「また、ダンテに会ったのか?」
「会った、と言うよりは姿を見た、と言った方が正しいです」
「しかし何も出来なかった」
「……はい。そもそも面識自体がありませんから。何と言葉を掛ければ良いかすら解りません」
アスタの事だ。恐らくバージルに役立たずと言われる事を恐れていたのかもしれない。以前から彼女はバージルが距離を置こうとすると酷く脅えた様な顔をする。彼女の生い立ちがそうさせている事位はバージルも理解をしていた。
余り過去の事を話したがらないアスタだが以前酒を軽く煽っていた時にするりと過去を溢したのだ。それに彼女の過去に関わる場所にも行った事がある。その時も独り言の様に小さく様々な言葉を溢していたのを今でも良く覚えている。
依存。他人に依存しなければ彼女は自分自身を保っていられない。そういう風に育て上げられてしまっていた。
だがバージルはアスタの働きに評価をしているし、それを自分で断ち切ろうと努力しようとしている事も良く知っている。だからこそ余り気にはしていない。
その後も少しだけ他愛のない話をして、まだ疲労が残っていたのだろう。アスタはそのまま目を閉じて眠りに付いてしまった。
だからこそバージルは一人で次の封印場所に向かっていた。本当はアスタも一緒に連れて行くつもりだったのだが回復能力に優れていると言っても彼女は元々人間だ。体に根付いてしまった疲労まではそう簡単には回復はしないだろう。バージルには良く解らない感覚だが。
アーカムに告げられた次の封印場所を探すのは実に容易だった。
白く塗料でコーティングされた大きな柵に、奥には灰色の形様々な墓石。
バージルは次の封印が隠されている街外れの墓地に来ていた。墓地の教会下に封印が施されていると言う。
「また教会か」とバージルは思う。父は何を思って教会に大罪を封印したのか。彼は偉大な悪魔だという事は息子のバージルは良く知っている。尤も記憶の中にいる父・スパーダは古の、伝説の魔剣士とは思わせない、少し厳しいが心根は優しい男であったが。
墓の列の合間を歩き、バージルは少しだけ寂れている教会の中に足を踏み込んだ。寂れているといえ未だに誰か彼か祈りを捧げに来ているのだろう。床や礼拝用の長椅子はほこりなど被っておらず綺麗な物だ。
「……この魔力」
しかし教会に入り奥に進むにつれ、バージルが知る物の魔力がその場に微かに残っていた
。
その途端、傲慢と対峙した時と同じ様に急に頭が痛み始める。ただ一つ傲慢の時と違う事は「頭が割れそうだ」とそう思いながら、低く呻き声を漏らしている事ぐらいだ。
脳裏に"あの日"の記憶が色濃く、再び甦る。
真っ暗な漆黒の空に赤いからすき星。バージルは夜の墓地に一人佇んでいた。幼い子供の、昔の姿のままで。
この後バージルは骨格標本の様な悪魔達に襲われた。昔の自分であればそれが途轍もない恐怖だったが今では百戦錬磨の剣士として成長している。この記憶の中でもその腕前が反映されていれば、の話だが。
抜き身のままの閻魔刀を手に取り、果敢にも子供のバージルは悪魔達に挑んでいく。
小さな体では閻魔刀は大きすぎる上に重たいのかどうしても隙が出来る。その隙を狙って悪魔はバージルの腕に噛み付いた。真っ赤な血が噛み跡から吹き零れる。
同じだ。この前傲慢の所で見たビジョンとなにもかも。
今更過ぎる。こんな物を見せられても。バージルはゆっくりと息を吐き、呼吸を、気を整える。その頃には頭痛も消え失せていた。
「……ダンテ」
ただ一人生き残っている肉親の名を呟く。
血を、肉を、魂を分けた双子の弟。昔から気が合わず衝突し、あらゆる事で気に入らなかった。
此処に浮遊し、残っている魔力もそれはダンテの物であった。
††††
同時刻。同協会の地下で赤いロングのレザーコートを身に纏った男は悪魔とのダンスを楽しんでいた。
急に街に沸き出始めた悪魔。その根源を追って此処に来た。彼は表向きには無名の便利屋を始めたばかりだが、実の所を言えば本職は悪魔専門の狩人、デビルハンターであった。
背には大剣・リベリオン。腰のガンホルスターには白と黒の双子拳銃・エボニー&アイボリー。どちらも彼にとって大切な人が遺してくれた大切な相棒だ。
当てもなく水で浸水した、血生臭い髑髏の海を歩いていく。ブーツの中がぐちゃぐちゃになるのを眉間に皺を寄せる。
そんな時、彼がいる地面の更に下から地響きを起こす様な、低く暗い呻り声が鼓膜とその空間を大きく揺らした。
『スパァァァァァァァァダァァァァァァァ』
彼はこの空間に対する不快感以上にその声に眉間に皺を寄せ、舌打ちを大きく響かせる。
Holy shit.またこの手の手合いか、とそう思うと憂鬱である。"有名人の息子"と言うだけで何時でも災厄は己の身に降りかかる。それは幼い頃から今までずっとだ。
声のエコーと空間の揺らぎが収まると彼の周りに赤く不気味に光る魔法陣が浮かんだ。それを合図に背に背負った反逆の名を持つ相方を手に取り、真正面の陣に向かって剣先から突っ込んでいった。
スティンガー。それがその技の名前。
リベリオンの大きく太い刀身には悪魔、ヘル・スロースの腹を貫き刺していた。瞬間、死したヘル・スロースの体が真っ黒な砂になり四散していく。
彼はリベリオンの刀身を肩に預け、声を張り上げた。
「スパーダは親父の名前だけどな、俺はスパーダじゃねぇ、人違いだ。俺の名はダンテ。良く覚えとけ」
そういうと今度は左右から襲ってくるヘル・スロースを双子拳銃で素早く打ち抜いた。
「Let's Rock!」
ダンテは愉快そうに口角を吊り上げ、犬歯を見せて吼えた。
其処からはその空間はダンテのワンマンショーの舞台へ変貌する。本人としては派手に彩られたスポットライトと豪快なBGMが欲しい所だが寂れた教会の地下深くではそんな物は望めない事くらい解っている。
リベリオンで突き殺し斬り殺し、エボニー&アイボリーで撃ち殺す。ただしそれは悪魔のみ。それがダンテの信条だ。人間は手に掛けない。嘗ての父・スパーダがそうしたように。
確かにダンテも人間に怨まれたり、変なやっかみを掛けられたり、色々と汚い部分を見せられてきたがそれでも人間を嫌う事は出来なかった。それは"そういう人間ばかりではない"と言う事をよく知っているからこそ。
背後を取ろうとしたヘル・プライドの眉間に弾丸を一発くれてやってその場での先頭は無傷のまま終了した。
これでも長年、あの日からデビルハンターとして悪魔を倒す為に特訓をしてきたのだ。背中に背負ったリベリオンと共に。
「さてと、そろそろこんな辛気臭くて不気味な場所からおさらばしたいぜ、まったく」
両掌を叩き合わせ、憎まれ口を叩きながらも先へ行く。灯りもなければ、道と言う道もない。本当に此処は教会の真下なのか。ダンテはそう思う。
だがあの場で立ち止まるよりは先へ当てもなく進んだ方がまだ幾分かましな様に思えたからそうする。
あの場所からまだ数十メートル程しか歩いていないだろう。だが、其処でダンテの身に違和感が走った。
体に電撃が走ったような気がした。
「?! っ、何だ今の……」
ダンテは水の中から競り出ている杭の様な物の上にいつの間にか移動していた。
もしかしたら殺気のやつらとは比べ物にならない、特殊な能力を持つ悪魔がその場にいたのか。もしそうであったとしても気付かない訳が無い。悪魔の気配や臭いは独特でダンテはそれを感じ分ける事がで来たのだ。
しかしそれを感じ取れなかったという事はその場に悪魔はいなかったという事と同義だ。
顔を上げればこれまたいつの間にか現れたか解らない大きな女体の像が其処に姿を現せていた。
首から上はなく、右腕も二の腕から下が崩れ落ちて確認が出来ない。
ダンテが像の体を何気なく眺めていると先程の声が聞こえてくる。
『封印されし長き年月。悔恨の日々。屈辱の年月』
ぽちゃんとどこかで水滴が水面に落ちる音がした。
『貴様に裏切られし我が身を恥じ、血の涙を流し、涙は海となり果て貴様の再来を待ち続けた。2000年……』
「何の話かわからねぇな」
『積年の思い如何に貴様に伝わるべきか。……スパーダ、臭いはすれどまだ貴様が見えぬ』
ダンテの存在を無視し、一人語りを続ける像にダンテは目を鋭く光らせ、その場から高くジャンプをする。その手にはリベリオンを確りと握り締めて。
「毎日シャワーも浴びてるのに臭うだなんて傷付くね。それに俺はスパーダじゃなくて、ダンテだ」
しかしそれでも尚、像は罅割れた声を震わせてダンテの事を『スパーダ』と呼び続ける。
そして弾丸の雨をダンテに向かって降らせる。雨と言うよりは魚雷に近いかもしれない。ダンテを狙って飛び交っているのだ。
しかしダンテはそれを避けるわけでもなく、リベリオンを大きく振り上げて一閃。骸骨を媒体にした弾丸を斬激で斬り伏せた。
足元を多い尽くす血の海は消え失せ、目の前の壊れた女体像はばらばらに砕け散る。
「ハハッ、ラクショー」
『スパーダ、スパーダァァァァ。我に、我に名を……』
目の前にある顔の、鼻から下のみの大きな塊が尚もダンテに語り掛ける。
その様にあきれ返りながらダンテは再度言葉を紡いだ。
「クレイジーだぜ。口だけになっても喋り続けるたぁ……」
もう一度背に負ったリベリオンの柄に手を伸ばす。
スパーダが昔この像に何をしたかは解りかねるが、これ以上は鬱陶しい。彼は「自分よりおしゃべりな人間は大嫌い」な性質だ。尤もこれが人間じゃない事くらいは解っているが喋りなのには変わりが無い。それに話も聞いてくれていない。
そんな時だ。像があった場所から大きな亀裂が走り、空間が崩れ始める。
「今度は何だってんだ」
そのままの流れに乗りダンテはリベリオンを構える。
暗闇の奥から人間のシルエットが浮かび上がっていた。その手には日本刀を握っている。
そしてそのシルエットは物静かに口を開いた。
「スパーダの名において……封印に名付ける」
その姿を見た途端、ダンテは大きく目を見開いた。それが此処にいるべき筈のない人物だと知っているから。
2015/02/24