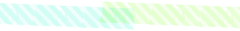name change
name change  clap
clap誰のあなた

恋人は甘え下手だ。なにをしてあげようとしても遠慮が抜けなく、なかなか我儘も言わない。加えてシャイときたものだから人前で触れ合うなんてことは皆無に近く、付き合い始めの頃、手を繋ぎながら街を歩くだけでも顔を真っ赤にしていたのが少し懐かしい。だから今この時いつ誰かが訪ねてくるかもわからない東隊作戦室で、俺に抱きついて顔を埋めている風花というのはかなりめずらしい光景だ。はからずも巡ってきたこの機会に喜びたいところではあるがそうも言っていられない。俺を後ろからぎゅっと抱きすくめる風花が恐ろしく静かで不安にさせられる。
「風花……?」
名前を呼ぶと風花はぴくりと反応したが、やはり何も言わなかった。なにかがあったことは確かだ。しかしまだ心の整理がつかないのだろう。彼女の中で渦巻くそれを口に出すべきか否か決まらず、どうしようもないままにこうなっている。あの風花が、恥ずかしがり屋で甘え下手を地でいく風花が、人目をはばからず俺に触れている。それだけで大変な事態であることは明白で、焦らせる言葉をかけてはならないと俺は黙ってされるがままになることにした。それからくぐもった声が背後から聞こえてくるまで数分を要した。
「あずまさん」
「……ん?」
ようやくだが少しずつ落ち着いてきたようだ。先ほどまで力を込められていた腕が、今は縋るように俺の背中側を掴む。その手から彼女の不安が伝わるようで、俺はできるだけゆったりと宥めるように返事をした。大丈夫だから、ゆっくりでいいから、と告げるように。
「東さんはすごい人ですよね」
「いきなりだな」
しかし彼女の口からは思いもよらぬ褒め言葉が飛び出してきて、俺は虚をつかれた。いまだ風花の顔は見えないためにどんな表情をしているのかわからない。
「すごい人です。弟子がたくさんいて、技術も戦術も、色んなことを伝えていかなきゃいけないし、上層部の人たちにも頼りにされて……ボーダーになくてはならない存在です」
……ああ、そうか。
「さっき俺がエンジニアと話してるの、聞いてたのか」
そう問うと、風花はややあってからこくんと頷いた。
さっき、というのは今朝のことだ。最近の俺は、上層部の大事な会議に呼ばれたり、弟子や後輩の子たちに戦い方を指南したりする中で、大学での研究が重なったりなんなりと忙しく、少々寝不足気味ではあった。それを今朝、本部の廊下でばったり会った知り合いのエンジニアに「お前の身体はお前だけのものじゃないんだから、ボーダーのためにも体調には気をつけろよ」と、冗談まじりに指摘されたのだ。俺は苦笑し「わかってるよ」と答えたような気がする。その時の会話を聞かれていたのか。
俺は俺の背中に額をくっつけて縋る風花から離れ、向かい合う形に体を動かす。風花の顔が見たいと思った。俯いたままの彼女の頬に手を当て、視線を合わす。その瞳は潤み、揺れていた。
「心配させたな。悪い」
やらなくてはならないことがある。それは事実だ。弟子たちに自分が培ったものを教えないといけないし、ボーダーのために尽くしたいとも思っているから、その頭脳でもある上層部に直接協力する機会があればする。それを言い訳にしたくはないのだが、だから風花と一緒にいれる時間も、他の恋人たちと比べたら断然に少ないのだ。
「確かに俺は色んなことをしなくちゃならないから、風花に寂しい思いをさせているかもしれないが……」
「ちがう……! そうじゃないです!」
俺の言葉を遮って風花は必死に叫んだ。俺はどこにも行かない、ここにいるのに。違うと言われ、では他になにが彼女をここまで不安にさせているのかと思考を巡らすが、思い当たる節がない。それなのに俺に触れる小さな手は僅かに震えるばかりだった。不安にさせたいわけではないのに。
すると彼女は、潤んだ瞳はそのままにしっかりと俺の目をとらえ祈るように語り出す。
「もしかしたら東さんも自分のこと、エンジニアの人が言ったみたいに、ボーダーのための存在って思ってるのかもしれないけど……。だけど、東さんはボーダーのものとか、誰かのものとか、もちろん私のものでもなくて」
少しずつ、少しずつ、ほどかれて。
「東さんは、東さんのものです」
真っ直ぐなその言葉は、そのまますとんと俺の中に落ちていった。
「……そうか。うん、そうだな」
一緒にいてあげられる時間が少なくて寂しい思いをさせているんじゃないかとか、嫉妬してくれているのだろうかとか、いや実際にそうだとしても、風花は俺が俺であることを願っていてくれていた。弟子たちのために、ボーダーのためにと従事していく内に、自分が誰のために存在しているのかも曖昧になっていくような、ぶれてしまっていた俺の在処を、彼女はずっと見失わずにいてくれていた。そして明確に示してくれたのだ。嬉しさも愛しさもぐちゃぐちゃになって、じんわりと胸が熱くなる。……でも。
「お前もわかっているとは思うが、ボーダーに必要とされてる以上、俺は俺の役目を果たしたいんだ」
「わかってます。それでいいです。東さんがもっと自分のことを大事にしてくれるなら」
風花のためにも、もちろん俺自身のためにもそうしたいとは思っているのに、それを約束することはどうしてもできない。すると俺の考えていることを察したのか、風花は鋭い口調で告げる。
「もしそれができないなら、私はボーダーを辞めてどこか遠くに行きます」
「それは……嫌だな」
それは俺にとって1番効果的な脅しだ。ボーダーと風花を天秤にはかけられないが、俺は風花をなによりも大事に思っており、大事にしたいのはなによりも風花だ。彼女が遠くへ行くのなら俺も着いて行くことをわかっていて言ってるあたり、風花は俺の扱い方を覚えてきたらしい。ああこれは、適わないな。
「わかった、約束するよ。俺は俺のものだ。だから無理はしない」
「……絶対ですよ」
「ああ、絶対だ」
風花それを聞いてようやく安心したのか、ふわりと顔をほころばすと、途端思い出したかのようにふいっと俯いてしまった。どうして今さら照れるんだと笑えば、力なく「だって」と返ってくる。それがすごく愛おしくて、俯いたままの彼女のおでこにキスを落とすと、弾かれたように顔が上がった。予想通り真っ赤だ。俺はそのまま両手で頬を包んで風花の顔を固定し、彼女が俺にしたようにしっかりと目を合わせる。
「ありがとう。風花」
俺を見つけてくれて。
誠意を込めて感謝を伝えたつもりでもまだ足りない気がして、代わりにそっと唇を重ねた。

[top]|[main]