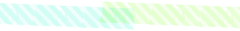name change
name change  clap
clap雪がとけてしまわぬよう

冬というのは不思議なことに、仲間内で集まりたくなる季節らしい。一緒のこたつに入ってみんなで鍋をつつきながら談笑する。まあ、おれたちみたいに常に隊で一緒だと冬もなにもないかもしれないが。それでもやはりこたつと鍋は恋しくなるもので、うちの気まぐれ隊長こと太刀川さんの「鍋パするぞ」の一言に反対する者などいなかった。約1名の某御曹司は「ナベパとは?」と首をかしげていたけど、放っておいていいだろう。というわけで、唐突ながら太刀川隊で鍋パーティーをすることに決定したのだ。
俺と風花は柚宇さんに買い出し係に任命され、今まさに白く染まった街にいた。サクサクと僅かに積もっている雪の上を歩き、目的の店を目指す。
「公平」
俺の隣を歩く幼馴染は、小さく俺の名を呼ぶ。風花は昔から口数が多い方ではなくかぼそくぽつりと言葉をこぼすため、時折この雪のように消えていってしまいそうな、そんな感覚になる。
「んー?」
「太刀川さんから渡された買い出しメモ、鍋用スープと餅としか書いてない」
「はは、さすが太刀川さんだな」
どうする? と目をまんまるくして首を傾ける姿は冗談抜きで小動物のようだ。
「さすがにそれだけじゃな。うーんと、鍋と言ったら豚肉とか白菜とか、しいたけとかか? それくらいは買っていこうぜ」
「うん」
風花とは小学生の頃からの付き合いの幼馴染であり、ボーダーに一緒に入隊した同期でもあり、現在は太刀川隊の仲間でもある。昔からこいつは小さい。身長のみに限らず、なんというか、手も、足も、声も、儚いという言葉はこいつのためにあるんじゃないかと思うほどに。雪のようだと形容したがまさにその通りで、思わず手を握って彼女の存在を確認したくなる。それは風花が、驚くほど自分自身に価値を見い出せない性分であるせいなのだと思う。自分のことはどうだってよくて、ともすればふっと消えてしまうかもしれない。いつだって怖いのだ。風花がおれの目の前からいなくなってしまうのではないかと。だからおれは、風花をつなぎとめておく何かが欲しかった。
電飾に彩られる商店街に着くと、若い女の人が一人また一人と通り過ぎてゆく。すると風花がちらりと一人を見やった。おれたちと同い年くらいの女の子で、ほのかなメイクと、耳元の控えめなハートのピアスがかわいらしい。……もしかして。その時おれは光が見えたような気がした。
「風花はオシャレとかしねーの?」
ふと、そんな疑問を投げる。風花はきょとんとおれを見、そしてまたかぼそい声をこぼす。
「おしゃれ……」
そう言えば風花は、女性が興味を持つようなかわいい服も、アクセサリーも、おそらく持っていない。ていうかこんなにも寒いのにマフラーも手袋もしていない。自分を彩るものを身につければ、自分自身を大事な人間のひとりとして認識できるのではないか、そう思った。
「あまり。似合わないと思うから」
「似合わねえって……アクセサリーとかが? おれ、お前がそういうのつけてるところ見たことないぞ」
「うん。つけたことない」
「じゃあ似合わねえとか、わかんないじゃん」
「…………」
似合わないからつけたくない。そう言った風花の声はいつもよりも消えてしまいそうで怖かった。どうしておれがこんな必死なんだと思ってるだろうな、こいつは。納得いかないとでも言いたげな視線を向けられれば、こっちだって考えがある。
「なあ、似合わねえと思うからそういうのつけないの?」
「うん」
「じゃあ、つけてみようぜ」
「?」
おれは風花の冷え切った手を握り、今ここに彼女が存在していることに安心する。そして目のついた雑貨店へと歩き出すと、風花は困惑して声を上げる。
「公平、そこは食品を売ってるお店じゃない」
そんなことはわかっている。買い出しは後回しだ。
店の中に入ると、たまたま目に付いた薄ピンク色の石がはめ込まれたネックレスを手に取る。
「これとかどう?」
「どう……」
風花はネックレスを見つめるが、困惑したままだ。
「……わからない」
「んじゃ、これは?」
おれは風花に似合いそうな白くて上品な花が付いたネックレスを手に乗せてみた。これが風花の首にかけられているのを想像する。うん、似合う。でも風花の表情は変わらず……。
「……公平」
「ん?」
「こういうの本当にわからない。柚宇さんならきっとなんでも似合う。でも私は……似合ってるとも、思えない……ごめんなさい」
そう申し訳なさそうに言われて、はっとする。これではただの押し付けだ。違う、そうじゃない。おれは誰かに服やアクセサリーをコーディネートされた風花が見たいわけじゃないのに。ただ……。
「あー……わりぃ、困らせるつもりじゃなかったんだけど」
ただおれは、風花自身を望んででほしいだけだ。自分の存在を。太刀川隊にいることも。ここに居たいと望んでくれたら。
「お前がさ、本当につけたくないならそれでいいけど、似合わないからつけないってんなら、違えなって思ったんだよ。だから、その……」
おれの言葉の続きを風花が待っていてくれることに安堵して、ゆっくりと、彼女に届くようにと願いながら紡ぐ。
「風花が気に入ったものなら、何をつけても似合うと思うぜ」
風花は驚いたようにぱちぱちと瞬きをして、そして、これまで見たことないような柔らかい微笑みを見せる。それからはっきりとこう言った。
「……うん。ありがとう」
繋がれた手が、ようやくぎゅっと握り返された。
「で、なんか気になるやつあったか? せっかくだし買ってやるぞ」
「えっと」
風花は店内をくるりと見渡したあと、少し悩みこんだ。そして真っ直ぐにおれを見る。
「公平がつけてるもの」
「え?」
今なんて言った?
「公平がつけてるもの。なんでもいい。使わなくなったら」
おれがつけてるもの……? そりゃ、おれはこいつにもっと自分自身を望んで欲しいと願ったけど。こいつが自分に価値を見い出せるようになって、自分の欲しいものを口にしてほしいと……。ちょっとまて、ということは、初めてこいつが欲しいと望んだのは。
「だめならいい」
「い、いや……!」
おれは手早く首からマフラーをはずし、代わりに風花の首にくるくると巻いてやる。赤くなっているであろう顔を見られないよう気をつけながら。
「どうだ。あったかいだろ?」
「いいの?」
だめなわけが無い。むしろ。
「おれがお前に使ってほしい」
そう言って、ニッと笑顔を作って見せると、本日2度目の笑顔が返ってきた。
太刀川隊の作戦室に帰ってくると、もう既に鍋の用意はできており、残りの3人ともこたつでぬくぬくとおれたちを待っていた。
「おっ、やっと帰ってきたな」
「待ちくたびれたよ〜」
おれたちが買ってきたスープと食材を5人で……いや実際は鍋の作り方も食べ方もわからない唯我を除いた4人で調理し、できあがった鍋を囲んだ。
「あれ? そういえば風花ちゃん、そのマフラー……」
あ、やっべ。
風花は相当気に入ってくれたのか、室内に入ってもマフラーを取らないままなので、柚宇さんになにか勘づかれたようだ。おれと風花を交互に見て、ははーんと意味ありげに呟く。
「? どうしました国近先輩」
「マフラーになにか付いてんじゃねえの」
唯我も太刀川さんもあほでよかった。ていうか、普通気づくだろ。おれが2人にバレなくてほっとしていることに、渦中の人物はまったく気づいていなかったようで。
「これは公平にもらった」
「ブッ」
おい風花お前素直すぎるだろ!というおれの叫び声、風花の言葉を聞きここぞとばかりに質問攻めしてくる太刀川さんたちと、それを楽しそうに眺めながらふわりと微笑む風花。この空間があたたかくて、おれはもう雪が消えてなくなる恐怖を感じることはなかった。

[top]|[main]