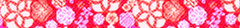
撫子世 「よし、何処からでもかかってこい!」 薄桃色の矢羽柄の着物に海老茶色の袴を身に纏い、茶の革靴で地を踏みしめ、目の前の少女は髪を結わえた紅色のリボンを揺らし、叫ぶ。 竹刀を手に構えながら。 (…どうしてこうなった) 相手に無理矢理握らされた竹刀を片手に、一人明け方の空を遠い目で見ていた。 俺はきらきらとした瞳で此方を見つめる少女の方に視線を戻すと、溜め息を洩らした。 この少女…留は幼なじみであり、親同士が決めた許嫁でもある。 現在、行儀見習い…もとい花嫁修行の為、俺の屋敷で共に生活している。 『たまには息抜きしたらどうだ?』 屋敷に来て間もなく、今までずっと女学校に行っては戻って稽古やら作法やらの繰り返しだった留に、自分の仕事の合間を見て、話を切り出した。 なんなら付き合うぞ、と慣れない花嫁修行で疲れきっている留に更に声をかける。 すると裁縫の手を止め、嬉しそうにこっちを見つめてきた。 『付き合ってくれるのか?』 その愛らしい微笑みに心が揺れる。 本当は、花嫁修行の息抜きなどとは建前で、自分がただ、留と一緒に過ごしたかったのだ。 慣れない花嫁修行を一生懸命やっている留の姿はとても可愛い。 その姿を見ているだけで俺は良い嫁さんを貰ったと誇らしくなる位だ。 ちなみにまだ、祝言はあげていないが、そんなことは別にどうでもいい。 俺たちが結婚することは決定事項なのだから。 けれども留は花嫁修行に構けてばかりで、肝心の夫になる俺の事は最近、どうでもいいような扱いになりつつある。 それが寂しいやら腹ただしいやらで構って欲しくて、声をかけた様なものだった。 そんな想いも内にあり、俺はここで断られたらどうしようかと思っていたのだが、嬉しそうに笑う留を見て安堵した。 『なんでも付き合ってくれるのか?』 『あぁ』 『じゃあ、明日まで考えておくから!絶対、付き合えよ!』 楽しそうにしている留を見ていると俺も嬉しい。 明日はとことん留に付き合ってやろう。 そう思ったのが昨日の夜のことだった。 (それで、お前に付き合うことがなんで剣術の相手になったんだ…) 今朝…といっても先程、早くに着替えた留が俺の寝室に来て、叩き起こされたついでに告げられた言葉は衝撃的なのものだった。 『文次郎、俺、色々考えたけど、やっぱりこれがいい。今すぐ相手してくれ』 寝起きにベッドで良い笑顔を浮かべ、留に竹刀を見せられた時、絶句したのは言うまでもない。 「…なぁ、今じゃなくても良くないか」 早朝から屋敷の庭で竹刀を構える婚前を控えた男女二人。 …何か違わないか。 「やだ。今すぐがいい!」 拗ねた様に頬を膨らませて言う留は相変わらず可愛かったが、その可愛さに騙されてはいけないと俺は自分を叱責した。 「何でこんな朝っぱらからなんだよ…この後、俺すぐに仕事なんだよ…お前も学校あるんだろうが」 「付き合うって言ったのはお前だろ!」 「…ちゃんと言わなかった俺が悪かった。今日は午後が暇なんだ、お互い帰ってきてからにしないか」 「だめ。学校から帰ってきたら課題で出された浴衣の続き縫わなきゃなんないから」 剣術>俺。 課題>俺。 お前にとっての俺の存在って一体何なんだ。 「…お前が息抜きで俺に付き合って欲しいことは本当にこれでいいんだな?」 「うん!薙刀の稽古見てもらうのとどっちが良いか迷ったんだけど、どうせなら一緒に身体動かした方が楽しいと思って」 「薙刀…」 留の考えがその二択しか無いという事実に目眩がしそうになる。 (コイツの中で、もう少し色気のある付き合いというものは無いのか?) 例えば、一緒にオペラを観に行くとか、喫茶店に入ってお茶をするとか。 俺の息抜きで付き合うと言った意味はそういうことだった。 しかし、留にはそんな考えはまるでないようだった。 「料理と裁縫は得意だからいいけど、作法が面倒で苛々してストレス溜まるんだよな…やっぱ俺に向いてるのは剣術だ!ストレス解消ということで、いざ勝負!ヘタレ少尉!」 「お前…仮にも未来の夫に対してなんて言い草だ!」 「なっ…う、うるさい!あくまでも仮だろ!もしかしたら破談になるかも知れないし!」 「バカタレ!ここまできて破談なんかにされてたまるか!」 (冗談じゃねぇ…!ここまで来るのに俺がどれだけ待ったと思ってるんだ!) もともとは親同士が決めた結婚だったので双方の意志というものは存在しない。 だが、俺は物心つく頃から一緒によく遊ぶ留のことを非常に気に入っていたので何も問題は無かった。 しかし、留の方は違った。 『俺は公家の嫁になんてならないからな!』 物心つくまではあんなに素直で可愛かったのに、そうなってからは態度が一変したのだ。 どうやら公家…俺の家の男尊女卑な考えが大嫌いらしく、家の決まりごとに縛られ、大好きな剣術を取り上げられるのが堪らなく嫌だったらしい。 それに何故か、留は嫁入りしたら家から一歩も出してもらえないのではないのかという思い込みがあった。 俺が留の家を訪問した際、顔を会わせたり、剣術の相手をするとなれば喜んで迎えてくれるのが、結婚の話になると頑なに拒絶するのだ。 確かに公家の嫁を務めるとなるとそれなりの教養が要求されるが、留の成績は「甲乙丙丁」の四段階の内の「甲」と「乙」しかなく優れたものだった。 その成績なだけあって留は手先が器用だった。 『公家の嫁になったって恥ずかしくねぇ成績なんだから別に良いじゃねぇか!』 『よくない!1日中屋敷で決まりごとばっかの監禁された生活させられるんだろ!』 『しねぇよ!俺がそんな人でなしに見えるのか!』 『見える!絶対に嫌だ!』『なっ…!剣術だって今まで通りやって構わないって言ってるだろ!』 『でも女は家のことを守るのが当たり前みたいな事、いつも言ってるだろ!男尊女卑の考えの癖に!』 『それは…!』 『それに…文次郎が俺と結婚したいのは家を守る為だろ…!文次郎は俺が好きな訳じゃないのに!俺はこんなに文次郎が好きなのに…!そんな虚しい結婚したくない!』 『留…』 『ばかっ!お前と結婚なんて絶対にしないからな!』 非常に間抜けな話なのだが、俺はこの時、留の本心が知れた喜びと自分の本心を伝えるという行為に照れた為、留に『好きだ』とは伝えられなかった。 後にこれが大きな誤解となり、留は俺が本当に家の為だけに結婚を申し込みに来ているのだと解釈してしまい、近所の伊作と駆け落ち未遂の事件を起こしたのは記憶に新しい。 流石の俺もこの事は相当堪えたので本心を打ち明けるより他はなくなり、『お前じゃなきゃ駄目なんだ』と正直に留に伝えた。 そして間もなくして、留は屋敷にやってきたのだ。 (突拍子もない行動力と負けん気だけは人一倍強いから厄介なんだよな…) 相手の無茶苦茶な行動のせいで、自分の中の男尊女卑と言われるものは大きく捻曲がっていく気さえする。 (結局、惚れた女の前では大和魂なんて形無しなんだろうな) 色々言っても、結局惚れた弱みで甘くなる一方なのだ。 「仕方ねぇな…」 一旦、竹刀を足許に置き、腰の帯革から軍刀を外し、邪魔にならない様、地面に軽く放り投げる。 褐色の制服の襟高に隠れる釦を一つ外した後に手袋をはめ直し、軍帽の鍔を掴み、整える。 先程置いた竹刀を拾い、構えた。 「…よし、来い」 「な、なんだよ!お前から来いよな!」 「…怖いのか?」 「だ、誰がっ!」 此方の言い分が頭に来たのか、赤いリボンを揺らしながら茶の革靴で地を蹴り、竹刀を振りかざし此方へと向かってくる。 それを竹刀で受け止める。 挑発に乗りやすい相手で良かったとつくづく思う。 悪いが流石に女相手、自ら攻撃しようとは思えないし、ましてや、本気など到底出す訳にはいかない。 例え、それが男尊女卑だと相手に罵られたとしても。 (けどコイツ、女のわりに意外と強いんだよな…) ガッ、ガッ、とぶつかる竹刀の音を冷静に聞きながらも何処か焦っている自分が居た。 半分も本気を出していないと言えど、それを凌ぐ留の力は相当のものだろう。 「遊んでないで、本気出せよ…っ!」 「誰が…!…っ!」 急に右足に何か引っ掛かった感じを覚え、自分の足許を見た。 その時だった。 「隙ありっ!」 「しまっ…!」 ぱぁん!、と軽快な音が辺りに響き、よろけたついでに何かを踏みつけ、その場に転倒する。軍帽が取れ、何処かへと落ちていく。 「いって…」 油断したと呟き、叩かれた額を押さえる。 気を取られた原因の足許を見てみると、右足の黒革の編上靴の紐がほどけていた。 理由がわかると悔しいやら情けないやらで複雑な感情が入り雑じる。 「調子に乗ってるからそういう目にあうんだよ。カッコ悪っ」 「…うるせぇ」 近付いてくる留に顔を見られたくなく、未だ倒れたまま、顔を反らした。 「よいしょっ…と」 「ぐあっ…!」 …が、次の瞬間下半身に受けた衝撃で、顔をそっちに向けざるを得ない状況になった。 恐る恐る見ると、留が俺の腰辺りに馬乗り状態でそこにいた。 「…っ!おま…っ!」 状況を理解した俺は流石に慌てた。 「何してんだ!お前!早く降りろ!」 「ん?なんかこういう状況ってなかないから敢えて乗ってみた」 「『乗ってみた』じゃねぇだろ!!早く降りろ!はしたねぇ真似するんじゃねぇ!」 「は?別にはしたなくないだろ?子供の頃、お馬さんごっことかして遊んだじゃんか」 ぎゅっ、と留の身体が俺の腰辺りを動くたびに、その柔らかい感触が俺の下半身に伝わり、焦る。 「…っ、ガキの頃とは違うんだよ!」 意識も身体の作りも理性の重要さも何もかもがあの頃とは違う。 その証拠に、下半身の中心に熱が集まりつつあって困っている。 「これ、そんなにいけないことか?」 「いけないことだ!今すぐ退けろ!」 でないと残り少ない理性がどうにかなりそうで非常にまずい。 「わかったよ、しょうがないから退けてやる」 なんで上からなんだよ。と若干思ったが、それどころではないこっちは敢えて黙っていた。 「降りてやるから、その代わり…」 「…っ、なんだ!」 兎に角、この状態から解放されたい俺は言葉の先を煽る。 「…っ、口づけ…して欲しい…」 蚊の鳴くような声で呟かれた、その言葉に自分の耳を疑った。 「…は?」 理性がギリギリのところまで追い込まれたせいか、ついに頭がおかしくなったのだろうか? 聞き返す前に、留は俺の身体から退け、顔の近くに屈む。 それに合わせる様に上半身を起こし、留の顔を見ると、金魚の様に真っ赤になっていた。 「お前…」 「なっ、なんだよ!これもはしたないって言うのかよ!」 「いや…」 どちらかと言えば、先程の馬乗り状態の方が遥かにまずいだろう。 なのに、口づけをねだるだけで、この様に恥じらうのは如何なものなのか。 「…っ、恥ずかしいんだけど…俺、どうしたらいいんだ…?」 褐色の袖をくいっと引っ張られ、上目遣いで此方を見られるとまた理性がぐらぐらと揺れ始める。 「…文次郎…嫌…か?」 好きな女に此処まで言われて嫌だと言う男が居る訳がない。 「…ちょっといいか」 「わ…っ…!」 肩を引き寄せ、その場に直ぐ様押し倒した。 その時ばかりは、互いの着物が汚れるのも最早関係なかった。 「留…目、閉じろ」 「え…っ…んっ…」 言い終わるや否や、直ぐに唇を塞ぐ。 留が目を閉じているかどうかも確認せず、己の欲に任せ、思う存分柔らかい唇の感触を堪能した。 「ふ…ぁ…っ」 唇から離れた瞬間、甘い吐息が留の唇から洩れた。 「…どうだった?」 そんな事を聞くなんてどうかしてると思う。だが、返ってきた言葉は更に俺の欲を煽るものだった。 「…よくわかんなかったから…もう一回…して…」 途切れ途切れに紡がれる言葉がもどかしい。 再び欲望のままに口づけて、唇の柔らかさを味わう。 このまま己の欲に従い、舌を入れて口内を激しく犯してやりたい衝動に駆られたが、それを何とかぐっと堪えた。 今はまだその時では無い。 焦らなくても後々その先は出来るのだから。 「あ…」 唇をゆっくりと離すと、留はうっとりとした表情を浮かべていた。 (今はまだ、これで十分なんだ) 欲に溺れて突っ走って留を傷つけるのだけは絶対にしてはならないと、そう自分に言い聞かせる。 俺は、留の上に覆い被さっていた身体を退け、隣へと横たわった。 「…制服汚れるぞ」 「…いいんだよ、汚れたってそんなに目立たねぇから。お前こそ、早く起きねぇと着物汚れるぞ」 「…お前が起きたら、一緒に起きる」 「髪、ぐちゃぐちゃになるぞ」 隣へと手を伸ばし、癖はあるが柔らかいその髪を一房だけ掴み、口づけた。 「…何してるんだよ」 「口づけ」 照れて例のごとく、顔を赤くして怒るかと思い、ちらりとその表情を窺う。 すると予想に反し、留の顔はただ不貞腐れている様だった。 「…何で不満そうなんだ、お前」 「だって…」 腕を掴み、身体を摺り寄せてくる。 「どうせなら唇の方がいい…」 珍しく素直な態度に思わず面食らう。 どうやら口づけがお気に召したらしい。 「…してくれないのか?」 「…して欲しいのか?」 「…ん」 小さく頷く、その頬を両手で包みこみ、唇を重ねた。 繰り返される口づけが互いに癖になっていく様に酔いしれる。 ぽすっ、と頭が胸に埋められ、それを腕で抱きかかえた。 夫婦としての道は、まだまだ前途多難な感じもするが、第一歩としてのスタートはまずまずではないだろうか。 (段々とそれらしくなっていけばいいさ) 約束された未来なのだから気長にいけばいい。 寄り添った留の身体の熱が、俺の身体に伝わっていくのが何だか心地よかった。 END ・管理人コメント はわわ…!留三郎が可愛過ぎる…! キスを恥ずかしがりながら強請る留が可愛過ぎてどうすればよいか…! 文次郎も押されながらもなんだかんだ男前で素敵! だってちゃんと我慢するところはしてるしね(笑) しかも管理人が大好きな大正パロ&女体化。 私が文留にハマったきっかけが明治大正パロ小説なので、思い入れがあるから余計に萌えました。 舞坂様、素敵な相互記念小説をありがとうございました! |