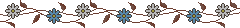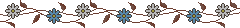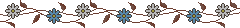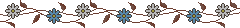
1
「イルーゾォ、ねえ」
寝苦しい感覚。
ふと目が覚めると、ミェーレが手を握り、俺を覗きこんでいた。
「どうしたの?」
いつの間にソファで寝ていたのか、今何時なのかというのはどうでもいい。
今一番の問題は、どうして彼女がそんな心配そうな顔をして、
俺を見ているのだろうかということだ。
上体を起こして彼女と向き合う、目を覚ましたこともあってか先ほどよりかは表情は和らいでいる。
「イルーゾォ、うなされてたから……大丈夫?」
うなされていた、そんなことを言われても特に嫌な夢を見ていた記憶はなく、
寧ろ夢を見ていたことすら記憶にない。
ふと窓のほうに目をやる。西日の差しこみ方から夕方近くか。
本当にいつの間に寝ていたんだろう。
「大丈夫、何の夢見てたかも覚えていないから。」
本当に?と聞き返され、
それに本当だと答えるとミェーレはよかったと微笑む。
どうにも、彼女は俺のことになると少々心配性なところがある。
とは言っても、ミェーレのことになると俺もそうなるところ、お互いさまと言えるんだろう。
「イルーゾォはいつもシエスタの時にうなされてたりするから、なんか心配で」
確かに、そうかもしれない。
寝苦しい感覚がして目を覚ました時はいつも彼女が起こしてくれていた。
それは、いつも、毎回。
こうやって、手を握って。
「…そうやって昔からお前がいつも起こしてくれるから、大丈夫」
「、ありがとう!」
そう言って彼女は笑顔で手を握り続ける。
あまり触れられるのは、ましてやこんな風にされるのは嫌いでも、彼女だけは別だった。
手を握るなんて、触れ合うなんて、そんな当たり前のはずで素朴な感覚は、子供時代から。
血の鉄臭さも、甲高い断末魔も、網膜に焼きつく××も、すべて忘れられる瞬間。
そんな手でも、握ってくれる。
この瞬間を、この子を守るために、この選択をしたことは
――間違ってなんかいない
誤認だろうと、自己暗示だろうとそんなことは問題ない。
彼女がそこで、笑っている。その事実があるだけでそれは正解なんだから。
← →