※教育実習生荒北
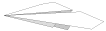
妙に薬品臭い空気も、黄ばんだ天井も利用者名簿も、何もかもがあまり好きじゃなかった。だけどあの息苦しい教室はもっと嫌いで、逃げるようにいつもこの白い保健室へとやって来た。中学校の保健室の先生はお母さんより少し年上のおばさんで、いつもどぎつい色の口紅を塗っていた。お腹が痛いと言ってもなかなか早退はおろか、ベッドに寝させてくれさえしない人で、私は嫌いだった。だから高校の保健室の先生がひどく優しいことに私はとても驚いた。少し具合が悪いと言えば、寝させてくれたし、担任に連絡して帰してくれた。この空間自体はやっぱりどうしたって好きになれなかったけれど、この先生はいつも優しかったし、私の顔を見るなり「どうぞ」と迎えてくれた。友達は少ないけどちゃんといたし、べたべたした付き合いではなかったので、特に問題なく学校生活は送れていた。それでもやっぱり嫌になる時はあって、とりわけ私は集団生活、ジョシコーセーという生き物が苦手だった。自分自身もそうなんだけど、それがとびきり嫌だった。
今日も真っ白なシーツの上に寝転び、ひんやりとした布団を被る。髪に型がつかないように気をつけながら頭を枕に落とし、しゃっとカーテンを先生が閉めてくれる音に耳を傾ける。実を言うとこの音だって好きではなかった。隣に誰かカーテンを隔てて寝ている時はそれはもう嫌だった。私だけこの閉鎖的で、だけど教室から解き放たれた場所にいる、ということが好きだったから。寝息なんて立てられたらたまったものじゃない。だから私はいつも携帯電話とイヤホンを必ず持って、布団の中でごそごそとそれを触った。
お気に入りの窓側のベッド。薄い白のレースカーテン越しに、グラウンドや職員駐車場が見える。嫌いな体育教師が通れば中指を突き立てたりした。見えてないでしょ、ばーかばーか。準備運動何回やり直しさせるんだようっぜー。ばーかばーか。一人でやってろ。…なんて、そんなことを思う私が馬鹿だ。だけどそれはそれで楽しかった。
今日も少し上体を起こして窓の外を見る。職員駐車場に誰かがいる。確か物理の先生。私は文系だし、物理のぶの字も分からないけれど、先生のことはなんとなく知っていた。その隣にいる人は、知らない。背はまあまあで、細身。顔はよく見えないけれど、白いシャツを腕まくりして、さらさらの黒い髪。誰だろう。うちの先生じゃない。あ、そうか。あれだ、教育実習生。私のクラスにも、無駄に大きな声で、明るい人が来ていた気がする。他のクラスのことはよく分からないけれど多分そう。その人も、首から何やら名札みたいなものを下げていた。大学生、かあ。私も来年は受験。とりあえず大学に進もうとは思ってるけれど、宙ぶらりんな2年生の今はよく分からない。なんだか眠たくなって、ぼーっと外を眺めていたら、黒髪の彼が私の方を見ている様な気がした。…そんなはずはない、レースカーテンが遮ってくれているはず。どきり、妙に真っ直ぐ、こちらを見つめているようなその視線には熱がない。ゆらゆらゆら、カーテン越しでよく見えないからかもしれない。あっちからは、ただのカーテンのかかった窓。そのはず。何かを物理の先生と話しているけれど、聞こえるはずはない。少しキツめの目元は私のクラスに来ている実習生とは、全く違う雰囲気だった。愛想なんかなくって、冷ややか。先生っぽくないな、そんなことを思って私は枕に頭を落とした。次に窓の外を見たらもう誰もいなかった。
「みょうじさん大丈夫?今日は帰る?」
「…帰ります、今日も」
「ほどほどにね。先生には連絡しておくわ」
保健室の先生はいつも優しい。私が保健室に来た日はいつだって早退するのに、「今日は」帰る?と聞く。優しいけれど放任だなって、そんな風にも思った。授業が終わって生徒達がざわざわする前に帰ろうと、鞄を肩にかけ保健室を出た。薬品臭がしなくて、少しほこりっぽい廊下の空気も清々しく思えた。蝉の鳴き声がうるさい。外は暑そうだ。
窮屈な上履きを脱ぎお気に入りの茶色いローファーを履くとスキップ。お腹が痛いのなんて嘘。そんなの先生も分かっている。私が保健室に来る理由を聞かない。いつも優しくしてくれて、ぬるま湯に浸かっている気分になる。だけど先生は私が溺れても助けてはくれなさそう。知らないけど。
「…あ、」
軽い足取りでよそ見をしていたら、目の前にいた人物に気がつかなかった。校門はすぐそこ、だけどここは職員駐車場。
「…ごめんなさ、」
あ。あ、あ、あの人だ。さっきレースカーテン越しに見ていたあの人。黒髪の、実習生。さっき見たときはそうでもなかったけれど、いざ目前にしてみると意外と背が高い。用なんてないのに見上げて顔をまじまじと見つめてしまう。
「…何ィ?早退?遅刻?」
ぶつかられたことに対しては特に触れられなかった。それよりも私は彼の口から出た声が、想像していたよりもずっと荒っぽいことに驚いた。語尾を若干伸ばすような口調は、仮にも先生を目指している人に相応しいとは言い難い。
「…早退です」
「フーン。…の割にゃ楽しそうだったけどォ?ま、関係ねェけど」
「きょ、教育実習生ですか?」
「ア?ああ、ったりーけどヨ。物理ネ」
なるほど、だからさっきあの先生と話してたのか。それにしても彼の態度はあまりに大きくてこっちが遠慮してしまう。普通実習生ってもっと学生に対して優しく優しく接するものじゃないの?
「私物理してないです」
「あっそォ。残念。気ィつけて帰れヨ」
ぽん、と頭に手を置かれて肩がびくっと震えてしまった。そんなこと気にも留めず彼は「じゃーな」と手をひらひら振りながら校舎の方へと消えていった。撫でるでもなく、ただ頭に手を乗せられただけ。まさかそんなことをされるとは思ってもいなくて、しばらく彼の背中を見つめていた。…今時の大学生って、ああなの?暑くてシャツの中ではじんわりと汗をかいている。頭に乗せられた手はあの冷たいと感じた視線とは裏腹に、とても熱かった。
∴
次の日も私は彼を見た。あのカーテン越しではなく、廊下で、たくさんの女子生徒に囲まれているところ。よくよく見れば彼は整った顔をしていた。にこにこと笑う笑顔は人懐っこそうにさえ見えた。あれ、そんな顔してたっけ。
彼は「アラキタ先生」と呼ばれていた。周りにいたのは女子ばかりかと思いきや、男子にも人気があるらしい。理系の友達曰く授業は分かりやすいし、今時の大学生みたいにチャラチャラしてなくって、とにかくいつも周りには人がいるんだって。ふーん。自分のクラスに来ている茶色い髪を無理矢理黒に染めました!みたいな彼も、明るくて悪い人ではなかったけれど、興味はこれっぽちもなかった。それよりも私はよく知りもしないアラキタ先生、のことばかりが気になった。物理をとっていないから、関わることなんてない。きゃあきゃあと騒ぎ立てる女子の中に入っていくこともできやしない。「気になる」と思ったものの、それが思い以上になることはないまま時間が過ぎた。
部活にも入っていない私は、暇つぶしに放課後も保健室に来ることがあった。先生はこの時も優しくて、自分のお菓子をわけてくれたり、紅茶を入れてくれたりした。本当にどうでもいい話をして、少しベッドでごろごろして帰る。先生は怒らなかった。いつもみたいにふんわりと笑っていた。
「すんません、絆創膏貰えます?」
ガラリと音を立てて入って来たその人の声を知っていた。窓側のベッドから、カーテンをこっそり開けて覗き見る。アラキタ先生だ。別に後ろめたいことなんてないけれど、隠れてしまう。話をしたいんじゃなかったの?
「あら」
「っとー…手、紙で切っちまって」
「消毒もしてあげるから、そこに座って」
「や、別に、大丈夫っス」
「いいから。あ、そうだ」
先生は誰にでも優しい。柔らかな笑顔に柔らかな話し方。左手に光る指輪を贈ってくれた、男の人の顔が見てみたい。アラキタ先生も、優しい先生のことを好きになってしまうんじゃないか。じいっと、そんな二人のことを私は陰から覗く。
「みょうじさん、よかったら紅茶、入れてあげてくれる?起きてるかしら」
先生がすっと目を細めて私、一番端、窓側のベッドの方を見た。その表情はなんだかいたずらっ子みたいで、いつもの先生とは少しだけ違う気がした。まるで私が二人の様子を覗いて、アラキタ先生が気になっていることを知っていたみたい。返事をしようかしまいか迷ったけれど、もしかしたら、という気持ちが勝り「はぁい」と、わざとだるそうな声で返事をした。
氷をたっぷり入れた紅茶のグラスはひどく汗をかいている。熱い紅茶が冷たい氷を溶かして、カランと音を立てた。アラキタ先生は一口それを飲んだ。感想は特に何も口にしなかった。私のこと、覚えてるかな。グラスを置いたとき、一瞬だけ私の方を見て会釈をしたけれど、ただ義務的にした、みたいなものだった。アラキタ先生の血の滲んだ指先を、丁寧に消毒して絆創膏を巻いてあげる先生の横顔は綺麗だった。アラキタ先生の指も白くて、綺麗だった。じんわり滲む赤い色が現実離れしていた。髪の毛はさらさら。私はここにいるのにまるで二人は私がいないかのような空気をつくっている。私の方がきっとアラキタ先生と年は近いし、保健室の先生とも私の方が仲がいい。それなのに。
「あざァす」
「はい、お大事にね」
結局私はアラキタ先生と言葉を交わさなかった。先生とアラキタ先生は何かを話していたけれど、あまり耳には入らなかった。アラキタ先生のいなくなった保健室は少しだけ煙草の香りがした。うわ、大学生なのに吸うんだ。変なの。ぼうっとした私をよそに先生はお代わりの紅茶を入れている。「いる?」と聞かれたけれど、「帰ります」と答えた。さっき飲んでいたグラスに入っていた氷を頬張って、保健室を出た。
∴
「紅茶サンキュ」
毒々しいおしろい花の花壇で会ったのも、アラキタ先生だった。後ろから声をかけられたけれど、すぐには振り向かなかった。私に向けられた言葉かどうかいまいち分からなかったから。それでも「聞いてるゥ?」なんて間延びした声が飛んでくるものだから、ゆっくり何てこともないふりをして先生の顔を見た。太陽が私たちを照りつける。先生のさらさらの黒髪は、光に当たっても綺麗な黒だった。傷んで茶色に見える私のそれとは大違いで少し羨ましいなんて思った。
「いえ、」
「三年?」
「二年です。一組」
「アー、文系?物理してないって言ってたっけ」
あちィと言いながら、ネクタイを緩めるアラキタ先生。綺麗な髪の毛から汗が滴っている。私もじっとりと汗をかいている。夕方だというのにまだまだ暑くて、蝉たちもうるさい。夏は好きだけど、暑いのはやっぱり毎年こたえる。勝手に気になっていた先生が今隣にいるというのに気の利いた言葉が一つも出てこない。先生の周りにいた女子たちみたいにきゃあきゃあ言えないし、保健室の先生みたいに柔らかな言葉も出ない。ミンミンうるさい。汗は噴き出てくるばかり。こめかみを流れる感覚が気持ち悪い。
「体調は、問題ねェの?」
「あ、いえ、ええっと」
「ハァ?聞こえねェ」
もぞもぞと話す私にイラついたのか、先生の声が急にボリュームアップ。男の人なんだけれど、どこか甲高い様なその声音に耳の奥がきん、とした。ような気がする。アラキタ先生って、人気、なの?これで?廊下で見たあの笑顔は偽物で、明らかにこちらが本性。どうして隠しているのか、そしてどうして私なんかの前で素を出しているのか。関わりがないから、だと思うけれどそれにしたって。
「…仮病ですもん、だいたい」
「……」
先生の問いかけに対しての答えは正直なものだった。隠す必要もないし、どうせすぐいなくなる人だから。
「ま、そんな日もあるだろ」
返ってきた答えは意外と優しいものだった。「駄目だろ」「嫌なことでもあるのか」「相談してみろ」。そんなことを言われたらうんざりするところだった。
「ありますよ。女子高生ですもん」
「ハッ。何だソレ」
目を細めて、下を向いて笑う先生の黒髪が揺れた。それはやっぱりさらさらしていた。私もなんだかつられて笑ってしまった。ゆるい、生暖かい風が吹いて煙草の香りがした。好きな香りじゃない。煙草を吸うなんてかっこいいことじゃない。そんなこと分かっているけれど、高校生の私には未知のものだからそれが「大人」を感じるもので、胸を高鳴らせたのも本当。私たちの前にあるおしろい花は、暑そうに首をもたげ、しなびている。その種の中に入っている白い粉で、小さい頃はよく遊んだ。今はそれをしようとは思わない。お母さんの「おしろい」みたいで、頬に塗ったけれど、かゆくなって、嫌いになった。花の色もそれ以来好きだと思えなかった。アラキタ先生は、どんな花が好きなのかな。
∴
教育実習生が実習を終えて帰るというので、私たちは色紙にメッセージを書いた。明るい私たちのクラスの彼は目を潤ませて、「立派な先生になります」と言っていた。私の書いたのは何だったっけ。確か頑張って下さいとかそんなもの。帰りのHRを終えみんなが彼のところに集まるなか、私はそそくさと教室を出た。向かったのは理系のクラス。わざわざ足を運んだくせに、そこへと入る勇気はない。アラキタ先生はやっぱりたくさんの生徒に囲まれて、花束やら何やらを持っていた。一緒に写真を撮っている子や泣いている子もいる。きゅうっとこんなに強く唇を噛んだのは初めてだった。
「アラキ、…」
名前は最後まで呼べなかった。尻すぼみになった私の声はきっと誰にも聞こえていないし、みんなの声にかき消されて私自身聞こえなかった。先生の髪は今日もさらさらで、とても綺麗。私がこのクラスにいたら、先生のその持っている色紙に何と書いただろう。自分の持っている気持ちが何なのか名前をつけられなくて、先生のことを見ていられなくて、私は今日もまたあの薬品臭い部屋へと行く。そして紅茶を飲んで、冷たいシーツに体を預けるのだ。帰りには、あの毒々しい花の前を通ろう。そうしてあの時のことを少しだけ思い出そう。ゆっくりと背中を向けて、保健室へと歩き出した。
20150710