またもキッチンから黄色い声があがる
「じゃあ私、急いで行って来る!着替えてくる。」
ルナは部屋に戻りすぐに出てきた
「ねえレン!こっちとこっち、どっちがいいと思う?」
娘が息子に服のコーディネートの選択を迫っている
「僕は、こっちのスカートに…これを合わせて…こうすると良いと思う。
…それよりそんな格好で出てくるなよ!」
「へへへっ。いいじゃない。よし、これで行こう!」
「行こうって、先輩の所?」
「うん!あっ、はい。これはレンの分」
ルナがレンに小包を渡す 微笑ましい光景だ
「あと、これはパパの分」
もちろん僕の分もある
「ありがとう。あとルナ、その先輩をいつか家につれてきなさい」
「…パパ…うん!ありがとう」
娘がパタパタと走り去っていく。
そのうちルナも結婚をしてこんな風に家を出て行くんだろうか…
ルナが幸せならそれも悪くない。
ライトさんに似ているルナのウエディングドレス姿は 可愛いんだろうな…
「父さん、何ニヤ二ヤしてるの?」
レンが僕の顔を気味悪そうに覗きこむ。
「ちょっといろいろね。」
「気持ち悪いなぁ…僕もちょっと出てくる。すぐ戻る」
ぶっきらぼうに行ってコートを羽織家を出て行く息子も見送る
2人とも立派に成長して、僕は嬉しい。
Side:Len
父さんの昔話はとても面白い。
小さい頃は、ただの夢物語だろうと思っていたけれど。
父さんが思い出を話すときの顔は真剣で、本当に一つ一つ大事に思い出しているようで、
いつからかその話を信じるようになった。
普通なら、小さい頃信じてた話が今となっては夢物語なのだろうけど、僕の場合は逆。
僕が今頑張って勉強しているのも、
父さんたちのいたパルスの事がもっと知りたいからでもある。
「…僕もちょっと出てくる。すぐ戻る」
またうるさいのに呼ばれたからね。
さっき姉さんが出て行ったばかりのドアを開ける。
数年前に建てたばかりのここらへんではめずらしい綺麗で大きな家。
こんな家に住めるのも、現役バリバリで活躍している女軍人の母さんと
なにより、軍で新薬研究をして多大な成果をあげている、有名な父さんのおかげだと思う。
僕はこの家が気に入っている。
今は勉強をして、将来僕はこの家を継ごうと思っている。
コミュニケーターで呼び出された場所に行く途中姉さんとその先輩がいた。
2人とも幸せそうな顔をしている。
そして、2人を通り過ぎすこし歩くと、公園につき、休日に僕を呼び出した張本人。
見慣れた幼なじみのココアがいた。
ココアの両親は、父さんや母さん達の友達のヴァニラさんとマーキーさん。
「レン!」
「どうした?」
「どうしたって…今日はバレンタインでしょ?
だからあんたにもおすそ分けしようと思って…
べ…別にあんたのために作ったんじゃないのよ?あ…余ったから」
「……へぇ。そう」
余ったから、ね。
「何よ!昨日かわいい女の子からいっぱいチョコもらってたじゃない。
それを食べ飽きたから私のは嫌だっていうの?いいもん!」
「そんなこと言ってないでしょ。大体あれは受け取ったんじゃなくて、ロッカーとか机とかに勝手に入ってったんだよ。」
「それをもらったっていうのよ!」
「…そうだとしても、僕が自分で受け取るのは…
毎年ばんそうこう手にいっぱい貼り付けて渡しにくるバカのだけだから。」
「なっ…バカ!?仕方ないじゃない!でも、
今年はレブロさんと一緒に作ったから絶対美味しいはず!そりゃ…見た目は悪いけど…。
どっかのバカにあげるにはこれ位がちょうど良…」
「ありがとう。ココア。」
ココアがうるうると涙を浮かべている。
涙もろいのも母親譲り。うるさいのは父親にらしい。
「…ふぇぇ…レ〜ン〜」
昔っから
バカなくせに優しくて
おせっかいで
素直なくせに素直じゃない。
小さい頃からいっしょにいた。
きっとこれからも。
泣き虫なこいつの事が僕は…好きなんだと思う。
「ルナもレンも青春ですね。」
昔と変わらぬ美しさを維持したままの愛妻に声をかける。
ライトニングはソファーに座ってコーヒーを飲みながら僕の分のコーヒーも勧めてくれた
「だな。お前もあんな感じだったぞ、昔は」
と、
いたずらっぽく笑い、僕の前に綺麗な包みを差し出した
「ハッピーバレンタイン、ホープ。」
「ありがとうございます。」
「中身はルナと同じなんだがな…味は…そこそこだと思うぞ。
なんたって、お前に似て器用なレンにレシピを教わったからな」
ノートの切れ端に細かくアドバイスの書かれたレシピをライトニングは見せてくれる。
小麦粉
グラニュー糖
ベーキングパウダー…
字はレンのものだ
包みを開けてみるとカップケーキが入っていた。
それを一口食べてみる
「………ライトさん…これ…砂糖と塩を間違えてませんか…?」
「何っ!?」
ライトニングはキッチンに走り先ほど使った材料を確認する
「これは…塩だ…大変だ、ルナもこれをもって…止めなくては!」
「待ってください!これ、少ししょっぱくて美味しいんですよ」
慌てるライトニングを落ち着かせ、一口食べるように促す。
色っぽい唇を開き食べかけのケーキを一口口に含むと驚いたように目を見開いた
おいしい、とつぶやき僕の座るソファーの隣に腰を下ろした
「…なるほどな…」
レシピのアドバイスに小さな字で書き込まれている字を僕にしめす
そこにはレンの字で、漫画みたいに砂糖と塩間違えても美味しくできるから安心しろ。
と
ここまで頭が回るのにはもはや笑うしかない
感心したようにレシピを眺めるライトニングの唇にクリームがついてるのを見つけ僕は
キスをするようにクリームをなめる
「クリームついてました。これが一番美味しいです」
そう言うとライトニングは少し頬を赤らめた
「…なぁホープ…もう1回ちゃんとして?」
めずらしく自分からキスをねだる妻に優しいキスをする。
次第に角度を変えて繰り返されるそれに息はあがり、だんだんと深くなっていく。
知り尽くしたお互いの味を再確認するかのように唇を重ねあう。
唇を移動に首筋にそって下から舐めあげると んっ という色っぽい声が小さくこぼれた。
「かわいいです。ライトさん」
普通はこの年齢になってかわいいなんて形容詞は当てはまらないのだろうが、
目の前のライトニングはその言葉がぴったりだ。
普段は母の顔をしているが、子供がいなくなるとすぐに女の顔に戻る。
母であるライトニングも、女であるライトニングも
なによりそのギャップがたまらなく好きだ。
「続き、しても良いですか?」
「…子供達が帰ってくるぞ?」
ライトニングは玄関のドアを気にかけるように見る
確かにこの現場は子供達には見せられない。
「…そうですね。」
「…お楽しみは夜までお預けだ、ホープ。」
身を寄せてくる妻を僕は優しく抱しめる。
幸せだ。
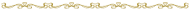
←戻る
8/11