五:朝明け、生生流転するは意思
「!!」
祖先の身体を貫いた感覚が確かにした。
その感覚が伝わると同時に、目の前が紫色に染まる。その紫はただの紫ではなく……幼いころの記憶と共に置いて来てしまった、桔梗の色だった。
「そう怯えた顔をするでない、子孫よ。我はすでに死した存在、其方が殺したわけではない」
その色を認識したと同時に聞こえたのは、祖先の声だった。
私は確かに祖先を刺したはずなのに、目の前にその姿がない。
声は聞こえたけど、位置を特定できるようなものではなかった。まるで、脳内に直接語り掛けるような……そんな感じだった
一体どこにいるの?
「ここだ」
次に聞こえた声は、位置を特定できた。
自分の背後を振り返れば、そこには平然とした様子で祖先が立っていた。
「強引であったことは認めよう。だが、それでも確かめたかった。我が継承した技が今、どのような者に継がれているのか。その実力がどんなものか見たかったのだ……すまぬ」
どこか悲しそうな表情にも見える祖先の顔を見たら、許してしまいたい気持ちになる。そもそも嫌々やっていたわけじゃない……自分で選んだんだ。
「祖先が謝る必要はありません。私……いいえ、桔梗院の血を持つものならば、祖先とこうして言葉を交わすことは夢のようなことなのです」
自分で言うのも変だけれど、将軍様から祖先と似ている、先祖返りではないかと言われたときは……私は祖先に近い存在なんだって思い込んでた。傲慢になっていたのかもしれない。
「おかげで祖先の実力をこの身で感じることができました。……ですが、1つだけ物申したいことがあります」
「申してみよ」
私たち桔梗院の血の頂点に立ち、受け継がれてきた技の祖である御方だ。……普通なら勝てるわけがない。
だというのに、私は祖先の背後を取り、その身に刀を通すことができた。それは何故か。
「どうしてあの時……笑っていらしたのですか」
祖先の身体を刀が貫くまでの一瞬……確かに私と祖先は視線が合わさっていた。だというのに、あの方は躱して反撃するのではなく……私を見て、微笑んでいたのだ。
それに気づいた時には止めることなど出来ず、刀は祖先の身体を貫いていた。
「……最後の継承者が其方でよかった。そう思っていたのだ」
「!」
なぜ、最後だと分かるのだろうか。
いいや、初めから考えた方がいいのかもしれない……唐突に祖先が現れたのには理由があるはず。
考えろ、私。
祖先が現れる理由になりそうなもの……そうだ、あれかもしれない。
「祖先は何故私が最後の継承者だと思ったのですか」
「桔梗院の名は我が考えた。その名が消えたことをこの地に残った我の残滓が感知し、不完全とはいえ1つの形として形成されたことで、我は現世へ戻った。それが其方の前にいる我の正体だ」
私が桔梗院家を終わらせたから?
そうはっきりと言う事は、始まりである祖先には言えなかったけど……祖先が答えた内容は、私の予想と一致していた。
言霊って本当にあるんだって感じたよ。けど、残滓ってそんなもの……どこに?
祖先は桔梗の花そのものだ。でも、桔梗の花はもうどこにも……。これも、私が終わらせてしまったから……。
「植物は炎に弱い。それは当然のことだ」
そんなことを考えていた時、ふと祖先はこんな言葉をかけてきた。
その意味、意図が分からないまま、私は下げていた頭を上げ、祖先を見る。
「だが、植物の根幹は地面の中にある。それを其方は知っているか?」
「……根のことでしょうか」
「そうだ」
ますます祖先の意図が分からない。祖先の前で変な顔をさらしていないだろうか……。
「我が桔梗院家の終わりに気づいたのは、この地に残る桔梗の花の根が教えてくれたからだ」
「!」
気づいていたんだ、私が残滓というものに疑問を抱いていたことを。
それに……今、桔梗の花の根があるって言った?
「これでも我は稲妻に住まう精霊の中では上位の存在だったのだ。人が使う炎なぞに完全に燃やし尽くされるような花は作らぬ」
「え、あの桔梗は祖先の力で……!?」
「さすがに時が経てば、その事実は徐々に消えていくだろう。故に、知らなかったことを謝る必要はない。人の時間が短いことを我は良く知っている。代を重ねる度に語り継がれていく事実が減っていくことも承知している」
そんな大切なものを私は守れなかったのか……。
何においても自分が情けない。
そう思っていた時、頭に何かが乗る優しい感覚がした。顔を上げれば、私の頭へ伸びる祖先の腕が見えた。
「命はいずれ尽きる。我がこの世から去ったことと同じようにな」
「祖先……」
「我が死しても桔梗を守り続けてくれていた。その事実があるだけで、我は良い」
だから、其方が悔やむ必要はない。
……そう言ってくれた祖先が、母様に見えたのは気のせいだろうか。
「さて、目的は果たした。この世に存在しておらぬ者がこれ以上現世にいては害をもたらす」
その言葉と同時に、頭からぬくもりが消える。
寂しさを覚えた私は、無意識に顔を上げて祖先を見た。だが、祖先と目は合わなかった。
祖先が見ている先が気になった私は、その視線を追うように首を動かす。そこにはいるはずのない人がいて。
「楓真、どうして……!?」
言葉にするならば、この空間の外にいる、という感じだろうか。
先ほど祖先が使った、私の技で言う”水幻・桔梗園”のような空間にいるのならば、楓真はこの空間の外でこちらを見ている、という感じなのだろう。
向こうにはこちらの様子は分からないようで、不安そうな顔の楓真がそこにいる。その顔を見ていると、今すぐにでも抱きしめて安心させなければという気持ちになる。
私は楓真ともう一人……万葉に黙ってここに来たから、尚更不安にさせているはず。どうしても自分のこの気持ちと決着を着けたくて……いつも自分勝手な母親でごめんね、楓真。
「楓真……それが、あの幼子の名か。薄くはあるが、我の血を感じる」
そう言った祖先は、いまだ座り込んでいる私を見下ろす。……気づいているんだろうな、あの子が私の子供であることを。
「不覚を取ったのは事実。そして、立て直そうと思えば、あの時其方の攻撃を躱すこともできた。それができなかったのは、あの幼子が我が子に見えたからだ」
私という存在がいるのなら、当然祖先に子供がいたということ。
……楓真を、自分の子供と重ねたのかな。
「我があの時言ったことは本気だった。どちらかが死ぬまで、この勝負を終わらせる気はなかった。だが、あの幼子を見た瞬間……見送る立場になるはずだった我が子を思い出してしまったのだ」
そよ風が吹く。
それに祖先の美しい髪が揺れる。その表情がどこか悲しそうで。
……確か、祖先は戦争で命を落とした、という話だったはず。だけど、子供を置いて行ってしまったというのは初めて聞いた。もしかして、ずっと悔やんでいたのだろうか。
「後出しばかりですまぬが、其方の実力を見たかった理由として……其方が愛する者を守れるほどの力があるのか。それも知りたかったのだ」
だが、其方の表情を見れば、それは杞憂のようだな。
……桔梗院家の技は守るためという意思が強くあるのだと言われてきた。だから、祖先の問いは唐突ではあったけれど疑問には思わなかった。
「では、祖先から見て私は……祖先の期待に応えられていましたか」
祖先を見てはっきりと告げる。祖先は目だけでこちらを見ていたが、やがて身体ごとこちらへ向いた。
……しばらくの沈黙の後。祖先は口を開いた。
「___期待以上だ。子孫よ」
祖先の声が聞こえた瞬間だ。
そよ風だった威力が増し、この空間に入る直前の花吹雪を彷彿させる。
……もう、行ってしまわれるの?
そう口を出したいのに声が出ない。せめて、会えて嬉しかったことだけでも……!
「其方の言葉は口に出しておらずとも聞こえておる。……そろそろ刻限だ。最後に、」
”影によろしく頼む”
その声が聞こえた瞬間、轟音が消え、無音になった。
影とは誰の事ですか?
そう問おうとしたが、それを尋ねることはできなかった。それよりも目の前のことが気になってしまったから。
「……!」
無音の中、開いた目に映った視界には祖先の後ろ姿が見えた。しかし、彼女だけではなかった。
祖先の目線の先には、楓真に近い身長の男の子と、祖先より少し身長が高い男性が立っていた。初めて見た人なのになぜだろう……男の子に祖先の面影を感じたからなのか、小さな子供は祖先の子供で、男性は祖先の想い人であり、私で言う万葉のような存在だろう。
「……やっと会えたんですね」
あの笑顔を見ていると、祖先が先に死んだことを悔やんでいたことが報われたように感じた。子孫である私が言える立場ではないけれど。
「ありがとうございました。祖先、キョウ」
そう言った私の声は、祖先に届いただろうか。
……いや、届いたと思いたい。だって、その言葉を口にしたとき、光の中で祖先がこちらを振り返ったように見えたから。
***
「___、名前! 大丈夫か!?」
「母上!!」
その声に我に返る。
視界いっぱいにパイモンと楓真がいて、少し驚いてしまった。
「パイモン、楓真……あれ、ここは?」
「お前が連れてきてくれたんだろ? もう忘れたのかよ!」
「だが、一瞬にして花が咲きほこったのだ! 見てくれ、母上!」
そういうとパイモンと楓真は自身の背後を私に見せびらかすように視界から消えた。彼らが隠していた背後の風景。それは___
「___っ、!!!」
幼いころで止まっていた美しき思い出。炎と共に燃えて消えてしまった懐かしの風景___もう幻想の中でしか咲きほこることはないだろうと思っていた桔梗の花が、桔梗の花園がそこにあった。
「これは一体、」
「”付き合ってくれた礼”だそうだ」
「!」
無意識にこぼれた私の言葉を拾ったのは、愛おしい人の声。声の聞こえた方へと振り返れば、そこには手を差し伸べる万葉がそこにいた。
「名前によく似た声だったが、それでも拙者には別人に聞こえたでござるよ」
「……それはきっと、祖先の声だよ」
これが、異国で言うさぷらいず、というものなのかな。
……ありがとうございます、祖先。またこの光景を見られるとは思わなかったので、本当に嬉しいです。
「なるほど、であれば似ているのも納得であるな」
その手を取れば、勢いよく引っ張られる身体。
その勢いに身を任せて立ち上がったと思えば、空いている万葉の手が私の顔へ伸び、頬に彼の親指が触れた。そこで気づいた……私、泣いてたんだ。
そう思ったときには万葉の方へ引き寄せられ、閉じ込められていた。
「満足したか?」
「……うん」
「次勝手なことをすれば、拙者は名前を閉じ込めてしまうかもしれぬな」
「それだと万葉を、楓真を……みんなを守れないよ」
「拙者は弱くはない。お主を守れるほどの腕はあるし、ぬるい鍛え方もしておらぬ」
口調はいつも通りだけど……次同じこと、黙って出かけたりしたら本当にやりかねない。よく考えたら桔梗院家のことも含めたらこれで2回目か。いや、桔梗院家の件と今回の件、そして今のことを含めると……3回目だ!
「……気を付けるから、離してくれない?」
「いやでござる」
「いや!?」
たしか、仏の顔も三度までって言葉があったような……。意味的には言葉通りの三回ではなく、何度も繰り返すとっていうものだったけど、3ってどこか区切りのいい数字だし……って、話が逸れだしてる。
「うぅ、万葉重い……」
「その重さは拙者の愛でござる」
「ほ、蛍〜〜〜っ、笑ってないで助けてよ〜〜〜っ」
視界の奥で早く、早くとこちらを手招く楓真とパイモン。私と私に引っ付く万葉を見てくすくすと笑う蛍。
……今なら、心の底から笑えるかな。
この雰囲気の中、無意識に出た表情はきっと変な顔はしていただろうけど、固いものではなかったって思えるんだ。
桔梗の章 第一幕 完了
泡沫の夢、桔梗は幻想にて開花する
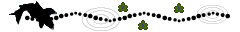
※現在、後日談を2話予定しています。
その後にあとがきを公開予定です。
2024年05月18日
前頁
戻る
×