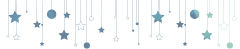4
食事を済ませなんとなく歩いていると
、一際イルミネーションが輝く公園の前を通りかかった。
「そういや今年も雑誌に取り上げられてたな…。ちょっと見てくか。」
そう言うと、陽平は秋弘の返事も待たずに公園へと入っていく。
ここで愛を誓うとそのカップルはずっと一緒にいられると言われているこの公園。
恋人達の聖地とも呼ばれこの場所には、毎年様々なイルミネーションが施され見るものを楽しませている。
「うっわすげぇ、めちゃくちゃ綺麗〜!…でも思ったよりカップル少ないんだな。」
「みんな励んでんじゃない、性夜だし。」
「ば、馬鹿!やらしく変換すんなっ。」
照れたように叩いてくる秋弘を軽く笑うと、じゃれるように後ろから覆いかぶさった。
「あーぁ、せっかくの休みだったのに何処にも行けなかったな〜。」
「う…だからごめんって!俺なんか待たずにどっか行けばよかっただろ。」
わざと責めるように言ってやればちょっと拗ねた口調で返ってきた。
そんな彼が愛しくて、背後から回している腕にそっと力を込める。
「……本当は先にお前ん家行ったから、終わる時間知ってたんだよな。でも試しにお前の様子見に行ったらそんな可愛い格好してるし、なんか心配で目が離せなかったんだよ。……ま、これから毎年一緒だし一回くらいいいけどな。」
「ーーっ!?」
(なんかそれって…)
ーープロポーズみたい。
そう思った瞬間、一気に頬に熱がたまるのを感じた。
「ん?なに赤くなってんだよ?」
夜でもイルミネーションの灯りで秋弘の耳が真っ赤になっていることに気付き、陽平は彼の顔を覗き込もうとする。
「べ、別に。何でもない!」
その視線から逃れるようにそっぽを向いてしまった秋弘のその手に、陽平の優しい体温が重なる。
「んじゃま、帰りますか。」
「……うん。」
その手に指を絡めながら思う。
ここが恋人の聖地なら、先ほどの陽平の言葉が現実になりますように。
来年も再来年もずーっとその先も、こうして彼の隣にいたい。
そう願いを込めて、秋弘は繋いだ指にそっと力を込めた。