21グラムの指輪
「……トロベリー」
二人の王国に、それの呼び名は存在しなかった。
たとえるなら少年にとってそれは、歌をうたうよりも喉が焦げ付くもので、踊りをおどるよりも足が着く場所を求めるもの、そして、うるさいほどに静かな恐ろしい夜を塗り潰すための、やさしく柔らかな、それでいてひどく熱い、夜のかたちをした慰めであった。
ただ一人の青年のための女王である少年は、その小さな頭に見えない冠を戴き、愛に盲いた愚か者にしか映せない純白を服の上から纏って、ただ相手の名前を呼ぶ。それだけですべては始まり、けれども何もかも正されないままに、善悪の輪郭が曖昧になるまで夜をかき混ぜ、朝陽がそれを蒸発させると共に音もなく終わってゆくのだ。
何が変わるというわけでもない、何が救われるというわけでも。それでも、少年はよく涙を流したものだった。悲しみのためではなく、虚しさのためでもなく。彼はまた、それの呼び名を知らなかった。或いは、忘れてしまっていた。ただ、夜の淵で一粒だけ光るものを、朝の陽に果てないものを、相手の口に含んでもらえるまで、少年は目尻にうっすらと浮かべていた。
「バニティ……?」
部屋の前で消え入りそうに呼んだ声に、しかし扉はすぐに開かれた。そうっと扉を開けながら、部屋の持ち主である青年は、扉の前で少年が自分の名前を呼んだことに少しばかり不思議そうな表情を浮かべている。普段ならば、少年はノックをすることもなく、否応なしに部屋の中に入ってくるものだったから、それも当然の反応であった。
「バニティ?」
長い夜の中、少年がいっとう目に映したいであろう青年が扉の向こうから姿を現したにもかかわらず、彼はその呼びかけにも応えないまま、ただ俯いていた。隙間風など入らない、彼らの完ぺきな城。この鮮烈な欲望と退廃的な色彩に塗れる国に、完全に溶け込む漆黒の屋敷。それでも底冷えした空気が長い廊下に低くたむろしている家で、少年は靴も履かずに裸足の姿を保ち、ひたすらに沈黙を守ってはその場から動かない。
「どうしたの、バニティ……?」
再三名を呼んでも、少年は依然応えない。そんな相手の、まるで立ったまま絶命しているような様子に、青年は焦燥の色を目に浮かべて瞬きをした。今、少年が生きていることを教えてくれるのは、彼の控えめに上下する薄い胸ばかりである。青年は、胸の下で両手を組み合わせている少年の頬に触れようと、その手を伸ばした。
「──わ、」
けれど、青年の指先が相手の輪郭に触れる前に、少年の未だ小さなままの手が青年の片腕を掴み、それをぐい、と自分の方へと引き寄せる。そうして彼は一瞬だけ顔を上げると、瞬きほどの時間も与えずに、青年の背へと自身の両腕を回した。それから少年は相手の心臓の上へと額を埋め、自身の指先の一つひとつで確かめるように、青年の背を覆っているシャツを握り締める。その手が、肩が小刻みに震えていたのは、きっと寒さのためではなかった。
「……バニティ、怖い夢でも見た……?」
こちらの瞳をそっと覗き込むような問いかけに、少年は相手の胸に額を押し付けたまま、柔くかぶりを振った。
「何か……大事なこと、忘れちゃった……?」
少年は、また首を左右に振る。
そんな、さながら言葉の発し方を忘れてしまったという風な相手の頭を、ひどくやさしい手付きで撫でてから、青年は余った方の手のひらでその背中も擦ってやった。そうする彼の口元はいつも通りに弧を描いてはいたが、しかしその眉尻は苦しげに下がり、眉間には深く皺が刻まれている。青年の暗やみで光る水色の瞳がただ一心に眼下の少年を見つめ、その長いウサギの耳も同じく、どんな小さな声も聞き漏らさないよう、相手の方へと向いていた。少年は、未だ青年を抱き締めたまま、動かない。それでも、青年は見ていた。見たのだ。
一瞬上がった少年の顔が涙に濡れていたのを、青年の目は見たのだった。
「ね、バニティ。ここは寒いよう。部屋の中、入ろ……」
いつ頃からそこに立っていたのだろう、雨にでも降られたように冷たくなっている少年の背を、青年は少しでも暖めようとゆっくり撫でながら、相手へと向かってそのように声をかける。返事の代わりに密やかな、それでいて少し苦しげな呼吸音だけが聞こえてきていた。青年は、おそらく少年が言葉を発するために息を整えているのだということに気が付くと、彼らしい辛抱強さで、相手の答えを待った。変わらず、薄い背を撫でてやりながら。
「……ここで……」
ややあって、少年の唇が淡く音を立てて息を吸う。それと同時に、青年の周りから、少年の発する音以外がすべて溶け消えた。
「……ここで、いい」
「でも、……身体が冷たいよ、バニティ」
「いいんだ、もう……」
そうしてようやく少年の喉から発せられたその声は、何か、不思議な響きをもっていた。
今しがた確かに泣き顔を目に映したというのに、それは涙声ですらなかった。笑っていたのだ、微かに。そして、笑うだけではない。その中に何か──何か、救いがたいものが一つ、紛れている。青年は初めて聞く少年のそんな声に、けれどもどこか既視感を覚えて、更に眉をひそめた。それは、たとえるなら。たとえるならば、諦め。そう、諦めだった。もう笑みしか浮かべられない、ひどい諦念だ。常に諦めることだけはしなかった少年から発せられた、諦めの声だった。
「トロベリー」
「うん」
「トロベリー……」
「……うん」
次に発せられたのは、泣き疲れて掠れた小さな声。
少年は青年の背をまた一つ強く抱くと、ぱた、と一粒涙を床の上へと零した。額だけを相手の胸へと押し付け、そのシャツが自分の涙で濡れないように、痕を残さないようにと、少年は自分自身で笑えるほど長く目を閉じる。静かに、それでも嫌な音を立てて鳴り続ける心臓の音をどうにか遠ざけて、少年は青年の背からやっと両腕を離した。
それから彼は天井まで連なる暗やみの中、頬を濡らす涙の痕を隠し立てするすべを持たないままに、その顔を上げた。そうして凜と背筋を伸ばし、形の良い眉もまなじりも口元もすべて自信に充ち満ちた、ひどくバニティバラッドらしい表情で、彼は真っ直ぐに青年の瞳を見る。そんな、突如変貌してみせた相手の様子に、ちょっとだけ驚いて瞬きをした青年へ向かって、少年は微笑みかけた。何か薄くて柔らかいもので、相手のことを包むように。次いで、少年は息を吸った。舞台に上がったときと、同じやり方で。
「──元の家に帰って」
「え、」
「おれのこと、忘れて」
「な……」
「全部、なかったことにして」
柔らかい口調で、ほとんど諭すようにそう発された言葉に、青年はおよそ鈍器で頭を殴られるのと同じ衝撃を受けた。或いは、それよりも大きく、重かったかもしれない。彼はその青い瞳孔を見開いて、ただ呆然と目の前の少年を見つめながら、死の間際さながらに走馬灯が頭の隅から隅までを駆け抜けるさまを思った。自分の心臓が脈打っている自信が、とにかく今の彼にはなかった。
「な、なんで……」
「やっと気付いたんだ。おれはほんとうに化け物なんだってことに」
急激に渇いて張り付いた喉から、どうにかそう言葉を絞り出した青年に、しかし少年は少し買い物にでも出かけるといった調子で軽々と言葉を放つ。
「自分のためなら、舞台に立つためなら、おれはどんな汚いやり方もできるし、どんな犠牲も払える。アリスとアリスがぶつかるように仕向けて、生き残った方に付き、ころされた方の成れの果てを食べ、そのくり返し。自分では手を下さずに、美味しいところだけを喰らっている。なんで、今まで気が付かなかったんだろう? こんなの、勧善懲悪物語の脚本には必ず出てくる、ひどい悪役の──人間の形をした化け物のやり方となんら変わりないのに!」
そうして少年は青年の元から一歩下がると、片手は未だ握り締めたまま、余った方の手を自分の胸へと当て、笑う。かわいらしく首を傾げ、薄く開いた唇を悪戯っぽく上げて。
「おれはこの国でいちばんの悪人だよ、トロベリー。こんな方法でここから出られたとしても、きっと行き着く先は元の世界なんかじゃない。地獄さ」
そう笑みながら、少年は胸元に当てていた手をぎゅうと握り締めた。まるでそこに傷口があるかのような相手の様子に、けれどそれをじっと瞬きもせずに見据えていた青年の目が、先ほどよりも少しだけ和らぐ。そんな青年のまなざしに、濡れた睫毛を鬱陶しがっていた少年は気付くこともできないまま、その赤い瞳を細め、言葉を継ぐためにゆっくりと呼吸をした。
「でも、おまえは違う。こんなおれを見捨てられないおまえは、この国で──世界でいちばん優しいんだ。おまえなら、もっといいとこに行ける。きっと、元の世界に帰れるよ。だから……」
そして、少年がすべてを言いきらない内に、青年は相手の薄い背をかき抱いた。
「……ばか」
「え、」
「バニティのばか」
それだけ言うと、青年は相手を正面から抱き締めたままの体勢でくるりと方向転換をし、すたすたと部屋の中へと少年ごと入っていく。そうして彼はその片足に扉の端を引っ掛けると、それを軽く内側へと弾いては、がちゃりと廊下と部屋を容易く分断してしまった。
「ちょ……っと、おい、離せ、」
「やだ」
「な、なんで……」
「先に抱き締めてきたのはキミでしょ、バニティ」
腕の中でばたばたというよりはもぞもぞと暴れる少年を軽くいなして、青年は軽々と相手のことを運んでいく。それは、この国の冷ややかな暗やみの内側で、痛いほどの静けさを保つ二人の屋敷の中で、大きな窓の下、柔く月光が降りてくるベッドの上、少年が世界で最も安心できるであろう場所へと。
青年はそのベッドの前へと足早に辿り着くと、その端に腰を掛け、少年を自分の膝の上へと向かい合う形になるように座らせた。そんな相手に少年は戸惑いながら視線を彷徨わせ、部屋の隅に溜まる黒い暗やみを不安げに見つめる。自分とは目も合わせられないといった様子の少年に、青年は困ったように眉尻を下げ、それでもその頭を柔らかく撫でてやった。
「バニティは……俺のこと、もう要らない?」
それからどれほどの時間の後だろう、青年は扉をやさしくノックするように相手の瞳を覗き込んだ。暗がりばかりを目に映していた少年の視線がその問いかけに導かれ、青年の方へと戻ってくる。
「そ、れは……」
「どうしたの、バニティ。何があったの……?」
少年は外側から叩かれた扉の取っ手に指先を掛け、それでもそこを開けるほどの勇気をもてないままに、また俯いた。はらりと流れる彼の黒髪が、その顔に青ざめた影を落とし、赤い瞳は睫毛に埋もれる。窓から降りる淡い月光が少年の輪郭を保ち、ただ、それはどこか吹けば飛んでいってしまいそうな脆さばかりを物語っていた。
「バニティ……」
青年が再び少年の名を呼ぶ。彼にそう名を呼ばれるたびに、少年は自分の鼓動が未だ脈打っていることを思い出すのだ。だから少年はその肩を震わせ、はく、と唇から息にならない空気を吸い込む。その姿は、とても完全無欠の役者には映らない。それはひどい悪戯をしたためにお仕置きとして家から追い出された子ども、家出をし、けれども夜中に戻っては鍵の掛かった扉の前で立ち尽くす子ども、扉一枚が世界のすべてだと錯覚している子ども、その類にしか見えなかった。
自分の腰に両腕を回して固定している青年の、その片腕に少しだけ触れて、少年はまた自身の瞳から涙を零した。相手の腕の上で片手を握り締めて、今にも呼吸の仕方を忘れてしまいそうな肺でどうにか息を吸う。
「お、まえが……」
「俺? うん……」
少年の前髪に隠れた眉間へと、きつく皺が寄る。彼はわなないた唇の端を、血が滲むほどに強く噛み締め、そうしてもう一度青年の胸へと自分の額を押し当てた。
「──おまえが、死ぬ夢を見た」
音はなかった。ただ、声だけがあった。静かだった。この夜みたいに、うるさいほど静かな声だった。それは、ぬるい暗やみに、冷たい温度の絶望を知る色。少年の両目から溢れ続ける涙が、何物にも照らされることなく、白いシーツに灰色の染みを作っていた。
「おれのせいなんだ」
呟き。少年はふと、自分にその権利がないことを思い出したようにそっと相手の胸から額を離すと、指先までを苦悩に満ちさせては、自身の髪をぐしゃりと握り込む。
「おまえが、おれのせいで。おれのせいで。おれの、せいで……」
「夢……」
「嫌だ……」
そう嗚咽を洩らす少年には、最早かぶりを降る余裕すらなかった。
「嫌だ……!」
彼は丸めていた背を更に丸め、胸の下で両手を組んだ。祈りのかたちを取りながら身を震わせ、項垂れる少年の姿は断頭台に立つ囚人さながらであり、また、これから火炙りに遭う魔女のようでもあった。或いは、自分に触れたところから穢れが移り、罪が移ると思っているのかもしれない。
「──だいじょうぶだよ、バニティ。ちゃんと見て。俺、生きてるよう」
そんな少年を離さないまま、青年は壊れやすいものに触れるときのような声色で、ひどくやさしくそう語りかけた。その言葉に少年の心臓は柔らかく脈打ち、けれど、それを自覚すると共に彼の血液は逆流さながらに泡立つ。少年は白い歯の隙間から荒く息を吸うと、自身の両耳を塞ぎがちに爪を立て、覆い被さる呵責の念に割れそうな頭を抱えた。
「でも、おれといたら、きっとよくないことが起こるよ。分かるんだ。ずっと、分かってたんだ。それなのに、おれは……!」
「いいんだよ」
「よくない。嫌だ、おまえが傷付くのは、嫌なんだ……おまえは十分、もう十分だよ、これ以上傷付かなくていい……」
「いいんだ。いいの、バニティ。俺、痛くないよ」
「嘘、」
「嘘じゃないよう。俺、痛くないんだよ……」
囁くよう、確かめるよう、そう発された青年の言葉に、少年は言葉を返すこともできないまま、ただ俯いて首を左右に振る。そんな相手を青年はぎゅうと抱き締め、更に自分の方へと引き寄せると、歪な音が鳴り始めた少年の喉を宥めるために、その背中を自身の微笑みほどに優しく撫でてやった。
「バニティがいるから、なんだよう……」
その言葉と共に、少年の耳へと、押し付けられた青年の心音が入り込んでくる。疑いようもなく、救いようもなく、ただ、どうしようもなく、相手が生きている音。ばかでやさしいそれは、少年にとって、世界でいちばん安心する音だった。
「全部、俺が決めたことなんだよ、バニティ」
きっと、もはや青年にとっては、少年の輪郭を確かめることが、自分の輪郭を確かめることに等しかった。背を撫で、頭を撫で、髪を梳き、俯いた頬をなぞる。そんな青年の指先を感じて、瞬きをしようがしまいがお構いなしに、ひたすら止め処なく涙が零れて落ちる少年の瞳が今きつく閉じられた。
そうして、頭よりも早くその心が彼の震える両腕を動かし、それは青年の背へと回る。そこできつく握り締められた少年の手に、青年は、自分の心臓を濡らす相手の涙のあたたかさを想った。
「バニティは、バケモノなんかじゃあないよ。それに、もしもバニティがバケモノなら、俺だってそうなんだ。俺だって、バケモノだよう。世界でいちばんの悪人だ……」
「ちが、違う……」
「違くないよ。俺はバニティと一緒がいいの……」
青年は相手を抱き締める腕に力を込めると、今度は少年の肩に自身の頭を埋めた。甘く浮かぶチョコレートの香りに混じって、白いバニラの花が控えめに香っている。涙には、においはなかった。ただ、つっかえるような嗚咽だけがすべてだった。
「……俺、バニティのためならなんでもできるよ。バニティのためなら、なんでもしたいの。だから、だからね、俺のこと、要らないなんて言わないでよう……」
それは懇願にも似て、哀願にも似た、けれどそれ以外の何か。或いは、きつく結んだ糸の色を確かめるようなものだった。子守唄よりも柔らかい、ゆっくりとした青年の声色に、少年の呼吸が緩やかに落ち着きを取り戻していく。両目から溢れる雫は未だ、止めるすべを持たないままに。
「バニティがいないなら、どこに行ったって一緒だよ。バニティがいないなら、どこに行ったって全部、全部つまんないよう。なんにも意味がない。キミがいなくちゃあ、なんにも……」
顔を見なければ、口元さえ見なければ──いいや、たとえ、その常に弧を描かなければいけない唇を目にしたとしても、少年にとっては今、青年が笑っているようにはとても感じられなかった。何もかもが間違っている。何もかもが狂っている。そんな国の底で、自分だけが、自分たちだけがまともであると、そう錯覚していたのはいつからだったか。それとも、まともだった歯車が狂い出したのは、一体。考えるまでもなく、言うまでもなく、それは、誰かがころした誰かの、その命のかたちをしたクッキーを口にしたときからだった。ああ、今さらだ。何もかもが今さらだ。今さらなのに。今さらだから。
だから。
少年の手が一度青年の背から離れ、けれどもその手は再び相手の背を強く掴んだ。もう逃げ場はない。後戻りはできない。けれども、逃げ場なく、自分の居場所が青年の腕の中にしかないことに、少年は心の棲み処で安堵していた。彼自身、それを自覚さえしていた。笑えた、涙が出るほど。でも、笑えなかった。唇から洩れるのは、どうしても醜い嗚咽ばかりで。
「トロベリー……」
「うん」
「……綺麗な、女王じゃなくてもいいの」
「いいよ」
「女王ですら、なくても?」
「いいよう、そんなの……」
少年は今、涙を流したままで、そのおもてをようやく上げた。そうして彼は青年の膝に乗ったまま、淡い明かりのやってくる方をまなざすと、窓枠より外に在る月の色を想う。赤でもなく、青でもなく、白でもなく。黄色ければいいのに、と少年は思った。彼の作るオムライスみたいに、まあるく、あたたかい黄色であればいいのに。
「──〝もしも急に何かの奇跡が起きて、明日ここを出られて真人間の暮らしができたら。前科も消えて、人にも追われずに〟」
あらすじどころか、もう題名も想い出せない物語。けれど、その一節ばかりが頭にちらついて、少年は思わずその台詞を自身の唇から解き放った。目に映せない月を眺めたまま、彼はどこか少女のような瞬きを一つ行うと、その視線をゆっくりと青年の方へと戻してみせる。
「そしたら、トロベリー、おれのこと……」
「うん……」
「おれのこと、」
「……なあに? なんでも言って。俺、なんでもしてみせるから……」
そう言う青年は、その水色のまなざしを、少年が月を見ている間も、唇から台詞を紡ぐ間も、ずっと彼ばかりへと注いでいた。少年はそんな相手の静かな水面を覗き込んでは、片手の五本指で、青年の少しばかり汗ばんだ赤髪を握り込む。夜の中で、少年にとって唯一しるべとなるような、触っても熱くない柔らかな火。それは、自分のつまらない涙を、決して灼いてくれないほのおだ。呼吸みたいな涙が、また少年の両目から零れ落ちていた。
「分からない……」
何をも演じられない少年の声は、今やぐずぐずに滲んだ涙声であった。そんな少年の髪が、微かに揺れる。そして、それよりもひどく睫毛を震わせたまま、彼はずっと握り締めたままだった片方の手を、ふと青年の前へと差し出してみせた。
「でも、……これ、受け取ってくれる?」
消えかけの蝋燭さながらの声で発された言葉と共に、少年の手のひらはそうっと開かれる。ぱたぱたと落ちる彼の涙を指先で拭い拭い、青年は目の前でちかりと輝いた光の正体を自身の視界に映した。
「──指輪?」
それは、細いリングに小さな石が填め込まれた、華奢な指輪だった。
派手好きなこの国では恐ろしく希有である、装飾などほとんど施されていない、玩具の指輪。雨が降れば錆びる見せかけの銀の輪に、引っ掛ければ壊れる偽物の石。ただ、透き色に見えるその石は、角度を変えると、淡くあわくその内側に色を宿す。この国では見られない、虹の色。美しい夢の色だった。
「うん。作り物の石だけど……」
「……綺麗だねえ、バニティ」
「だから、おまえに受け取ってほしいんだ。トロベリー」
少年は、首を傾げてそう微笑んだ。それから彼は少しだけ手のひらの上でその指輪を転がし、赤から桃へ、桃から水色へ、水色から青へ、青から紫へとほのかに遊色する透明の石を眺めると、満足したように指輪を指先で摘まみ上げ、それを青年の指へと密やかに通してみせる。左手の薬指。そこを選んだ理由は、少年自身にも分からなかった。
「で、でも俺、バニティにあげるもの……」
「いいよ。いつも色々貰ってるし……」
「え……ええ? だけど……」
「あ、……じゃあ、」
指輪と相手を交互に見やり、ちょっとだけ慌てはじめた青年に、少年はくすりと口内だけで笑うと、ふと何かを思い付いたように、ぱち、と瞬きをする。そうして彼は自分の左の指先を青年の唇に押し当てると、案の定薬指だけを淡く持ち上げて、依然涙を流したままにその目を細めた。
「はい。ここ、噛んで。痕が残るほど、強く」
「え。えっ?」
「噛んでくれ。なんでもできるんだろ」
「でっ、できないよう、バニティが痛いのは……」
「いいからさ、ほら」
そんな少年の突飛な物言いに、青年はおろおろと視線を彷徨わせると、それでもぐいぐいと押し付けられる相手の指先に観念しては、自身の肩を困ったようにすくめた。それから彼は控えめにその唇を開くと、歯が当たらないよう少年の薬指を口に含み、しばらく迷ったのちにようやく自身の歯を立てる。それは、ほんとうにほんの少しだけだった。甘噛みと呼ぶにももどかしいほど、柔らかい代物だった。自分の指輪がはまっているのと同じ位置へと歯を立てた青年は、その痕を舌先で申し訳なさそうに舐めてから、少年の指を自身の唇から解放する。
そのさまをじっと見つめていた少年は、戻ってきた自分の薬指の痕をひどく愛おしげに撫でて、それからやはり、おのれの赤色からぽろぽろと涙を流したのだった。
「……はは、おまえは優しいなあ……」
そうして少年は青年の首元へと自分の両腕を回すと、瞬きをし、瞬きをし、そのたびに透き色を零して、それでも痛々しいほど幸せそうに微笑んでいた。
「トロベリー。……おれのこと、もう慰めなくていいよ。でも、その代わり……」
「その代わり……?」
「いや……なんて、言えばいい、ん、だろう……」
少年は真っ直ぐに青年のことを見つめたまま、まなざしだけで戸惑いがちに首を傾げる。その睫毛の間を濡らす涙がきらきら光って眩しくて、青年は少年の瞼にそっと口づけを落とした。それから彼は少年の髪を梳いてやりながら、その身体をあたたかくて柔らかいもので包むかのように、ゆっくりとした口調で語りかける。
「いいよ、バニティ。上手じゃなくても、綺麗じゃなくてもいいから、言ってみて……」
青年から与えられた言葉に、少年の唇が何事かを紡ごうとしては、息だけを吐き出して閉じられる。それが数回くり返されても尚、相手の言葉を待ち続ける青年に、少年は鐘の音を鳴らす心臓を抑えようと深く息を吸った。
「……その、」
「うん」
「抱き、締めてほしい」
「うん」
「頭を、……撫でていて」
「うん……」
「……できたら、キスも」
「ん……」
少年の小さな、けれどもはっきりと発せられるその言葉に、そのすべてに青年は応えた。彼はまるで母親のように、少年を抱き締めていた腕に強く力を込めた。兄のように、その小さな頭を確かめながら柔らかく撫でた。それから、口づけをした。一度だけ、口づけを。欲望もなく、同情もなく、ただ愛しいだけのそれを彼らは交わした。まるで恋人のように。
「──ここに、いて」
少年は、泣いていた。
「おれのこと、忘れないで」
ずっと、泣いていた。
「おれが……世界一の悪者でも、一緒にいて。おれのこと、離さないで。お願い……」
けれど、青年にとってはそれが何より、世界でいちばんやさしい涙だった。
青年は一層強く少年のことをかき抱くと、涙の代わりに、その背をきつく握り締めた。涙を流せないから、彼は自分の血液の中で透明に輝くものをどうにか外に出すために、呼吸をした。呼吸をして、瞬きをして、また息をして、それから言葉を発した。
「バニティ」
「……うん」
「俺、ここにいるよ」
「うん……」
「バニティのこと、忘れないよう」
「うん……」
「バニティと一緒にいる。バニティの夢は俺の夢。俺は、バニティが好きだよ……」
その言葉に、その約束に、少年は音もなく笑ってみせた。涙に濡れ、滲んだ彼の瞳は、青年の目の水色、髪の赤まで吸い込んで、さながら指輪の石のような色をしていた。細められ、なんとなく不器用に弧を描いた少年の瞳は、それでも青年にとっては世界で美しいものに変わりなかった。愛おしげに、幸せそうに、泣き濡れながらもこちらを一心に見つめる瞳。それはまるで。
「──それが、聞けてよかった」
まるで、夕暮れの風に吹かれたかのように、ひどく切なげだったのだ。
「ありがとう、トロベリー……」
ほんの一瞬だけだった。ほんの一瞬だけ、青年の心臓が虚を突かれては不可思議な音を立てる。けれど、そのさまに瞬きの隙も許さず、少年は青年のことを抱き締めたまま、目の前の唇に口づけを落とした。
「バニティ……?」
少年の唇が、青年のそこから離れていく。そのあわいを縫って青年が相手へと声をかければ、名を呼ばれた彼は照れたように頬を染め、小さく微笑みながら首を傾げてみせた。濡れた頬の上、暗やみでも分かるほど、少年の頬は朱に染まっている。彼は青年の髪を自身の細い指先で撫でながら、黒く長い睫毛を相手のストロベリー色をしたそれにくっつけ、唇の隙間からそうっと息を吐いた。
「トロベリー……」
「……バニティ」
「ああ、トロベリー……」
そうして少年は相手の唇に口づけを落とした。声にならない言葉をおくるように、何度も。何度も。それに応えた青年もまた、少年の唇に口づけを落とす。相手の存在を確かめるように、角度を変えながら、何度も。何度も。何度も。それをくり返す内、彼らの唇の隙間から火が咲いて、二人は互いの唾液を交換し、自身の吐息を与え合った。完ぺきには一つになれないとしても、彼らは互いの身体を重ね合い、その影を、影ばかりは一つの生き物となって、この低く暗い暗やみの中で呼吸をした。
「ずっと、こうしていられたらな……」
そんな塩辛い水の中に身を沈めながら、少年は笑い、そして、やはり泣いていた。
夜が明ける頃、彼の薬指に付いた痕は、もうすっかり消えてしまっていた。
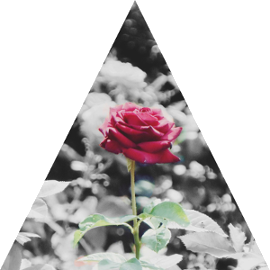
「──それじゃあ、ちょっと行ってくる」
それから幾ばくかの月日が流れ、少年の見た目は変わらず少年のまま、青年の見た目も変わらず青年のままの朝、少年は玄関先のポーチで青年へと向かい、いつも通りにそう発してみせた。
いま頭上で煌々と輝く今日の陽も、二人で長い夜を乗り越えた後に迎えた、明けの光だった。つまるところ、霞んだ視界を抱える少年にとっては、蹴飛ばしたくなるほどに鬱陶しい代物である。少年はそのまばゆい白光に眉根を寄せ、隠す素振りすら見せずにあくびをしてから、ひどく重たい衣装鞄をそうとは見えないようひょいと軽々持ち上げ、ちらりと青年の方を見やった。
「うん、気を付けてねえ。帰りは遅くなるのう?」
「いや。今日は黒い雨が降るかもしれないらしいからな、用が済んだらすぐ戻るよ。おまえも、危ないから家にいろよな」
にこにことそう問いかける青年に、少年は事もなげに返事を発する。それから相手の左手薬指にきちんとはまっている玩具の指輪をまなざすと、そこからすぐに視線を離して、まるで何かを思い出したように彼は握り締めた片手を青年の方へと差し出した。
「……ああ、そうだ、トロベリー」
「うん?」
「ガクランのボタンが取れちゃったんだ、上から二番目の。渡しとくから、後で付けてくれるか?」
「あはは、なあんだ。お安いご用だよう! じゃあ俺、なくさないようにちゃんと持ってるね」
「……ふ……大げさなヤツだなあ」
くつ、と喉の奥で呆れたみたいに笑って、少年は青年の手のひらへと一つのボタンをぽとりと落とした。それが丁寧に青年の上着の内ポケットへと仕舞われるのを見届けてから、彼は何かを考えるように睫毛を伏せ、自身の指先をパチパチと鳴らす。
そして、その拍子に片手にしている衣装鞄が微かに揺れ、そこから金属質の音がガシャ、と小さく響いた。少年はそれを誤魔化すためにもう一度指先を鳴らすと、上機嫌にこちらを見つめている青年の方を見上げ、微笑む。
「トロベリー。そういえば、今日の朝ごはん、美味しかったよ」
「ホント? ふふ、よかったあ。夕ごはんは帰ってからのお楽しみ、ね!」
「うん。あ、でも……」
「でも?」
少年は、折った人差し指を口元に当て、柔らかく笑った。
「おれ、おまえのオムライスが食べたいなあ……」
きっと今日の月こそ、黄色いだろう。そんな少年の思いを知る由もない青年は、彼の言葉に心底嬉しそうに笑んでみせると、そのやさしい水色の瞳を楽しげに細めて、変わらずうきうきと自身の両手をぱちんと合わせてみせた。
「──オムライス? あは、りょーかい! バニティはオムライスが好きだねえ」
「ホットケーキも好きだよ。ハンバーグも、ピザも、パスタも、おまえが作るものなら……」
「それじゃあ俺、全部作っちゃおっかな?」
「はは、まったく……誰がそんなに食べるんだよ」
「バニティと俺!」
その言葉に少年は、いよいよ仕方がなさそうな笑い声を上げた。いつかみたいな涙が目尻から零れそうになるのは、きっとこの可笑しさのためだと自分自身に言い聞かせ、彼はくすくすと音を立てて笑った。少年の衣装鞄には、この屋敷の中にあった、ありとあらゆる刃物が仕舞われている。彼がただ一つ汚したくなかった、青年が料理に使う刃物以外のすべてが、今、彼の鞄で息を潜めていた。
もう一度だけ。
もう一度だけ、名前を呼んだら。
「トロベリー」
彼は、見えなくなった自分の左薬指の痕を、まなざし以外のものでそっと見つめた。ただ、目は、目だけは青年の方をまなざして、その名前を呼んだのだ。それは歌うように、軽やかな声色で。
「あっ、はあい」
「──じゃあ。また、あとで」
「うん。行ってらっしゃい、バニティ!」
少年は微笑み、いつも通りに、ほんとうにいつも通り、ひらりと軽く手を振った。
今日の彼は、完ぺきだったのだ。青年の前ですら、完全に演じられるほどに。こんなことは、彼が青年と出会ってからというもの、初めての出来事であった。ばかみたいに太陽が輝く晴天の下、少年は、悲しいほどに完ぺきな役者だった。
雨は、降らない。
そして、彼はその後、ついぞ家には戻らなかった。
もう、二度とは。
Strawberry Vanilla Ice cream
20200517 執筆
…special thanks
トロベリー・クラウン @橋さん