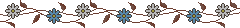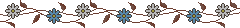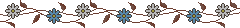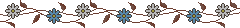
久しぶりに降りた湯本の駅は高校時代とそう変わらない。まだ夏が始まる前だからか人はそう多くはないけれど、東京より少しだけ涼しい気がする。
電車に乗りっぱなしで少し鈍った身体をぐっと天に向かって伸ばした。ついでに隣を歩く真波をチラリと見れば、何を考えてるのか分からない真顔でただ目の前を見つめているだけだ。ロマンスカーの中でも真波はずっと窓の外を見つめていた。車内で会話はほとんどしていない。でも、あのいつでもどこでも眠れる真波にしては珍しく寝ていなかったと思う。寝ている時の真波は隣にいればわかるくらいに小さく寝息を立てることを知っているけど、寝息は聞こえてこなかった。
デートの時でも電車に乗ればすぐにうとうとしていたし、高校時代に合宿などでバス移動をするときも真波は席に着いたらすぐに眠ってしまっていた。
外なんか見ないくせに窓際に座りたがるから他のみんなは真波の隣を嫌がっていたけど、私はそんな真波の隣に座ってこっそり寝顔を見るのが好きだった。
真波はなぜかいつも私の肩に頭を乗っけて寄りかかるようにして寝てしまう。寝てしまう真波はずっしりと重たかったけど、それも幸せな重みだった。長いまつ毛も、たいして手入れもしてないくせにつやつやの肌もすぐ近くにあってたまらなくドキドキした。一度寝た真波はなかなか起きないから何度かいたずらでほっぺたを突いてみたこともある。
いつからか、真波の隣の席は当たり前のように私の特等席になっていて、真波から「澪さんの肩ってよく寝れるから好き」なんて言いながらえへって笑われたらもう私は恋に落ちていた。真波の、そういうところが好きだ。
甘え上手なところ。天使みたいな顔して笑うところ。周りなんか気にしない、自由なところ。そして我が強くてわがままなところ。
でも自転車に乗るとその雰囲気がガラリと変わる。特に坂を登ってる時の真波はあの甘い雰囲気なんて全く感じさせないくらいにピリッとした空気を纏っていて、そのギャップにもころりとやられてしまった私。
真波を好きになってからは、色々苦労したなぁ。女の子たちから黄色い声援をあびる真波に肩を落として、諦めなきゃなぁなんて思っていた時もあった。だけどマネージャーとしてそばで真波の成長を見ていればもっともっと好きになってしまって、真波にも振り向いて欲しくなってしまった。
そして、ある晴れた日。外周から帰ってきたみんなにドリンクを渡して迎えていたら東堂が真波がいないと騒ぎ出して、その後取材が入っていたみんなに変わって私がママチャリに乗って真波を探しに行くことになった。荒北がおそらく真波がいるだろうサボり場所を教えてくれたのでそこを目指してママチャリを必死に漕いだら、草むらに仰向けになってすやすやと眠っている真波を見つけた。ママチャリを降りて、真波へと近づいていく。真波は変わらず目を閉じてすやすやと子どもみたいな寝息を立てているから、私は真波の横に座り込んで独り言のように『真波が好きだよ』と言ってしまった。
恥ずかしくなって、膝に顔を埋めて丸まっていれば寝ていたはずの真波がガバリと勢いよく起き上がる。私はそれにびっくりして膝から顔を上げたら、すぐ目の前に真波の顔。
『オレも澪さんのこと好き』
とびっきりの笑顔でそんなこと言う真波に、私の心臓は全部持ってかれてしまった。あの時からずっと私の心は真波のもの。好きで好きでしょうがなくて、私は真波に弱かった。
真波も同じように私に優しかった。べたべたしてたつもりはなかったけど東堂たちには「イチャつくな!」って散々怒られたなぁ。真波と付き合うなんて、想像できなかったけど実際に付き合ってみると真波は私が思っていたよりもずっと普通の男の子だった。私が東堂と話していればヤキモチを妬いていたし、デートにも出かけてくれたし手を繋いでもくれた。愛情を言葉にもしてくれたし、私に触れたがった。キスもしたし、高校を卒業して大学生になってからそれ以上もした。
電気を消して真っ暗になった真波の部屋。ぼんやりと見えたのは私に触れて、見たことのない顔をした真波。息を乱して、眉を顰めて、余裕のない顔を見た時、私が天使で不思議ちゃんで、天才だと思っていた真波もただの男の人だったんだなと知った。
そうして幸せに浸って、私から手を伸ばして真波を抱きしめて受け入れた。
「澪さん…澪さん?」
名前を呼ばれて、くいっと服の裾を引っ張られる感覚にハッと意識が戻る。私の顔を覗き込んで不思議そうにきょとんと目を丸くした真波。ごめんね、と謝ってから駅の階段をスタスタと降りていくと駅前の出店も人はまばらだ。
「どこ行くの?かまぼこでも食べる?」
「うわ、懐かしい。よく学校帰りに下山して食べたね」
「澪さん毎回悩むくせに毎回チーズなんですもん」
「真波だっていっつも玉ねぎじゃん」
「あはは、だって美味しいんだもん」
「お腹すいたの?」
「んー、そうでもないかな」
「よかった。じゃあご飯はあとでね。向こうで食べようと思って持ってきたんだ」
背負ったリュックともう一つ、手に持っていたバスケットをチラリと真波の目の前に見せつける。すると真波は目をキラキラさせてバスケットのフタを開けて中身を確認した。
「おにぎりだ!」
「好きでしょ?」
「大好き!澪さんのおにぎり!」
嬉しそうに笑う真波を見たら、早起きしてたくさん握った甲斐がある。おにぎりなんて久しぶりに作ったけど、いざ作り出したら手が自然と動くし、なんとなく塩の量も覚えてるんだからすごい。
「じゃ、早く行こう。あ、バス来てる!」
「おにぎり持つよ」
「ありがと」
「で?結局どこ行くの?」
バスケットを持って私より先にスタスタ歩いて行く真波は、もう絶対に分かってるはずなのにわざわざそんな質問をするなんて、意地が悪い。
「とりあえず、箱根学園までかな」
バスに乗り込んで1番後ろの広い席に2人で並んで座る。膝の上に手を置けば、その上にそっと真波の大きな手が重なってきた。そのまま私の手を覆うようにして、指先がきゅっと絡み合うようにして繋がれる。
「…自転車、持ってくればよかったな」
少しだけ寂しそうに、ぽつりと真波がこぼす。
昔は学校から下山するのにもバスなんて使わずに部室にあったママチャリで行ったなぁ。もちろん真波は自分のロードに乗っていたけど、意外と私と一緒に走る時はちゃんとペースを合わせてくれていた。
レースの時は、当たり前だけど一緒に走ることなんてできない。私に出来ることはゴールで祈りながら真波を待つことだけ。そして一生懸命ペダルを回して、全部全部出し尽くして飛び込んでくる真波に「お疲れ様」って両手を広げて迎えることしかできない。
でも、私はそれが好きだった。
真波が私に向かって飛び込んでくるのも、自転車に対して純粋で、真剣な眼差しも全部含めて丸ごと真波を愛していた。
だから真波にはずっと自転車に乗っててほしいんだよ、私。