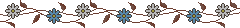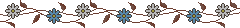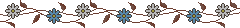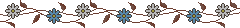
次の日もいつものように仕事が終わったのは20時過ぎ。
真波が家にきてから4日が経った。
私はいつものように仕事へ行くけど、真波が昼間何をしているのかは知らない。ただ日に日に部屋が綺麗になっていくから、もしかしたらずっと部屋にいて掃除とかしてるのかもなんて思うとちょっと笑えた。いや、笑えない。なんであいつ私の家に転がり込んでるの。
真波にだって日常があるはずだ。あいつは大学を卒業して、実業団チームで活躍しているはず。はず、というのは私が実業団になった真波を知らないから。私が知ってる真波は、実業団になる寸前の真波まで。大好きを仕事にする。大好きな自転車とずっと続けられるなんて、凄いことだねって、そう言おうと思ってたのに、それを伝える前に真波に別れを告げられてしまったから。私はそれ以降の真波を知らないまま。
真波以外にも、自転車を仕事にした人たちが私たちの代にはたくさんいた。あれだけ真面目に、一生懸命取り組んでいたんだから嬉しいと思うし、やっぱり羨ましいと思う。プロの世界だし厳しいことや辛いこともあると思うけど、それでも続けられるくらい好きなものがあるってすごいことだ。
駅の改札を通るために、鞄の奥底からスマホを取り出そうとすれば、タイミング良くスマホが震える。画面を確認すれば表示されたのは懐かしい名前。もうしばらく連絡を取っていなかったけど、とりあえず通話ボタンを押してスマホを耳に当てた。
『もしもし、椎名か』
「東堂、どうしたの」
『む…まだ外にいるのか?夜遅いというのに』
「仕事帰りだから」
『そうだったか。遅くまでお疲れ』
「…ありがと」
懐かしい声に、少し気が抜けてしまう。まるで昔に戻ったみたいだ。
東堂はマネージャーの私のこともよく気にかけてくれていた。騒がしい奴だったけど基本的には優しくて紳士的。特に仲良くなり話すようになったきっかけは、そういえば真波だったなぁ。真波の自由さに振り回される東堂は見ていても面白かったけど、東堂は振り回されているように見えて本当は自由な真波の背中としっかりと押していた。真波も東堂のことを尊敬していたし、東堂は真波を特に気にかけていたのはよく知っている。
『単刀直入に聞くが、椎名。真波を知らないだろうか?』
「…は?」
『真波が消えた。どこにいるか知らないか?』
「…消えたって、何」
東堂が言うには、真波がチームにも何も言わず家にも帰らずどこにもいなくなってしまったという。
東堂も実業団で自転車を続けているが真波とはチームが違う。しかし真波と同じチームには新開がいて、新開から東堂へ今の私のように『真波を知らないか』と連絡が回ってきたらしい。
東堂へ話が回ってきたということは、きっと福富や荒北、もしかしたら泉田や黒田も同じように真波を探しているんだろうか。
こんな大事になってるなんて、知らなかった。
だって私の家にいる真波はそんなこと何も感じさせず、ニコニコ笑っていて、よく食べてよく眠る。私から見た真波はいつも通りに見えたから。まさかそんな感じで、チームを飛び出してきてるなんて知らなかったし、思いもしなかった。
『椎名に聞くか迷ったが…他に当てもない。オレもあいつのことは目にかけていたから、違うチームといえど放っておけなくてな』
「…そう」
『それで、何か知ってるか?何でもいいんだ』
「…私、もう真波とは連絡とってないから」
東堂も私と真波が別れたことは知ってるはずだ。だけどそれでも私に連絡してきたということはそれほど焦っているんだろう。
電話の向こうで東堂がはぁっとため息をついたのがわかる。
きっと東堂も真波を探し回っているんだろう。可愛がってた後輩がいなくなってしまって連絡も取れないなんて、気が気じゃないだろうな。東堂は面倒見がいい奴だから余計に。
でも、ごめんね東堂。
「ねぇ、東堂」
『なんだ』
「真波、ちゃんと速く走れてた?」
実業団のことなんて、調べようと思えばいくらでも調べられた。ネットだってあるし、レースだって高校時代の時から見に行ってたから馴染みもあるし調べて行こうと思えばいつだって見に行くことができた。
でもそれをしなかったのは、真波にとって私が重荷になってることが怖かったからだ。
真波は、速く走りたいと言って私を置いていった。私がいると真波は速く走れない。そんなこと言われてしまえば、見に行くことなんてできない。それに、私がいなくなったことで速く走る真波だって見たくなかった。
『オレはチームが違うから詳しくは知らんが、最近のあいつは何かに縛られてるかのようだった』
「え?」
『あいつが速いのは、自由だからだ。思うままに、あいつらしく走るから速い。楽しく走るから速いんだ。だけど…最近はそれができていないように思う。何か変だと、そう思ってたのに、チームが違うと遠慮して何も言えなかったオレの落ち度だ』
東堂は1ミリも悪くない。むしろ優しすぎるくらいだ。こんなに大切に思ってくれる先輩がいるのに、真波はどうしてウチにいるんだろう。
うまく走れない?ならなんで私のところにきたの。私は、あんたが速く走るために終わりにしたっていうのに、どうしていまさら。
東堂との電話を切って、改札を通って電車に乗り込む。満員電車に揺られながら、目を閉じればやっぱり私の前に現れるのは高校時代の真波だ。
今より少し幼い顔をしていて、楽しそうに笑う。外周から帰ってくると「澪さん!」と私の名前を呼んで飛びつくように抱きついてきて、それを東堂が引き剥がして荒北が拳骨を落として、新開が笑って、福富も少しだけ表情を緩ませる。
みんなかっこよかったけど、やっぱり私の目には真波だけがキラキラ輝いて見えていた。自転車に乗る真波が好きだ。私の名前を呼ぶ真波が、誰よりも速くて自由で生きれる真波が好き。
「おかえり澪さん」
「ただいま真波」
ガチャリと玄関を開ければ、真波の声がする。
想像しなかったわけじゃない。こうして、同じ家で暮らすことを。真波のためにご飯を作って、2人で食べて、今日あったことをお互い布団に潜って話しながら抱き合って眠る。大人になっても2人一緒にいて、そんな未来がくることを夢見てた。
だけど、あんたの未来には私がいなかった。
「真波」
ベットに寄りかかって、テレビを見ていた真波がくるりとこちらを向く。
真波の背後には狭い部屋の中で端っこに追いやられるようにして置かれた白のLOOK。いつだってピカピカなのは、きちんと手入れされている証拠。
「なぁに?どうしたの澪さん」
ニコニコ笑う真波。好きだなぁ、と思う。
忘れたことなんか一度だってない。いつだって私は真波に恋をしていた。ずっとこのままウチにいてくれたっていい。ずっと一緒にいたい。このままずっと。
だけど、私が好きになったのは自転車に乗って、誰よりも速くて、キラキラ笑う真波だから。
「…ねぇ澪さん」
「ん…」
「今日は、一緒に寝ていいかなぁ」
ねだるように手を伸ばしてくる真波の腕の中に飛び込んでしまいたい。抱きついて、離さないでって泣いてしまいたい。
ずっとここにいていいよ。逃げてもいいよって、そうやって甘やかしてしまいたくなるから、やめてよ。
『真波が甘えてくるなら、お前だと思ったんだがな』
電話を切る前に東堂が言った言葉がぐるぐると頭の中を回る。
真波は、もう笑ってなかった。いや、笑ってはいるけどその顔は何だか泣きそうで、結局私は真波の手を取ってしまうのだ。