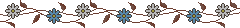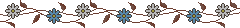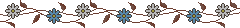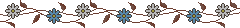
毎日毎日、同じことの繰り返し。
朝起きて電車に乗って、コンビニでコーヒーと朝ごはんを買って出社。あとはひたすらキーボードを叩いて、たまに上司の意味わからない仕事を請け負ったり後輩のやり残した仕事を終わらせていたらあっという間にやってくる定時。自分の分の仕事を定時後に回して、気がつけば2時間。20時過ぎに会社を出て、また電車に揺られて家に帰る。
誰もいない部屋に「ただいま」なんて挨拶して、足が浮腫んでぎゅうぎゅうになったパンプスを脱ぎ捨ててスーツのままベットへダイブ。まだだやらなくちゃいけないことが山ほどある。洗濯とか、夕飯とか、公共料金の払込とか…だけどそんなのももう慣れっこというか、日常になってしまった。ベットに寝転がったまま狭いワンルームを見渡す。社会人になって買ったお気に入りのテーブルの上には大量のハガキとチラシ。目を通さなきゃいけないのもわかってるけど、時間がない。思わずはぁっとため息をついてしまった。
大人になるってもっと楽しいと思ってた。自由で、毎日キラキラしてて、やりたいことやって、好きな仕事をする。そんなのはひと握りの人間しか辿り着くことができない世界だと思い知った。私の周りはそのひと握りがたくさんいる。だけど彼らだって一生懸命努力をして掴み取った物だと知ってるから、嫉妬をするなんておかしな話だ。分かってるのに、時々どうしようもなく苦しくなる。
それでもまた私が明日も仕事に行って、頑張って生きようと思えるのはそんな彼らと高校時代のキラキラした思い出があるからだ。
3年間、楽しくて、毎日充実していて、やりがいもあった。みんなと一緒に部活に打ち込んで、マネージャーという立場だったけど悩んだり泣いたり笑ったり。本当にあの3年間が私の人生のピークだったんじゃないかってくらいに宝物。
『澪さん、好きですよ』
そうやって高校時代を思い出して目を閉じれば、いつでも目の前に彼が現れる。
笑って、私を好きだと言う彼が私も大好きだった。これからもずっと一緒にいたい、当たり前に一緒にいれるものだと思ってたんだ。
あいつの自由を分かってあげられるのは私だけ。ふわふわしてて、何考えてるか分かんないくせに自転車に乗ると空気が変わる。普段の天使みたいな顔も好きだけど、私は坂を登ってる時のあの真面目な顔も好きだった。苦しい時も悲しい時も、もちろん嬉しい時もずっと一緒にいたから、だからこれからもそれは変わらないと思ってた。
『ごめん。オレ、もっと速くなりたい』
そう言われた時、あぁ、私ってあいつにとっていらないものになっちゃったんだなぁってショックだった。悲しくて、つらくて、潰れてしまいそうだったけど、それよりもずっとあいつのほうが辛そうな顔をしてたから。好きで好きで仕方なかったのに、私は年上ぶって笑顔でさよならを言ったんだ。そうやって終わりにした。もう会うことはないだろうと思ってた。
それなのに、
「澪さん、おかえり」
ガチャリと音を立ててお風呂場から出てきた真波は私を見て、あの頃と変わらない笑顔で笑う。
真波にとっては、もう私のことは終わった出来事でしかない。じゃなきゃ昔の女の家を突然訪ねてきたりはしないだろう。
あと頃と変わらない、愛車の白いLOOKと小さなリュックだけを持ってウチの玄関の前に真波が立ち尽くしていたのは3日前。
その時追い返せばよかったのに、それが出来なかったのは真波が笑っていたからだ。昔と変わらない顔で笑って『澪さん』と甘えたような声で名前を呼ぶから、今もずっと恋をしている私はそんな真波に弱いから、何でもないふりして、あの頃のように真波の名前を呼んで部屋へと入れてしまった。
私も早く、過去の綺麗な思い出として真波のことを大事に大事に記憶の中に仕舞わなければいけないのはわかってる。だけどできない。私はまだずっとあの頃のまま、真波のことが好きなまま。
「…ただいま、真波」
「スーツ、皺になりますよ」
「…真波にそんなこと言われる日が来るなんて思わなかった」
「あはは、オレも」
どうしてこの人はここに現れたんだろう。
そんなことも聞けないまま、私はまた真波をこの部屋にとどめてしまう。追い返すことなんかできない。終わりにしたはずなのに、真波を前にすると私はあの頃に戻ってしまうのだ。
「ご飯作ったけど食べる?」
「んー…」
「オレもまだだから、一緒に食べよう」
「…ん、今日は何?」
「キーマカレーですよ」
「好きだねぇ」
「うん、ずっと好きなんだ」
真波の顔が見れなくて、化粧のことも忘れてベットに顔を埋める。
私だって、ずっと好きなんだよ。
いまさら友達になんかなれるわけもないのに、どうしてそんな平気な顔してるのよ。
なんで私のとこに戻ってくるのよ、ばか。