嘔吐中枢花被性疾患。通称花吐き病。
遥か昔から潜伏と流行を繰り返してきたらしいその病は、片想いを拗らせると口から花を吐き出すようになると言われ、その吐き出された花に触れると感染するという。
根本的な治療法は未だ見つかっておらず、両想いになると白銀の百合を吐き出して完治するのだとか。
私はそんな病に感染していることを、発症するまですっかり忘れていた。
げほげほと止まらない咳。胃や食道から何かが込み上げる感覚に不快感も込み上げる。私の咳と同時に辺りに散らばったのは篝火のような形をした白色の花弁だった。おそらくシクラメンであろうその花弁は、綺麗なはずなのに……初めて見た花吐きの花もあんなにも綺麗だったのに、自分から生み出された物はどうしてこんなにも醜く汚らわしいと思ってしまうのだろう。
初めて花吐き病を見たのは、父子家庭だった私たち親子に善くしてくれた近所のお姉さんだった。
いつもにこにこ笑顔のお姉さん。けれど、唯一辛そうにしている瞬間が。……それが花吐きだった。小さいながら心配になった私は彼女に不用意に近づいてしまい、そして花弁に触れてしまった。確かあれは……綺麗な竜胆の花だった。
お姉さんにはたくさん謝られた。「ごめんね、ごめんね」謝る声は酷く辛そうで、状況を飲み込めていない私でも、何か非常事態なのだとわかるくらいだった。
病気が発病してからしばらく経ったけれど、当たり前だが症状が良くなる兆しはない。むしろ良くなるどころか、吐き出す花弁に赤が混じるようになって来ていた。それは桃色のため、血ではないようだけれど、否定したくてもできない"目に見える恋心"に頭が、心が、おかしくなりそうだった。
勿論仕事も順調とはいかなかった。花を吐く以外にもこの病気は身体に不調を起こさせる。酷い時は立っているのもやっとで、吐き気も抑えきれない。職業柄、花吐き病がバレるわけにもいかず(最悪バレても大丈夫だが、万が一完治しまってはもう救いようがない)、私は泣く泣く休業した。
「舞園さん……だいじょうぶ?」
トイレで思う存分吐き出した後、眩暈がして廊下で蹲っていると、聞き慣れない声が前方から聞こえる。聞き慣れないといっても知らないわけではなく、むしろ良く知った……一番聞きたくて聞きたくない声。
声を聞くだけで、姿を見るだけで催すこの吐き気に似た胸の圧迫感や息苦しさに涙が出てしまいそうだった。
「千崎さ、んっ……大丈夫です」
「あー……っと、ごめんね、聞き方間違えた。大丈夫じゃなさそうだから保健室行こう?」
その優しさに今日一番の息苦しさが襲う。いつもはあまり話しかけて来てくれないのに、弱っている時に優しくなんてされたらもっともっと好きになってしまうじゃないですか。
「立てる?肩貸すよ」
「大丈夫です。自分で立てます」
その言葉通り自ら立ち上がろうとするも、うまく行かず壁に体を預ける形に。千崎さんはそれを辛そうに見てくるものだから、居た堪れない気持ちになる。
千崎さんへの好きを拗らせて体調の悪い私なんて気にかける必要ないんですよ。……なんて、言えるわけないんですけど。
「やっぱり、肩かすよ。それとも腕の方がいいかな?」
「じゃあ……腕、貸してくれますか?」
「うん」と笑顔でエスコートするかように腕を差し出してくる千崎さん。その腕は意外と筋肉質で、なんだか安心すると同時に羞恥心が込み上げる。彼女に触れた場所から熱くなっていく身体に治まって!と願っても届くわけもなく、千崎さんに気付かれてしまった。
肩だと距離が近すぎると思い、腕にしたのは間違いだったのかもしれない。
「身体も熱いし顔も赤いけど、もしかして熱もある?」
「いえ……それは」
はっきりしない私の言葉に、千崎さんは首を傾げると「ごめん、触るね」と言って私の額に手の平を宛がう。本当に熱でもあるかのように、彼女の手はひんやりとして気持ちが良かった。
「熱い。無理しない程度に急ごうか」
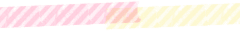
保健室に着くなり先生は用事があるからと出て行ってしまい、ふたりきりに。慣れたように体温計を取り出す千崎さんをベッドから横目に私はため息を吐いた。だって、今は落ち着いているけれど、いつ発作が起きるかなんてわからないんですから。
「はい」という言葉と共に差し出された体温計を受け取り脇ではさむ。千崎さんはといえば、ベッドの近くに椅子を移動させそこにちょこんと可愛らしく座っていた。
待っている時間退屈させないようにと江ノ島さんの話をしている彼女の声はまともに耳に入ってこない。滅多に話せないのだから私と話してくれたっていいのに、なんてわがままなんですかね。
何の偶然か、ぴぴっという電子音と共に嘔吐感が込み上げる。まずいと思ってももう遅く、いつもの発作と似た咳が出はじめた。体温計を千崎さんに渡し、口をおさえる。
「舞園さん!?」
「大丈……夫です。いつものことなので」
げほげほと容赦なく出る咳。さっきまで意地でも隠し通そうと体が頑張っていた反動か、もう隠しようがないと諦めた瞬間、私の口からまさに篝火のような真っ赤な花弁がはらりと落ちた。
その色を見て、以前調べたシクラメンの花言葉を思い出す。もし、花言葉と発症者の心情がリンクするというのならば、私は今彼女の話に登場しただけの江ノ島さんに嫉妬したということだ。
千崎さん、私こんなにも拗らせるくらいあなたを愛しているのですがどうしたらいいですか。
……彼女が放り投げた体温計は私が風邪でないことを証明していた。
16/9/19