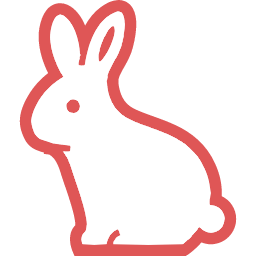淀んだ空気を身にまとい、優希は訓練室の扉を開けた。端末を見る。あまりにもひどい訓練結果に、優希は溜め息をついた。
心を悩ませている理由は分かっている。自分がもろに心理状況が態度に出るタイプなことも。ともなればこの現状を何とかするにはその理由を何とかする必要がある、のもわかる。
声、を、かけなければ。こないだの、あの、コーヒーの人に。
先日の一件の後、よくわからないままブラックコーヒー片手に立ち尽くしていた優希は、自分が物をもらったことに気付いてぱああっと明るくなった。おそらく端末を見つけた礼の品ではあるが、それでも人から物をもらったことなんて片手で数えるほどしかない優希からすれば大事件である。普段は飲めもしないが、大喜びで帰ったことを覚えている。
しかし、だ。冷静になってから優希は気付いてしまった。自分が物をもらったにも関わらず、礼の一つも言わずに影浦を見送ってしまったことに。なんと失礼なことか。しかも相手は年齢もボーダーへの入隊も先輩だ。無言で受け取るなんてもってのほかである。次に会ったときにお礼を言うべきだ。……という考えにたどり着いたのが、二日前のことだ。昨日は影浦隊自体が非番だったこともあり、見つけることはできなかった。見つけるとすれば今日。もし見つけられなければ、作戦室に直接行くしかない。
キリキリと胃が痛む。正直、影浦は普段なら絶対に声をかけられないタイプだ。男の人だし、隊長だし、年上だし。先日の会話を見るに言葉遣いも怖い。あっ思い出したら怖くなってきた。帰りたい。いやでもお礼は言わなきゃ。ああでもやっぱ怖い。文香ちゃんに会いたい。頭の中で怖い怖いと繰り返したところで、今日行かないと結局行かなくなりそうだ。やはり、行かなければ。
ふう、と息をはく。一旦落ち着こう。そうだ、下の売店で飲み物でも買おう。飲み物でも飲みながら文香ちゃんと少し話して、それから探そう。そうしよう。ひとりコクコクと頷いて、優希は一旦現実逃避をすることとした。
ど、どどっどどっしよう。壁に背をくっつけたまま、自分の心臓の音が大きく聞こえた。
売店で飲み物は買えた。おいしそうなのを買って、柿崎隊の作戦室へと向かった。その、道中。つまりはまだ全然心の準備ができていない状況で、見つけてしまったのだ。その人を。
予想外のこととはいえ、見つけてしまった以上もう声をかけたらいいのだが、そこは臆病さでは右に出る者のいない久野優希である。すぐさま近くにあった壁に隠れ、はあはあと胸をおさえた。
お、お礼、あの、なんだ、なんだっけ。そ、そうだ!コーヒー!コーヒーをくれて、あの、嬉しかったです。びっくりしたけど、帰り道、嬉しかったので。嬉しい。まずい、言葉出てこないどうしよう……。急いで即席のお礼の文章を考えるが、こうも焦ったままでは頭が働かない。一旦退散してもう一度あらためて作戦室に向かうべきだろうか。それはそれで影浦以外の知らない人にも囲まれて言葉がでてこないかもしれない。やはり、今、言うべきではないか。お礼を。
「……なにしてんだお前」
「っっ!!?」おそらくそのときわたしは、盛大に飛び退いた。多分ジャンプした。うおっと小さく影浦さんが驚いたが、正直その何百倍も驚いた。
「あ、あ、」
「……おい、やべぇ顔してんぞ」
驚きすぎて逆に悲鳴も出らず呻いているとそう指摘された。おそらくおばけでも見たような顔をしていたに違いない。
「ごっ、ごめ、なさ」
おばけを見たみたいな顔をしてしまったこと含めて謝る。影浦は謝ったことに対して返事はせず、面倒そうに「なんか用あんだろ」と言ってきた。「え、は、はい」隠れていたのをすぐに見つけたり用があると見抜いたり、影浦さんはもしかしたらすごく推理力のある人なのかもしれない。頭の片隅でそんなことを思った。
「あ、あの、あの。こな、こないだ、あの、ありがと、ございました……」
「こないだ?」
「こ、こーひぃ」
「…………」
思い出すように右上を見ながら影浦が眉間にしわを寄せる。数秒経って、「ああ」と思い出したような声で言った。
「うれ、うれしくて、帰り道とか、あの、すごいうれしくて、お、おい、おいしかった、です!」
ぺこぺこと頭を下げる。視線は常に下を向いている。口に出してから、「帰り道の話いらなかったな」と後悔した。頭を下げたまま、また数秒間影浦からの返事がなくなる。足元に影浦のブーツが見えるためいなくなってはいないはずだが……変に思い、優希はゆっくり頭を上げた。
影浦が優希の手を見ていた。手、というか。手に持っていたものを。
「……あ」
優希が持っていた、「新発売! ミルクたっぷりカフェオレ」を。
「え、えと、あの! こ、ここ、こ、れはえあ、ち、ちちちちちぎゃって」
まずい、この状況は、まずい。普段からミルク多めのカフェオレを飲んでいる人間がブラックを飲めるとは普通思わない。自分だったら思わない。影浦の表情は相変わらずむすっとしたままでよくわからないが、視線は確実に手元のカフェオレを見ている。も、もしかしたら「こいつブラック飲めないから捨てたんだろ」とか思われた……!?も、もしくは「飲めないブラック渡して悪かった」とか気遣われてる……!?一気に優希の顔色が悪くなった。
「あっあの、ほ、ほんとうにコーヒーは!の、飲んで!」
「いや……どうでもいい」
本気でどうでもよさそうな影浦だったが、その言葉は優希をさらに「お前なんてどうでもいい」……!?と被害妄想に拍車をかけた。
「あ、あの、でもほんと、美味しくて。うれしかったから多分、あの、美味しくて……!」
「……」
「お、美味しかったんです……」言葉尻が下がると共に顔を下げる。もはや半泣きである。ああ、なんで今日に限って甘いカフェオレなんて飲んでたんだろう。本当に、嬉しかったのに。名目があったとはいえ、誰かにものをもらうなんて、嬉しくないはずがなかったのに。
「……お前」
頭上から影浦の言葉が降ってくる。小さく返事をする。
「……飯食ったか」
影浦の言葉に、優希がえ?と涙目で顔をあげた。
「い、い、いいんですか、こ、こんな……」目の前に置かれたものを見て、優希が挙動不審に言った。
「たかがうどん一杯だろ」
「で、でも、てて、天ぷりゃが乗ってる……」
「……天ぷらひとつでよくそこまで感謝できんな」
でもぉ……でもぉ……、と腰の低い優希に、影浦が呆れたように言った。
「てかおめぇそれだけで足りんのかよ、もっと食えよ」
「こ、これで、おなかいっぱいになる、と、思う、ので……」
そういう優希だが、自分なら絶対に足りないと影浦は思った。女子ならこんなもんなのだろうか。自分の隊のオペレーターはどうだったろうかと考えた。伸びるから食え、と言われてようやくそろそろと優希が天ぷらうどんに手を伸ばす。
一口食べて、「うう……おいしい……」と言うが、なぜか顔はすごく辛そうだ。ちくちくと罪悪感が刺さっているのを感じた影浦は「なんだこいつ」と眉をひそめた。
先ほどの会話で、「美味しかった」「嬉しかった」という言葉に嘘がないのはよくわかった。わかった上で、よくわからない。なんでこいつはここまで相手に遠慮をしているのだろうか。
最初に会ったとき、体質じゃなくてもわかるくらいに怯えられたのでコーヒーを与えてさっさといなくなった。しかし今日は遠くからざくざく「声をかけたい」「でも迷惑かも」みたいな非常に面倒臭い感情を刺されまくり仕方なくこちらから声をかけた。すると勝手にびびりあがり勝手に感謝し勝手に半泣きにまでなられてしまった。本気で面倒くさい。なんなんだこいつ。
悪気はないようだったため、さすがに半泣きのまま放置するわけにもいかず、とりあえず食べ物を与えればいいだろうと飯をおごることにした。自分の一番身近な後輩たちは大抵飯を食べれば元気になる。そう思った訳だが、おごられてもこの面倒臭さである。よくわからねぇ奴、と思いながら影浦は自分の分の飲み物を飲んだ。
ちょびちょびとうどんを食べる優希に「お前」と影浦が声をかけた。ひゃい!と驚いたのか優希が肩を揺らした。
「人に奢られたくらいで大げさだろ。あとんなひでえ顔して食うな」
「ででで、でも、あの、……な、なんでおごってくれたんですか?」
「……別にいいだろ。大体お前だって隊長に奢られたことくらい……」
「た、た、たいちょうは、その……い、いなくて……」
「はあ? あ?お前ソロか?」
そそっそ、そうですと優希が頷く。こいつどもらずに話せねーのかよ、と影浦は心の中で思った。
「……先輩っつーのは後輩におごるもんなんだよ」
あまりにも悲しい感情が刺さっていたのでおごったというのが本音だったが、そんなことは言いたくなかったのでよくある理由を説明しておいた。優希はその言葉に「せんぱ」と小さくつぶやく。
「せんぱい、先輩……」
うわごとのように言っていた優希から刺さってきた感情に、「は?」と影浦が怪訝な顔をする。なんだ、こいつ。
「かげうらさ……か、かげ、かげうらせんぱい……」
ちくちく「感動」という感情が刺さってきたことに影浦が顔をしかめていると、優希が小さく自分のことを呼んだ。「なんだよ」と返事をすると、今度はそれがどでかい「嬉しい」という感情となって自分に刺さってきた。
「せ、せせ、先輩……! せんぱ……うええええ……っ!!」
「!?」
途端に泣き出した優希に影浦ががたんっ!!と立ち上がる。な、なに、なんで、なんだこいつ。決して「怖い」とか「悲しい」とかの感情ではなく泣くそいつに、影浦はどうすることもできず「く、食え!」ととりあえず食事を取らせた。泣きながら「おいしいですうう……!!」という優希はなおも「嬉しい」という感情を影浦に刺し続けていた。